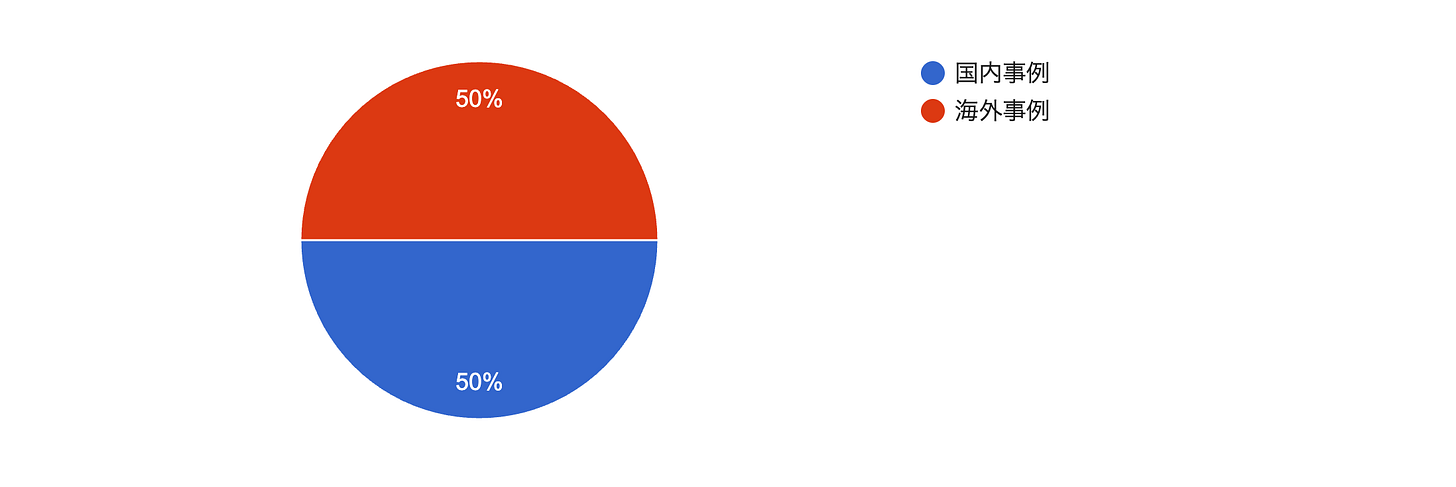企業はなぜ「人文知」を求めるのか?【後編】対談 山下正太郎・若林恵
企業が徐々に「人文知」に接近していく1970年代から現代にいたるまでの歴史をたどりつつ、大学の社会的な役割の変化、会社員が読書することの意義、さらには企業にとっての「倫理」とは何か等々を考える。企業と「人文知」の関係をめぐる、WORKSIGHT編集長の山下正太郎とコンテンツディレクター若林恵の新春対談の後編。
illustration by EmBaSy / iStock / Getty Images Plus
(本記事は前後編の後編となります。前編はこちら)
組織は思った通りに動かない
若林(以下W):前編は、企業というものが、70年代からとっくに統治不能になっているという話で終わりましたが、後編は、そうした統治の危機を乗り越えるべく、いかに企業が「人文知」をあてにしてきたのか、70年代からいまにいたるまでの歴史を概観するところから始められたらと思います。
山下(以下Y):そうですね。前編では、70年代がひとつのターニングポイントとなったのは、それまでの計画・命令・統制(command-control)による工業的統治モデルが破綻したことにあったとするグレゴワール・シャマユーの分析を紹介しました。こうした背景から、この頃から企業で採用されたのは、エルトン・メイヨーらの「人間関係論」や、アブラハム・マズローの「欲求段階説」、ダグラス・マグレガーの「Theory X/Y」といった、人間の動機づけや集団力学に関する心理学・社会学系の知見だったとされています。
W:マズローってのは、この辺から出てくるんですね。前からあれはおかしな理屈だと思っていましたが、何年か前に、マズローの「欲求段階説」がどうやって広まったかを跡づけた論文を読んだら、あれは心理学の世界ではまったく取り上げられず、そのアイデアを拾ったのは経営学だったとされていました。しかもあのピラミッド型の絵は、マズローが描いたものですらないそうで(笑)。
Y:いい加減なものですね。言われてみれば、ビジネス界がずっとありがたがってきた『ハーバード・ビジネス・レビュー』のようなメディアは、アカデミックな装いはしていますが、特に査読のプロセスがあるわけでもないので、言うなればただの「ビジネス誌」なんですよね。そう思えば、ビジネスサイドの言説を、アカデミアが苦々しく思うのも当然です。結局のところ、ビジネスサイドは、自分たちのビジネスをさまざまな観点から良くしてくれるものであれば何でもいいのが本音で、学問的な厳密さを求める義務もなければ、インセンティブもないんですよね。
W:身も蓋もない(笑)。
Y:とはいえ、70年代以降、企業はますます「人文知」をあてにするようになっていきます。その背景にあるのは、合理的な戦略や制度を整えても「なぜか組織が思った通りに動かない」という経験の蓄積です。
そこで80年代になると、新自由主義の広がりとアメリカ企業の競争力の低下、日本企業の躍進といった状況のなかで、「企業文化」ということばが一気に広まります。言うなれば、ここで数字や構造では説明しきれない何かを指し示す概念として「文化」が召喚されたわけです。
この時期にはトム・ピーターズとロバート・ウォーターマンの『エクセレント・カンパニー』(大前研一訳)のように、優れた企業を定性的に観察し、その共通点を「価値観」や「行動様式」として語る試みが流行し、文化人類学や記号論、組織行動論の知見が、経営のことばとして急速に取り込まれていきます。心理学者のエドガー・ヘンリー・シャインの「組織文化論」が広まったのもまさにこの文脈で、文化を雰囲気や精神論ではなく、組織を動かしている深層の前提として理論化した点が決定的でした。
W:文化がある企業ほど強い企業である、と。それだけ聞くと何を意味しているのか、さっぱりわからないですが(笑)。
Y:いまからするとその通りなんですが、当時は「強い企業には強い文化がある」とするこの言説が、一種の希望として受け入れられたそうです。ただ、これは一方で、文化を「分析することが可能で、場合によっては戦略的に変容できるもの」と見なすことを促し、「文化」をマネジメントの対象に変えてしまったともされます。
そこから90年代に入ると、「企業文化論」の延長で、今度は「文化をどう観察するか」という実践的な手法として、エスノグラフィが注目されるようになります。
W:前編で話題に出た、いわゆる「デザインシンキング」につながる文脈ですね。
Y:はい。IntelやXerox PARCといった組織内に人類学者が定着したのも、この流れのなかで起きたことです。技術や戦略そのものよりも、人がそれをどう意味づけし、どう使いこなしているのかを見る必要が出てきた、ということがこの潮流の背景にあります。
ちなみに経営学者のピーター・ドラッカーが「知識社会では教養、つまりリベラルアーツこそが最も重要なスキルだ」と繰り返し説いたのもこの頃で、知識労働者の思考力や世界の捉え方そのものが、企業の競争力と結びつけて語られるようになっていきます。
ワーカーの教養と経費
W:自分はまったく読んだことがないのですが、山下さんはドラッカーは読んでます?
Y:ほとんど読んでないのですが、父親が熱心に読んでいましたので、実家の本棚にはずらっと並んでいました。父親は経営者でもなんでもないただのサラリーマンですが、あれだけ熱心に読んでいたのを見るにつけ、何らかの切実な問いがあったんだろうという気はします。
W:ただでさえ「なぜ働くのか」が宙吊りにされてしまっていたところ、バブルも弾けて「金儲け」に浮かれるだけでは虚しいということもわかってしまうと、個々のワーカーも、深いところで「働くことの意義」を内省せざるを得なくなりますよね。
Y:そうしたなかドラッカーみたいな人が「これからのワーカーには教養が必須になる」と言えば、そこに「教養あるビジネスパーソン」という指針が立ちますので、それを目指して自己研鑽できるということにはなるんでしょうね。
そこから2000年代に入ると、IT革命や金融工学の進展によって株主至上主義が暴走し、その一方でエンロン事件やリーマンショックが起こって、企業もワーカーも、改めて社会的正当性(legitimacy)が問われるようになり、そこから企業内で「倫理」が語られるようになっていきます。その結果、ビジネス倫理学が勃興し、CSRからESGへの移行が進み、マイケル・サンデルの著作がビジネス界隈でも広く読まれるようになるんですね。
W:サンデル教授、流行りましたね。それこそ2010年に来日講義があって取材に出向いた記憶はあります。内容はまったく覚えていないのですが、当時のレポート記事を読むと、講義の議題に上がっていたのは、「市場の果たす役割について」と「バイオテクノロジー、特に遺伝子工学」だったとそうですから、ビジネスセクターの人たちが興味をもつのも、さもありなんですね。
Y:「トロッコ問題」を最初に流行らせたのも、サンデル教授でした。
W:自分の記憶では会場はパンパンで、実際500人くらいの動員があったそうですから、やっぱりビジネスセクターを動員できると、本の売れ行きが全然変わってくるというのはあるのだと思います。版元にしてみれば思惑通りだったんじゃないでしょうか。
Y:ビジネスセクターが動くと本が売れるのはなぜなんでしょうね。
W:仕事だと思えば、読むかどうかは別にしても、本を買うハードルは下がりますよね。仕事のためだからという理由で本を買うのは、「自分が読みたいと思う本を買え」と言われるよりはるかに心理的ハードルが低いですし、それが直接役に立たなかったとしても、さほど損したと思わずに済む気がします。それを経費として落とすことができたら、さらにハードルは下がりますよね。山下さんは、めちゃめちゃ本買ってる印象ですが、経費で落としてます?
Y:どっちもありますね。
W:その線引きってどういう感じですか?
Y:役に立つかどうかわからないものこそ、自腹で買います。経費にすると、どうしても会社への説明責任が生じるじゃないですか。仕事のタネって「説明がつかない無駄な読書」のなかに落ちていることが多いので、その自由度を確保するために自腹で買っています。
W:そもそも、なんでそんなにたくさん本を買ってるんですか?
Y:自分をアップデートしているような感覚はありますね。ちゃんと時代にアジャストできているのかどうかを測るというか。その意味では、あえて古典を読もうみたいなことにはなかなかならず、どうしたって新刊中心にはなってしまいます。
W:嫌な言い方にはなりますが、やはりそのときそのときの潮流というか、トレンドを追いかけているという感じですよね。自分がいまどういう時代を生きているのかを知るというか。そうであればこそ、ベストセラーと呼ばれるものにも一応目を通しておくことには重要な意義がある。
Y:そうですね。その意味では、非常に企業的な人文知の摂取をしているとは思います。
会社と社会、乖離と接近
W:脱線してしまいました。サンデル教授ブームの話の途中でした。
Y:2010年代の話でしたよね。この頃、ビジネス界隈に大きな影響を与えた出来事のひとつとして挙がるのは、スティーブ・ジョブズが「技術だけでは不十分だ」(Technology alone is not enough)と語ったことです。これによって、それまでの技術中心主義から、人間の物語や直観・美意識を統合する経営へのシフトが後押しされ、それによって企業が人文知のほうに、より傾くことになりました。
W:たしかに、スティーブ・ジョブズの存在は大きいですね。ジョブズを「人文」の人と呼ぶのは正確ではないとは思いますが、少なくとも「テック」を一種のカルチャービジネスとして扱ったことで、ビジネス界隈の人文/カルチャー出身者は大いにエンパワーされたでしょうし、一方で工学的なマインドでドライブしてきたテック界隈のカルチャーコンプレックスを大いに刺激したのは間違いなさそうです。また技術中心主義からの脱却ということで言えば、日本では、3.11を機に、行き過ぎた資本主義や技術への反省が強く出てくるようになりました。
Y:そうですね。それと並行して、GAFAに代表されるプラットフォーム企業が国家以上の統治パワーをもつようになり、個人の感情や行動が経済の対象となっていきます。そのなかで、行動経済学(ナッジ)や心理学が、法や強制による統治ではなく、「選択肢の並べ方」や「快適さ」を通じて望ましい行動を誘導する「穏やかな専制」のエンジンとして実装されたりもします。さらにその派生系として「UXデザイン」が、ユーザーの痛点を取り除き「自然にそう振る舞ってしまう」導線を引くための微細な統治技術として機能しました。かつての企業文化がイデオロギーによる統治だとしたら、UXやナッジは環境設計による行動変容、つまり「アーキテクチャによる統治」だと整理できそうです。
その後AIが台頭してくると、ハラリが「AI時代には『自己物語の編集力』が最も重要だ」と主張するなどして、リベラルアーツ再評価の世界的な気運を醸成することになりますが、そこでの人文知の役割は、「統治の支援」から「統治不能な主体同士がどう共存できるかを探る共生知」へと移行していくことになります。
概念的に70年代以降の歴史を整理するとこんな感じですかね。
W:なるほど。これ、しかし、言うなればずっと「統治」をめぐる歴史なんですね。
Y:そうですね。20世紀終盤から現在にいたるまでの企業と人文知の関係性を見ていくと、「企業を社会のなかでどう定位していいかわからない」という社会の困惑、「ワーカーを社内でどう定位していいかわからない」という経営層の困惑、そして「働くことを自分のなかでどう定位していいかわからない」というワーカー自身の困惑、という3つの困惑が折り重なっているわけですが、企業の側からすると、それはすべて「統治」の問題へと翻訳されることになるんですね。
W:面白い。
Y:企業というものは、ある部分では極めて非人間的なもので、ときに非常に邪悪なものともなりますが、そこで働いている人たちが社会に害悪をもたらしてやろうと思っていることはむしろ稀だと思うんです。もちろん目先の利益に目が眩んで、結果社会に大きな害悪をもたらしてしまうことはありますが、こうして改めて歴史を振り返ってみますと、どうやったら会社と社会の間にある溝を埋めることができるのかを考えるなかで、都度「文化」「教養」「倫理」「人間中心」「リベラルアーツ」といった概念をもち出しては、なんとか自分たちのものにしようとしてきたとも見えます。
W:ある意味、涙ぐましい歴史でもある、と。
Y:もちろん、その一方で、ビジネスセクターは、人文学や社会科学から、耳あたりの良さそうなことばを都合よくもち出しては、ウォッシングに使ってきたというのも事実だと思います。ただ、企業側の人間として言うのも気が引けますが、それが果たして企業だけの問題なのかといえば、必ずしもそうとは言えない部分もありそうです。
W:というと?
Y:例えば、先ほどスタンフォード大学の「d.school」の話が出ましたが、それを模倣するかたちで2009年に東京大学のなかに「i.school」というイノベーションプログラムができたことからもわかるように、国の教育政策や公的な教育機関のほうが、むしろビジネスセクターの側に寄っていくようなことは、実際に同時に起きてもいたわけですから。
W:大学経営も言ってみればサバイバルモードでしょうから、企業と組んで研究予算を捻出できるなら、むげに断ることもできないというのが、おそらくは実情ですよね。
Y:当然、そうやって企業がアカデミアに近づいていってしまうと、企業は当然費用対効果を求めますから、必然的に学問が合目的的にならざるを得ないという問題は発生してきます。それはそれで問題ありですが、背に腹は代えられないという現実もあります。
大学が企業に似ていく
W:山下さんは社員でありながら、大学で教員をされてもいますよね。それはどういうモチベーションからやっていて、それこそ学生に対しては何を授けようと思ってやっているんですか?
Y:わたしは、いわゆる国が推進する「クロスアポイントメント制度」(通称:クロアポ)を使っている立場です。これは、企業の社員でありながら大学で教えるという制度で、産学連携の成功例として語られたりもしますが、実際にやってみると、かなり倒錯した感覚を与えてくれるものです。大学と企業とでは、本来、時間の感覚も、成果の定義も、問いの立て方もまったく違うはずなのに、気がつくと企業側のことば、企業側の評価軸で回り始めてしまうんです。そのズレと収斂の両方を、日常的に体感させられています。
W:何か具体的な例ってあります?
Y:とりわけ複雑な気持ちになるのは、例えば学生に一番喜ばれているのが、講義そのものよりも就職相談だったりすることです。こちらは「中の人」として企業の論理がある程度わかりますから、採用において会社が何を見ているのか、どこで差がつくのかを学生に伝えておくと、面白いくらいに内定が取れてしまうんです(笑)。
W:それでいいのか、悪いのか。
Y:もちろんそれ自体は現実的に役に立ちますし、悪いことではないとは思いますが、大学における「知」が、気づかないうちに企業への適応装置として機能してしまっていることに、正直ゾッとするところもあります。大学に関わるモチベーションがあるとすれば、産学をうまく接続することよりも、その接続が、こうしてあたかも自然な装いで密やかに進行しているということを、当事者として考えることにあるのかもしれません。
「クロアポ」という制度自体が、自由で柔軟な人事制度のように見えながら、実は企業的な合理性や統治の論理が大学のなかに入り込むための通路になってしまっているのが現状であるなら、その居心地の悪さを手がかりに、なぜ大学が自ら企業に似ていってしまうのか、なぜ本来自由であるはずの知がこれほどスムーズに目的化されていってしまうのかを、学生と一緒に考えたいというのが、自分としては大きなモチベーションなのだと思います。
会社は「倫理」の主体になれるのか
W:それこそ70年代以降、新自由主義が広まっていくなかで、「小さな政府」という号令のもと、公営事業がどんどん民営化されていきますよね。それについて、たしかシェルドン・ウォリンという政治学者は、あれは政府が小さくなったのではなく、むしろ政府が民間にまで拡大したものと見るべきだといったことを書いていた気がします。ちなみに、そうした観点から、ウォリンは「転倒した全体主義」という概念を提出することになります。
Y:前編にあったユク・ホイの話にあったように、国家よりも企業が優位な状況になってしまっているのであれば、新自由主義によって際限なく肥大化した政府が、民間企業に完全に乗っ取られてしまったのが現状だとも言えそうですが、それはそれで由々しき事態ですね。
W:少なくともアメリカの状況を見ていると、政府が金融やIT産業にどんどん飲み込まれていっているように見えますし、アメリカのAI産業についていえば、少なくともOpenAIは、はなから公共予算で食っていこうという腹づもりのようにしか見えません。
Y:ピーター・ティールのパランティアのビジネスモデルですね。
W:まさにそれです。超巨大企業の原理が、国家よりも優位なになってしまえば、政府はこうした超巨大企業の手足でしかなくなります。そうなったら、もはや選挙や民主主義なんていうお題目も、まるで意味がなくなってしまいます。
Y:「市民」の消滅ですね。ヤニス・バルファキスがいうところの「テクノ封建制」が、いよいよ現実味を帯びてきます。
W:そうしたなか、皮肉なことに、中国だけが国家の優位を保持したまま、民間企業や自由市場の役割を明確化しつつ、それをうまくコントロールできているように見えたりもします。
Y:たしかに、そういうふうに見える局面はありますね。
W:中国企業の人に、商売人はできるだけ政治に関わらないようにするのが、中国ビジネスのエトスなんだ、と言われたこともあります。つまり、政治と商売は別物という考えです。ジン・クーユーという中国人の経済学者は、「アメリカは政治と金が近すぎる」とも言っていました。
Y:カナダの哲学者ジョセフ・ヒースは『資本主義にとって倫理とは何か』のなかで、企業倫理についてかなり踏み込んだ議論をしていて、まさに「企業が政治や道徳の主体のように振る舞うこと自体が、資本主義を歪めている」と指摘しています。ヒースの考え方では、企業はそもそも「社会をよくする主体」ではなくて、競争という制度のなかで役割を割り当てられたプレイヤーにすぎない。だから、企業に「地球を守れ」とか「社会課題を解決せよ」と期待するのは、ある意味で役割の取り違えだとされます。
W:SDGsの話なんかはその最たる例ですが、どの企業も「地球を守る」みたいなことを標語として掲げてはいますが、そもそも一企業に「地球を守る」ことのできるキャパシティなんてないですよね。できる範囲で環境を汚さないように気を配ることは必要だとしても、民間企業が行政府を肩代わりすることはできませんし、いくら環境に良い製品をつくったとしても、それが従来の製品と比べて割高であれば、なかなか買ってもらうことができないという現実もあります。
Y:ヒースは、企業に求められる倫理とは「善いことをする」ことではなく、市場の前提条件を壊さないことだと言っています。環境の話で言えば、「地球を救う」ことではなく、環境コストを他人に押し付けて競争優位を得ないこと。そこまでが企業の責任だ、という考え方です。
W:いいですね。いずれにせよSDGsやESGは、2025年で一気に萎んじゃいましたよね。ちなみに2025年に中国企業を視察に行ったのですが、訪ねた企業でSDGsの話をしているところはほぼなかったです。唯一テンセントだけがプレゼンテーションルームの最後のほうで、それをちらっと謳っていたくらいで。
Y:それって「企業が前面に出る話ではない」と割り切っているからなんでしょうか。
W:感覚的な印象ですが、基本デジタルトランスフォーメーション(DX)を進めていけば、必然的にグリーントランスフォーメーション(GX)が起きるという考えがベースにあるようで、少なくとも「グリーン化」をゴールにする発想は、企業にはなさそうでした。
Y:逆に日本や欧米では、それをゴールにしてしまったことで、この間、企業がどんどん倫理的主体であり準政治主体であるような振る舞いを求められるようになりました。
W:アメリカを見ていると、そうやって企業を全面的に政治主体化してしまったことが、逆に、政府を企業化してしまうといった反作用を生んでしまったように感じます。テック企業なんて、もはや政府の一部にしか見えないですし。
Y:イーロン・マスクやオラクルのラリー・エリソンとトランプ政権の近さをして「オリガルヒ」(寡頭支配)といった批判が出ていますが、社会がそれを要請してしまった部分があるということですよね。
W:企業が「倫理的」な主体であることを求められ、それに応えよう行動したり発信したりしても、結局は自己宣伝になってしまいますよね。その一方で、会社がワーカーに「倫理的な振る舞い」を強制するわけにもいきません。企業が「倫理」を担保するって、言うほど簡単ではないですよね。
Y:ヒースが強く問題にしているのはまさにその点です。企業が「倫理的であろう」としても、どうしてもウォッシングか、経営者の裁量の拡大、もしくは越権行為になってしまう。しかも競争環境にある以上、善意やお気持ち頼みの倫理は長続きしません。
W:売り上げとのバランスのなかでしか「倫理」を考えることができないのであれば自ずと限界があります。
Y:であればこそ、「倫理」というものを、各社の覚悟やエピソード的な美談に委ねてはいけないというヒースの意見には納得感があります。ヒースの立場では、倫理は個人の心の問題ではなく、制度として競争条件に埋め込まれるべきものなんです。情報開示やガバナンス、取り引きの透明性といったかたちで、「ズルをしたほうが得をする構造」をなくす。企業が問うべきなのは、「どこまで善人になるか」ではなく、「自分たちが市場の前提を壊していないか」なのだと思います。
シンカーと新書
W:ここまで話してきて面白いなと思うのは、ビジネスセクターは、企業ガバナンスをめぐる最新トレンドをほぼほぼアメリカから仕入れてきたことです。しかも90年代以降は、IDEOの例をはじめ、かなり強くシリコンバレーのアイデアに引っ張られてきました。デザインシンキングからアジャイル、リーン、ティール等々、次から次へと闇雲に輸入してきたわけですが、そこで人文知のようなものが援用されていたとしても、どこか胡散臭く見えてしまうのは、一方で、わたしたちが「人文知」といってイメージするのが、ヨーロッパの知的伝統や、それに根差した教養といったものだったりするから、ということもありそうです。
Y:個人的な印象ですが、そもそもアメリカの学問は、使ってなんぼ、使われてなんぼといった感覚が強くあるように見えます。ある意味プラグマティックと言いますか。なので、どんな学問であれ、使えるものは企業も政府も躊躇なく使いますよね。
W:ゾンビパウダーを探して文化人類学者がハイチに行った『蛇と虹:ゾンビの謎に挑む』という面白い本があって、のちにホラー映画監督のウェス・クレイブンが映画化しますが、本を読むと、これがNASAの委嘱を受けて実施した研究だったと書いてあります。なぜNASAがゾンビパウダーの秘密を知りたがったのかは忘れてしまいましたが、これを「人文知」の援用と呼べるかどうかはおいても、学問、あるいは学者の使い方としては、かなり思い切りがいいですよね。
Y:広報(PR)の父と呼ばれるエドワード・バーネイズの存在なんかも象徴的です。彼はフロイトの甥っ子ですが、叔父の精神分析の理論を、そのまま広告やプロパガンダに応用して、人間の無意識を「欲望」として資本主義の駆動力に変えてしまいました。学問を聖域化せずに道具として使い倒す手つきは、アメリカならではという感じがします。
W:社会調査の手法を次々と開発していった社会学者のポール・ラザースフェルドについて、『WORKSIGHT』のプリント版27号『消費者とは?』で取り上げましたが、このラザースフェルドという人も、同じような意味で面白い人でした。
Y:アメリカにおける「知」は、過去の蓄積として保存されるものではなく、現在進行形で使われ、都度アップデートされ、組み替えられていくリソースなんでしょうね。伝統や重みといったウェットな感覚はあまりない。一方で、日本やヨーロッパでは、知というものがどうしても時間を経た重みや連続した伝統と強く結びついています。だからこそ、企業が急に人文的なことを語り始めると、どうしても違和感が出てしまいます。
W:前編で挙げたカーティス・ヤーヴィンなどもそうですが、アメリカって「知」の担い手として、「シンカー」(Thinker)と呼ばれる人たちがいますよね。『テクニウム:テクノロジーはどこへ向かうのか?』のケヴィン・ケリーもそうですし、自分はダグラス・ラシュコフなんていう人が好きなんですが、この人たちが知識人としてどういうカテゴリーに収まるのか、よくわからないところがあります。キャリアや肩書きだけを見れば、ケリーは「元編集者」ですし、ラシュコフは「批評家」が一応の肩書きですが、アカデミアとはほぼ無縁ですし、「思想家」と呼ぶのは重すぎて、ジャーナリストと呼ぶのもちょっと違う。「シンカー=考える人」という呼び方は、そう考える絶妙ではありますが、実体が判然としないんですよね。
Y:TEDで講演するような人たちですよね。アカデミアの人もいれば、起業家もいて、アーティストがそこに含まれることもある。
W:The Rootsのドラマーのクエストラブや有名音楽プロデューサーのリック・ルービンなんかは、それこそ前編でちらっと触れた「クリエイティビティ」の第一人者として、ある種の「知」を体現する存在になっていたりします。
Y:そこにプラグマティックな「知」があるという見立てなんでしょうね。
W:リック・ルービンの話なんかは、たしかに仕事に役立つようなところもあって、ポッドキャストなどで話を聞いているとしばしば膝を打ったりもするんですが、そういうものと、いわゆる古典的な教養とを分け隔てる線引きが、どんどん曖昧になってきているのは感じます。
Y:メディアの問題は大きいのかもしれません。ポッドキャストのような空間では、ただの素人コメンテイターも、アカデミアで実績のある学者も、ジャーナリストも、起業家も、ある意味等価な存在となってしまい、どんな意見や見解・分析も、ひとしなみに「考察」になってしまいます。
W:マスメディアの時代は、新聞社やテレビ局や出版社がゲートキーパーとなって「ちゃんとした人」を選別し、コメンテイターの発言の権威性や真実性をそれなりに担保してきたわけですが、その枠組みが壊れて「ちゃんとした人」を受け手のひとりひとりが自分で判断せざるを得なくなれば、どうしたって混乱が起きますよね。
Y:たしかに。
W:これは何もデジタル空間だけで起きていることではなくて、出版でも例えば「新書」というものの位置づけの変化として現れていたりもします。かつて「新書」といえば「岩波新書」と「中公新書」が基本ツートップで、そこではアカデミアの第一人者が入門者を書くというのがスタンダードになっていたはずですが、90年代くらいから他の出版社が新書マーケットに多く参入するようになると、各社ごとにスタンスや著者のラインナップ、取り上げる内容の傾向などが差異化されていき、かつてあったはずの権威的な装いが、良くも悪くも壊れていきます。極端な言い方をすると、新書が雑誌の代替になっているような感じになったんですよね。嵐の「ニノ」(二宮和也)の『独断と偏見』が新書として刊行されるのは、もはや驚くべきことでもないとは思いつつ、「そういう感じなのか」と思ったりはします。
自己内省のための道具として
Y:そうやっていわゆる「公的な言説」がなし崩しに溶解してしまったことと、企業が明確な指針をもてなくなっていったことは、やはり関係がありそうです。昔の会社の重役といえば、午前中は新聞を広げて読んでいるといったイメージだったじゃないですか。で、その重役が読んでいた新聞を社員の大半も購読していたわけです。80年代以降は、それこそ「日経新聞」が、ビジネスパーソンにとっての「社会像」のコンセンサスをつくっていたわけですよね。
W:それがソーシャルメディアの時代ともなってくると、会社のトップが見ている情報と若手が見ている情報が乖離していくことになる。
Y:みんなで一体となってどこかに向かおうと思っても、そもそももっている地図が違うということになると、戦略も、戦術も成立しなくなってしまいます。であればこそ、会社にとって「ミッション」が何よりも大事だということにもなってくる。
W:ただ、この「ミッション」というやつも、とかく上滑りしがちです。
Y:ただの標語になってしまって解釈が統一されなかったりもしますしね。
W:自分が企業と付き合うなかで、よく感じるのは、企業っていうものは「現在」というものにほとんど興味がないんだなということです。というのも、企業は常に「次はどこに投資すべきか」ということを考えないといけないという意味で、ずっと未来を向いているじゃないですか。なので、一生懸命、次はどこへ向かうべきか、それを教えてくれそうな予兆を探しているわけですよね。
Y:そうですね。投資すべき「未来」と、投資に役に立つ範囲での「過去」には興味あるはずですが、たしかに「現在」は、ぽっかり空いてしまっているかもしれませんね。
W:経営者が「アート」になぜ興味をもつのかという話は、前編でもチラと出ましたが、それっておそらく「アート」というものが、わかりやすく投資対象になっているからですよね。逆に「アート」のなかでも、例えば音楽はそういう意味で「財=アセット」になりづらいので、経営者や企業は音楽になかなかお金を落としません。
Y:音楽は、数あるアートフォームのなかでも、最も「現在性」が高いものですしね。もっとも最近では、名のある音楽家の楽曲群は、IPとしてアセット化され、激しく売買されているようですが。
W:いずれにせよ、企業というものは、そうやっていつも次の行き先を探しているわりには、自分たちの「現在」、つまり「いまどこにいるのか」についての見立てがほとんどないので、A地点からB地点に向かおうにも、そもそもA地点がはっきりしていないから、本来線であるべきものが、ただの「点の移動」になっているようにしか見えないんです。
Y:たしかに。
W:ところが一方の人文学は、自分はフランス文学専攻だったんですが、ここでの勉強って、基本フランスの文学が過去からどうやって現在まで辿り着いたのかをさまざまな角度から学ぶ以外のことがないんですよね。要は過去を通して「現在」を知るための学びがすべてで、そこには「未来」がはなから視野に入っていない気がします。企業と人文知との間には、何よりも、そこに大きな齟齬があるように感じたりもするのですが、どうでしょうね。
Y:たしかに、企業は概ね過去には興味がないというのは前提としてあります。また、企業にとっての「現在」は、基本的に乗り越えるべき「課題」として認識されますので、その課題自体は分析しても、どうやってここに辿り着いたのかという経緯を含めて考えることはあまりしません。
W:これは『WORKSIGHT』のニュースレターで、人類学者のティム・インゴルドが語っていたこととも関わってきそうですが、そもそも「現在」を課題として定義した時点で、それって「未来」の話ですよね。
Y:ほんとですね。もちろん「創業何周年」といったタイミングで社史が編纂されたりして、過去と向き合うこともたまにはありますが、それも結局「未来の役に立つ」という合目的的な文脈で正当化されてしまいがちです。
そう考えると、先ほどお話しした「企業×人文知」の胡散臭さは、結局、未来志向の装置である企業と、過去を引き受ける営みとして理解されてきた人文知の時間感覚の決定的なズレから立ち上がってくるのかもしれませんね。
W:山下さんのいるコクヨは2025年に創業120周年を迎えましたが、「生活社史/社誌」は、その意味では、会社の過去を「勝者の記述」ではないやり方で記述するチャレンジですよね。
Y:「生活社史」はまさに、企業が陥ってしまう「合目的性」からいかに逃れるかをめぐる試みだと言えます。通常の社史が、経営者視点で描かれた「正史」、つまり直線的な成功物語だとしたら、「生活社史」が記述しようとしているのは、そこで働く人たちの「生活史」です。そこには、製品や売り上げの変遷だけでなく、失敗したプロジェクトや、当時の食堂のメニューへの不満といった「ノイズ」も含まれます。でも、そうした澱(おり)のような部分にこそ、その会社の本当のカルチャーや体質が宿っている、という見立てです。
過去を無理やり未来への教訓として回収せず、ノイズ混じりのまま置いてみて初めて、自分たちの現在地であるA地点が、綺麗な舗装道路ではなく、泥臭い獣道だったということが立体的に見えてくるのだと思います。未来に向かうために過去を利用するのではなく、現在の座標を確かめるために過去を見る。企業における人文知の意味があるとすれば、たぶんそのあたりにあるんじゃないかと思っています。
W: とはいえ、それもまた、どこかの時点で「合目的性」に回収されてしまい、それ自体が成功物語として消費されてしまうことにもなりかねません。
Y:そうですね。ここは悩ましいところですが、少なくとも、わたしが「生活社史」だけでなく、人文知のようなものと関わる際に大事にしたいと思っているのは、次の条件を満たしているかどうかです。
第一に「説明責任」(Accountability)。その施策によって誰が得をし、誰がコストや痛みを負っているのかを、隠蔽していないか。耳あたりのいいことばで負担の所在を曖昧にしていないか。第二に「可逆性」(Reversibility)。何らかの間違いが起きたときに、修正や撤回ができる余地が残されているかどうか。あるいは、UXやナッジが、ユーザーなりの選択肢をあらかじめ奪ってしまうような設計になっていないかどうか。そして最後に、自己言及性(Reflexivity)。人文知を「相手を分析する道具」として使うだけでなく「それを使う自分たちは何者か」を問うために使っているかどうかです。
W: 最後の「自分に対して使う」は重要なところかもしれませんね。「人文知」が何であれ、それが自己内省を促すものであるところに価値があるというのは、納得しやすいかもしれません。
Y: デザインから人文へのシフトは、企業が単なる機能の提供者から、社会のなかに歴史的に位置づけられた「意味の生成者」へと成熟していくための、避けて通れない通過儀礼なのではないかと思っています。未来に行きたければ、まず過去を見る。B地点の話の前に、A地点を確かめる。それをする勇気をもつことが、いま企業にとって一番の人文知的実践なのかもしれません。
山下正太郎|Shotaro Yamashita 本誌編集長/コクヨ ヨコク研究所・ワークスタイル研究所 所長。2011 年『WORKSIGHT』創刊。同年、未来の働き方を考える研究機関「WORKSIGHT LAB.」(現ワークスタイル研究所)を立ち上げる。2019年より、京都工芸繊維大学 特任准教授を兼任。2022年、未来社会のオルタナティブを研究/実践するリサーチ&デザインラボ「ヨコク研究所」を設立。
若林恵|Kei Wakabayashi 黒鳥社/TIGER MOUNTAIN/WORKSIGHTコンテンツディレクター。『WIRED』日本版編集長を経て黒鳥社を設立。2025年には古書店「TIGER MOUNTAIN」をオープン。著書に『さよなら未来』(岩波書店)、『実験の民主主義:トクヴィルの思想からデジタル、ファンダムへ』(宇野重規との共著/中公新書)。訳書にジョン・バージャー『第七の男』(金聖源との共訳/黒鳥社)。最新刊に『会社と社会の読書会』(黒鳥社)ほか。photo by Kaori Nishida
【WORKSIGHT SURVEY #34】
Q:企業はもっと「人文知」を取り入れるべき?
企業やビジネスパーソンは、もっと「人文知」を取り入れるべきなのでしょうか? あるいは、これ以上は必要ないのでしょうか? 取り入れるべきだとするなら、どんな「知」をどのようなかたちで取り入れるのが望ましいのでしょうか。みなさんのご意見をぜひお聞かせください。
【WORKSIGHT SURVEY #33】アンケート結果
2025年、WORKSIGHTで最も読まれた記事ベスト10(12月23日配信)
Q:今後、WORKSIGHTでより多く読みたいのは国内事例?海外事例?
【海外事例】海外の事例はまだソースが限られているので、独自の取材で取り上げてほしい。
【海外事例】日本にいると情報が日本語に偏り、海外の情報が不十分だから。
【国内事例】色々な記事を読ませていただきましたが、読後も印象に残っているものは国内事例が多く感じました。
【国内事例】最近潰れた喫茶店跡地にいくつも中華料理店ができていたが、Google Mapにはまったく載っておらず、そこに見えているが認識できていないようなものを見てみたい。
【第5期 外部編集員募集のお知らせ】
WORKSIGHTでは2026年度の外部編集員を募集しています。当メディアのビジョンである「自律協働社会」を考える上で、重要な指針となりうるテーマやキーワードについて、ニュースレターなどさまざまなコンテンツを通じて一緒に探求していきませんか。ご応募お待ちしております。
募集人数:若干名
活動内容:企画立案、取材、記事執筆、オンライン編集会議(毎週月曜夜)への参加など
活動期間
第5期 外部編集員:2026年4月〜2027年3月(予定)
年間を通じて継続的に活動に参加していただける方を募集します。単発・スポットでの参加は募集対象外となります。
募集締切:2026年2月18日(水)18:00まで
応募方法:下記よりご応募ください。
次回1月13日は、これからの都市における空間の在り方を問うシリーズ企画「『場』の編集術」第4弾として、東京都狛江市にある「野口晴哉記念音楽室」を拠点に、音楽鑑賞会や対話の場を運営する「全生新舎」の主宰・野口晋哉さんへのインタビューを配信します。お楽しみに。