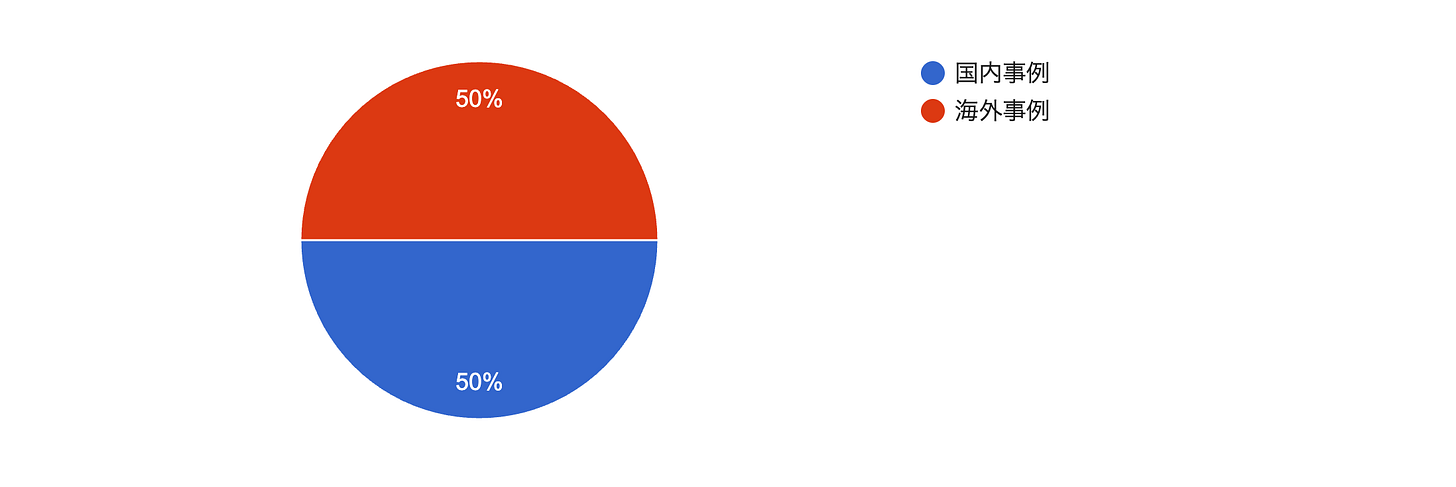企業はなぜ「人文知」を求めるのか?【前編】対談 山下正太郎・若林恵
2025年末から「人文」「人文知」の語が世間を賑わせている。そしてその消費・受容主体として、企業や会社員の存在もクローズアップされる。そもそも企業やビジネスパーソンと「人文知」との関係とはいかなるものだったのか。企業と人文知をつなぐ回路を、WORKSIGHT編集長の山下正太郎とコンテンツディレクターの若林恵がゆるゆると語ってみた、長文対談の前編。
illustration by EmBaSy / iStock / Getty Images Plus
(本記事は前後編の前編となります。後編はこちら)
人文知への4つの回路
若林(以下W):年末から「人文」や「人文知」といったことばが話題になっていることもあって、今日は、企業と「人文知」というものの関係を改めて考えることができたらと思っています。と言っても、そもそも「人文知」ってあまりピンとこないことばで、自分ではあまり使わないのですが、山下さんは、どうですか?
山下(以下Y):自分もよくわからないというのが正直なところです。今回こうやって対談をすることになったので、これまで企業がどのように「人文知」を取り込んできたかをざっと調べてみたのですが、そこで取り上げられる学問は、主に、文化人類学、社会学、認知心理学といったもので、それらを厳密な意味で人文学と呼んでいいのどうか、自分はよくわかりません。ちなみに、ごく最近、哲学者のマルクス・ガブリエルが「哲学コンサルタント」を設立したというニュースを見ましたが、これなんかは明確に「企業による人文知の取り込み」、あるいは「人文知の企業への接近」の好例と言っていいのかもしれません。
W:企業の側から見ると、人文知は、言うなれば「効く薬」としてこれまでも利用されてきたし、いまも利用され続けています。その一方で、人文学の側には「人文知」を企業がビジネスにおいて活用できる「有用なもの」と見なしたくないという反発が根強くありそうです。ここにまずは大きな齟齬がありそうですね。
Y:そうですね。人文学側の反発はもちろんよくわかるのですが、企業の人文知への接近という事象には、単に「効く薬」を求めてのことだというだけでは足りない経緯とニュアンスがあるようにも思いますので、今日はその辺を、主に企業側の目線から語ることができたらと思います。
W:企業の側も、お金が儲かりそうであればなんでも取り入れる、というわけでもないということですね。
Y:もちろん金儲けが企業の根本の欲求であるのは間違いないのですが、とはいえ企業というものは、もう少し複雑な成り立ち方をしているはずです。であればこそ、直接お金儲けにはつながりそうにもない「人文知」を求めることにもなるのだと思います。自分が見るところ、企業による人文知の取り込みは、おそらく4つの役割の回路がありそうですが、ひとつはそこそこお金儲けに直接つながる役割で、残りの3つはかなり婉曲的なものです。
W:ほほう。
Y:企業が人文知に求めることのひとつ目は「発見装置」としての役割です。これは、顧客の潜在ニーズや現場のインサイトを探るために人文学を援用するという回路で、エスノグラフィや心理学がここでは主に援用されます。
W:これは比較的お金儲けにつながりそうな使い道ですね。
Y:そうですね。とはいえ、ここからはやや間接的なものになります。ふたつ目は「統治装置」としての役割です。これは、組織の文化をつくる、動機づけをする、あるいは社員やユーザーの行動をある方向に誘導するために人文知を用いる回路です。ここでは組織文化論や「ナッジ」「UX」といった行動経済学などと関わるような分野が企業で援用されます。
3つ目は「正当化装置」としての役割です。企業の社会的責任や倫理的正しさを担保し、社会の許可証(legitimacy)を得るために人文知を用いる回路で、ここでは倫理学や哲学が、「ESG」「CSR」「パーパス」といった領域に紐づくかたちで採用されます。
W:先のマルクス・ガブリエルの会社のミッションステートメントには、こんなことが書かれています。「わたしたちは、倫理を可視化します。誰にとってもアクセスしやすく、理解しやすく、実践可能なものとして。……学際的な専門家ネットワークの支援のもと、テクノロジー、AI、ビジネスに関する複雑な問いに答えます」。これは、広く言えば、この3番目の「正当化装置」に該当しそうですね。
Y:そうですね。そして最後の4つ目が「現在地を測定するための装置」としての人文知です。これは企業として自分たちを歴史のなかにどう位置づけるのか、あるいは「自分たちは何者なのか」を把握するために人文知を用いる回路で、歴史学、アーカイブ、生活史のような取り組みがここに入るのではないかと思います。
W:それこそ山下さんが率いるヨコク研究所では、「生活社史」というプロジェクトが進行しています。これは、人文学的なアプローチから「社史」というものを編成し直す試みと言えそうですが、お金儲けに直接はつながらなそうな取り組みではありますよね。
Y:たしかにこうした取り組みは直接的な「利益」にはつながらないものではありますが、ただ、いまの企業が直面している根本的な困難は、「ここはお金儲けの話」「ここは組織ガバナンスの話」「ここは社会貢献の話」といったように、先に挙げた4つの領域を切り分けて扱うことができなくなってしまったことにあります。
これはデジタルテクノロジーが浸透したことで激しく進んだ傾向です。「発見」(顧客理解)がそのまま開発に直結し、開発をアジャイルで回すほどに「組織の統治」が問われるようになり、統治が問題になれば、それに合わせて「正当化」「倫理」「ミッション」が求められる。そして、それらがうまくつながらず、会社の全体像があやふやになっていくと、改めて「現在地の測定」の必要が出てくるといったように、すべてが連動してしまいます。
W:なるほど。
Y:これまでの企業は、プロセスをいかに効率よく切り分けて処理するかを洗練させてきました。いわば、企業は自らを工学的なシステムだと考えてきたわけです。ところが、そのシステムは、あらゆる部門や内と外とが融通無碍につながり合ってしまうデジタルテクノロジーの原理とは極めて相性が悪いんですね。つまり、企業がいま直面している最大の問題は、その環境変化にどうやって適合するかという困難で、そう思えば、企業がこれまであてにしてきた理工系の「科学」や「工学知」以外のものを求めるようになるのは、ある意味必然だったと言えます。その結果、企業が「人文知」に注目するようになったのだとすれば、その背後には、それなりに切実な問題意識があったと見ることはできます。
イノベーションと哲学
W:先のマルクス・ガブリエルの話に戻ると、10年くらい前にも、Googleをはじめとする企業が哲学者を雇っているといったニュースをよく聞きましたが、人文知の導入が、まずは巨大IT企業で大掛かりに始まったのは、いまから見れば象徴的ですね。企業の人文への接近が、社会のデジタル化によって加速したというのは、面白いですね。
Y:ソーシャルメディアやAIのガバナンスがビジネスの領域を超えて社会的・政治的なイシューになり、デジタルテクノロジー企業が盛んに「倫理」といったことばを用いるようになったのが、現在の人文シフトのひとつの大きな底流ですよね。そうした動向が目に見えて活発化したのは、トランプが台頭してきた2016年前後のことだったと思います。
W:それこそ自律走行車がもたらし得る問題を考える上で、「トロッコ問題」のような古典的命題がよく取り沙汰されたのを覚えています。ちなみに自分も2017年頃に『WIRED』というメディアで「哲学講座」を企画実施したことがあるので、人文知を求める気運はビジネス界隈に、その頃からたしかにあったんですよね。
Y:それって、どういう経緯から「哲学」を取り上げることになったんですか。
W:まず前提として、雑誌のビジネスは雑誌の売り上げではビジネスが成り立たないので、広告をはじめとした企業から入ってくる収益をあてにしないといけない構造に1980年代くらいからなっていたわけです。ところがソーシャルメディアの時代になると、雑誌やウェブメディアに広告予算が流れなくなります。なので、メディア側も、別のやり方で企業からお金を引っ張ってこられないか知恵を絞らざるを得なくなりました。そうしたなか、例えば「イノベーション」をキーワードにしていた『WIRED』のようなメディアは、「企業をイノベートする」ことを課されていた「新規事業部」をターゲットにして、コンサルみたいなことをやるようになるんです。
Y:詐欺まがいですね(笑)。
W:否定はしません(笑)。ただ言い訳をすると、ことの成り行きから言えば自分たちから「コンサルやりますよ」と営業して回ったというより、むしろ企業のほうから「相談に乗ってもらえないか」と問い合わせが来るようになったのが先なんです。こちらもどうやってマネタイズするのか困っていたところ、企業もどうしていいかわからんと困っていたので、これは渡りに船だと。
Y:それがどうやって「哲学」に行きつくんですか?
W:これも自分たちの方から「これからは哲学!」と謳ったわけでもなかったはずです。もちろん講座を売り出すにあたってはそういう打ち出し方はしますが、基本的には需要がありそうだという見込みがあってのことですから、当時、周りのビジネスパーソンが「これからは人文だ、哲学だ」と言っていたのを聞いて、そういうトレンドなんだなと思ったのがきっかけだったと思います。あまり確証はないのですが、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』のブームを境に、それまで「デザインシンキング」と言っていた人たちが、急に「人文」「哲学」といったキーワードにシフトしたような印象があります。
デザインシンキングという転回点
Y:それは感覚としてよくわかります。企業の「人文」へのシフトというのは、歴史的に見ると色んな段階がありますが、直近でいうと、たしかに「デザインシンキング」が重要な契機になっていそうです。
デザインシンキングは、1991年に設立された「IDEO」という、のちの「デザインコンサルティング」の第一人者とされる企業が提唱したものです。とりわけ、1999年に放送されたアメリカABC Newsの「Nightline」のテレビ特集「The Deep Dive」は、IDEOとデザイン思考を世界的に有名にした決定的メディア事件だとされていまして、自分も大学の指導教官が熱っぽく録画を見せてくれたことをよく覚えています。さらにビジネス界に大きなインパクトを与えたのが、2001年に刊行されたIDEOの共同経営者トム・ケリーの共著書『発想する会社!: 世界最高のデザイン・ファームIDEOに学ぶイノベーションの技法』(The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, America’s Leading Design Firm、2002年邦訳刊行)です。
W:ふむ。
Y:このIDEOの発想を受けて、トム・ケリーの兄で、IDEO創業者でスタンフォード大学の教授も務めていたデビッド・ケリーが、2004年、同校に「d.school」を設立するのですが、それを資金援助したのが「SAP」の創業者ハッソ・プラットナーでした。
W:SAPもテック企業ですね。
Y:はい。ハッソ・プラットナーがd.schoolを支援した背景には「大企業病からの脱却」と「原点回帰」という強い動機があったとされています。2004年の『BusinessWeek』の特集「The Power of Design」を読んだプラットナーは、IDEOの手法に「顧客の隣で開発していた創業期のSAP」の精神を見いだし、即座にデビッド・ケリーに連絡を取ったといいます。さらに資金援助するにあたって彼は、「イノベーションはサイロ(縦割り組織)のなかでは起きない」とも明言し、エンジニアリング偏重や部門間の壁を打破するには、異分野の人材が交わる「デザインシンキング」の場が不可欠であると結論づけました。
先述したトム・ケリーの書籍も含めて、これは、デザインというものを「意匠=専門家の技」から、織変革とイノベーションのための「経営資源」「組織の思考様式」へと転換させた、歴史的な転回点だったと考えていいと思います。
W: そこから、デザインが個別の部署の課題ではなく、全社的な課題になっていく、と。
Y:デザインシンキングがビジネス界で広がったとき、表向きは顧客理解や課題解決の手法として普及したのですが、その一方で同時にサイロを壊して組織を横断させる仕掛け、つまり組織開発や統治のツールとしても機能することにもなりました。加えて、IDEOは創業当時から、ビジネスの現場を多様な人材が交わる交差点だとする見方を提唱し、「人間理解」を重視することを謳いました。それを実現するための手法として、IDEOは、エスノグラフィをビジネスの現場に応用していくこととなります。
W:「デザイン」がいわば人文知的なものへの接近の布石になった、と。
Y:企業が「人文知」と呼ばれるものに接近したというより、それに先行するかたちで「デザイン」というキーワードのなかに、人文知が「密輸」されていたとも言えるかもしれません。
W: 山下さん自身も、会社でビジネスエスノグラフィの研修を受けたんですよね。
Y:そうなんです。わたしがコクヨに入社して若手だった2008年頃、研修で受けたのがまさに日本で初めて開催された「ビジネスエスノグラフィ」の講座でした。文化人類学のエスノグラフィ(民族誌)の手法をビジネスに応用して、顧客や組織の現場に入り込み、言語化されない潜在的ニーズや行動原理、文化を深く理解する調査・分析手法です。当時それを積極的にプロモート・実践していた代表的なプレイヤーが「博報堂イノベーションラボ」でした。
W:面白い。『WIRED』にいた当時、「d.school」のプロモーションを相談されたことがありましたが、相談に来た方が、博報堂イノベーションラボの出身でした。いまでも仲良くさせていただいている方ですが。
Y:ちなみに、その後「デザイン」ということばに飽きた人が向かった先としては、「アート」がありましたよね。
W:はいはい、ありましたね、「アート思考」。
Y:デザイン思考が「課題解決」の手法として一般化するにつれ、そこからこぼれ落ちる「0から1を生む力」への渇望が、2010年代後半にかけて一気に高まりました。米国では2016年、エイミー・ウィテカーが著書『アートシンキング:未知の領域が生まれるビジネス思考術』(Art Thinking: How to Carve Out Creative Space in a World of Schedules, Budgets, and Bosses)で「デザイン思考はA地点からB地点へ効率よく行くためのものだが、『アート思考』はそもそもB地点がどこにあるかを発明するためのものだ」と定義し、その違いを明確にしました。
日本でこの流れを決定づけたのは、2017年の山口周氏による『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?:経営における「アート」と「サイエンス」』です。「論理(サイエンス)だけでは勝てない時代に直感(アート)が必要だ」という論旨は、閉塞感を抱いていた日本のビジネスパーソンに深く刺さり、国内独自の「アート思考」ブームを巻き起こす起点となりました。
W:「アート思考」も、たしかに広義の「人文シフト」の一例と言えるのかもしれませんが、一方で「アート」は、ビジネスで成功した人が求める価値としては、昔からある古典的なデスティネーションでもありますよね。
Y:創業者がどこかの時点でアートを買い始めるという、あれはいったい何なんでしょうね。企業や企業経営者のアートへの傾斜は、かつてであれば「メセナ」ということばで正当化されていたものでしたが、そのことばが有効性を失ってしまったところに「アート思考」が入り込んだという図式なんでしょうか。
W:ひとつの合理的な説明は税金対策ということなのでしょうけれど、アートNFTのバブルが起きたときに強く感じたのは、ビジネス界のアート/カルチャーコンプレックスはなかなか根深いものがあるなということでした。一方で、アートセクターのテック/ビジネスコンプレックスも大きく作用しているようにも見えましたが。
Y:コンプレックスとまでは言わずとも、双方に何かしら憧れがあるというのは実際そんな感じがします。いずれにせよ、デザインというキーワードをビジネスセクターに向けて広範に売り出していくにあたって、IDEOは当時から社会学や人類学のバックグラウンドをもつ人たちを採用するようになり、その流れは、いまも続いていると思います。また、2015年前後に、マッキンゼーやアクセンチュアといったビジネスコンサルがIDEOのようなデザインファームを買収するかたちで内製化していったのも、ビジネス界隈における「人文知」の一般化を印象づける出来事でした。
近代的経営の終焉
W:2025年末にWORKSIGHTのニュースレターで配信した、「フィールドワークは万能じゃない:民俗学者・辻本侑生の試行錯誤」という記事は、民俗学者の辻本侑生さんにインタビューさせていただいたもので、辻本さんは、民俗学を学んだのち、一時シンクタンクに勤めた後、再び大学に戻られていますが、こうしたキャリアは、IDEO以降さほど珍しくなくなったということなのかもしれません。実際、山下さんが所長をしているヨコク研究所には、民俗学を学んでる方もいますし、『WORKSIGHT』と並んで『YOKOKU Field Notes』という雑誌も刊行しています。これはその名の通り、民俗学や人類学が培ってきた「フィールドワーク」という手法を、企業R&Dの観点から取り入れたものに見えますが、そもそも、なぜ企業が、それをやらなきゃいけないんでしょう。
Y:コクヨに限った話をしますと、弊社のようなものづくりの会社は、第二次大戦後、欧米流の働く環境に追随し、日本経済が伸びていくなかその潮流に乗って成長してきたんです。みんなが同じ方向を向いていた時代ですから、物事をあまり深く考えずとも、物をつくれば売れるのが当たり前という環境で育ったわけです。ところが、おそらく2000年代くらいからでしょうか、弊社で言えばオフィス用品のEC企業「カウネット」を設立して以降、つくるべきものがわかっていた時代が次第に終わっていきます。
W:何をつくったらいいかわからなくなると。
Y:はい。そうしたなか、企業としてもっとユーザーのことを知らなきゃいけない、表層的なマーケティングよりもさらに深いインサイトを捕まえないといけない、ということになったんだと思います。自分が入社した頃には、何十万円もするビジネスエスノグラフィ研修に若手を放り込むぐらいですから、そうした考えがかなり一般化していましたし、いまも基本的に、その考えは変わっていないはずです。外部環境が変わっていったときに、社会で何が起きているのかを、より解像度高く理解する必要がある。そのために、人文社会科学の知見を取り入れるという構図は、いまも続いていると思います。
W:となると、それって結局は、新手のマーケティング手法だということになるんですかね。
Y:そうとも言えますが、そうとばかり言えないところもあります。これは、ヨコク研究所から2025年に発行した「クリエイティブシフト:未来の仕事とクリエイティビティ」という冊子でも指摘したことですが、それまでのやり方が行き詰まった結果、ワーカーの「クリエイティビティ」を積極的に開発しなければならないといったことがアメリカで言われ始めるようになったのは、1950年代のことでした。ここで参照すべきは、サミュエル・フランクリンが『クリエイティブという神話:私たちはなぜそれを崇拝するのか』のなかで指摘した歴史的背景です。
スプートニク・ショックに動揺した当時のアメリカは、ソ連の画一的な全体主義に打ち勝つために、民主主義的な「個人の自由な発想」を国家戦略として掲げました。その要請に応えるかたちで、心理学者たちが「創造性」を、それまでの「一部の天才による神秘的な才能」から、訓練によって誰もが発揮できる「測定可能なスキル」へと再定義(発明)したのが「クリエイティビティ」という概念の現代的な用法の始まりだとされています。
ここでまず開発の対象となったのは、主に研究開発に取り組むエンジニアたちですが、その一方で、ワーカーの「クリエイティビティ」は、広告やマーケティング戦略においても重視され、さらに人事や組織ガバナンスという観点からも採用されるキーワードになっていきます。
これと同じようなことが、「デザインシンキング」ということばを通じて起きたと考えるなら、「デザインシンキング」がワーカーに開発を求めた、「深いインサイトを発掘し取り出す能力」は、必ずしもマーケッターだけに求められたわけではありません。
W:いわゆるデザインシンキングが流行った際に、そこから派生するかたちで「デザイン経営」なんてことばも出てきました。自分も当時、特許庁が行った「デザイン経営」に関するリサーチをお手伝いしたことがあって、そのなかでIDEOのトム・ケリーや、デンマーク・デザイン・センターのクリスチャン・ベイソンにインタビューさせてもらったのですが、ふたりが基本的には「デザイン」を「組織マネジメント」の話として語っていたのに対して、日本の企業経営者を相手に行ったアンケートでは、「デザイン」というものを「良いプロダクトをつくるために必要なもの」と考える人や、「顧客理解のためのツール」だと認識する人などが混在していたのを覚えています。
Y:ここはたしかに混乱するところなのですが、冒頭の4つの回路のところで話した通り、その混乱もある意味必然的に起きたことだと言えます。というのも、トム・ケリーやクリスチャン・ベイソンなどが語ってきた「デザイン」は、部門ごとに工学的に適用できる概念ではなく、そもそもそうした工学的な組織観が失効してしまった後に、いかに包括的に組織や事業・プロジェクトを運営することが可能かを問うものだったからです。
先ほどお話ししたように、企業というものが直面している課題が、これまで工学的・機械論的に編成されてきた近代企業の統治が成り立たなくなってしまったところから派生しているのだとすれば、現在の会社が直面している問いは「どうやったら儲かるのか」という戦術・戦略的なものを超えて、「会社とは何か」というある意味哲学的なものになっています。いまとなっては、それと向き合うための処方として「デザインシンキング」というアイデアは提出されたと見ることもできるわけです。
加えて、そうした変化が、工学部品と見なされていた働き手の価値や定義のアップデートを求めるものだったことを思えば、「会社とは何か」という問いは、必然的に「働くとは何か」「働き手であるわたしとは何者か」というワーカーのアイデンティティをめぐる問いにまで派生してしまうんですね。
W:クリスチャン・ベイソンは、「デザイン経営」の反対語は「近代的経営」だと言っていましたが、そうだとするなら、近代的経営からデザイン経営への転換は、大袈裟に言えば、もはや文明史的な転換ですね。
物が売れない時代の企業
Y:デジタル化、グローバル化が、それまでの企業のモデル、つまり近代的経営を根底から変えてしまっているというのは、ベイゾン氏の言う通りだと思います。また、企業という存在が、どうにも身動きが取れなくなってしまっている状況の背景には、物がすでに行き渡ってしまった成熟した市場では、もはや商品の「機能」は売り物にならないといったこともあると思います。
W:というと?
Y:生活における「必要」や「欠如」を満たすための「機能」は、基本もういらないわけです。その代わりに人は「意味」や「価値」を消費に託すようになっていくんですね。
W:なるほど。
Y:こうなってくると難しいのは、企業側から「意味」や「価値」を押し付けても意味がないということです。成熟したマーケットにおいて、消費者はあるモノの「意味」や「価値」を、自分たち自身で発見し、決定したいという欲求を強くもっています。
わかりやすい例で言えば、昨今のK-POPに代表されるファンダム文化ですよね。そこでは、事務所が完成されたスターを一方的に供給するだけでなく、ファンがアイドルの些細な言動から関係性や物語を読み取り、考察し、あるいは二次創作を通じてその「価値」を自分たちで増幅させていくプロセスこそが熱狂を生んでいます。逆に言えば、企業側があらかじめ「これが感動するポイントです」「これが正解です」とガチガチに固めた価値を押し付けてしまうと、ファンが介入する余地、つまり「参加する楽しみ」が奪われたと、むしろ煙たがられてしまうわけです。
W:かつては一方向だった企業と消費者の関係が、双方向性をもつようになってしまったと。
Y:まさにそうです。若林さんと以前『ファンダムエコノミー入門::BTSから、クリエイターエコノミー、メタバースまで』という本を一緒につくったのも、まさにそうした「企業と個人の関係性の変化」に対する強い問題意識があったからこそですよね。企業はもはや一方的な支配者ではなく、ファンやユーザーとともに価値を醸成していくパートナーにならざるを得ない。そうした文脈で言えば、外部編集員の方々とともに制作する『WORKSIGHT』も、まさに同じような「協働」の取り組みと言えるわけです。それが何か目に見える成果を生んでいるかどうかは判断が難しいところではありますが。
企業統治の困難
W:最近見たポッドキャストに、シリコンバレーの保守系有力シンカーのひとり、カーティス・ヤーヴィンが出ていまして、そこでヤーヴィンは「歴史上人類はほとんどの期間を王政でやってきた」みたいなことを言っていたんです。加えて、「民間企業ってのはいまだに基本的には王政でしょ」とも言っていて、ちょっと驚いたんです。
Y:面白いですね。
W:企業の統治形態が、厳密に王政と言えるのかどうかはよくわかりませんが、とはいえ、企業が民主的に統治されているかと言えば、そんなことないのは明らかなような気もします。ヤーヴィンは、民主主義国家においてすら企業は王政のままなんだから、国の統治も企業に倣うような格好にして、大統領がCEOであるような体制にすればいいと言っていますが、それがいいのかどうか疑問もありつつ、議論としては面白い。
Y:2025年にアメリカで起きた大規模なデモは、たしか「No Kings」という標語のもと行われましたが、「大統領=CEO=王」という図式から見れば、かなり的を射ていたとも言えそうです。
W:たしかに。
Y:ヤーヴィンの話をどうこう論評できるほどの知識はもち合わせてはいませんが、アメリカの動向などを見ていると、GAFAMにNVIDIAとイーロン・マスクを加えた、いわゆる「マグニフィセント・セブン」が、もはや国家というものよりも上位の概念になってしまっているようには感じますよね。その意味で、「国家」に紐づくかたちで設定されてきた「市民」という存在よりも、「企業」に結びついた「会社員」のほうが、一個人のなかにおいても優位になってきてしまっているのかもしれません。仮にそうだとするなら、「会社員」という存在を、社会のなかにどう定位しうるのか、新しい考え方が必要になってきそうです。
W:「会社員」という概念に「市民」という概念を対置して、その重要性を語ることは不可欠だとは思う一方で、新自由主義化がますます進行する政治やビジネスのリアリティを考えると、「市民」という概念を盾にそれを食い止められる気はしません。
Y:自分が調べた範囲ですと、例えば香港出身の哲学者ユク・ホイは、現代のプラットフォーム企業は、単なる経済主体ではなく、技術を通じて特定の倫理や世界観を実装する「宇宙技芸の担い手」で、国家の統治原理とは異なる原理で社会を構造化する新たな「統治体」となったと語っています。そうしたなか、企業という組織体は、「人々の存在論的な居場所(home of practices)を構築する制度」として再定義され得ると語っています。会社員は、仕事の仕方、他者との関わり方、共同性の経験といった「生きられた世界(lifeworld)の建築家」となり、組織と社会の文脈翻訳者として機能する可能性を秘めているというんですね。
W:大手企業の正社員にはいい話かもしれませんが、ワーカーの非正規化、個人事業主化がどんどん進行するなか、大企業が社会構造を編成していくドライバーになっていくというのは、納得したくないところもありますね。
Y:たしかにそうなのですが、とはいえ、社会というもののなかにおける「企業」というものの影響力や存在の大きさを考えると、「社会が企業をいかにガバナンスするのか」ということと、「企業がその内部において『市民でもあるワーカー』をいかにガバナンスするのか」ということは、双方が入れ子になった政治的なイシューではあるので、企業がどこに向かって動いていくのかは、やはり注視すべきことだと思うんです。ユク・ホイの論点は、それに賛成するかどうかは別にしても、生活者の「存在論的な居場所」としての役割を企業に与えることで、企業というものそれ自体の「存在論的な居場所」を定位しようとしたという意味で注目すべきものだと思います。いずれにせよ、「企業の存在意義」をめぐるこうした問いは、2026年に、より活発になっていくような気がします。
W:ちなみに「エデルマン・トラストバロメーター」という世界的な信頼度調査の2025年版によると、日本では、政府・メディア・NGOと比べると、企業への信頼は48%と最も高いとされています。また「自分の雇用主」は、日本の組織で働くワーカーのなかで唯一信頼されている組織機関と位置づけられているとの結果も出ています。世界的に見ると、それでも信頼度は低いのですが、政府やメディアへの信頼が底なしの低さであるのと比べると、企業に対しては、愛憎半ばするというか、期待したい気持ちが少なからずあることは見て取れます。
Y:実際、企業は、生活に直結する存在でもありますから、しっかりしてほしいという気持ちは、どうしたってありますよね。そうした観点から第二次大戦後の企業のあり方を見直していくと、とりわけ1970年代以降の企業は、「統治の困難」にずっと直面してきたとも言えるんですね。つまり企業は、ずっと不安定な状態に置かれてきたわけです。
これは、グレゴワール・シャマユーという哲学者が『統治不能社会:権威主義的ネオリベラル主義の系譜学』という本で分析したことですが、70年代当時の経営者たちは、単なる不況だけでなく、工場でのサボタージュやストライキ、街頭での抗議運動といった「権威に対する反乱」に直面したことに深刻な危機感を抱いていたとされています。シャマユーによれば「民主主義の過剰」によって企業が文字通り「統治不能(Ingovernability)」に陥ったというわけです。
W:民主主義の過剰。企業経営の視点からすれば、たしかにこれは大問題ですよね。先のヤーヴィンの指摘の通り、企業と民主主義は、そもそも相性が悪そうです。
Y:シャマユーの指摘にならえば、企業の統治は、すでに70年代にはうまく立ち行かなくなっていますので、その後の企業は、どうやったらうまく会社が回るのか、ずっと試行錯誤を重ねざるを得ず、しかも利益を出し続けないことには会社を維持できませんから、よりシビアに生存戦略を検討せざるを得ませんでした。
もちろん、そうした試行錯誤が、社会やワーカーへの善意から出てきたものかといえば必ずしもそうではありませんが、それでも従来の管理や統治のやり方では、どうにもならないので、良さそうなアイデアなら何でも飛びつくことになります。
シャマユーはこれを、上からの命令で縛る「規律権力」から、労働者の主体性を巻き込んで自発的に競争させる「新自由主義的マネジメント」への転換だと指摘しています。つまり、ワーカーの「反乱」を鎮圧し再び統治可能な状態をつくり出すための、エリート層による意図的な「反革命」の技術として、新しい経営思想が導入されたわけです。
W:「反革命の技術」って、それだけで頭に血が上りそうなことばですが、とはいえ、資本主義経済の重要な主体である企業からしてみれば、そこで統治を手放してしまえば、企業としての存在理由もなくなってしまいますよね。であればこそ、できるだけ穏便に、ワーカーも社会も、できるだけみんながハッピーに過ごせるような工夫を重ねてこざるを得なかった、ということですか。
Y:ビジネスセクターが「人文知」に期待を寄せたことの背景には、それなりに切実な課題感があったのはたしかだと思います。世界の企業にとって大きなターニングポイントになったのが70年代だと言えるのは、60年代後半から公民権や環境問題、日本であれば公害問題などが社会の前面に出てきたことで、外部性というものに対する企業の責任が厳しく問われるようになったからです。
そこに世界的なオイルショックなどが重なることで、それまでの計画・命令・統制(command-control)による工業的統治モデルが破綻し、労使関係の軋み、生産性の停滞、ストライキや離職といった「管理できない労働者」の問題が深刻化したとされています。このとき、企業が外部からの批判をかわすために戦略的に採用したのが「ステークホルダー」(利害関係者)という概念でした。シャマユーは、これは批判者を「敵」として排除するのではなく、あえて対話のテーブルに着かせて議論に巻き込み、法規制や政治的な対立を骨抜きにするための、高度な「対反乱戦略」だったとしています。
W:「ステークホルダー」の語は、いまでは何やらいいことばとして流通していますが、それも元を辿ると企業のエゴから出た方便でしかなかったという。
Y:こういう話は、会社員である自分としても、どう腹落ちさせていいのかがわからなくて難しいですね。企業は、そもそも善意や倫理で動くものではないのですが、その企業を構成しているのは、自分と同じ市民であり、人間です。抽象概念としての「企業」を嫌ったところで、実際に自分が働いている「企業」には、いい人もいるし、経営者だって必ずしも極悪人というわけでもない。であればこそ、信頼したい気持ちはどうしたって生まれてくるのですが、とはいえマクロで見ると、企業というものが利益のためなら社会を壊すことも厭わない装置であることも否めません。
W:公害問題を通して、企業の社会的責任や倫理を強く問われるようになったのは、社会からするといいことだったのだとは思いますが、一方で、国のためだと思って必死に戦後復興から経済成長を支えた個別のワーカーにとっては、痛みをともなうものだったろうと思ったりもします。市民としての自分は、もちろん企業というものの残虐さに怒りを覚えたとしても、会社員としての自分や同僚たち、先達たちの功績を全否定することはできなかったのではないかとも想像します。自分のなかの「市民」と「会社員」が乖離し、引き裂かれてしまうようなこともあったのではないかと思うのですが、その分裂は、いまもずっと続いてる気がするんですよね。
Y:ほんとですね。であればこそ、企業もワーカーも、その「存在論的」な危機を乗り越えるために、人文知に救いを求めてきたということなのかもしれません。【後編につづく】
*後編は2026年1月7日配信
山下正太郎|Shotaro Yamashita WORKSIGHT編集長/コクヨ ヨコク研究所・ワークスタイル研究所 所長。2011 年『WORKSIGHT』創刊。同年、未来の働き方を考える研究機関「WORKSIGHT LAB.」(現ワークスタイル研究所)を立ち上げる。2019年より、京都工芸繊維大学 特任准教授を兼任。2022年、未来社会のオルタナティブを研究/実践するリサーチ&デザインラボ「ヨコク研究所」を設立。
若林恵|Kei Wakabayashi 黒鳥社/TIGER MOUNTAIN/WORKSIGHTコンテンツディレクター。『WIRED』日本版編集長を経て黒鳥社を設立。2025年には古書店「TIGER MOUNTAIN」をオープン。著書に『さよなら未来』(岩波書店)、『実験の民主主義:トクヴィルの思想からデジタル、ファンダムへ』(宇野重規との共著/中公新書)。訳書にジョン・バージャー『第七の男』(金聖源との共訳/黒鳥社)。最新刊に『会社と社会の読書会』(黒鳥社)ほか。photo by Kaori Nishida
【WORKSIGHT SURVEY #34】
Q:企業はもっと「人文知」を取り入れるべき?
企業やビジネスパーソンは、もっと「人文知」を取り入れるべきなのでしょうか? あるいは、これ以上は必要ないのでしょうか? 取り入れるべきだとするなら、どんな「知」をどのようなかたちで取り入れるのが望ましいのでしょうか。みなさんのご意見をぜひお聞かせください。
【WORKSIGHT SURVEY #33】アンケート結果
2025年、WORKSIGHTで最も読まれた記事ベスト10(12月23日配信)
Q:今後、WORKSIGHTでより多く読みたいのは国内事例?海外事例?
【海外事例】海外の事例はまだソースが限られているので、独自の取材で取り上げてほしい。
【海外事例】日本にいると情報が日本語に偏り、海外の情報が不十分だから。
【国内事例】色々な記事を読ませていただきましたが、読後も印象に残っているものは国内事例が多く感じました。
【国内事例】最近潰れた喫茶店跡地にいくつも中華料理店ができていたが、Google Mapにはまったく載っておらず、そこに見えているが認識できていないようなものを見てみたい。
【第5期 外部編集員募集のお知らせ】
WORKSIGHTでは2026年度の外部編集員を募集しています。当メディアのビジョンである「自律協働社会」を考える上で、重要な指針となりうるテーマやキーワードについて、ニュースレターなどさまざまなコンテンツを通じて一緒に探求していきませんか。ご応募お待ちしております。
募集人数:若干名
活動内容:企画立案、取材、記事執筆、オンライン編集会議(毎週月曜夜)への参加など
活動期間
第5期 外部編集員:2026年4月〜2027年3月(予定)
年間を通じて継続的に活動に参加していただける方を募集します。単発・スポットでの参加は募集対象外となります。
募集締切:2026年2月18日(水)18:00まで
応募方法:下記よりご応募ください。
次回1月13日は、これからの都市における空間の在り方を問うシリーズ企画「『場』の編集術」第4弾として、東京都狛江市にある「野口晴哉記念音楽室」を拠点に、音楽鑑賞会や対話の場を運営する「全生新舎」の主宰・野口晋哉さんへのインタビューを配信します。お楽しみに。