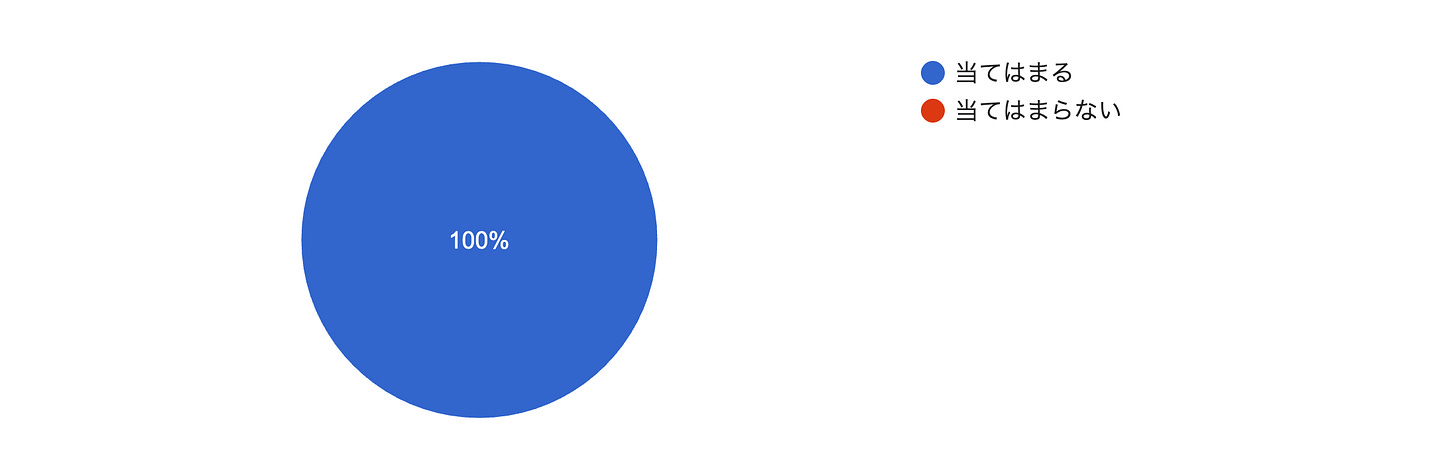同胞は死に、わたしは料理をする:パレスチナ人スターシェフが記録する"大地の味”
パレスチナ人としてエルサレムに生まれ、ロンドンのスターシェフとしてキャリアを重ねてきたサミ・タミミは、シェフの仕事を退いた現在もパレスチナ料理をつくり続ける。故郷が惨劇に見舞われるなか、その地で育まれた伝統料理と向き合い、記録する。その意義に迫る独占インタビュー。
屋外で食事の準備をするパレスチナの女性たち
photographs courtesy of Sami Tamimi
interview & text by Kei Wakabayashi
「パレスチナ、大地の味」サミ・タミミ
パレスチナの「マクルバ」。この料理の起源は13世紀にまで遡ることができるのだとか。この一皿は肉抜き
わたしは1970年代のエルサレムで育ちました。当時もいまも台所は女性の聖域です。強烈な個性をもった女性たちが、食材の買い出しから調理までのすべてを行います。パレスチナの伝統料理は、女性を通じて何世代にもわたって伝承されてきました。受け継がれたレシピは滅多に変更されることはありません。そのことは、多くのパレスチナ人が、故郷を離れることを余儀なくされてきたことを思えば、とても重要な意味をもっています。料理はただ腹を満たすためだけのものではなく、文化を生かし続け、伝統を守るという意味において、とても重要なのです。
わたしは子どもの頃から料理に魅せられてきました。台所に潜りこんでは「友だちと外で遊んでおいで!」と追い払われたものです。言うまでもなく、パレスチナの社会は古いタイプの男性優位社会です。であればこそ、男がシェフになるなんていうことは、誰にとっても思いもよらぬことでした。16、17歳の頃に、父に「シェフになりたいんだ」と告げると、「気が狂ってるのか?」と言われたものです。わたしの実家は運送業を営んでいましたから、誰もが当然わたしも家業を継ぐものと思っていました。わたしはシャイで痩せっぽちの子どもでしたが、ひどく頑固でした。シェフになるためには、伝統的なルールを破らなければなりませんでしたが、親の言うことを聞くこともなく、エルサレムでシェフとして働き始めました。
わたしが育った頃のエルサレムは、イスラエルがエジプトに侵攻した6日間戦争のあとで、もちろん緊迫していましたが、それでもユダヤ教徒とキリスト教徒とイスラム教徒とが、それなりに調和をもって暮らしていたように思います。多様性のあるコスモポリタンで食事も多様でした。一種のフードハブだったのです。お互いの料理を食べ合うようなことは、ほとんどなかったと記憶していますが、それでもみな同じ場所で食材を買っていました。いまにして思えばナイーブだったのかもしれませんが、世の中がきっとよくなるといった雰囲気が当時はまだあったのです。わたしが故郷を離れ、ロンドンへと旅立った1997年時点でもそうでした。ところが、やがて徐々にキリスト教徒がこの地を離れていき、次第にイスラエルの文化に街が染まっていきました。それまで保たれていたバランスが崩れていったのです。
パレスチナの路地は、かつて多様な食に溢れていた
わたしはエルサレムで何軒かのレストランで働いたのちに、テルアビブのレストラン「Lilith」で働くようになりました。そのレストランは、カレン・ハンドラー・クレマーマンというカリフォルニア出身の女性がやっている店で、わたしはヘッドシェフを務めたのですが、彼女は、地の素材を使ったグリル料理を得意としていました。彼女がわたしたちの故郷の食材を、思いもよらぬやり方で扱うのを見て、目をみはらされました。同じ素材でも、異なるテクニックを用いることで、違った料理を生み出すことができる。それはわたしにとって、大きく視野が広がる体験でした。
その後、わたしはロンドンに移り、「Baker & Spice」という店で働いたあと、友人のヨタム・オットレンギと「Ottolenghi Deli」という店を始めました。わたしたちがそこで提供した料理は、中東のフレイバーを少しだけまぶしたフュージョン料理で、パレスチナのルーツを押し出すことはしませんでした。というのも、正直政治には巻き込まれたくなかったからです。わたしはただ仲間と、おいしい料理を提供したかっただけなのです。けれども、ゆっくりと確実に、状況がそれを許さないようになっていきました。そして2023年の10月7日以降、状況は一変してしまいました。
一介のシェフが政治について語るなんて、自分でもおこがましいことだと思うところもないわけではありませんが、わたしは料理というものを通じて、自分なりに語れることがあると感じるようになってきました。料理は、必ずしも人を連帯させることはできませんが、それを通して、わたしたちの話や歴史に耳を傾けてもらうことはできます。料理と無関係に生きている人はいませんから、誰もが我が事として感じることができるのです。ですから、パレスチナの料理をせっせとつくってはインスタグラムに投稿しています。同胞が三等国民として扱われながら毎日死んでいくなか、わたしは日々、パレスチナの伝統料理をつくっています。
元々ひとつの地域でしたから、パレスチナの伝統料理は当然、ヨルダンやレバノン、シリアの料理と似ています。フムスやファラフェルといった有名な料理は共通しています。そうしたなか、パレスチナ料理の特徴といえる何かがあるとすれば、季節の感覚、そして採集ではないかと思っています。パレスチナでは、近隣で採ってきた葉っぱやキノコを使って料理することが多いのです。より大地に近い料理なのです。レバノンの料理が優雅で柔らかいのに比べて、パレスチナの料理は野趣に富み、力強いのです。




左上から時計回りに:マクルバ/スフィーハ。パレスチナのラムを用いたパイ/ナスやトマトをトッピングしたフムス/ワラク・イナブとズッキーニ。ブドウの葉に詰め物をした、サミの幼少時代のお気に入り
中東の歴史において、料理は非常に大きな役割を果たしてきました。オスマン帝国によって支配されていた時代でも、料理を通じて、食材や調理技術が、盛んに交易されていました。ですから、シリア料理はイランの影響が色濃かったり、レバノン料理はトルコの影響が強かったりと、その関係はかなり錯綜しています。それこそスペインのアンダルシア地方には中東料理の影響が見られますし、逆にアンダルシア料理の影響を中東で見ることもできます。
戦争や占領の最中であっても、人びとは、祝宴を開いて食事を振る舞い、たくさんの人をもてなし、そのなかで料理を交換し合い、ときには料理人を交換し合いさえしたといいます。そうしたことを何世代にもわたってやってきたのです。
パレスチナを代表する料理は何かと聞かれた際に、わたしが「マクルバ」と答えるのは、こうした理由からでもあります。それは単にパレスチナを象徴する味だという意味だけではありません。マクルバは、常に身近にある材料からつくられるものですから、まず安価ですし、ひとりで食べるものでもありません。テーブルの真ん中に置いて、みんなで分け合って食べる。それは、友愛、もてなし、絆の象徴であり、手間がかかるという意味で、献身の象徴でもあります。
わたしはこれまで3冊のクックブックを出してきました。そのうち2冊が故郷の伝統に関わるものですが、わたしたちの錯綜してきた歴史を思えば、料理を記録しておくことには大きな意味があります。同じ名前の料理であっても、シリアとパレスチナでは内実が異なることも少なくありません。加えて世の中には、自分の都合のいいように歴史を書き換えようとする人もいます。
現在の状況が、すぐによくなるようなことはないようにも思いますが、きっとよくなるという希望は失ってはいないつもりです。であればこそ、自分たちの文化や伝統がどういうものであるのか、きちんと手がかりを残しておきたいのです。それを失ってしまえば、そもそも生き延びる意味を失ってしまいかねませんから。
サミ・タミミ|Sami Tamimi シェフ。エルサレム生まれ。17歳のときにエルサレムのブティックホテル「Mount Zion」でポーターとして働き始め、すぐに朝食担当シェフに昇進。以後レストランやカフェ、病院の厨房を経て、21歳でテルアビブの有名レストラン「Lilith」で料理長を務める。1997年にロンドンに移住し、2002年にヨタム・オットレンギと「Ottolenghi Deli」をオープン。市内に5つのデリと2つのレストランを含む多数の店舗を展開する。これまで『Ottolenghi』『Jerusalem』『Falastin』の3冊の料理本を執筆し、ジェームズ・ビアード財団の国際図書賞を含む多くの賞を受賞。https://www.sami-tamimi.com
*『WORKSIGHT[ワークサイト]23号 料理と場所 Plates & Places』(2024年5月15日発行)より転載
【WORKSIGHT SURVEY #38】
Q:最近、パレスチナの文化に直接触れたことはある?
サミ・タミミ氏は、パレスチナ料理独自の「大地の味」を記録し、発信し続けることで、パレスチナの文化・伝統を人びとに届けようと試みています。あなたはここ数年のあいだに、料理に限らず、音楽や詩など、パレスチナの文化に直接触れる経験をしたことはありますか。触れたことがある方は、どのような文化に触れましたか。触れたことがない方は、今後どのような文化であれば触れてみたいと思いますか。みなさんのご意見をぜひお聞かせください。
【WORKSIGHT SURVEY #35】アンケート結果
庭師のように考えよ:ブライアン・イーノと考えたストリートデザインの新原則(1月8日配信)
Q:庭師の比喩は、建築家以外の仕事にも当てはまる?
【当てはまる】フリーマーケットを庭師の比喩に当てはめられないだろうか。例えば駅の側や公園などにフリマで売り買いされた物を許可を得て一時的に展示する展示棚を作成する。見る人はこんなものが近所で売り買いされてると知れて楽しいし、フリマ熱が高まって不用品が減ったり、展示された人の意識が高まったり、段々面白いものが出展されるようにならないだろうか。
『WORKSIGHT[ワークサイト]23号 料理と場所 Plates & Places』
photograph by Hironori Kim
cover illustration by Machiko Kyo
書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]23号 料理と場所 Plates & Places』
どんなにグローバリゼーションが進もうと、料理は「その時/その場所」でしか味わえない。どんなに世界が情報化されようと、「食べること」はバーチャル化できない。料理を味わうという体験は、いつだってローカルでフィジカルだ。歴史化されぬまま日々更新されていく「その時/その場所」の営みを、23の断章から掘り起こす。WORKSIGHT史上、最もお腹がすく特集。
◉エッセイ
#1「サフラジストの台所」山下正太郎
#2「縁側にて」関口涼子
#3「バーガー進化論」ジェイ・リー/ブルックス・ヘッドリー
#4「ハイジのスープ」イスクラ
#5「素晴らしき早餐」門司紀子
#6「トリパス公園の誘惑」岩間香純
#7「パレスチナ、大地の味」サミ・タミミ
#8「砂漠のワイルドスタイル」鷹鳥屋明
#9「ふたりの脱北者」周永河
#10「マニプールの豚」佐々木美佳
#11「ディストピアの味わい」The Water Museum
#12「塀の中の懲りないレシピ」シューリ・ング
#13「慎んで祖業を墜すことなかれ」矢代真也
#14「アジアンサイケ空想」Ardneks
#15「アメイジング・オリエンタル」Go Kurosawa
#16「旅のルーティン」合田真
#17「タコスと経営」溝渕由樹
#18「摩天楼ジャパレス戦記」佐久間裕美子
#19「石炭を舐める」吉田勝信
#20「パーシャとナレシュカ」小原一真
#21「エベレストのジャガイモ」古川不可知
#22「火光三昧の現場へ」野平宗弘
#23「収容所とただのピザ」今日マチ子
◉ブックガイド
料理本で旅する 未知の世界へと誘う33冊のクックブック
書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]23号 料理と場所 Plates & Places』
編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)
ISBN:978-4-7615-0930-9
アートディレクション:藤田裕美
発行日:2024年5月15日(水)
発行:コクヨ
発売:学芸出版社
判型:A5変型/128頁
定価:1800円+税