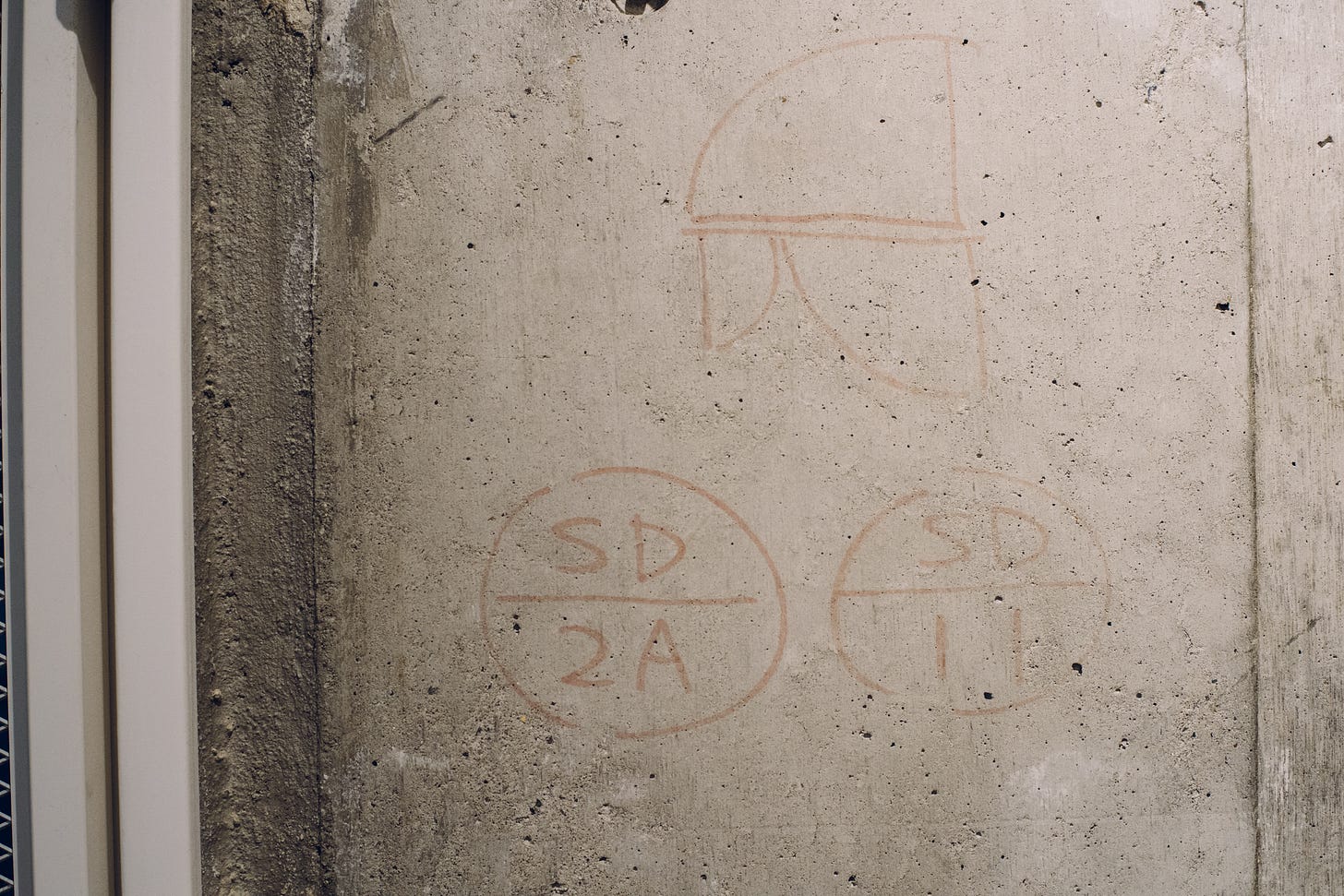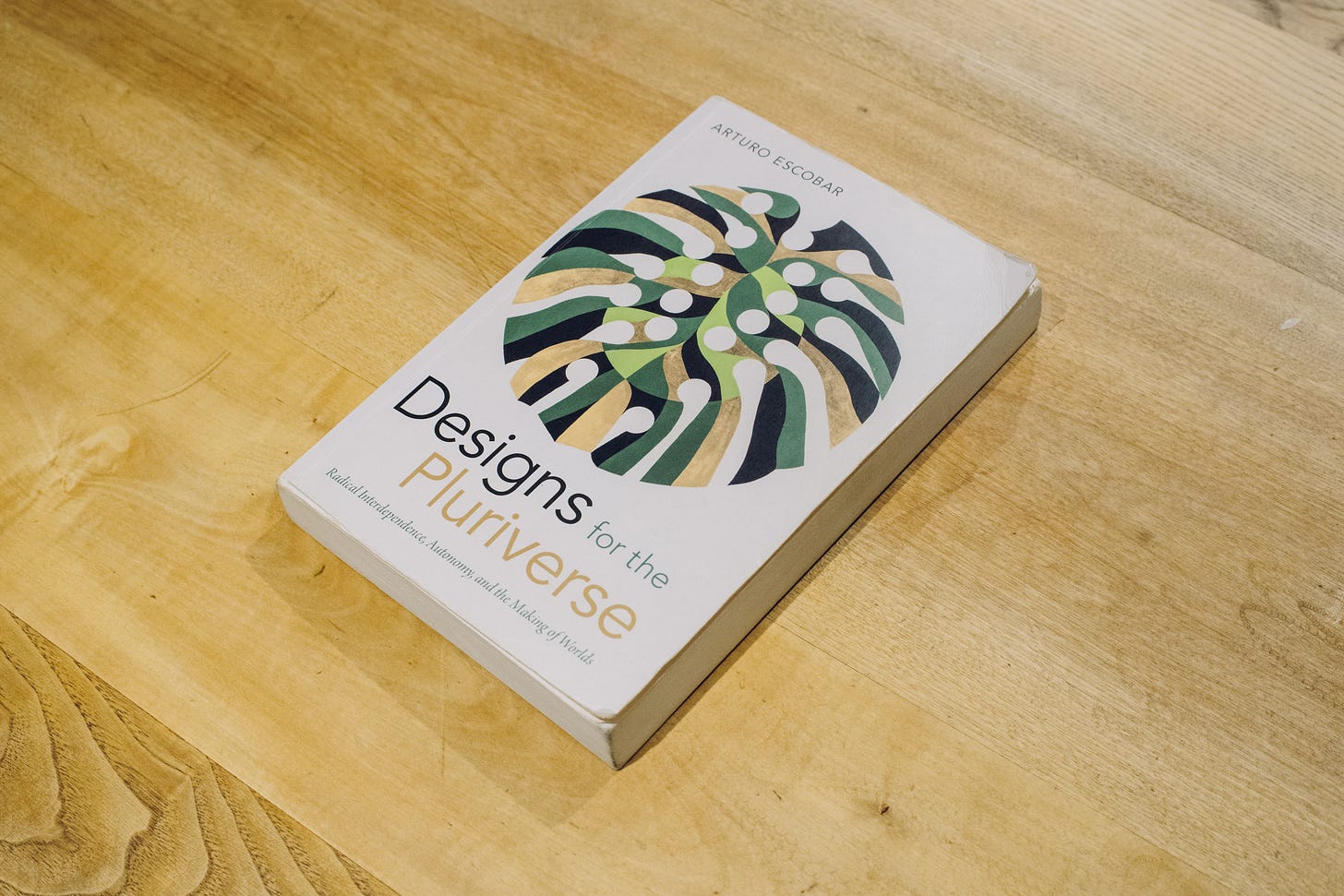多元世界・サパティスタ・水俣:A・エスコバルに学ぶ「デザイン」の新たなディシプリン
人類学の立場からデザインの再構築を図ったアルトゥーロ・エスコバルの著書『Designs for the Pluriverse』。2018年に発売され、世界的な注目を集めた同書の日本語翻訳版が今年2月、ついに発売を迎えた。エスコバルとは何者で、タイトルにも含まれる「Pluriverse(多元世界)」とは何を指すのか。翻訳者のふたりに尋ねた。
コロンビアの人類学者アルトゥーロ・エスコバルの『Designs for the Pluriverse:Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds』は、家父長制資本主義近代を真正面から批判し、ひとつのモノクロームな世界をつくるためではなく、各地域から出発した自治=自律のためのデザインのあり方を提示し、新たな文明への移行をわたしたちに呼びかける。デザインをはじめとするあらゆる「つくり手」の必読本、その日本語訳である『多元世界に向けたデザイン:ラディカルな相互依存性、自治と自律、そして複数の世界をつくること』(ビー・エヌ・エヌ)がついに出版された。監修を務めた大阪大学人間科学研究科教授の森田敦郎さんと、翻訳を務めたPoieticaの奥田宥聡さんに本書を解説してもらった。
interview by Shotaro Yamashita / Teruka Sumiya / Kei Wakabayashi
text & edited by Kei Wakabayashi
photographs by Shunta Ishigami
森田敦郎|Atsuro Morita 大阪大学人間科学研究科教授/Ethnography Lab, Osaka 代表。人類学者。テクノロジー・社会・環境の関係をエスノグラフィの手法を通して研究してきた。特に、日々の暮らしが環境・気候危機といかにつながっているのかを、物流、エネルギー、生産などのインフラストラクチャーに注目して理解しようとしてきた。工藝をモデルに循環型モノづくりを目指すパースペクティブの理念に共感し、ファブビレッジ京北のラボ事業に参加。「つくること」を通して、暮らしを支えるテクノロジーと環境の関係を探究するクリティカル・メイキングの実験も行っている。
奥田宥聡|Hiroto Okuda 合同会社Poietica共同代表。1998年生まれ、京都工芸繊維大学博士前期課程デザイン学専攻在学中。学部時より京都のNPO法人にて企業におけるソーシャルイノベーションのための新規事業領域探索に3年ほど携わる。Kyoto-design-labのリサーチアシスタントやフリーでのデザインリサーチの業務を経てPoietica設立。デザインリサーチやプロトタイピングの方法論を活用した事業開発や作品制作に携わる。
エスコバルとは何者か?
──まず、著者のアルトゥーロ・エスコバルとはどういう人物か教えていただいてもいいですか。
森田 エスコバルは人類学業界ではすごく有名な人です。わたしは1999年に大学院の途中で移籍して人類学を始めましたが、その前に、エスコバルの著作『Encountering Development:The Making and Unmaking of the Third World』が出版されていて、2022年に日本語にも翻訳(『開発との遭遇:第三世界の発明と解体』、新評論)されましたが、普通に授業で必読文献になるくらい、当時から人類学業界の誰もが知っている人でした。
エスコバルはもともとミシェル・フーコーの思想などに基づいて批判的に開発研究を行ってきたとても理論的な人であると同時に、コロンビアのアフロ系住民の人たちと共に社会運動を実践する人でもあります。「世界経済フォーラム」の対抗組織として、「世界社会フォーラム」という社会運動の世界的な連合体があり、その共同創設者のひとりでもあるのですが、ここに日本から、水俣運動とも関わりがあった栗原彬さんという有名な社会学者が参加されており、その縁でエスコバルは日本の研究者とも交流がありました。
そうした経歴を踏まえると、エスコバルが「デザイン」と関係があるとは、アメリカの人類学者含めて、実は誰も考えていなかったんです。わたしが『多元世界に向けたデザイン』の原稿を初めて読んだのは、2013年にカリフォルニアでの会議に参加したときでしたが、その会議にエスコバルも来ていて、開発に関する批判理論的なトークをするのかと思ったら、この本の原稿が回ってきて、読んでくれと言われ、会場のみんなが驚いたんです。「実はここ数年、授業ではデザインを担当しているんだ」と言い出して、ビックリしたんですよね。
──なるほど、『開発との遭遇』からは、20年近い時間が経っているということですもんね。その間に一種の転回のようなものがあったということなのでしょうか。
森田 エスコバルは、2008年にもう1冊『Territories of Difference:Place, Movements, Life, Redes』という本を出していて、その本はコロンビアのアフロ系住民の社会運動に関するものなのですが、彼が2013年に言っていたのは、そこで一区切りがついたということでした。それに加え、彼はもともと化学工学のプラントのデザインや経済開発のプランニングを学んでいて、ポスドクのときに、この本にも出てくるテリー・ウィノグラードやフェルナンド・フローレスなどのカリフォルニアの1980年代のサイバネティックスの研究にもかなり触れていたらしく、そこに原点回帰していったのかなということのような気がします。
デザイン思考以後の「デザイン」
──そうした前提を踏まえて、『多元世界に向けたデザイン』がどういう本か簡単に教えていただけますか。
森田 簡単に、ですか(笑)。まず、この本は、基本的には人類学の立場からデザインを再構築することを試みる本です。ヴィクター・パパネックの『Design for the Real World:Human Ecology and Social Change』(邦題『生きのびるためのデザイン』、晶文社)をモチーフにしています。つまり現在の破壊的で、消費主義的な産業や社会、テクノロジーのあり方を変えていく、持続可能性のためのデザインを構想しようということです。パパネックは、当時の適正技術運動という流れのなかでガンジーやインドの在来技術を再評価するというのをモチーフにしていましたが、エスコバルは、この本では、南米の社会運動の戦い方に基づいて、デザインのあり方を再構築しようとしています。
──デザインということに関して言えば、この10年くらい「デザイン思考」なんていうことばがもてはやされ、ある時期からそれも飽和してしまった感じもしますが、そうした流れと関連で見ると、どのように位置付けられるのでしょう。
森田 デザイン思考との関係で言うと、本来的にはデザイン思考のなかにも多様な流派や出自、アプローチがあったはずですが、この間流行ったのは、ネオリベラルなデザイン思考で、ことばは悪いですが、かなり手早くソリューションを得るという薄っぺらな感じになってきてしまった感はあります。そうしたデザインのありように対しては、エスコバルはかなり批判的です。その一方で、デザイン思考が基盤にしていたデザイン理論については、かなり好意的なのではないかと思います。
エスコバルは『多元世界に向けたデザイン』の前半部分では、デザイン思考の背後にある膨大なデザインの蓄積や議論をレビューしています。そこには資本主義的なソリューショニズムに向かう流れも強くある一方で、もっとラディカルに問題を問い直す可能性も潜在的にあったと、流行化してしまった「デザイン思考」に覆い隠されてしまったデザインの批判的なポテンシャルを改めて評価し直しています。
──エスコバルがそこで語るデザインは、例えば「デザイン思考」がそう喧伝していたように、企業のソリューションとして活用していくようなことができるものなのでしょうか。
森田 この本自体の主要な意図は、ディシプリンとしてのデザインの理論的な基盤をよりラディカルな方向に向けて再構築することにあります。ここで言う「ラディカル」は、物事を考える上での基本的なベースラインとなる視点を、南米の先住民運動や都市の社会運動、労働者運動などに置くということ意味です。
ですから、どうやって実践に移せばいいのかがわからない、どうやって具体化したらいいかがわからないといった批判は、刊行当初から実はあります。その一方で、この本が、とりわけアメリカのデザインスクールのデザイン基礎論のような初級のコースの教科書として、急激にとり上げられてもいまして、それはやはり、この本がデザインというものを広範にレビューしつつ、持続可能性の問題や、先住民と開発の問題、フェミニズムの問題といった、極めて現代的な問題にしっかり立脚してデザイン理論を再構成しているからなのだろうと思います。
プルリバース=多元世界という構想
──この本の重要なコンセプトである「プルリバース」というのはどういうものとして考えたらいいでしょう。巷で言われる「多様性」と何が違うのか、という。
森田 この「プルリバース」が、言うまでもなく本書のキモでして、それが本書が広く受け入れられた理由のひとつでもあります。「プルリバース」の概念自体は、人類学や科学技術論のなかで、ブルーノ・ラトゥールや彼の周辺の研究者たちが過去20年ぐらいかけて行ってきた、いわゆる「存在論的転回」をめぐる議論のなかから派生したものです。
例えばエドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロは、文化は多様だけれど世界はひとつであり、その唯一の世界の客観的な姿は西洋の科学だけが解明できるという、従来の西洋の考え方を批判しました。南米先住民の世界では、自然がむしろ多様なものとしてあり、生活の形式=フォームとしての文化はひとつであるとして、自然と文化の多様性の関係を逆転させた「多自然主義」という概念を提唱しています。それを受けて、ラトゥールやイザベル・スタンジェールが、西洋科学だけが明らかにすることができるひとつの世界に対する感想文みたいなものとして多様な文化があるという考え方は、本質的に植民地主義的であると指摘しています。科学者の活動の詳細なフィールドワークに基づいて彼らは、物理的な世界もまた、テクノロジーや科学実験や科学論文によってさまざまにかたちづくられており、物質的な世界のほうにも多様性があるという議論を展開しています。
つまり、わたしたちが科学を基盤につくり出してきた世界と、南米先住民がつくり出してきた世界というのは、単に考え方が違うというだけではないということです。物質的・生態学的な観点から、実際にどんな環境がつくられ、そこからどんなテクノロジーが生まれ、それが地球システムにどのような影響を与えているかというところまで含めて考えると、それぞれの文化において、物質的にも多様なリアリティがつくり出されていると考えられるわけです。「プルリバース」とは、簡単に言えば、そういう考え方です。
さまざまな実践によって、世界あるいはリアリティそのもの、現実そのものも多様につくられている。そうしたなかで、わたしたちはひとつの世界ではなく、複数の世界が常に創発しながらオーバーラップして存在している世界に住んでいる。そうやって折り重なって存在している多様な世界の関係性、つまりポリティクスを考えなきゃいけないというのが大筋の議論だと言えるかと思います。
──わかるようなわからないようなところですが、逆に「これはプルリバースではない」といったものって何でしょう。「プルリバース」という概念に関するありがちな誤解、と言ってもいいのですが。
奥田 デザイン寄りの話になってしまいますが、書籍のタイトルにある「デザイン」の語が、原題では「Designs」と複数形になっているところは、無視されがちですが案外重要かもしれません。本書を一読された方のなかには、いわゆるバナキュラー建築みたいなものや、土着的な知恵の利用といったことを思い浮かべられる方も多いかもしれません。もちろんそうした在来知を使った実践自体を、エスコバル自身も特に棄却してはいないのですが、複数形のデザインには、科学技術やインフラストラクチャー自体が存在論的に、わたしたちが認識し得ないレベルで自分たちをつくり直している、つくり替えていることを深く理解することを促す意図があるのではないかと感じます。
実際、本の後半でエスコバルは、そうしたインフラストラクチャーを変えていくためのアイディアをいくつか提示しています。例えばコンピューターひとつを取っても、それはわたしたちの生活をかたちづくっているインフラストラクチャーとなっていますが、それがいかにわたしたちをつくり替えてしまっているのかを検討せぬまま、ただ在来的な知識を使えばいい、ローカルな実践をすればいいということになってしまうと、書籍の意図とはかなり異なった理解になってしまいそうです。
サパティスタとミナマタをつなぐ
──先住民という話が出てくると、とりあえず頭に思い浮かぶのがアマゾンの奥地に住んでいるような人たちだったりします。そうした人たちは、ある意味純粋な存在としてロマン化してしまいがちですが、実際にはスマホを使っていたり、お寿司を食べていたりするわけですよね。
森田 わたしの教え子のひとりがアマゾニアの先住民の研究をしていますが、実際、お寿司屋さんの2階を拠点にフィールドワークしていました(笑)。
現在の、特にエスコバルが始めたといってもいいような先住民研究の国際的な流れのなかでは、先住民を「孤立した他者」ではなく、同時代の開発や圧制に対して戦っている、あるいは気候変動に抗してアマゾニアを守っている、いわば社会運動のフロンティアに立つ存在として理解する方向にシフトしてきています。そもそも「プルリバース」の概念自体がメキシコのサパティスタたちのことばから来ているんです。サパティスタ解放戦線に「多くの世界がフィットするひとつの世界を求める」というの有名な宣言があるのですが、これがまさに「プルリバース」という概念の根幹にある発想ですから、『多元世界に向けたデザイン』は、端的に言ってしまえば、サパティスタの立場からデザインを再構築しようということなんです(笑)。
──それこそデヴィッド・グレーバーも『民主主義の非西洋起源について:「あいだ」の空間の民主主義』(以文社)で「サパティスタの出した答え──革命とは国家の強制的装置を奪い取ることだと考えるのをやめて、自律的コミュニティの自己組織化を通して民主主義を基礎づけなおそうという提案──は、完璧に有効である」と語っていましたが、サパティスタは、実際何がすごいんですか。
森田 従来の社会運動や共産ゲリラの蜂起というのは、政権を取ることで上から社会を変えていくという闘争のかたちを採ります。ボトムアップの運動ではあっても、最終的にはトップダウンで社会を変えることを目指しています。
それが1980年代には行き詰まってしまい、その後社会運動が新たなやり方を模索していたときに、サパティスタがチアパスで蜂起しました。蜂起したはいいのですが、首都であるメキシコシティに進撃するわけでもなく、戦い方がそれまでのやり方とはどうも違う。もちろんインターネットに対応し始めたといったこともありますが、サパティスタたちの特徴のひとつは、地域にもともとあった先住民共同体がもっている自律性を防衛して、それに基づいて社会を下からつくり上げ、そのために軍隊を組織して自律性を守るための解放区みたいなものをつくっていったところにあります。そういう意味では「自律」を目的とした運動で、かつ、その「自律」もすごくローカルに根差している。中央集権的なクメール・ルージュのような組織とは真逆で、極めて分散的。そうしたアプローチで、国家の領域内に半自律的な領域をつくり上げたんです。そうしたアプローチが新しいラディカルなあり方として注目を集めたんだと思います。
──中南米でのそうした動きと現代の日本とを結びつけるにあたって、どんな結節点があり得るのでしょう?
森田 水俣の運動のことを冒頭でも少し触れましたが、エスコバルの思想は、日本の70年代の、特に水俣運動や作家の石牟礼道子さんの活動と強くつながっているように感じます。実際、石牟礼さんも「もうひとつの世界」や「もうひとつの現実」といったことばで、プルリバース的で存在論的な議論をしているんです。そして、その石牟礼さんの議論を社会と結びつけたのは、冒頭でも触れた社会学者の栗原彬さんや見田宗介さんといった方々で、見田先生は1990年代半ばの時点ですでに「存在論」を語ってもいましたので、実は『多元世界に向けたデザイン』の議論を、日本がすでに先取りしていたと言えそうなところもあります。
──面白いですね。日本の水俣をめぐる運動は、南米における先住民運動にあたる、と。
森田 水俣における議論が、現在のさまざまな問題を先取りしていたのは、実際そうだと思います。見田先生の存在論の議論もそうですし、石牟礼さんの紹介者であり、『逝きし世の面影』(平凡社)で知られる渡辺京二さんの社会運動の戦略というのも、いまから考えると、ものすごくオートノミスト的なんです。権力をもつという方向には行かないんです。
そのアプローチはサパティスタをある意味で先取りしていたといってもいいと思うのですが、渡辺さんや石牟礼さんが主導した有名な運動に「死民運動」というものがあります。これは主に石牟礼さんが考えたものだと思いますが、水俣の運動というのは死んだ民、つまり近代的な市民が権利を求める運動ではなくて、死んだ人や死んだ魚も含めた「市民ではない者」の運動なんだと謳ったんですね。
存在論的には「市民」の枠に入らない「死民」。で、「死民」と書かれたゼッケンをつけて、「怨(うらみ)」の字を白で書いた真っ黒なブラックフラッグをみんなで掲げて、お経を唱えながら行進するようなことをやっていたんです。これはもうまったく近代政治ではないですし、権力の奪取を目指したものでもない。完全にプルリバーサル・ポリティクスなんです。
人類学という土台
奥田 学生のときに、水俣で地域の方々と一緒に事業のアイデアを考えるワークショップに参加したのですが、そこで印象的だったのは、わたしが関わった人たちが、いかにしてその問題を語らずに新しい事業をするかに非常に腐心していたことでした。
もちろん語る人もいらっしゃったんですけど、「水俣病があったけれど、もう過去のことにして前に進みたい」という気分があったのだと思います。『多元世界に向けたデザイン』を訳しながら、過去を忘れてしまえるような新しいアイデアを考えることが、デザイナーの立場として果たして望ましいことなのかどうかということを、ずっと考えさせられました。
デザイン人類学という観点でいうと、人類学の研究自体が、常に物事の歴史的な背景や批評の視点を重視してきました。わかりやすい言い方をするなら、ブレーキをかける役割を、人類学の方法論や研究自体が担ってきたということだと思うのですが、デザインをもう少し異なるありようにしていくために、人類学のそうした機能を、具体的な現場での実践において用いることは、すぐに検討できることだったりするのではないかと経験的には感じます。
森田 たしかに『多元世界に向けたデザイン』は、デザインのそうした欠落を埋めるための基礎理論としても読めると思います。わたしは以前、建築の人たちと働いていたことがあって、建築とデザインを比べることが多いのですが、建築の世界では、建築だけでなく都市の歴史研究なども盛んで、歴史に学ぶという姿勢が強くあることは感じます。過去の名建築に学ぶといった観点も強くありますので、そういう意味ではディシプリンとして自分たちの過去の実践をベースにして、いま何をつくるべきかということを議論している印象があります。歴史、人類学、社会学、経済学、政治学をすべて取り込みながら、自給自足的なディシプリンになっています。その一方で、デザイン学科みたいなところは、そういうふうには成立してこなかったように思うんです。
過去のものを評価することは、プロダクトとかグラフィックの世界でも部分的にはありますが、全体としては、最適化を目指す工学的な考えが強く作動してきたように感じます。そうしたなか、デザインをする対象がどんどん広がっていったわけですが、その際に、自分がデザインをする対象がいったいどのような問題をもっているかを考えるためのツールがないままになってしまっています。建築であれば、過去の建築に学び、建築の歴史を研究することで建築上の問題を提起するような部分を、デザインにおいては、2000年ぐらいから、人類学が肩代わりしてきたという状況なのかもしれません。
さらに建築のアナロジーで考えると、建物を新築するにあたっても、基本的な姿勢として環境や町並み、そこに住んでいる人たちの生活に応じたものをつくらなくてはならないという理念的な制約があり、過去の例や人類学、地理学との対話のなかで、議論の仕方、アプローチの仕方のバリエーションも洗練されてきたように見えます。
『多元世界に向けたデザイン』における人類学の役割は、まさにそれなんです。人類学を使ってユニバーサルな解決策を押しつけるのではなく、それぞれの地域、場所の、さまざまな人びとの活動のなかで、人と環境がいかに相互作用しながら世界をつくり上げているかを捉える。多元性を捉えるための基本的なセンシビリティというか、考え方を提供する大きなメタレベルでの土台というふうに考えるといいのではないかと思います。
新しいデザイン・ディシプリンに向けて
──そうした多元的な世界のなかで物事が進んでいくとき、どうやって決断されていくものなのでしょう。意思決定というものには、どうしたってある種の権力が伴ってしまうのではないかとも思えるのですが。
森田 その点に関して言うと、『多元世界に向けたデザイン』はかなり政治的な本だと思います。この本の立場というのはすごくラディカルで、誰かの決定にみんなが従うという考え方自体、そういう組織のつくり方自体が持続不可能で、それに代わるようなあり方を考えなきゃいけないということがベースにあるのだと思います。
だからこそ南米の先住民が参照されるんですね。というのも、先住民の社会ではそのような意思決定をしないんですよね。日本でも例えば村の寄り合いとかだったら、わたしたちが考えるような意思決定はしません。そういった、現状とは違う意思決定の仕方を想像する。それを全員ができるかどうかはわかりませんが、デザインの思考の地平として、そうしたものを含んだ思考が必要だと思うんです。それがまったくないと、デザインがディシプリンとして非常に弱いものになってしまいます。
常々思うのは、工学や土木、建築、デザインは役に立つ実践的で企業的なものでもあるけど、それ自体がひとつの独立した、専門的で内的な倫理をもった活動でもあるということです。
デザインの研究でよく引用されるドナルド・ショーンという人は、都市計画と精神分析、精神科医と看護と教育をとり上げて「プラクティショナー」と呼び、彼らの知のあり方を研究したんです。そこではデザイナーと看護師は同じものとされています。
というのも、看護師も建築家も、ビジネスでどうやるかとは違う使命やビジョンがあるじゃないですか。建築家としての倫理観は、看護や教育のようなまったく商業的ではない別の価値に基づく実践とも共通している。わたしはデザインにも、本来的にそれがもともとあると思っていますが、資本主義の世界ではみんなが商売をしていかなくてはなりませんので、それが優先になってしまう部分は誰にもあります。
けれども、その一方で、自分のなかに商売とは異なる世界というのも必要だと思うんです。であればこそ、多くのプロフェッショナルスクールには人類学の科目があるんですよね。
看護では人類学が必修になっていますし、建築は、歴史や人類学的なことを絶えず学んできた。そうであるがゆえに、資本主義のロジックのなかで仕事をしながらも、それとは異なる世界を含んだ広い地平をもつことができています。そうした職業自身に内在する価値とか倫理を保つためにも、それぞれの分野にミニ人類学みたいなのが必要なのではないかと思いますが、デザインの世界では、その点はまだ制度化されていません。
『多元世界に向けたデザイン』は、デザインにおいて、そういったものを授けてくれる本だと考えていただけるんじゃないかなと思います。
次週4月16日のニュースレターは、シジュウカラのための不動産屋として巣箱を製作・販売する「BIRD ESTATE」のプロデューサー・工藤洋志さん、自邸のギャラリー「(HOUSE)」で巣箱のエキシビジョンを開催したmethod代表・山田遊さんのインタビューをお届けします。お楽しみに。