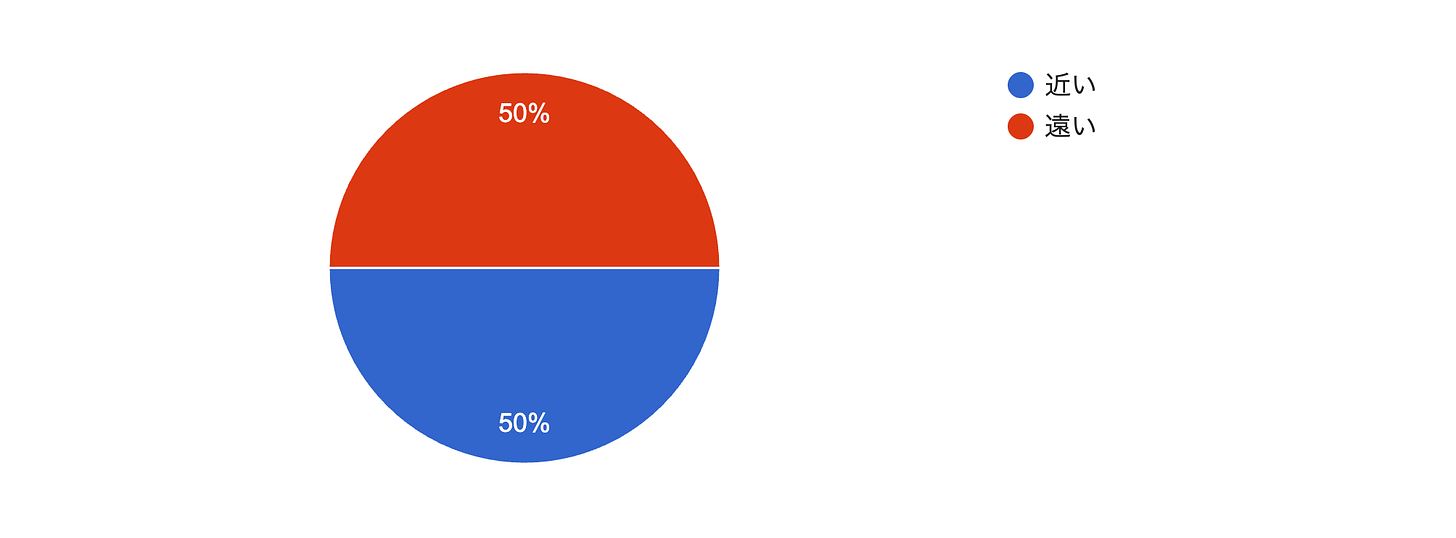音楽で世界を良くする方法:『ミュージックシティで暮らそう』書評【tofubeats特別寄稿】
音楽はいかに行政において政策化し、「公共化」することができるのか。その青写真を描き出した注目の書『ミュージックシティで暮らそう:音楽エコシステムと新たな都市政策』を人気音楽家・DJのtofubeatsが読み解く。
1970年に開催されたグラストンベリー・フェスティバルの第1回の光景 Photo by Robert Blomfield Photography/Getty Images
tofubeats 1990年生まれの音楽プロデューサー・DJ。2007年頃よりtofubeatsとしての活動をスタート。2013年に「水星 feat.オノマトペ大臣」を収録した自主制作アルバム『lost decade』をリリースソロでの楽曲リリースやDJ・ライブ活動はじめ、さまざまなアーティストのプロデュース・客演、映画・ドラマ・CM等への楽曲提供から書籍の出版まで音楽を軸に多岐にわたる活動を続けている。最新作は地元神戸のラップデュオNeibissとの共作「ON & ON feat. Neibiss」。2025年、主宰レーベル/マネジメント会社HIHATTは10周年を迎える。
https://www.tofubeats.com
https://hihatt.com
クラブと選挙カー
今日も参院選に向けた選挙カーが家の辺りを走り回っている。早起きする予定はなかったのに安眠は妨げられ、わが家の愛犬もきっとストレスを抱えているに違いない。それでもこの選挙カーは行政に認められており、細かな規制はあるにせよ完全に合法的な行為である。自分が警察に電話して、「うるさいので止めてください」と言ってもそんなことはしてくれないに決まってる。
音楽や音について考えるとき「人の耳を塞ぐことはできない」ということについてよく考える。好きでもない音を聞かされ続けることは非常にストレスだ。そこに壁があっても音はそれを貫いて耳に届く。自分たちがクラブやライブハウス、はたまた公共空間やそれに近い場所でランダムに音楽をプレイするとき、それが選挙カーのようにうるさく聞こえている人がいることに思いを巡らせる。
音楽による「騒音」と選挙カーとの違いは、実際に騒音騒ぎで警察がクラブに来るようなことがときおりあるということである。大阪で風営法による規制が厳しかった頃には、私服警官がガラガラのクラブにやってきたことがあった。福岡では横並びにさせられて写真を撮られたこともあった。出演したDJ4人がブースに立たされ、イベントの様子の証拠として警察に撮影されたのだが、なんとも不思議な気分であった。先日も韓国でDJをしていたら騒音騒ぎで警察がやってきたが、万国共通の景色にいっそ感動を覚えたほどである。音楽の仕事はただでさえ不安定なのに、こういうことがあるたびに、自分たちのやっていることが悪いことなのかと定期的に疑わさせられている。こんな仕事がほかにあるだろうか?
音楽ベニューは誰がために?
たしかに、まあ、人びとがたむろするクラブやライブハウスの前を横切るときにこんな場所が万人に受け入れられるわけもないわな、と思う瞬間もある。とはいえ本来はそういった騒音や選曲・演奏するジャンルを外の世界から切り離し、双方にとっての物理的・心理的安全性を保つために音楽ベニューというものはある。そのためにクラブやライブハウスの営業には許認可制度が存在する。クラブやライブハウスに遊びにきている人だって大半は昼間は真面目に働いているはずだが、そんな人びとがある意味自分を解放するための場所として音楽ベニューはある。そこでは大音量で音楽が演奏されていて、酒類が提供され、狭い空間で人と肩がぶつかっても、それが許容される。好きでない曲がかかったり、タバコを吸う人がいたりするかもしれないけれど、そうしたデメリットもある程度は甘受した上で楽しむのである。
つまりベニューがやっていることは、音楽にまったく興味のない人と音楽リスナーとの間に仕切りをつくることであり、もっと言えば、そこではジャンルやムードによって音楽をやっている人間も細切りにされる。そして、こうしたメリット/デメリットのバランスや、問題が発生した際の対処における「自治」のレベルは、個々のベニューによってさまざまだ。
これは、音楽を楽しむ人びとがこうした分類や、音楽というものの、ある意味での「公共性のなさ」を、自明の理として受け入れている証左でもある(ストリートミュージシャンのような例外もあるが)。音楽を愛するわれわれは、音楽が良いものであると漠然と直観的に考えているにもかかわらず、音楽が個人的な趣向に左右されるものであることを認めている。
であればこそ、世間の迷惑にならないよう注意を払いながら音楽を楽しむことになるのだが、そうやって頭を低くしていたとしても、どうしても下界と接触してしまうことはある。そしてときおり、音楽を楽しむ際に発生するデメリットを受け入れる前提のない人びとによって、音楽が中断させられてしまうことが起きる。ずっとその場所で営業を続けてきた老舗ベニューさえもが、新たに建った住宅に移り住んできた近隣住民などによって批判にさらされるようなことが、ときに起きたりする。
マンチェスターの伝説のクラブ「ハシエンダ」のエントランスでボディチェックを受けるコラバー Photo by Peter J Walsh/Peter J Walsh/PYMCA/Avalon/Getty Images
恣意的なボーダー
その一方で音楽が公共的なものとして使われるときもある。公営のイベントやコンサート企画では音楽は良いものとして扱われ、大物アーティストのスタジアムライブや音楽フェスは経済効果があるからなのか、街に音が響き渡っても問題になることがない。わたしが神戸市に提供した楽曲は、街中でランダムにプレイされた。そのおかげで文化奨励賞なるものも受賞した。
こちらの音楽には公共性があって、あちらには公共性がない──こうしたボーダーは、とりわけ音楽においてはランダムに、ときに恣意的に線引きされる。ここでの問題は、そのボーダーが明確には存在しないこと、さらにそのボーダーについてコミュニケーションを取る場が存在しないところにあるように思える。また、行政や一般市民の思う公共性・公益性というものと、音楽の現場の認識のズレについても考える必要があるだろう。
「音楽における公益性」と言われると、多くの人は市民ホールで行われるクラシックのイベントのようなものを思い浮かべるのかもしれないが、実際に現場で活動しているわれわれが特定の街のことを思い浮かべるとき想起するのは、だいたいがライブハウスやクラブ、そしてその店長たちの顔、そこで活動するローカルなアーティストたちである。
行政のバックアップを受けずに活動する彼ら/彼女たちがその街の発展やイメージに寄与していないとは到底思えないのだが、そう認識されることは滅多にない。少なくとも自分が地元・神戸市のイメージアップに貢献していたとするなら、それはこうしたネットワークの賜物にほかならないし、いずれ有名になって行政と関わることになるようなアーティストや組織にしたって、その活動は必ず草の根から始まっている。
「音楽監査」の新しさ
ようやくここで、『ミュージックシティで暮らそう:音楽エコシステムと新たな都市政策』という本の話となる。行政府に対して「音楽政策」の導入をサポートしてきた英国のコンサルタント企業「Sound Diplomacy」の創業者であるシェイン・シャピロの初著書の邦訳版のなかで、シャピロは「行政は音楽のイメージを活用しているにもかかわらず戦略的計画をもっていない」と喝破しているが、ここまで書いてきた話は、まさにその格好の実例だと言えないだろうか。行政は音楽を規制対象だと考えるが、その音楽産業から、知ってか知らずか多くのメリットを享受している。
Sound Diplomacyが世界のさまざまな都市で実施してきた「音楽監査」は、まさにそこに手を入れていく。「音楽監査」とは、その都市における音楽のもっている公益性を数字や効果として洗い出し、行政上の課題としてその問題を解決していくプロセスの第一歩となるものだが、この「音楽監査」にはふたつの新しさがある。
ひとつ目は、音楽全体がもつ公共性や公益性を明確に打ち出したことである。著者のシャピロは、音楽によって「自分が暮らす地域をより良く」することができ、音楽が「持続可能な開発・公正性の促進に役立つ」と信じている。また、音楽を水道水にたとえ、「音楽の繁栄は地域の繁栄」だとする。先ほどわたしは「音楽を愛するわれわれは音楽を良いものであると直観的に考えている」と書いたが、シャピロはこの命題に真剣に向き合い、客観的に音楽が社会的に「良いもの」であることを証明しようとする。これはリチャード・フロリダの「クリエイティブ都市論」をある意味彷彿とさせる理論でもあるが、シャピロはそれをさらに一歩進めて、特定の階級や属性の人びとにのみもたらされていたチャンスや恩恵を、「みんなのもの」として整理し直すことを試みる。それは、市民ホールでの公演や公共の教育プログラムにHIPHOPは含まれないといった偏見や、その背後にある人種問題や隠れた差別に目を向けさせることを促し、さらに音楽業界内における不均衡やバイアスをも同時に明らかにする試みだ。
ふたつ目の新しさは、音楽産業の再定義にある。これまで音楽というものは、文化行政のオプションやただの民間事業・個人事業として存在してきたが、シャピロはそれを、より広い「音楽エコシステム」の一部として新たに捉え直すのである。
ギグエコノミーの上に成り立っている音楽産業が一枚岩になるのは常に難しい。音楽業界で働く人びとには、音楽が個人的な趣味嗜好であるという認識が強くあり、ベニューにもそれぞれの自治がある。けれども、そもそも音楽に関わる施設はこうしたベニューだけでなく、楽器店、バー、音楽教室、練習スタジオなど多岐にわたり、これらが絡まり合って音楽はひとつの巨大な生態系を成している。それをエコシステムということばのなかに内包したのは見事である。また、音楽産業がひたすらグローバル化していくなかで、音楽産業をローカルな視点から定義し直しているのにも注目すべきだろう。
音楽は世界を良くするか
こうした観点から実施された音楽監査によって得られたデータ/実測値を手に、行政と手を取ってローカルな音楽エコシステムを整理し刺激していくことから生まれた、ロンドンやアラバマ州ハンツヴィル/マッスルショールズなどにおける実例の数々も実に興味深い。「音楽監査」を行うことで、行政側も客観性をもってボーダーを引くことができるようになり、是々非々で恣意的に引かれていたラインを規定し、一般化することで、業界側の負担をも大きく減少したのは素晴らしい成果だと言える。
その一方で、本書でも指摘されている通り、財務状況に余裕のある行政府にしかこうした音楽監査ができないといった問題はあるし、どういう数値をもって音楽の効果・便益を測るのかという問題に関しては一定の議論の余地もありそうだ。行政や監査側に適切なガイドラインがなければ結局これまでの是々非々での決定が繰り返されてしまう。そもそも音楽に効果や便益、ジャンル間の均衡が必要なのか、といった議論ももちろんある。
それでも本書は音楽を用いた地方行政のモデルケースとして有用なものには変わりはない。なにより音楽の力を軽んじないシャピロの姿勢には感銘を受けた。音楽がきっと世界を良くする鍵になると思っているすべての人にとって、何かのヒントになる1冊であるのは間違いない。
【WORKSIGHT SURVEY #12】
Q:行政府は「文化」にもっとコミットすべき?
音楽はときに「騒音」として扱われ、ときに「公共性」の象徴として重用されます。その線引きは恣意的で、行政の理解や関与の有無によって大きく左右されてきました。行政府は文化に対して、もっと積極的に関与すべきなのでしょうか。みなさんのご意見をお聞かせください。
【WORKSIGHT SURVEY #11】アンケート結果
ハンセン博士とつくられた「正史」:らい菌発見をめぐる国家と科学の物語(7月15日配信)
ハンセン病患者、回復者、その家族の個人史を記録してきた写真家・小原一真は、ハンセン病の原因となる細菌を発見した医師アルマウェル・ハンセンの足跡を辿るべく、ノルウェー・ベルゲンを訪ねた。そこで出会った科学史家は、ハンセン病発見の「正史」に隠された政治的意図を語って聞かせてくれた。
Q:現在「科学」と「国家」の関係は近すぎる? それとも遠すぎる?
回答理由(抜粋)
【近い】大学や研究機関の研究(への助成など)が、国家の政策によって削られたり、不要なものと論じられたりしている。企業への即戦力のための大学の再編や、国家のデジタルや軍事への課題解決のための研究機関の矮小化も、同様の問題であると思う。
【近い】ハンセン病は治る病になっても日本では国家の政策で隔離が続き、患者と家族への差別が続きました。国と科学の不作為だったのではと思います。
【遠い】国家はその遂行に科学的手段をつかわず、演繹的手段に頼っている。科学を斥候として、未来予測につかうべきだと思う。
【遠い】科学的に現象を理解するということと、それをどう政策に反映させ政府としてどう広報していくのかという点が混然としている。
次週7月29日は、インテリア雑貨ブランド「Mitate products」を立ち上げたプロダクトデザイナー・瀧口真一さんのインタビューを配信します。プロダクト第1弾としてリリースしたお香立て「Beaker incense stand」は、実験用ビーカーや金属棒など他社製のパーツを、ユーザー自身が購入・組み立てて完成させるプロダクトです。既存の製造業やメイカーズムーブメントとは一線を画す、そのユニークなものづくりの姿勢について伺います。お楽しみに。