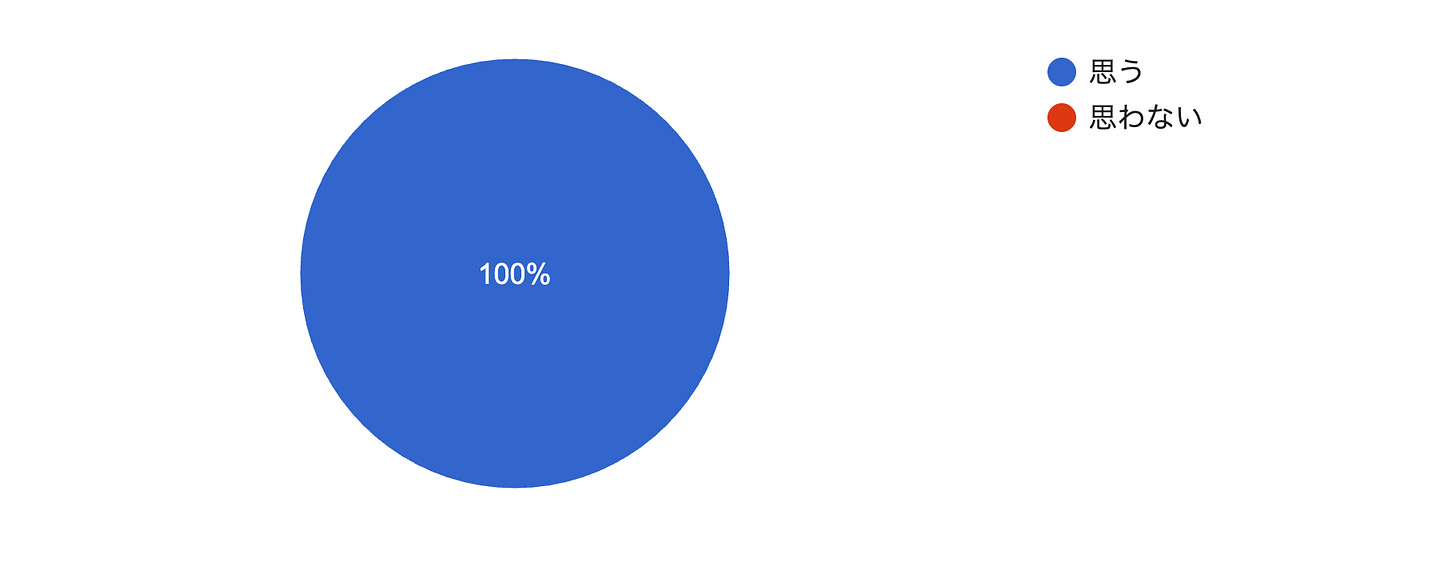ハンセン博士とつくられた「正史」:らい菌発見をめぐる国家と科学の物語
ハンセン病患者、回復者、その家族の個人史を記録してきた写真家・小原一真は、ハンセン病の原因となる細菌を発見した医師アルマウェル・ハンセンの足跡を辿るべく、ノルウェー・ベルゲンを訪ねた。そこで出会った科学史家は、ハンセン病発見の「正史」に隠された政治的意図を語って聞かせてくれた──国家によってつくられた科学のナラティブと、その語られざる真相に迫る。
ハンセン博士の実験室。らい菌の培養器やハンセン病患者にテストされた薬のボトルが現在も保存されている。ハンセン博士の没後50年を記念して1962年に完全予約制の博物館としてオープンした。ノルウェー、ベルゲン。2025年5月。photograph by Kazuma Obara
時間は不可逆的である。どの歴史も、時間の経過とともに歩みを進める。その経過をひとつの線として可視化するのが年表だ。歴史的事実が羅列されたそれは、多くの場合、無味乾燥で、詩的ではない。それがゆえに、年表は主観も感情もない真実の物語としてのもっともらしい威厳を帯びる。けれど、どの年表にも目的があり、主張がある。記される出来事が選定され、物語の始まりを決めた誰かがいる。
2025年5月、わたしはハンセン病医学の「始まりの地」、ノルウェー第二の都市、ベルゲンを訪れた。1873年2月28日、若きノルウェー人医師、アルマウェル・ハンセンはこの場所で、当時原因不明とされてきた不治の病、のちに自身の名前が病名に付けられたハンセン病の原因となる「らい菌」を発見した。それは後世のハンセン病政策に多大なる影響を与えた歴史の始まりである。しかし、科学的発見が行われた時点と、その発見が歴史的に意味をもつ時点は、往々にして異なる。歴史の創作は、時の権力や地政学に大きな影響を受けるのだ。では、その「発見」は、どのように語られ、誰の手によって歴史となったのか? そして、それはどのような影響を後世に与えてきたのか。科学史家でハンセン病研究を専門とするマグナス・ヴォルセット博士が語ってくれた。(ヴォルセット博士のインタビューをモノローグとして再構成した)
interview, text and photographs by Kazuma Obara
科学史の問いから始まった思索
アカデミックな科学史というのは、「わたしたちは、なぜいまのように物事を知っているのか?」「わたしたちの理解はどうやって形成され、どのように変わってきたのか?」という問いを扱います。
2001年、わたしが歴史学の修士課程の履修や指導教員を決める相談をしていた頃、偶然、ノルウェー・ベルゲンの「ハンセン病アーカイブ」がユネスコの『世界の記憶』に登録されたというニュースを知りました。それでわたしは思ったんです。関連する伝記的な本はすでに何冊か出ているけれど、19世紀のノルウェーにおけるハンセン病を歴史家の視点から体系的に研究した人はいないのではないか、と。
2005年、わたしは「19世紀ノルウェーにおけるハンセン病の歴史」に関する修士論文を完成させました。それから、しばらくはジャーナリストとして働き、さらにはバングラデシュで開発支援の仕事にも携わりました。しかし、自分の修士論文には「何かが欠けている」という感覚が自分のなかにずっと残り続けていました。そして、あるとき、他の国のハンセン病の歴史を読んでみると、どこの国の歴史も同じ構造をもっていることに気づきました。それらはどれも、時代と場所をあらかじめ設定し、それに沿ったハンセン病の歴史を構築していくという、ある種のテンプレートに沿ったものでした。
例えば、19世紀のインド、中国、コロンビア、それらのハンセン病の歴史は、それぞれの国の枠組みのなかで、国内で起きた出来事の延長として説明されていたのです。中国の文献を読むと、そこではハンセン病は中国の過去の流れを背景に説明されていて、ノルウェーはまったく登場しません。同じようにわたし自身も、ノルウェーでの出来事を、あくまでノルウェーの文脈で説明していました。
同様の現象(例えば、病気が「遺伝的」なものと見なされていたのが、突如「感染症」だと捉え直される転換)は、ノルウェーでも中国でも同時期に起きているのに、それぞれ「自国の過去」のみによって説明されてしまっていたのです。インドであれば、それは「帝国の歴史」や「イギリス統治下での議論」によって語られています。
そこでわたしは思いました。これは、まるで「パズルのピース」をそれぞれ別々につくっているようなものだと。それぞれの国が、パズルのピースのように歴史を描いているけれど、それらがどう組み合わさるのか、どうつながっていくのかは注目されないのです。もしかしたら、最初からあるテンプレートに従ってしまっているせいで、パズルのピースがどう組み合わさるべきかについて、十分な理解がないまま自己満足的に断片を量産しているのではないか。わたしはそう感じたのです。
そうしたなか出会ったのが、「トランスナショナル・ヒストリー」(国境を越える歴史)のアプローチでした。特に印象的だったのは、ジェームズ・セコードが書いた「Knowledge in Transit」(移動する知識)という論文です。彼はこう主張していました。
「科学史家は、何かの『最初の観察』や『始まり』に固執する傾向があるが、それよりも科学の歴史をコミュニケーションの歴史として見るべきだ。つまり、『人びとがその発見をどのように知るに至ったのか』『その知識はどのように広がったのか』に注目すべきなのだ」
彼の論旨は、「知識は自然に伝播するものではない」というものです。知識が伝播するには、必ず人の手が必要となるのです。それこそが実際の「仕事」なのです。その「仕事」とは、物語を読み、調査を行うことでもありますが、同時に他者にその知識を読ませ、その地元の文脈に応じて受容・翻訳させるような働きかけでもあるのです。
わたしは、博士課程で「ハンセン病のグローバル化──医療知の生成と循環のトランスナショナル・ヒストリー(1850年代~1930年代)」に取り組み始めました。
ハンセン病という国家課題
ノルウェーで最初に出版されたハンセン病に関する文書は1816年のもので、当時ノルウェーは400年に及ぶデンマーク支配から解放され、スウェーデン領へと移行した直後でした。その文書では、500年以上にわたってハンセン病患者を受け入れてきた施設で働く医師が切実な人道支援を求めていました。同時に、謎だらけのこの病気の医学研究の必要性を訴えていました。
一方で、この病気が存在しない地域に住むヨーロッパの人びとは、それを“恐怖の病”と見なしていました。そして文明化されたヨーロッパ大陸からハンセン病はすでに消えたと考え、ハンセン病が存在することを文明の遅れと見ていました。ハンセン病が存在しないことをヨーロッパ人が他の国々よりも文明的である証拠として用い、植民地主義の正当化に使ったのです。
ノルウェーはというと、先ほど申し上げたように、デンマークからスウェーデンに譲渡されました。王様はスウェーデン人でした。わたしたちは独立を望み、独自の言語や習慣、歴史を誇りに思っていました。だからこそ、”文明の遅れ”の象徴のように見られていた病気を国に抱えていることは、独立を目指す上でマイナスになりかねなかったのです。
1836年には国勢調査が行われ、国内に何人のハンセン病患者がいるかが数えられました。その9年後に再調査された時点では、その数は2倍になっていました。「これは放っておけばとんでもないことになる」、彼らはそう考えました。このままでは40年で8倍になるかもしれない。だから、いますぐ何かをしなければならない。このようにして、ハンセン病は「社会への脅威」としても認識されるようになっていきました。
こうした背景から、ノルウェーでは治療法の確立を目指した研究に大きな関心が寄せられるようになったのです。そして、導かれた結論は、国家が「保護施設」を建設し、ハンセン病の影響を受けた人びとに適切な住居とケアを提供するべきだ、というものでした。
その頃は福祉国家という概念はまだ存在しておらず、「救貧制度」というかたちでの公的支援はあったものの、村落社会では生産された余剰資源が救貧のために使われていました。ハンセン病患者が地域に留まれば、地域住民が彼らの生活費や介護費を負担しなければなりません。一方、国家施設に入れば、国家がその生活とケアを引き受け、地域の税負担は解放されることになります。さらに、施設では国家が誇る最良の医師たちの診察を受けられるだけでなく、治療法の確立に向けた研究にも貢献し、他の患者を救う手助けにもなります。この取り組みの一環として、患者の監視制度が開始されました。これは世界で最も古い全国的な患者登録制度であり、ノルウェーのハンセン病患者登録がその始まりです。1856年以降、この制度はノルウェーにおけるすべてのハンセン病症例を網羅するようになりました。
しかし十数年経っても、治療法の探索は一向に成果が上がりませんでした。軟膏や油剤、内服薬、注射、入浴療法など、あらゆる手法が試みられましたが、どれも効果的な治療にはなりませんでした。短期間で改善する人もいましたが、根本的な解決には至りませんでした。
そのような状況のなか、若き医師、アルマウェル・ハンセンが登場します。ハンセンは自分の考えを数理モデルで説明し、それが現実を十分に反映していることを確認しました。彼は顕微鏡をのぞき込み、明確な特徴をもつ桿状の微生物を発見しました。この最初の観察は、1873年2月28日に行われました。この細菌については、イギリスの植民地で勤務していた英国人医師が同1873年、印刷物の巻末付録の直前の最終ページに注釈として記しましたが、それ以外でこの発見はほとんど注目されることもなく、あくまで数ある医学的報告のひとつとして扱われました。
世界的に見ても、これが「ユリイカ(見つけた)!」的な瞬間として評価されることは少なくとも当初はなかったのです。
上:ハンセン博士のオフィス。教育の場で使用することを目的としたハンセン病患者を模した模型。これらのマスクを使って、医学生はハンセン病の臨床的徴候を認識する練習を行った。1901年、ハンセンが60歳の誕生日に贈られた。下:ハンセン病博物館内の展示物。研究に使われた顕微鏡、資料のほか、ハンセン病患者に関する残された記録が展示されている。ノルウェー、ベルゲン、2025年5月。photograph by Kazuma Obara
知識はどのように移動したのか?
先述の、わたしが書いた博士論文は二部構成になっていました。前半では、「知識がどのように移動するか」というテーマを扱いました。異なる年代ごとに、どのような技術や実践が知識の伝播を可能にしていたのかを検討したのです。19世紀中頃以降、多くの人びとがハンセンの元を訪ねるべくベルゲンへと旅をし、実際に治療を目の当たりにし、報告を書く、ということがありました。こうした物理的な「移動」は、「通信」と並ぶ、知識の移動の重要な手段のひとつでした。ちなみに当時、アルマウェル・ハンセンは、ドイツ人医師ロベルト・コッホ(炭疽菌、結核菌、コレラ菌の発見者)とも頻繁に書簡を交わしていました。
「移動」「通信」に加えて、もうひとつの知識の伝播方法は、アルベルト・ナイサーが学会で発表を行ったことです。彼は1879年の秋にベルゲンを訪れ、ハンセンの研究を紹介され、診療所でその技術やラボの手法を見せられ、20人ほどの患者から採取されたサンプルを受け取って帰国しました。1879年のクリスマスの頃、ナイサーはこの発見を自然科学会議で発表し、「ハンセン病の原因菌を発見した」と宣言しました。「これがその菌です。これがサンプルです」と。そして、ハンセンの名前を一切挙げませんでした。サンプルがノルウェーから提供されたものであることも、自分が最初の発見者ではなかったことも一切言いませんでした。彼はただ、それを自分の「発見」として報告したのです。
この報告が掲載された学会の議事録が出版されるまで、ベルゲンの医学共同体はこの件を知る由もありませんでした。しかし彼らは、非常に広範な情報ネットワークをもっていました。「ここにハンセン病に関する新しい発表があるぞ。発見だって? ハンセン、これ、君の発見じゃなかったか? 君、数年前にこれをやっていたよね?」と気づいたのです。ベルゲンではこの問題について議論が起こりました。そして最終的に、ハンセンは助言を受けて、自分がらい菌の発見者であるという事実を証明するに至ったのです。
「発見」を国家が語るとき
わたしが博士論文を書いた際、1873年に起きた、この一連の物語に始まりを置くのではなく、むしろその28年後、すなわち1901年にベルゲン博物館(現在のベルゲン大学)の庭園においてハンセンの胸像が除幕された出来事から話を始めました。この胸像は、国際的評価の象徴として設置されたものであり、式典ではドイツのオスカー・ラッサー教授がスピーチを行い、ハンセンの発見を「いまや支配的な見方の基礎となった」と称えました。
胸像には「アルマウェル・ハンセン、らい菌の発見者、世界中の医師たちからの贈り物」と記されました。このことによって、全員ではないにせよ、医学界の大多数が「病気の原因は細菌であり、最初にそれを観察したのはアルマウェル・ハンセンである」と認めたのです。
発見から28年後、ハンセン病は「病気」として定義されるようになりました。それまでは、神からの罰、先祖の罪を受け継いだものなど、そこには強い恥やスティグマ(烙印)が伴っていました。しかし、らい菌の発見を契機に、こうした迷信と科学とを分けることが可能になっていったのです。すなわち、人類が闘うべきは「ハンセン病者」ではなく、ハンセン病の原因となるこの「細菌」そのものであるという医学的認識がこの時点で確立されたということです。
現在、らい菌の発見という出来事は、しばしば「1873年2月28日」に起きたと語られます。われわれはその日を記念日として祝っており、100周年記念でも、150周年記念でも祝いました。そしておそらく、200周年記念の際にも再び祝われるでしょう。たとえその頃には、この病気が歴史書のなかにしか存在しなくなっていたとしても、です。
ハンセン病の研究者たちは、ハンセンがらい菌を発見したのがどこでだったか、誰が指導教員だったのかを語って聞かせてくれるでしょう。なかには、検体を提供してくれた患者の名前まで覚えている人もいるでしょう。それほどに重要な瞬間が、この式典によって世界に認定されたのです。
なぜ「物語」として必要だったのか
とはいえ、それまでの間に何があったのでしょう。らい菌の発見当時、ノルウェーはまだスウェーデンによって統治されていました。1814年には議会も存在し、独自の憲法を採択していましたが、行政権を握る政府職員はスウェーデン王によって任命されていたのです。この政治体制のなかで、ノルウェーの政治エリートたち(そこには医師たちも含まれていました)は、独立を求める運動を展開していました。彼らは単なる医師ではなく、政治家であり、知識階級の一部だったのです。彼らは、ハンセン病の歴史を我が物にすることを、政治的戦略として用いたのです。
つまり、「ハンセン病が存在する」ということが「中世に取り残された遅れた国家」の証しであるとする従来の捉え方を反転させ、「細菌の発見」の物語を用いることで、「ノルウェーは世界最高の研究者が輩出している国である」「ここでは科学的ブレイクスルーが起きている」「世界中の専門家がここを訪れて学んでいる」といったことを世界に喧伝しようとしたのです。
この物語によって、「ノルウェーは近代化しており、進歩した国であり、先端科学の拠点である」というナラティブを打ち出すことができたのです。そうなれば当然、次のような問いが浮かびます。「これほどの進歩を遂げている国が、なぜいまだに独立していないのか?」。1901年当時のノルウェーでは、ハンセン病の議論を通して「いまこそ独立のための投票が必要だ」という主張がなされていたのです。そうした主張を経て、ノルウェーは1905年に、ようやくスウェーデンから独立を果たしたのです。
国立ベルゲン大学の庭園に現在も設置されているハンセン博士の胸像。1901年に除幕式が行われた。ノルウェー、ベルゲン、2025年5月。photograph by Kazuma Obara
「発見」の固定化と政策の正当化
ノルウェーでは、1850年代にハンセン病対策が開始されて以来、全国的な患者数が年々着実に減少していました。減少の理由としては、隔離政策に加え、住宅環境の改善や栄養状態の向上などが複合的に寄与していたと考えられています。隔離だけが効果的だったとは言えません。
けれども当時においては、隔離が唯一の成功要因であるということが「証明」されることが、政治家にとっても、ハンセンや他の研究者たちにとっても、その成果を強調する上で極めて重要なことでした。(編注:ハンセンがらい菌を発見した1873年の段階では、らい菌発見は医学的に広く受け入れられておらず、当時の隔離政策はこの発見を根拠としたものではなかった)。つまり、彼らは、こう主張したかったのです。
もしあなたの国にハンセン病があり、それを解決したいと思うなら、解決策は存在する。ノルウェーを見よ。ノルウェーには、ハンセン病対策の「青写真」があり、それは機能している。あなたの国でも、国勢調査を行い、研究機関を整備し、患者を感染していない人びとと分離するための施設を建設しなさい。そうすれば、次世代への感染拡大を防ぐことができる。この病気は何千年も人類と共にあった。いま行動しなければ、これからも何千年と続いてしまう。始めるのは“いま”なのだ。
当時、こうしたメッセージは、非常に説得力をもっていたのです。
1411年に建てられた聖ヨルゲンス病院。1820年からハンセン病専門病院とされた。現在はハンセン病博物館として一般公開されている。ノルウェー、ベルゲン、2025年5月。photograph by Kazuma Obara
ヴォルセット博士が語るパズルのピースは、世界的な連関のなかで、常に相互に影響を受けながら変化していくものだ。1907年、日本では「癩(らい)予防ニ関スル件」として、路上で生活するハンセン病患者たちを強制隔離する法律が成立した。鎖国が終わりを迎え、欧米からの視線が国内に向けられた時代、ハンセン病患者が存在する遅れた「中世」として見られることを日本の政治家たちは恐れた。患者の終生隔離を規定した法律は1996年まで続いた。年表における日本の物語は、「法律廃止」という断定的な文言によって、ある種のピリオドが打たれたかのようだ。しかし、物語の始まりを決める誰かがいるように、物語の終わらせ方もまた誰かが決めるのである。
ノルウェーに行く前、わたしは日本にあるハンセン病療養所に住む男性の部屋を訪ねた。彼は、療養所の敷地から見える海の風景を長年にわたって写真に撮り続けている。アルバムには、「らい予防法」が廃止された1996年も、その以前も以後も、同じ位置から撮った海の写真が並ぶ。変わるのは印字された日付だけだ。彼は今日も同じ砂浜に立っている。それは、大きな歴史の流れのなかで、静かに折り重なるもうひとつの物語である。
マグナス・ヴォルセット|Magnus Vollset ベルゲン大学(ノルウェー)准教授。専門は医学史および科学史。ハンセン病のトランスナショナル・ヒストリーに関する博士論文を執筆。2023年に開催されたらい菌発見150周年記念事業の責任者を務めたほか、アルマウェル・ハンセン記念室の管理者、聖ヨルゲンス病院財団の理事長を務めている。
ハンセン博士のオフィスにて。ノルウェー、ベルゲン、2025年5月。photograph by Kazuma Obara
【WORKSIGHT SURVEY #11】
Q:現在「科学」と「国家」の関係は近すぎる? それとも遠すぎる?
科学は国家から独立して存在すべきなのでしょうか? それとも国家の庇護/管理のもとに置かれるべきなのでしょうか? パンデミックからAIにいたるまで、科学と国家の関係性が鋭く問われるような事象が増えているなか、みなさんのご意見をお聞かせください。
【WORKSIGHT SURVEY #10】アンケート結果
アニメスタジオ、音楽レーベルを始める:MAPPA代表取締役社長・大塚学に訊くmappa recordsの必然(7月8日配信)
『呪術廻戦』をはじめ、数々の大人気アニメの制作を手がけるスタジオ・MAPPAが、2025年4月に音楽レーベル「mappa records」を設立した。時代を牽引するアニメスタジオの新たな試みの必然性とは。現代のアニメに求められるクリエイティブのあり方について、代表取締役社長・大塚学に訊いた。
Q:今後、国内外のアニメスタジオが、他領域との連携を強化するための機能を自社内に設け、多機能化をさらに進めていくと思いますか?
回答理由(抜粋)
もっと国外や他領域と積極的にコラボしてほしい。音楽なら海外アーティストやインストロックバンド、ファッションならハイブランドと組んでリアルクローズとして魅力的なものをつくってほしいし、スポーツともコラボして運動用のミュージックビデオ的な展開があってもいいと思う。
次週7月22日は、音楽プロデューサー/DJ・tofubeatsさんによる、7月21日刊行予定の新刊『ミュージックシティで暮らそう:音楽エコシステムと新たな都市政策』(黒鳥社)の書評を配信します。「クリエイティブ都市論」を引き合いに出しながら、音楽の公共性やベニューの自治性、都市との関係性について、自身の経験も交えつつ考察します。お楽しみに。