発注とケアと職業倫理の罠
WORKSIGHTコンテンツ・ディレクター若林恵による年頭コラム。積年のテーマである「発注」を考えることで見えてきた、仕事というものをめぐる根源的な問題とは?
Photo by Rock'n Roll Monkey on Unsplash
text by Kei Wakabayashi
編集者は素人
「発注」ということについて、ここ数年わりと気にしてきたのは、自分が「編集」を仕事にしてきたことと深く関わっている。編集者と呼ばれる職種には、基本、何の専門性もない。政治学の本を担当したからといって、その編集者が本を書いた作者よりも政治学に詳しいといったことは、あったとしても極めて稀だ。仮にそんな編集者がいたとしても、次に担当するのが心理学の本だったりすれば、話は元に戻る。編集者は、基本、素人なのだ。
にもかかわらず、本や雑誌の企画の、そもそもの言い出しっぺは、当該の編集者だったりする。素人である編集者は、専門家である作者のところに行って、「こんな本つくりませんか?」と提案する。もちろん合議を経て企画は立ち上がったり、立ち上がらなかったりする。
こうやって企画が立ち上がってくる瞬間は楽しい。本のコンテンツをつくる当人である作者と、それを補助し伴走する役割を担う編集者は、企画の立ち上がり当初は同志のような関係にある。「一緒にがんばりましょう!」。編集者にとっても、おそらく筆者にとっても一番楽しい時間だ。そこではお互いの利害が完全に一致したように見える。一心同体。けれども、実際にはそんなことはない。
コンテンツをつくる側と、編集者との利害が必ずしも一致しているわけではないということが明らかになるのは、経験的には制作が終わりに近づいた頃、販売戦略といったものが検討されだすあたりから起きがちだ。とはいえ、それ以前にも、そうしたズレが明らかになることはままある。いざコンテンツがつくられ始めた段階で、「思っていたようなコンテンツになっていない」と編集者が感じるようなことは起きる。そこで、編集は一定の介入を行うことになるのだが、ここで問題になるのは、何をもってその介入が正当化されるのか、ということだ。
先に述べた通り、編集者は、対象となっているコンテンツについては素人だ。とはいえ、自分が企画の言い出しっぺであり、制作費やフィーを払うのも編集者が属する出版社であれば、「発注通りにやってもらわないと困りますよ」と介入することは商取引上、妥当な行為ではある。さりながら、コンテンツをつくる側が専門家としてそれなりに思考をめぐらせた結果として、ひとまず「納品をした」ということなのであれば、その内容について、素人がああだこうだと口を挟むのは僭越だとも言える。
ここでよくもち出されるのは「編集者は最初の読者だ」という理屈だ。編集者は読者を代表して、原稿と向き合っている、というわけだ。読者の観点からの介入。この視点に立てば、編集者が素人であるという立場は、たしかに大いに効力を発揮する。「これでは読者に伝わりませんよ」。そう言われたら作者としても反駁しづらいだろう。とはいえ、この論理は、出し方を間違えると感情的な反発を招くことがある。最初は同志だったはずの編集者が、いつの間にか「客」の側へと立場を変えるのは、相手にハシゴを外したような感じを与える。
加えて、そもそも編集者が、なぜ「読者をレペゼン」する立場たりうるのかという点についても根拠は薄い。選挙で選ばれたわけでもない人間が、「客」や「市場」を盾にものづくりに介入することは、根拠がないだけなく、数の暴力に頼るような身振りともなる。それは結果として、マーケティングをものづくりよりも優位に置くことになり、企画部門があくまでも営業・流通、マーケティング部門の下請けにすぎないと認めることにもなってしまう。
もちろんこうしたさまざまな難局を乗り切るにあたって、あれこれと手の打ちようはあるので、ここに書いたようなわかりやすい亀裂が生じるのを避けることは、もちろん可能だ。その技術をもって編集者は、つつがなく日々の仕事を遂行できているはずだが、結局のところ、つくり手の側と企画側との間に、それなりの信頼関係が築かれていれば、一時の感情的な齟齬なども最終的には解決されたりはする。
いずれにせよ、問題は多くの場合、最初は意気投合した同志のコラボのように見えた仕事も、金銭的なやり取りをともなう仕事であれば、そこに明確に「発注」が作動している、というところから生まれてくる。
受注者は自動販売機か
「発注」という行為は、仕事のなかで日々繰り返されているものだが、そのやり方を学ぶことはほとんどなく、そもそもそれが「何をやり取りすることなのか」が明記されることもない。それでも編集者としてさまざまな発注をしてきた経験から、おそらくふたつほど留意しておくべきことがあるように思われる。
ひとつは、発注する側は基本「素人」であり、素人であればこそ「プロ/専門家」への発注が行われるということだ。これは何も編集者の仕事に限ったことではない。ウェブサイトの制作をウェブ制作会社に発注するあらゆる人や組織、ビルの設計を建築家に発注する施主やデベロッパー、感染症をトラッキングするアプリの制作を発注する行政職員等々、だいたいの世の仕事は、素人の発注にプロが駆り出されるという構成を取る。発注者が自分でできるなら、そもそもプロの手を借りる必要はないのだから、そんなことは当たり前といえば当たり前なのだが、このことは、つまるところ扱う対象をめぐる情報や技術の量やクオリティにおいて、非対称性があるということを意味している。言うまでもなく「発注する側」は、それらが「欠如している側」なのだが、そのことを強く発注者が意識しているのかといえば、どうも怪しいと感じざるを得ないのは、発注にはもうひとつ別の非対称性が存在しているからだ。留意すべきことのふたつ目は、このことに関わる。
情報や技術の非対称性において弱者であるはずの「発注者」は、多くの場合「金を払う側」なのだ。そして、そうであればこそ、発注者は出来上がったものに対する最終的な決定権をも担う。そこには権力勾配とでも呼べそうなものが明確に発生する。企画の生殺与奪を決定するのは、多くの仕事において、素人の側なのだ。
そう考えると発注という行為が、いかに危うい綱渡りの上に成り立っているかが見えてくる。世の多くの仕事というものには専門家が必ず関わっているにもかかわらず、最終判断を下す立場にあるのは、ほとんどの場合専門ではない人である、というのが「発注」という観点から見たときの「仕事」の基本的な構図だ。そうだとすれば、世のビジネスというのはだいぶ危なっかしい。それでよくビジネスが回っているなと不思議な気持ちにすらなってくる。
ただそれも、発注側の欠如をお金を払って専門集団に埋めてもらうということだと見れば、どんな発注もごくごく当たり前のシンプルな取り引きだ。電球が切れたからコンビニに買いに行ったり、缶コーヒーを自動販売機で買うようなものだといえばたしかにそうとも言える。本づくりのような仕事も、そうやって割り切って考えたら、シンプルな調達だと見なすことはできる。ウーバーで夕飯を注文するのと同等のものとして「発注」を考えることはもちろん可能だし、実際、このご時世の経済は、多分にそんなふうに回っていると見えなくもない。
この世で売り買いされるすべてのものを、それがたとえ専門化された情報や技術といったものであれ、サービス化された商品だと考えるのであれば、発注は、たしかに、ただのお買い物にすぎない。そして、それがお買い物なのであれば、安くていいものを賢く手に入れることができさえすれば「いい発注」だということになる。そんな趨勢が進行すればしただけ、発注者は、あらゆる取引先を自動販売機と見なすようになっていく。それはたしかに便利で効率がいい。しかし、果たして仕事は、そんなに簡単なやり取りだけで済むものなのだろうか。
プロンプトという名の発注
ChatGPTの登場以来、いわゆる「プロンプト」の書き方をめぐって、多くの人が競ってよりよい手法の探索に取り組んでいるさまは、「発注」という観点から見ると興味深い。自分が望んだようなアプトプットを得るべく、プロンプトというインプットを重ねていくことを「発注」と見なすなら、そこで行われているのは、世にも珍しい「発注の訓練・探究」だと言うことができる。
相手が機械なので、ときに乱暴な発注を試すことも、何度も試行錯誤を繰り返すことも可能だが、ChatGPTで面白いのは、受注者である機械は、発注者に忖度したり気持ちを汲み取って先回りしてくれたりといった自発的な工夫はしてくれないという点だ。つまり、工夫を重ねる行為が課せられるのは、常にプロンプトを出す側=発注者なのだ。
そこで自明とされているのは、「発注の仕方が悪いから、いい結果を生み出せないのだ」という、ある意味かなり謙虚な態度だが、機械相手にそう思えるのなら、人に対する発注ではなぜその態度をもてないのかという問いが必然的に首をもたげてくる。熱心なプロンプト制作者たちが言う通り、プロンプト書きがすでにしてクリエイティブな行為であるなら、「発注という行為には、すべからく『発注する側』のクリエイティビティが求められるのではないか」という問いを立ててみたっていいだろう。
どだい、多くの仕事における発注が、AIよりもはるかに不安定に揺らぐ予測不能な「人間」を相手にしていることを思えば、わたしたちは、AIに向きあうよりもはるかに複雑で難解な「3次元プロンプト」(あるいは扱う対象に「心」のようなものを含めるなら「4次元」か)のようなものを、個々の「発注」の現場で駆使していくことが求められていることにはならないだろうか。決まったコマンドを押せば決まった答えが返ってくるような自動販売機的な発注が、すでにして機械相手にも通用しないのであれば、発注者は、いい加減、自分たちがこれまで人間を相手に行ってきた発注では、もはや何も得られないということに気づいてもよさそうだ。
そう考えていくと、ここには、わたしたちが「仕事」というものをどういうものとして考えていきたいのかをめぐる大きな分岐が指し示されているようにも思えてくる。
さながら自動販売機で缶ジュースを買うように、モノやサービスを調達して何かをつくっていくことが「仕事」なのか。あるいは、相対する取引先を、AIよりもときに複雑、ときに融通の利かない相手と見なし、ときに慮り、ときになだめ、ときにすかしながら、互いに納得いくようなアウトプットを試行錯誤しながら求めることが「仕事」なのか。
どちらの道を取るのも自由だが、前者のやり方ばかりでは、早晩仕事が立ち行かなくなるであろうことは、どんな職場であれ、薄々と感じられていることなのではないかという気がしなくもない。
すべての仕事は「ケア」で成り立つ
この分岐については、文化人類学者のデヴィッド・グレーバーが、『ブルシット・ジョブ:クソどうでもいい仕事の理論』という本のなかで実は語っている。マルクスの労働価値説の落とし穴を論じた章で、彼はこう書いている。
ほとんどの労働者階級による労働が、それをやるのが男性であれ女性であれ、実際には女性の仕事と基本的にみなされるものに類似しているという現実がみえなくなっているのである。つまり、労働とは、槌で叩いたり、掘削したり、滑車を巻き上げたり、刈り取ったりする以上に、ひとの世話をする、ひとの欲求や必要に配慮する、上司の望むことや考えていることを説明する、確認する、予想することである。植物、動物、機械などなどを配慮(ケアリング)し、監視し、保守する作業についてはいうまでもない。(中略)
多くのフェミニスト経済学者が指摘しているように、すべての労働はケアリング労働だとみなすこともできる。というのも、たとえば橋をつくるのであっても──本章の冒頭に戻るならば──、つまるところ、そこには川を横断したい人びとへの配慮(ケア)があるのだから。引用したもろもろの事情からあきらかであるように、みずからの仕事の「社会的価値」について考察するとき、人びとは実際にこうした観点から考えているのである。ところがふつう、「生産的」であるということは、自動車やティーバッグ、医薬品などが、女性が赤ん坊を生産するのと同様の痛みに満ちた、どこかミステリアスである「労働」を介して工場から「生産される」という、魔術的変容のことを意味している。そして労働の価値をそれが「生産的」であるかどうかで考えること、生産的労働の典型を工場労働として考えることは、こうした[ケアにかかわる]すべてを抹消してすませてしまうことである。さらにいえば、こういう発想があるから、工場所有者はいともたやすく、労働者は実際にはかれらの操作する機械となんら変わるところがないと考えることができるのである。これはあきらかに、「科学的管理法」と呼びならわされるようになったものが発展するにつれ、いっそう容易になった。だが、人びとが「労働者」と聞いて、料理人や庭師や女性マッサージ師を思い浮かべるようであれば、そのようなことは起こりえなかっただろう。
グレーバーはここで、いわゆる「生産的」な仕事と、そうとは見なされない女性のケアワークの二項対立を、「ケアワークも生産的なのだ」と論駁することで対等のものとして扱おうとするやり方とは真逆の方法で向き合う。グレーバーはむしろ、「生産的な仕事のほうこそ本来的にはケアワークなのだ」と言い切ることで、生産とケアの二項対立を無効化しようとするのだ。
それはすなわち、仕事というもののすべてを自動販売機から買うようなものとして扱うことはできないということを意味してもいる。あらゆる仕事において、「ケア」はむしろその基盤であって、グレーバーの言う通りなら、わたしたちは「生産性」ということばや「科学的管理法」といった手法によって、そのことがただ見えなくなってしまっているだけなのだ。
発注というものを、この観点から改めて見つめ直すと、素人にすぎない発注者が、なぜプロの仕事に介入することが許されるのかという問いに対する論拠のようなものもうっすらと見えてくる。
素人であるところの発注者が、ものづくりに伴走するとき、そこにおける行為は、生産性や管理といった観点から査定されるものであるよりも、「ケア」という観点から理解されるべき何かに近いように思われるからだ。実際、作者やデザイナーといったつくり手たちと相対するときの編集者の仕事は、まさにケアと呼ぶに相応しい。優秀な編集者は、たしかに自分の仕事に関わる人たちの心の機微、欲望や願いへの「配慮」に長けている。
「職業倫理」の暴力性
ケアの政治学者として知られるジョアン・C・トロントは、『ケアリング・デモクラシー:市場、平等、正義』という本のなかで、こうした「ケア倫理」と仕事の関係性について語っている。ここで面白いのは、トロントが「ケア倫理」の反対概念として「職業倫理」というものを問題化しているところだ。しかも、おそらく多くの人がいいものだと考えがちな「職業倫理」が問題あるものとして語られているのが重要だ。
イデオロギーとしての職業倫理は、実社会を比較的均一なものとして描いている。つまり、もしもある個人が勤勉に働く意欲があるのなら、あと必要なのはハードワークによる利益を享受し、善い生を送ることだけであるという具合に。そのため、職業倫理の世界観は、新自由主義のそれと両立可能である。その世界観とは、集合的な生活について知っておくべきこととは、自由市場において効果をもつ、異なる諸個人の能力についての考察だけだというのだ。
他方、関係性のなかにあるケア倫理は、個人の努力を異なる観点から見ている。ケアの複雑さのことを念頭におけば、よいケアをすることは、どの労働者も彼や彼女自身の福祉だけではなく、家庭における親密関係にあるひとたち、友人や隣人たち、そしてより遠く離れたひとたちのような、他者のもつニーズのあり方にも調子をあわせることが求められる。
ここでのトロントの指摘は、グレーバーの論点と通じ合っている。グレーバーが語った「生産的労働」と「ケアリング労働」の対比は、新自由主義とも共存しうる均一的な「職業倫理」の世界観と「ケア倫理」の対比と符号するだけでなく、それらの二項を分かつ分断線としてジェンダーが指摘してされている点も共通する。
トロントは、さらにここから、「生産」と「保護」というケアの形態が、個人主義化され、かつ男性の領域としてジェンダー化されてしまったことで、「暴力の所在や、多くの社会的思考を支えている個人主義的で競合的な『職業倫理』について理解することができなくなっている」と指摘している。
このトロントの指摘を発注という観点から読み直すなら、「生産」は「こうしないと売れないんですよ」「売れるものをつくらないと意味ないんですよ」といった、いかにも冷徹な現実主義を装うような態度、「保護」は受注者に対して「仕事をくれてやっている」といった態度に現れるようなケアのありよう、と読み換えることができる。
いずれも仕事の現場で頻繁に見かけるものだが、それがケアの形式と見なされるのは、それが相手のことを思ってのことであるかのように行われるからだ。ただし、そこには絶えず上から目線の温情主義が見え隠れしている。そうであればこそ、それは容易に服従関係や隷属関係を生み出し暴力ともなるのだが、トロントが指摘したのは、その暴力が職業倫理という観念によって覆い隠されてしまっているということだ。
職業倫理の仮面をかぶったこうした暴力は、実際わたしたちが普段からやたらと目にしていることでもある。相次ぐ大物タレントの性暴力事件から、紅白歌合戦における発注者の選曲ミスをめぐる騒動にいたるまで、上記のトロントの指摘を裏書きするような出来事は少なくない。いずれも詳細は外野には知る由もないが、それが大枠において受発注関係の不均衡や歪みから生じた問題で、かつその歪みが常態化するにいたった背景に、受発注システムのなかに巣食った「個人主義的で競合的な『職業倫理』」があると見るのは、あながち的外れではないはずだ。
「仕事をくれてやっている」「自由市場で成功するためには多少の犠牲も必要」といった理屈によって正当化される傲慢や怠慢、無責任は、「集合的な生活について知っておくべきこととは、自由市場において効果をもつ、異なる諸個人の能力についての考察だけだ」という世界観と密接に関わっている。こうした世界観に則って、女性のセクシュアリティを「効果をもつ個人の能力」と見なせば「上納」のような商習慣がまかり通ったとしても不思議はないが、トロントに倣えば、このような性暴力さえもが「職業倫理」の名のもとに正当化されてしまっているということになる。
関係者の頭のなかのロジックは知る由もないが、ビジネス上の成功を大義名分とした隷属や暴力の強要は、残念ながら芸能界に限らず他のビジネスにおいても珍しいものではないだろう。社外に対してであれ社内においてであれ、こうした世界観に基づいた不健全な発注が、ある種の暴力へと発展するさまを仕事の現場で見たことがないという人のほうが、むしろ稀なのではないだろうか。
発注は「流れ」をつくる
先に見た通り、発注者は基本「素人」だ。にもかかわらず発注者が金を払う側で、そうであるがゆえにすべての決裁権をもっている。発注という行為は、そんな危うい均衡の上に成り立っていればこそ、いったんそのバランスが崩れると瞬く間に暴力の温床ともなる。そうであればこそ、そのバランスを制御することに、発注者/受注者の双方が細心の注意を払わなくてはならないわけだが、そのバランスが極端に崩れれば、当事者間の努力では解決しえない、社会全体の問題ともなって、法的な介入も必要とされるようになる。
わたしたちの発注環境は、時を経るなかで絶えず変化にさらされてきたもので、その変化にはもちろん制度的な介入も大きく寄与している。ナイーブな発注者を騙してやろうという悪徳受注者が跋扈していた時代があったからこそ、厳しい罰則をもって望ましくないプレイヤーを排除することである程度透明な取り引きが安心してできるようになったのだろうし、一方で外注叩きのような悪徳が蔓延れば、それを是正すべく法的な介入も行われてきたはずだ。
昨今のフリーランス法などもそうした介入の最新系とも言えるものだが、コーポレート経済の論理に蹂躙され尽くしてしまわぬよう、フリーランサーの取り引きを透明化・安全化しようという試みは、人権配慮を後押しする風潮と相まって、一定の意義をもたらすことになるのかもしれない。しかし、そうした透明化が、逆にフリーランサーをますます体よく自動販売機化してしまうのではないかという疑念は尽きない。社員という存在がますますフリーランサー化させられている状況のなか、ワーカーの保護は制度的な介入だけでは不十分のようにも思える。
先のグレーバー/トロントの議論に戻るなら、わたしたちは、おそらく根本から、仕事というものをイメージし直さなくてはならない局面にある。このままひたすら自動販売機になるのか、それともそうではない道を進むのか。もたもたしているうちにも、多くの受注者が、発注において発生した不合理を黙って飲みこんでいるような状況は続いている。
上記の問題以外にも、昨年わたしたちは、マンガ作品のドラマ化において生じた改変をめぐってマンガ家自身が自殺に追い込まれるといった悲劇も目撃してきたが、こうした事件においても、本来徹底的に問われるべきだったのは、発注側の責任だったように思えてならない。ただでさえパワーバランスにおいて大きな非対称性があるにもかかわらず、受注者である作家自身に課せられた自己責任の重さに比べて、発注側の責任はあまりに軽く扱われていたように見える。
事を荒立てたら二度と仕事をもらえなくなるという恐怖のなかで多くの受注者が暴力を耐え忍び、それを「職業倫理」の名の下に自己責任化させられているのであれば、世の仕事は、目に見えているよりもはるかに不健全なものになってしまっているのかもしれない。
何にせよ、わたしたちは、仕事というものにおいて、当たり前のこととして観念化されている枠組みを一度根本から解除すべきなのだ。グレーバーやトロントの著作は、そのやり方のヒントを与えてくれる。わたしたちは、「職業倫理」よりもむしろ「ケア倫理」のようなものによって支えられているという観点から、あらゆる仕事を見つめ直すべきなのだとふたりは示唆する。言い換えるなら、それは、仕事というものをアマチュアリズムという観点からイメージし直すということでもある。
その一方で、個別に切り出された各業務において、より高度なプロフェッショナリズムが求められるという趨勢は同時に進行している。けれども、仕事というものの本質を、そうやって切り出された各業務をつないで一連のフロー/流れに変えるところに見いだし、そうやって小刻みになった業務と業務の間をつないで流れをつくり出す行為を「発注」と見なすのであれば、そこで前景化されるのは「職業倫理」よりも「ケア倫理」であるほうが、きっとふさわしい。
そう考えなければ、わたしたちは、「発注」という行為が概ね素人によって行われるという危険な矛盾を、おそらくうまく乗り越えることができないのではないか。
若林恵|Kei Wakabayashi 黒鳥社/WORKSIGHTコンテンツディレクター。平凡社『月刊太陽』編集部を経て2000年にフリー編集者として独立。2012年に『WIRED』日本版編集長就任、2017年退任。著書・編集担当に『さよなら未来』(岩波書店)、『実験の民主主義:トクヴィルの思想からデジタル、ファンダムへ』(宇野重規との共著/中公新書)。訳書にジョン・バージャー『第七の男』(金聖源との共訳/黒鳥社)。最新刊に『会社と社会の読書会』(黒鳥社)ほか。photo by Kaori Nishida
次週1月21日は、東京・渋谷区本町に位置するポップアップスペース「nakaya」の取り組みに迫ります。なぜポップアップという形式に着目したのか。本町の魅力を活かしながら、"街に溶け込む"という考え方でスペースを運営をする、空間デザイナー・永井健太氏らに話を聞きました。お楽しみに。

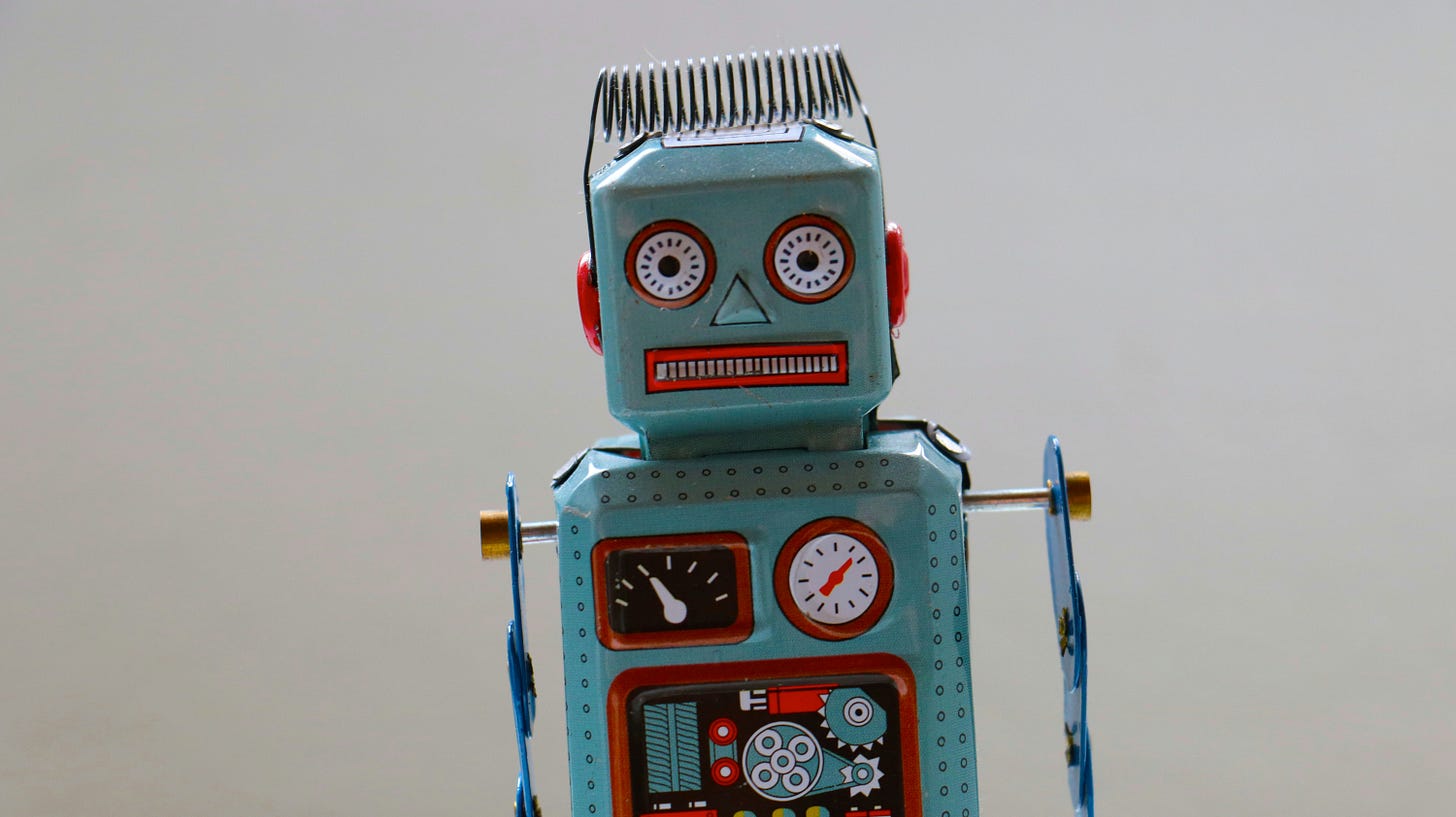


社内で語られたどの訓話や挨拶分よりも、新年の仕事始めにふさわしい記事で、初めての感想を送らざるを得ない心情になりました。ありがとうございました。
個人的に、日本の(特に地方の市役所などの)公共建築に隈研吾氏が採用され、増殖し続けるのも同じ理屈のような気がします。建築という非常に重要な器に対して、商品ロゴを欲しがっている発注者の素人考えが透けて見えます。これをずっと由々しき事態と考えていました。(隈さんが問題なのではないです。)
そしてGLAYが全盛期にCMソングを依頼された際に、「まだイントロのラフしか出来上がっていないから聴かせられる段階にない」と発注者側に話したら、「それでもいい。CMにGLAYのクレジットが入ればいい」と言われて、GLAYを解散することも検討したという話も思い出しました。
仕事を消費として考えたくないものです。