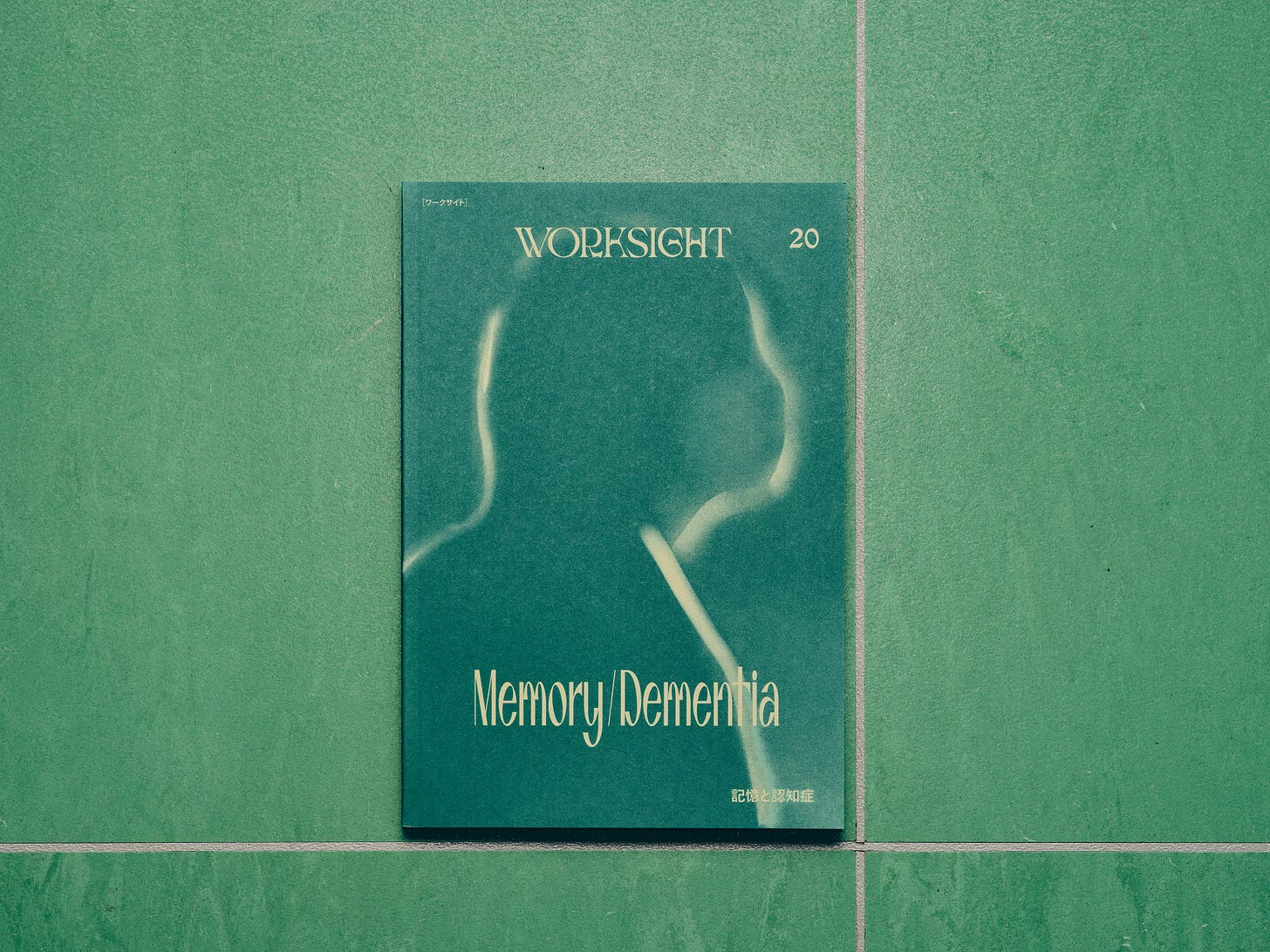隔離からつながりの回復へ:WORKSIGHT刊行記念イベントにて、金熊賞受賞作『アダマン号に乗って』上映会を開催【特別ニュースレター】
パリ・セーヌ川に「アダマン号」と呼ばれる船型のデイケアセンターがある。精神疾患をもつ人たちのケア施設が自然を感じられる街なかに設立されたのは、彼らを社会から隔離してきた歴史への反省からだった。刊行記念イベントの開催にあたり、WORKSIGHTプリント版・20号「記憶と認知症」より、本誌編集長・山下正太郎によるアダマン号の取材記を特別転載してお届けする。
セーヌ川に浮かぶデイケアセンター「サントル・ド・ジュール・ラダマン」(以下「アダマン号」)。精神疾患をもつ人々を”隔離”するのではなく、社会と再統合することを目的としたフランスの公的医療機関だ。
WORKSIGHTプリント版最新号『WORKSIGHT[ワークサイト]20号 記憶と認知症 Memory/Dementia』では、本誌編集長・山下正太郎が実際にアダマン号を訪れ、先進的なケアの現場を取材。このユニークなデイケアセンターが設立されるにいたったフランスの歴史的背景、デイケアセンターの内部や入居者の様子などをレポートしている。
WORKSIGHTでは、プリント版最新号刊行を記念し、第73回ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞したドキュメンタリー映画『アダマン号に乗って』の上映会&トークイベントを開催。上映会実施に際し、アダマン号の取材記を本誌より転載してお届けする。
text by Shotaro Yamashita(WORKSIGHT)
photographs by Shinji Otani
(巻頭記事〈記憶をめぐる旅の省察〉より抜粋)
正常と「その外」の境界
取材5日目。
「心のすぐ隣に起爆装置がある
人間爆弾は君だけのもの
自分の大切なものを奪われたら
それは人間爆弾/君だけのもの
心のすぐ隣に起爆装置がある
人間爆弾は君だけのもの
自分の運命を誰かに支配させたら
それは君のもの
自分を手放すべきじゃない
手放すべきじゃない/絶対にダメだ
自分の運命を/誰かに支配させたら
それは人間爆弾」
腹の底から声を絞りだすかのような、迫力ある姿にすっかり見入ってしまう。第73回ベルリン国際映画祭で金熊賞に輝いたドキュメンタリー映画『アダマン号に乗って』の冒頭シーンだ。誰ともわからない中年男性が、フランスで1970~80年代に活躍したロックバンドTéléphone(テレフォン)の「La bombe humaine(人間爆弾)」を歌いあげる、その場所こそが最後の取材地、セーヌ川に浮かぶデイケアセンター「アダマン号」だ。
(上)全身のエネルギーを使って「La bombe humaine(人間爆弾)」を歌う男性。彼を取り囲むように周りで聴いていた人たちが拍手喝采をおくる(下)個性豊かなアダマン号の利用者たち。カメラに向かい、普段考えていることを語ってくれる
案内をしてくれるのは、精神科の元看護師でこのアダマン号の創設に携わり、現在ケアのコーディネーション、そしてスタッフ全員を束ねるディレクターの役割を果たす、陽気でおしゃべり好きのアルノー・ヴァレさんだ。日本から初めての取材だそうで、アダマン号創設の経緯から、熱弁をふるい始める。
アダマン号についてご紹介する前に、簡単にフランスの精神病の歴史を振り返っておきましょう。フランスでは20世紀中頃まで、精神疾患にかかった方は、社会または日常生活から締め出され隔離される状況がありました。どんな症状であっても、生きていくという欲求をもつためには、何らかの関係性やルーティン化された習慣などが必要ですが、精神疾患をもつことで、そこから排斥され、生きたいという欲望からも遠ざけられてしまったのです。精神病棟に隔離し、外から部屋の鍵をかけ、完全に社会から切り離す。まさにミシェル・フーコーが『狂気の歴史』で書いたような状況です。
かつて、パリで精神疾患にかかった人はここから40キロほど離れた精神疾患の病院に一括収容されていました。ところが第二次世界大戦後、この精神病棟に収容されていた患者の半分が食糧難によって飢餓に陥るという事態が発生したことで、患者たちを地域ごとに分けてそれぞれの地域でケアするという方針が立てられました。これは現在も引き継がれている方針で、このアダマン号はパリのノートルダム寺院周りの住民を対象としています。わたしたちは、こうした経緯への反省も踏まえて、精神的なケアもしながら、一度断絶してしまった社会との関わりを回復することを重視して運営しています。
ミシェル・フーコーの『狂気の歴史』はまさに、アルノーさんが説明してくれたようなフランスの状況をもとに書かれた。そのフーコーの問題意識が、現代のケアの現場に直接流れ込んでいることに、取材陣一同大きな感銘を受けることになったのだが、フーコーの提示した論点を改めて見ておこう。
「監禁は、十七世紀に固有な制度上の産物である。一挙にそれは、中世に実施しえたような投獄制度といかなる共通の次元をももたぬ広大さを獲得した。それは経済上の措置、社会的な安全策という点で新機軸の価値をもっている。ところが非理性の歴史のなかでは、それは決定的な事件をしめすのである。すなわち、貧困、労働にたいする無能力、集団への不適応などの社会的視野のなかで、狂気が知覚される契機、そしてまた、狂気が都市の諸問題と関連をもちはじめる契機をしめすのであるから。貧困にくわえられる新たな意味、労働の義務に与えられる重要性とそれにつながるすべての倫理上の価値、それらが、狂気にかんする人々の経験を遠くから限定し、その経験の意味方向を曲げる。
ある一つの感受性が生れたのである。ある一線を画し、敷居を高くし、そして、選択し、追放する一つの感受性が」(ミシェル・フーコー『狂気の歴史:古典主義時代における』pp.108-109)
フーコーは、ここで、17世紀のフランスで、「狂気」の概念が忌むべき対象として新たな意味を獲得していった過程をあとづける。それまでのヨーロッパで、宗教的体験の一種として時に神聖視されることもあった「狂気」は、17世紀に入り「理性」が社会を統合する原理となるなかで、理性の外にあるものと位置づけられ、それがやがて道徳的な観念になっていくことで、理性とその外側を隔てる境界線がより強固に引かれることとなったとフーコーは説明する。つまり、「狂気」が監禁をもたらしたのではなく、監禁という状況が「狂気」に輪郭を与え、狂気は狂気としての新たな意味をもつに至ったというわけだ。
アダマン号のディレクターを務めるアルノー・ヴァレさん(手前)と、船舶の内装設計を専門とする「セーヌデザイン」のジェラール・ロンザッティさん(奥)。水面が照り返す自然光、落ち着いたウッディな設えが心地よい
閉じた世界に穴を穿つ
こうした過去の「監禁」の時代と比べてみると、このアダマン号は、空間からして隔世の感がある。陽光がきらきらと揺らめきながら木製のインテリアを照らす。船内は、穏やかで開放的で、静かだ。それにしても、いったいなぜ「船」なのだろう。
船をケアセンターにするというアイデアは、人間らしい環境でケアを行うことに注力したパリの病院で委員長をされていたエリック・ピエールさんのものです。彼は以前兄弟で船上暮らしをしていたそうで、その暮らしを利用者たちにも提供したいという思いがありました。
そこで船舶の内装設計を専門とする「セーヌデザイン」のジェラール・ロンザッティさんに声をかけ、贅沢ではないけれども人間らしく充足した環境づくりを目指してデザインをお願いしました。この船は動力がありませんので川に浮かんでいるだけですが、それでも自然のなかにいるという感覚を常にもたらしてくれます。
普通の建物でももちろんケアはできます。けれども、大きな変化は生みづらいと感じます。事務的につくられたビルに足を踏み入れること自体が、セラピーに対する心理的ブロックをもたらしてしまいます。白々とした建物のなかで蛍光灯のもとで会話を交わしても、心を開くことはできません。ここは決して広いわけではありませんが、空間が多様で、モノトーンではありません。
わたしたちはとかく、精神疾患をもっている人は、他者に対する認識に欠陥があると考えてしまいがちです。会話を意味する「カンバセーション」の語源は、「コンベルセ」ということばで、それは「他者とともにいる」という意味なんです。
精神疾患というものを、わたしは心に穴が空いているような状態としてイメージしています。自分と他者との境界が脆く、花崗岩のように開いていて、自分なのか、他者なのか、関係性がわからなくなってしまうのです。であればこそなおさら、閉鎖的な空間に閉じ込めてはいけないのだと思います。通気性のある、透明度の高い空間が必要なのです。
加えて、精神疾患をもつ人は生きたいという欲求が著しく低下しますので、これはわたし個人の考え方ですが、好奇心を刺激することが大事だと思っています。例えばパラノイアの人は、すべての答えが自分のなかにあるといった感じで、精神が閉じてしまっています。その閉じた殻に風を通し、外との関係性を回復するにあたっては、環境が大きく作用するのです。
また、船をケアセンターにするというアイデアは、精神疾患に対する社会の恐怖を和らげることにも役立ちます。ちょうど今週もどこかの精神病院で患者が看護師を殺してしまった事件があり、メディアは大騒ぎしていますが、そのような事件があるたびに社会の認識が恐怖のほうへと傾いてしまいます。
けれどもアダマン号は、このようなデザインであることによって、社会の好奇心を刺激することができます。今日もみなさんに取材に来ていただけたわけですし、午後にはベルギーの著名な作家が取材に来られます。ケアを受けている人たちのみならず、ここで働くスタッフも、外の社会との関係性が構築しやすい状況がつくられるのです。
ハイデッガーは『ハイデッガーの建築論:建てる・住まう・考える』で、建物のなかに誰かが住めば、その建物自体を再構築することができると書いていましたが、わたしはそれを実践したいのです。ここを訪れる人たちの歴史や記憶、過去とのつながりを刺激することで、人びとの関係性を再構築することを目指しています。
この取材で、「船舶」を専門とする建築設計事務所があるのだということを知った。パリを代表する専門アトリエを35年にわたって率いてきたジェラールさんは、パリのみならず、ロンドンやドバイなど世界各地で水上建築のデザインに携わっている。後日ジェラールさんに、船特有の空間体験について伺ってみた。
アダマンは、木製のシャッターで覆われ、それが時間によって開閉するのですが、わたしはそれを建物に洋服を着せるイメージでデザインしました。朝晩にそれが開閉することで、建物自体の雰囲気が大きく変わります。太陽の動きによって光が入ってくる角度も違いますし、水の照り返しもありますので、空間は常に穏やかに動いていることを感じられます。空間自体が生きてることを感じやすい、そんな設計を心がけました。建築は開かれた本だとわたしは思っています。そこに集う人びと、季節、そこにある環境のすべてが、お互いに関係し合うことで、空間は終わりのない物語を語りかけてくれるものなのです。
センター内にはキッチンや音楽室、ミーティングスペースなどが効率よく配置され、決して広くはないにもかかわらず、開放感に満ちている
思えば「川」は近代の管理思想を象徴する対象でもある。自然を技術によってコントロールし、人間にとって都合の良い部分だけを享受できるようシステム化することで、わたしたちが暮らす都市は発展した。けれども、それは一方で反作用をももたらす。
日本の河川に比べれば緩やかなセーヌ川も、1910年の洪水によって花の都は数カ月にわたって浸水を許し、腸チフスをはじめとする伝染病の蔓延を引き起こした。現在では、気候変動による長雨によって新たな脅威がもたらされており、さらなる護岸工事を求める声も上がっている。川はそうやってわたしたちが生きる空間から排除され、遠ざけられていく。近代都市が、「狂気」というものを都市の外へと追いやり、高い壁の向こうにそれを封じ込めたやり方と、なんと似ていることだろう。
日本を代表する河川工学者である大熊孝は、こうした近代的な治水技術によって失われたものに目を向け、過去の日本人の川との付き合い方を参照しながら、新たな自然との共生を説いている。
「近代技術を駆使した河川改修が進むにつれて、水害の頻度は確実に減っていった。一方ではそれと並行するように、水利組合や水害予防組合の組織が弱体化してゆくのである。それは地域共同体の崩壊であり、水害対応のあり方も必然的に江戸時代とは大きく変化していった」(大熊孝『〈増補〉洪水と治水の河川史:水害の制圧から受容へ』p.152)
アダマン号が川に浮かんでいることには大きな意味がある。都市社会から切り離され、目の前にあるにもかかわらず人との関係性をもつことができなくなってしまった川を、いま一度社会のなかに取り戻す試みは、わたしたちが都市の外へと追いやってしまった「狂気」と、どのようにつながりを回復するのかという試みと相似形を描いている。そして、それは、近代以降の社会を規定してきたあらゆる観念を、根底から見直そうという遠大な試みでもある。
アダマン号は引き裂かれてしまった自然と人、人と人の中間地点をぷかぷかと漂っている。
水面との近さがアダマン号の内部の空間に言いしれぬ安らぎをもたらしている。今回訪れた他の取材場所と同様、ここでもセンターのスタッフと利用者の区別がほとんどつかない。銘々がそれぞれに活動に勤しみ、にこやかに日本からの見学者を迎えてくれた
わたしはタンタン
船内を案内してもらっていると、中央のオープンスペースで熱心に書き物をしている、ある入居者と目があった。映画『アダマン号に乗って』にも登場し、強い印象を残した人物だ。アーティストか映画監督を思わせるただならぬ風貌だが、話しかけてみると、穏やかな口調で楽しげに返してくれる。記憶とアイデンティティをめぐる以下の不思議なやりとりが、今回の短くも長い取材での最後のインタビューとなった。
(ちなみにあとでわかったことだが、会話に出てくる「サトウ教授」は『タンタンの冒険』が載っていた週刊漫画雑誌「タンタン」で連載されていた別の漫画、『ブレイクとモーティマー』に登場するキャラクターだった)
──こんにちは。何をされているんですか?
70年代のドキュメンタリーや映画作品のリサーチをしています。これらの作品がいかにわたしの人生からヒントを得てつくられているのかを調べているんです。わたしは、若い頃はデッサンや漫画の制作を学んでいました。18歳のとき以来、ずっと病気なのですが、40年経ってようやく自分に何が起こったのかがわかってきたんです。だからリサーチしています。
──そのスクラップブックを見せてもらえませんか?
もちろんいいですよ。これは映画監督のロベール・ブレッソンが70年代につくった反逆者を主人公にした作品『湖のランスロ』の資料ですが、この作品も、わたしの物語なのです。ちなみにヴィム・ヴェンダースの『パリ、テキサス』も、わたしとわたしの弟について描いた作品です。
──興味深いですね。
でしょう? 他にも色々あります。この絵は、高校生のときに描いた17歳のわたしの自画像なのですが、気づきませんか。
──何にですか?
ほら、タンタンにそっくりでしょう?
──言われてみればたしかに。
タンタンには、わたしの父や弟も出てきます。そうそう、わたしはタンタンのサトウ教授の大ファンなんですよ。タンタンのお父さんも、中国や日本の歴史にも詳しかったでしょう? ですからわたしはタンタンを通して日本のことを知りました。日本の方ですよね。
──そうですそうです。日本に興味をもってくださりありがとうございます。
つまりタンタンとわたしとの関係性もそういうことなんです。あなたとわたしとの関係性も、そういうことではないですか?
(続きは本誌『WORKSIGHT[ワークサイト]20号 記憶と認知症 Memory/Dementia』をご覧ください。)
映画「アダマン号に乗って」にも出演するセバスチャンさん。タンタンと映画監督ロベール・ブレッソンを熱心に研究し、手づくりのスクラップブックにはセバスチャンさんの過去への探求が凝縮されている
サントル・ド・ジュール・ラダマン︱Centre de Jour I’Adamant
2010年設立。セーヌ川右岸シャルル・ド・ゴール橋のたもとに浮かぶ、船型のデイケアセンター。精神疾患のあるパリ1区の成人を無料で迎え入れ、アートセラピーやワークショップなどを提供している。サポートチームは精神科医、心理学者、看護師、作業療法士、専門教育者、精神運動療法士、ケアコーディネーター、病院サービススタッフのほか、アーティストやアートセラピストといった、さまざまな外部協力者によって構成されている。
建物は水面に浮かぶフローティング・ビルで、設計は船舶の内装デザインを専門とするジェラール・ロンザッティさんが率いる「セーヌデザイン」が、チームのメンバーだけでなく来訪者とも密接に協力し合いながら手がけた。日照にあわせて開閉する木製のパネルや、雨音を感じ雨水が階段状に伝う屋根など、利用者が自然のなかにいることを感じられるつくりになっている。
www.hopitaux-saint-maurice.fr/Adamant/5/138/102
山下正太郎|Shotaro Yamashita 本誌編集長/コクヨ ヨコク研究所・ワークスタイル研究所 所長。2011 年『WORKSIGHT』創刊。同年、未来の働き方を考える研究機関「WORKSIGHT LAB.」(現ワークスタイル研究所)を立ち上げる。2019年より、京都工芸繊維大学 特任准教授を兼任。2022年、未来社会のオルタナティブを研究/実践するリサーチ&デザインラボ「ヨコク研究所」を設立。
【イベント情報】
© TS Productions, France 3 Cinéma, Longride–2022
映画『アダマン号に乗って』上映会&アフタートーク
『WORKSIGHT[ワークサイト]20号 記憶と認知症 Memory/Dementia』の刊行を記念して、書籍で取り上げた映画『アダマン号に乗って』の上映会&トークを9月29日(金)に開催いたします。
日仏共同製作のドキュメンタリー映画『アダマン号に乗って』は、第73回ベルリン国際映画祭で金熊賞〈最高賞〉を受賞。現代ドキュメンタリーの名匠ニコラ・フィリベール監督がセンター利用者の日常をそっと見つめ、深刻な心の問題やトラウマを抱えていても彼ら・彼女らのなかに光る人となりや創造性を、優しい眼差しで映し出しています。
映画の上映後には、〈記憶〉をめぐる取材の旅に同行したWORKSIGHTコンテンツ・ディレクターの若林恵が、本作品と「特集=記憶と認知症」に迫るアフタートークをお送りします。参加者の皆さんと一緒に思いを巡らすオープンディスカッション!奮ってのご参加をお待ちしています。
【概要】
■日時
2023年9月29日(金)19:00 - 22:00
■タイムテーブル
18:30 - 開場・受付開始
19:00 - 20:50 映画『アダマン号に乗って』上映(109分)
20:50 - 22:00 アフタートーク
■アフタートーク登壇者
若林恵(WORKSIGHTコンテンツ・ディレクター)
宮田文久(WORKSIGHTシニア・エディター)
■開催場所
ツバメスタジオ/Tsubame Studio 3階(東京都中央区日本橋小伝馬町13-2)
■参加費
入場券:1,500円(税込)
書籍付き入場券:2,980円(税込)
■定員
30名
■主催
WORKSIGHT/黒鳥社
■協力
ロングライド
Photo by Hiroyuki Takenouchi
『WORKSIGHT[ワークサイト]20号 記憶と認知症 Memory/Dementia』は、全国書店および各ECサイトで販売中です。書籍の詳細は8月24日(木)配信の特別ニュースレターをご覧ください。
【目次】
◉記憶をめぐる旅の省察
文=山下正太郎(WORKSIGHT編集長)
・ザ・ホーグワイク|認知症居住者が自律協働する「町」
・マフトルド・ヒューバー|ポジティブヘルスという新たな「健康」指標
・エミール|ケアの技法を学生に授けるスタートアップ
・デポ・ボイマンス・ファン・ベーニンゲン|アート・収蔵庫・市民の記憶
・ヴィラージュ・ランデ・アルツハイマー|認知ケアを社会に開くために
・サントル・ド・ジュール・ラダマン|セーヌに浮かぶ開かれたデイケアセンター
◉記憶・知識・位置情報
桑木野幸司・ルネサンス期の「記憶術」が教えること
◉記憶をめぐる本棚
◉内戦の記憶・時空を超える音楽
ベイルートの音楽家・建築史家が描く「ホテルの戦い」