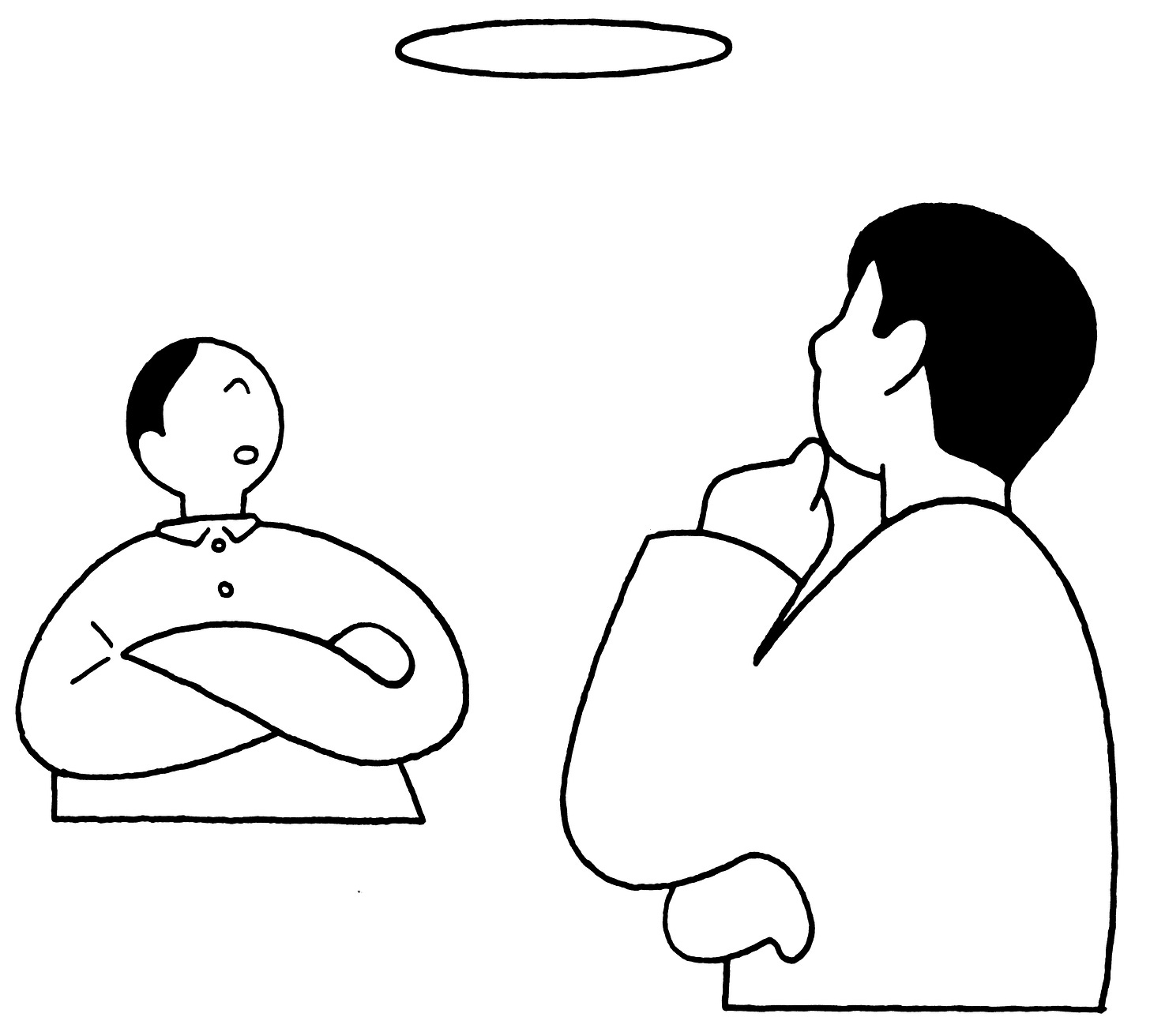人の話を「きく」ためのプレイブック:哲学者・永井玲衣と"対話"を考える
毎日誰かと触れあい、ことばを耳にしながらも、なかなかうまくできない「きく」ということ。そもそも、人の話を「きく」とはどういうことだろうか。学校や企業などさまざまな場所で「哲学対話」の活動に取り組む哲学者・永井玲衣とともに考えた。
スケーター、文化史家、哲学者、音楽家などへの取材を通じ、「声」をきくこと・書きとめることの困難と可能性に向き合ったプリント版『WORKSIGHT[ワークサイト]19号 フィールドノート 声をきく・書きとめる Field Note』。
本日7月25日(木)、本誌に登場する哲学者・永井玲衣の新刊『世界の適切な保存』が発売された。これに際し、永井玲衣による「きく」ための5つのヒントと、WORKSIGHT編集部員3名が加わり「きく・きかれる」ことの難しさを語り合った企画「人の話を『きく』ためのプレイブック」を特別公開する。
行為だけでなく態度としての「きく」とは。また、その過程で経験する「わからなさ」や沈黙との向き合い方についても掘り下げた。
永井玲衣|Rei Nagai 学校や企業、寺社、美術館、自治体などで哲学対話を行うほか、哲学エッセイの連載も手がけるなど、幅広く活躍している。著書に、『水中の哲学者たち』(晶文社)などがある。詩と植物園と念入りな散歩が好き。
A Listening Playbook
人の話を「きく」ためのプレイブック
哲学者・永井玲衣とともに
Illustration by Kenro Shinchi
Interview & Text by Sonoka Sagara/Yasuhiro Tanaka/Fumihisa Miyata
1. そもそもこの場は「きく・きかれる」ができる場だろうか?と問う
いきなり人に話をきこうとする前に、まず自分たちがいる場が「きく・きかれる」ことができる場なのか、じっくり問い直すことから始めてみませんか。「きく」は独立した行為ではなく、「きかれる」ことと密接に関係しています。さらには単なる行為でさえなく、こうした問い直しの態度も含んでいるものです。
なぜ、場を問い直すのか。それは、そもそもなぜわたしたちには「きく・きかれる」が必要なのか考えることと、密接につながっています。果たして、いまの社会は「きく・きかれる」ことができる場所でしょうか。「大丈夫じゃない場所」で溢れていて、誰しも傷ついた経験があるのでは。
だからこそ最初に、一人ひとりが「ここならいてもいいかな」と思える、大丈夫だと感じられる場であるかを問い、互いに確認してみましょう。よく「きく」ために必要なことはルールや技術ではなく、「きかれる」ことも含んだ土台自体へのケアなのです。
ただ、「大丈夫だと思える場」は、「傷つくことがない場」ではなく、「傷ついたとしても、ここなら大丈夫かな」と思える場、「きく」「きかれる」が途切れることなく続いていく場であることも重要です。定義や縛りがきつすぎると、「きく・きかれる」は続きません。逆に、どういった場で「ない」のかは問うていい。急がされない、強いられない、決めつけられない、損ねられない……こうした輪郭のもと、フワッと場が立ち上がるかもしれない。
もし、のちほど挙げるキーワードとともに「きく・きかれる」経験をしたと思えたなら、次はそうした場を身の回りに増やしていくこともできるはずです。まだ社会では一般的ではない「きく・きかれる」経験を、日常にもち込み、試してみる。自分以外の人たちと、大丈夫だと思える場で「きけた・きいてもらった」経験談を、集めるのも素敵です。こうした積み重ねをしていくと、いつの間にかわたしたちの日常が少し変わっているかもしれません。
2. わからなさの共有
いざ「きく・きかれる」を始めてみると、たくさんの「わからなさ」や「ままならなさ」に出会うかと思います。それらを無理に消そうとするのではなく、隠すのでもなく、そのまま受け入れてみるとどうでしょうか。
「きく・きかれる」のなかで、「わからない」と感じることがあったとき、ついつい先を急いでしまってはいませんか。沈黙を恐れ、間を埋めるかのようにことばを発して、ますますわからなくなる。そのうちに「わたしは何を言っているんだろう」「わかっていないやつだと思われたんじゃないか」と不安が募る。そんな経験が、誰にでもあるのではないでしょうか。
沈黙は怖いもの、埋めたいものだと感じられがち。そんなとき、こんな風に考えてみるのはどうでしょう。
──沈黙は、「きく」ということが自分のなかに響いている時間。
こう考えることが、「そのまま受け入れてみる」ことにつながる。「きく」を本当に集中してやろうとすると、わたしたちはことばを失うことがあります。あまりにもその人のことばが自分のなかに流れ込んだとき、何も言えない時間が訪れる。沈黙も「きく」のうちなのですね。恐れながらも、恐れすぎない。その絶妙な距離感が鍵かもしれませんね。
沈黙を味わったあとは、ことばを発してみましょう。わからなさと沈黙のなかで生まれたものを、ゆっくりと自分のことばで表現してみる。まとまっていないことばたちを否定するのではなく、他の人のことばを借りてみるのでもなく、自他のままならなさをそのまま悩み、受け入れながら発してみるとよさそうです。
そもそもわたしたちは、わからないからこそ「きく・きかれる」をしているのです。「わかったふり」のかわりに、「わからない」と言える場所にしてみるのも面白い。わからないな、ままならないな、と感じながら、まずはそのなかに滞在してみる。そうすることで、自分のなかから浮かんでくることばたちにも気がつけるかもしれません。
3.「人それぞれ」にしない
突然ですが、「人それぞれ」ということばにあなたはどんな印象を抱くでしょうか。寛容さ、多様さ、冷たさ、諦め……さまざまなニュアンスがありますよね。誰かの話を「きく」とき、相手の考えを尊重する意味での「人それぞれ」という考え方はとても大切です。
一方で、それが「きく・きかれる」の最後に「やっぱり、人それぞれだよね」というように使われてしまうと、どうでしょうか。個人と個人が切り離されて「あなたはあなたでご自由に」という意味がにじんで、なんだかシャットダウンされたかのような気持ちになってしまいませんか。とはいえ、わたしとあなたが違う人間であることもまた事実です。
だからこそ、「人それぞれ」ということばを、ゴールではなく「スタート」にしてみましょう。「人それぞれ」だという認識を踏まえて、「きく」を続けてみませんか。「きく・きかれる」というのは、他者と互いに交わろうとする行為です。「人それぞれ」を起点にしつつ、その交わりを諦めず、「きく・きかれる」をできるだけ続けてみませんか。
もしも「きく・きかれる」を諦めて「人それぞれ」に着地していく流れになると、「あなたはあなたですよね」とその場が閉じてしまうばかりでなく、逆に相手(の意見)を「変えてやる」と、論破に必死になるような状況も生まれかねません。
ですから、「人それぞれ」はあくまでスタートラインなのです。「人それぞれ」をゴールにして他者との交わりを諦めてしまうか、あるいは相手を無理やり変えてしまうか、といったような二元論に陥るのではなく、その間を探求してみましょう。「きく・きかれる」の往復のなかで、自分も相手も変わりうるからこそ、自分と相手とはどこが同じで、どこが違うのか、問いを重ねていく。そんな時間にできればいいですね。
4. 問いをひらく
みなさんは「きく・きかれる」の最中、どこを見ていますか。話している人の目? それとも口元? 何かしらの目的のために、みんなで改めて集まって話す場というのは、なんだか緊張しますよね。
そんなとき、みんなの真ん中に「問い」をひらいて、置いてみるといいかもしれません。そうすることで、お互いに目をバチバチと合わせなくても、共通のものを見つめながら話すことができます。これは別に、「今日はこれについて話し合おう!」というハードかつマッチョな問いをドンと置こう、ということではありません。
「きく・きかれる」を、リラックスして、みんなの共同の営みとして続けていくために、「問い」を媒介にしてつながりを見いだしていったらどうだろう、ということなのです。ですから、世間一般に「問い」と呼ばれるものでなくてもいい。お互いの間の媒介物を見つけましょう、とも言い換えられます。「いま、同じことについて話しているよね」という感覚だとも言えます。
それでも、媒介物を「問い」と呼んでみるとよいことがあって、それはお互いのわからなさが前提となることです。「テーマ」として定めると、お互いの知識量などの差に意識がいき、「きく・きかれる」が萎縮することもある。結論や正解を急いで見つけるのではなく、共通の「問い」から「きく・きかれる」の循環を引き出してみましょう。
さて、「きく・きかれる」の場における媒介といえば、ファシリテーターといった立場の人間がいることもあるかもしれません。でも実はファシリテーターも、「きく・きかれる」場をうまくひらく媒介となれるかどうか、不安を抱えていることだってあるんです。媒介となるファシリテーターもまた、人間ですから。ちなみにわたしはいつも不安です。
だからこそ、参加者一人ひとりが「みんなでこの場をつくっている」という共通意識をもてればいいですよね。媒介物としての「問い」は、みんなにひらかれているものなのです。
5. もろさを大切にする
もろさを大切にするというのは、自分の前提が壊れてしまったり、あるいは自分が変わっていったりする可能性を想定しておく、という構えのことです。自分が変わってしまわないよう構えるのではなく、むしろ変わりうることをあらかじめ受け入れておく、と言ってもいいかもしれません。
「きく」側も、「きかれる」側も、互いにもろい存在です。「わからない」からこそ「問い」をひらいて場を共有するのと同じように、わたしたちは明確な主張をもって集まるのではありません。手ぶらで集まり、同じ問いを眺めながら、相手のことばと、そこから生まれる自分のことばに、耳をすましてみるわけです。
ですから、確固たる自我をもつ個人同士がディベートするような議論モデルとは、当然異なってきます。「きく・きかれる」場が刻々と変容するなかで、自分も相手もまた、ふっと変わっていく瞬間がある。その「もろさ」を大事にしてみたいのです。
決して、自他がどんどん変わっていってしまうことを受け入れよう、ということではありません。例えば、相手が深刻な話をしているとき、「この話のすべてを受け止めることはできないかも」と思う瞬間はあるでしょう。「すべてには共感できないけれども、でもこの人がわたしに向けて話してくれているということ自体は受け止めたい」と感じることもあるかもしれない。
そうして悩んだり、葛藤したりすることがすでに、もろさを大切にする営みの一環であるはずです。別の言い方をすれば、メソッド化された議論のようにすぐ整理してしまうのではなく、「きく・きかれる」を続けるなかで、自他が宙づりのままでいられるかどうか、ということかもしれません。
「きく・きかれる」は、辞書を引いたら見つかるような答えに最短でたどり着くことが目的ではありません。むしろ、「きく・きかれる」を繰り返すことで、もろさを基盤にしたわたしとあなたがそっと変容する瞬間に出会うことこそが、とてつもなくかけがえのないものなのです。
「きいてもらえた」ことって、ある?
永井 これから「きく」とはどういうことだろうと考えていく前に、そもそも編集部のみなさんも含めて、わたしたちは「きく・きかれる」ということを経験したことがあるだろうか、ということが気になっています。「聞く」「聴く」といったいろんな意味を含めてわたしは普段「きく」とひらがなで書くのですが、その上で、編集部のみなさんがわたしに「きく」のではなく逆にわたしからみなさんに、「今日、きいてもらえたな」「ここはきかれる場だな」と思えた過去の経験を「きく」ことから始めてもいいですか?
編A なんでしょう……仕事ではあまり思い浮かばないですね。
編B わたしも仕事上はあまりないですが、プライベートでは少し思い当たります。2年前に父が倒れてしまい、その話を友人にしたら、彼は普段まったく泣くタイプではないのに一緒に泣いてくれて。そのとき「きいてもらえた」と感じました。また、それ以来、父は寝たきり状態でわたしが話をしてもことばは何も返ってこないけど、少し笑顔になっている表情を見ると、「ああ、きいてくれているな」と感じることがあります。
永井 「きく」というのは「きいたよ」と言われて認識するわけじゃなく、ことばがなくても「あ、いまきかれた」と直感するというのは面白いですね。あと、きかれた経験が仕事の場であまり思いつかないというのも、ものすごく興味深い(笑)。
編C 仕事柄、きくことは多いのですが、医者の不養生とでも言うのか、やはり「きかれた」経験はなかなか……(笑)。プライベートではありますが。
編A わたしは「きいてもらった」ときより、「きけた」ときのほうが安心するかもしれません。普段の友人とのお喋りでも、たくさん話してしまうと「話しすぎちゃった」と帰り道に反省しがちなのですが、相手の話をよくきけたときは安心感があります。
編B 仕事において「きかれる」経験があまりないと感じるのは、お互いに仕事上の役割があるからかもしれません。家族や友人関係だと仕事のときほどは役割が明確ではないから、「きかれた」という感覚が立ち現れるのではないか、と。
永井 その役割というものは、わたしも感じることがありますね。普段「哲学対話」という実践をしているのですが、ある会社から哲学対話のご依頼を受けて、事前に主催者の方と簡単に会話をしたときは、「きく・きかれる」がとてもうまくできたんです。でも後に仕事としてミーティングをした際、その方がスライドで説明する場面になった途端、「ご質問はございますか? はい、はい、なるほど。では次は……」というように、語り方が司会者のそれに切り替わっていて、その方の話を「きく」ことも、わたしの話を「きかれる」こともできなくなってしまった。役割がお互いの関係性を如実に変えるんだ、そしてこの語り口をどうやってもわたしは変えられない、と思ったんです。別に無理に変えたいわけじゃないんだけど、わたしがどんなにきいても、あるいはわたしが話しても、この人はずっとこの語り方で固定されて、もはや「きく・きかれる」ことはできないんじゃないか、という直感的な不安に襲われたんですよね。
編A 「きく・きかれる」という関係が自然と発生していた場が、議論モードへと変わってしまったということですよね。逆に議論の場を、「きく・きかれる」の関係性へと変えていくことはいかに可能なのか、考えることがあります。会議であれば、何らかの結論を出すとか次のアクションを決めるといった目的があるはずなので、なかなか難しいところだと思うんですけれど……。
永井 みなさんは、どう思いますか?
編B わたしは去年、ある方に4日間密着取材したんです。最初はあらかじめ用意した質問を投げかけていたのですが、そのうち想定していた質問なんて使い尽くしちゃって。そこからは、ちょっとでも気になったことにつっこんだり、自分の意見も言うような態度で接したりしていたら、後から「こんなに自分の活動や思いを本音で話せたのは初めてです」と言っていただけたんですね。「最初は仕事のような感じだったかもしれないけど、わたしに心の底から興味をもってくれるような質問に変わって、だからわたしもそれに応えないといけないと思った」と。
編A 本来「きく」には、たっぷり時間があることが必要なのかもしれません。普段の会議だと、特に最近はリモートで効率化も重視されていて、必要最低限のことだけ話す態度になってしまっている気もします。
この場を、どういう場にしたいのか
編C 時間ということですと、信頼のおける場であることを確認するために流れる、“はじまり”の時間が気になります。取材仕事では冒頭で「わからないなりに、あれこれ調べて準備してみたんですが……」と相手の信頼を得ようとすることがありますが(笑)、でも「きく」ことは、そういう準備の話じゃないですよね。わたしは相手の声のボリュームやテンポに自分のそれを自然と合わせることもありますが、短時間での信頼の場は、どう築けばいいでしょうか。
永井 悩ましいですね……。わたしが実践している哲学対話は他にもさまざまな場で行われているので、進め方は人によって違うのですが、わたしの場合、対話のはじめに“世界観の共有”の時間をつくっているんです。「こういう場にしたいんだ」という思いを開示する時間でして、「わたしはこうしたいんですけど、どうでしょうか」と呼びかけながら信頼の場をつくる。会議でも単にアジェンダの共有だけでなく、「今日はこういう場にしたい」という場の設定への思いを共有するのはひとつ有効かも。
編B 会議だと、仮に「冒頭は雑談時間」みたいにルール化された瞬間、それ自体がまた仕事のようになってしまうという変な連鎖が起こりがちですよね。ルール化ではなく場の設定をみんなで考えるのはよさそうです。
編C ワークショップでも、最初に「ひとまずアイスブレイクしましょう」と言われると、何のためのアイスブレイクなのかよくわからなくなりますよね(笑)。
永井 友人主催の哲学対話が、興味深かったんです。彼女は冒頭に「こういう場にしましょう」とルール化するのではなく、「安心できる場所にしたいんだけど、そのためにみんなはどうしたいですか」と投げかけていたんですね。「セーファープレイス」と書いた紙の下に「わからなくなってもいい」「ちょっと嘘をついてもいい」とか、参加者一人ひとりの希望を書いていきながら、全員でその場をつくっていたのが新鮮で。ここがまさに「わからなさの共有」にも関わってくるところですが、わからないし不安だからこそ、協働的に一緒に表現する場をつくろうとすることが、「きく・きかれる」に力を与えると思うんです。
編A その上で「わからなさ」をどう共有できるか、ですよね……。「意見が途中で変わってもいい」「考えがまとまってなくても話していい」ということを前提にできる場もあるにはありますが、とはいえ会議であれば限られた時間でやはり収束させなくてはならなくて。頭でわかってはいるんだけど、実行するのは難しいなと思うことも多いです。
永井 本当にそうですよね。時間の制約はあれど、「わからなさ」を共有しながら「きく・きかれる」の関係が生じている場ってあるのだろうかとモヤモヤ考えていたんですが……あるとしたら、それはどんな場なんでしょう。
編C お互いに問いがうまくひらけたときは、少し「わからなさ」を共有できている心地がします。一方的にきき出す関係じゃなく、こちらがきこうと思っていたことは相手がしゃべりたいことなのかどうかの確認も含めて、結果的に話が第三項としての問いへと発展していったときには、互いに結論もなくふわふわしながらも、短い時間で「きく・きかれる」関係が築けた感じがします。
永井 そうしたケースを、わたしは普段、「場がちゃんと育っている」ということばで表現しています。場が育っていたら時間の制約があっても平気なのかもしれません。ただ、それに油断して「どうせこの人はこういうことを言うだろう」と思い込むと、「きく」を阻害してしまうこともあるんですけど……。だからこそきちんと丁寧に場を育てたいと思うのですが、初対面の人への取材や新しいクライアントとの会議など、関係性もできておらず時間の制約もあってすごく大人数でというような、場を育てることが難しい場合はどうしたらいいのでしょうね。
相槌の耐えられない軽さ
編C 悩むのは相槌です。短時間で相手にとって話しやすい場をつくるために、すぐに「なるほど」「へえ」と言ってしまうんですけど、よく考えたらそれを連発している自分は何なんだろう、と(笑)。相槌を打たないと場は育たないけれど、入れすぎると逆に何かをオミットしている感覚もあります。
編B わたしはもしかしたら、自分の居心地の悪さを排除するために「なるほど」などと相槌を打って、間を埋めようとしているかもしれません。まずは相手の意見を批判せず受け入れてから意見を、というような会議の心構えは社会人の常識だと教わることもありますが、それもまた自分が実践する場合、居心地の悪さを無意識的に回避しているだけかもしれないな、と。
編A わたしは「なるほど」と言われると、「人それぞれだよね」と言われたときと同じような感覚になります(笑)。もちろん、相手が心の底から「なるほど」と思ってくださっていることが伝わるなら別ですが、「なるほど、なるほど」と軽く相槌を打たれると、実はわたしが話してることと相手は違う意見をもっているんだなと思ってしまい、諦めのニュアンスを含んだ「人それぞれ」ということばに似た寂しさを感じることがあるんです。
永井 「人それぞれ」と諦めてしまうと、そこで「きく」営みも停止してしまうんですよね。相手のことを「わかりたい」とか「わたしとどう違うんだろう」とか、そういった葛藤のなかで「きく」は永遠に続くはずなのに、表面的なダイバーシティ尊重で終わってしまう。そう考えると、相槌もまた難しいですね……。過去に学生たちと、相槌を打たずに対話する実験をしたことがあるんです。Aさんのお話にあったように、相槌という「『きいていますよ』サイン」が、きかれている側からしたら評価の軸になってしまうことがあるので、相槌を禁止してみたんですよね。実際やってみると、ものすごくしんどい。きかれて話しているほうもしんどいんですが、きいている学生もみんな身体を動かさず、目はバキバキで息も止めてしまうくらい(笑)。
編B きくほうも辛くなるんですね。
永井 Bさんがお話しくださったような、自分を居心地よくするための相槌という側面も、大事な気がします。「わたしがここにいてもいいかなと思える場をつくる」というのは、言い換えると「自分にも相手にも無理をさせない場をつくる」ことでもある。間を埋める行為も、やっちゃいけないというよりは、“やっちゃうもんだと思いながらもやる”葛藤を抱えていればいいと思うんです。間を埋めたくなるのは当然で、沈黙が気まずいのも当然、それを「気まずいよね」って認めることもまた大事なのかなと。あといま、「きく・きかれる」ってつくづく“態度”の話なのだなと思いました。「きかれている」という感覚は、「きく」人が「うん」と言って身体を動かすとか、ちょっと息を吸っているとか、そういう「きく」側の全体性を「きかれる」側が受け取ることで訪れるのだなと、改めて感じましたね。
きいて、きかれて、少し変容してゆく
編A とはいえ、「問いをひらく」ことにも関わる点として、安全な場や居心地のよい場にしたいと望んでいても、なぜか“自然な流れ”でそれが脅かされてしまうこともありますよね。例えば、悪意はないんだけれども論破癖をもっていたり、口調が怖かったりといった人が場のなかにいると、本人も意図せぬままに場の安全が脅かされてしまうことがある。すると、問いを共有したり、お互いのつながりを見いだしたりできなくなってしまいます。そういう場合にできることって、何かあるでしょうか。
永井 これもまた難題ですね……みなさんはどうしてますか?
編C 他の人に話を振るとか、相対的にその人のもち時間を減らすということはよくしますね(笑)。限られた時間内で、その人の態度変容まではなかなかいけないだろうなと……。人生をかけて培ったハビトゥスごと場にもち込まれているはずなので。
編A わたしは相手にシンプルに尋ねちゃうタイプです。本人も自分のハビトゥスに気づいていないこともあるので、「え、それってどういうことですか?」などと、無邪気にきいてしまいます(笑)。
編B わたしも基本的に個人は変えられないと思っているので、場を中和させようとしますね。あえてその人と真逆の意見を言ったり、ある人が別の人をひどく批判してたら、批判とは真逆の擁護をしたり、批判されている意見の素晴らしいところを口にしてみたり。あと、笑っちゃうこともあります。それも中和に近いかもしれません。
永井 みなさん共通するのは、焦点が人というより場に当たっていることですよね。人が発する言葉、身体性、雰囲気、それらから構成されている場すべてをできるだけケアしようとすることが、大丈夫だと思える場に近づくことを可能にするのではないかと。
編C そうした安全な場だからこそ、“変容”が可能なのかもしれないですね。
永井 はい、これは「もろさを大切にする」ということにも関係しそうです。お互いに知らない場にたどり着くような可変性だとか、冒頭でBさんがおっしゃっていたような「あ、泣いてくれるんだ」といった思いもよらないような体験、あるいは気づいたらこんなに話していた、というような出来事は、「きく・きかれる」がグルグルと動いているからこそ生まれるものだと思います。「もろさ」というのは、このときに重要になる。例えば、相手がとても切実な話をしているのをきいていると、その人と一緒に自分が弱くなっていく感じがする。「それってこういうことだよね」と超越的にその人のことばを整理するのではなく、真剣に耳を澄ませたときに、自分も痛みを感じることがある。決して相手の痛みと同じわけではないのだけど、きくことで自分が崩れてしまうような、ある種のもろさを大切にするという感覚でしょうか。議論モードだと異なる意見に勝たなくてはいけないので、弾を込めるように自分を硬化させると思いますし、そうしたモードが場を脅かすと、「もろさ」を大事にできません。「きく」「きかれる」とことばは使い分けているけれど、今回改めて、ものすごく密接で相互的・共同的なものだと実感しました。「きく・きかれる」を分離せず、あえて絡まり合ったままの状態で、かつ外にひらきながらわたしも探究したいと思っていますし、このプレイブックも同じように、読者のみなさんへひらいておきたいなと思います。
※本稿は『WORKSIGHT[ワークサイト]19号 フィールドノート 声をきく・書きとめる Field Note』の転載記事です。記事の内容は発行日である2023年4月27日時点のものです。
『WORKSIGHT[ワークサイト]19号 フィールドノート 声をきく・書きとめる Field Note』は、全国書店および各ECサイトで販売中です。書籍の詳細は4月27日(木)配信の特別ニュースレターをご覧ください。
【目次】
◉巻頭言・ノートという呪術
文=山下正太郎(WORKSIGHT編集長)
◉スケーターたちのフィールドノート
プロジェクト「川」の試み
◉スケートボードの「声」をめぐる小史
文化史家イアン・ボーデンのまなざし
◉ノートなんて書けない
「聴く・記録する・伝える」を人類学者と考えた
松村圭一郎・足羽與志子・安渓遊地・大橋香奈
◉人の話を「きく」ためのプレイブック
哲学者・永井玲衣とともに
◉生かされたレシピ
「津軽あかつきの会」の営み
◉野外録音と狐の精霊
デイヴィッド・トゥープが語るフィールドレコーディング
◉それぞれのフィールドノート
未知なる声を聴く傑作ブックリスト60
◉ChatGPTという見知らぬ他者と出会うことをめぐる混乱についての覚書
文=山下正太郎
【書籍詳細】
書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]19号 フィールドノート 声をきく・書きとめる Field Note』
編集:WORKSIGHT編集部
ISBN:978-4-7615-0925-5
アートディレクション:藤田裕美
発行日:2023年4月27日(木)
発行:コクヨ
発売:学芸出版社
判型:A5変型/128頁
定価:1800円+税