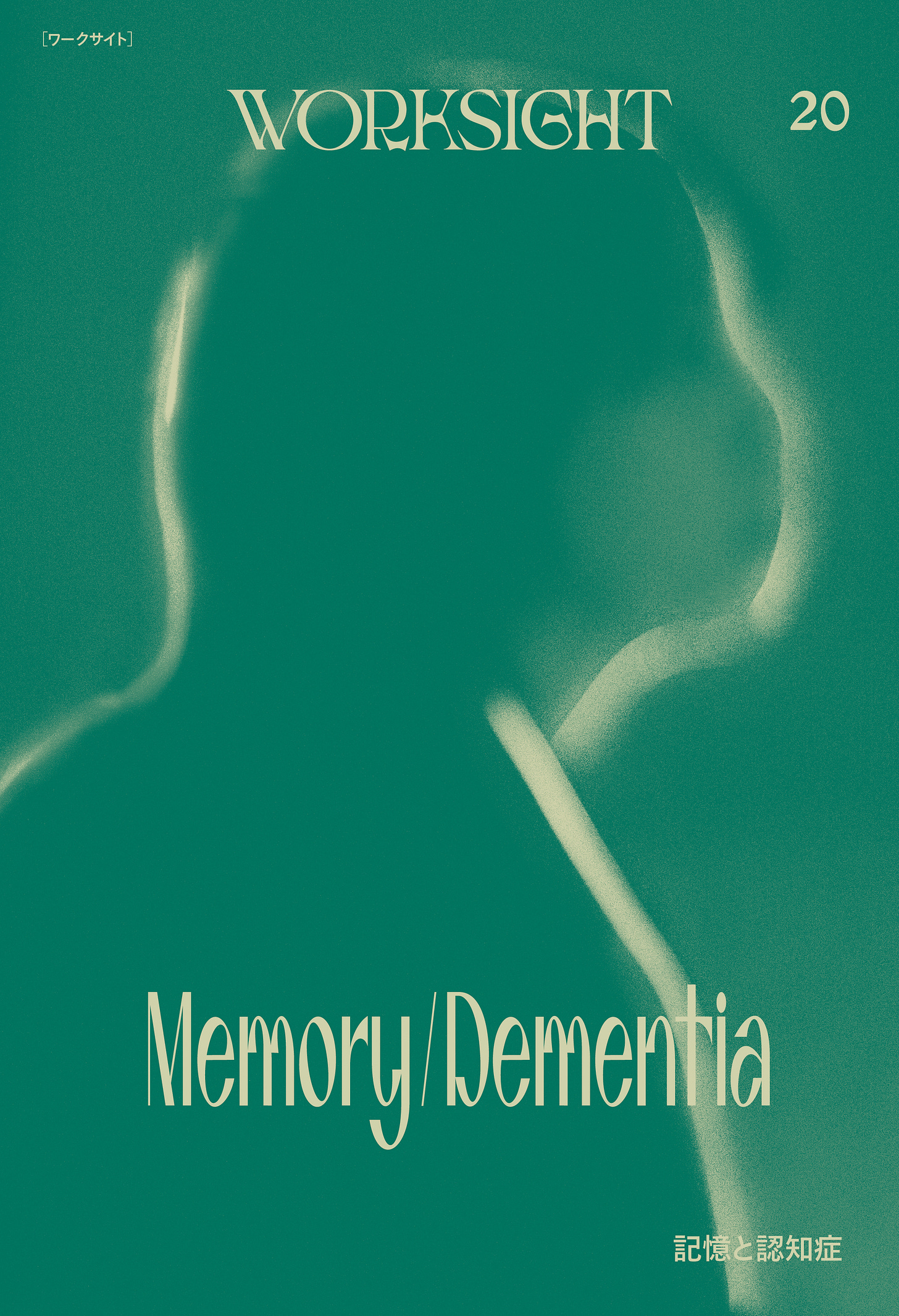「サラリーマン」の欲望と、無個性性の地平:鈴木貴宇さん、真実一郎さんと思案する「会社」【会社の社会史#6】
わたしたちの社会を象徴する存在であり続けてきた「サラリーマン」。会社と家の往復のなか、人びとは何を欲し、他方でその意識は何に縛られてきたのか。トークシリーズ「会社の社会史」第2シーズン第3回は、民俗学者・畑中章宏、WORKSIGHT編集部・工藤沙希(コクヨ ヨコク研究所研究員)、若林恵(黒鳥社・編集者)、サラリーマン研究の第一人者である鈴木貴宇さん、真実一郎さんが集い、充実した議論が展開された。
1987年の東京、パチンコ店の光景 Photo by Raphael GAILLARDE/Gamma-Rapho via Getty Images
多様なキャリア観や家族観が広がるなか、職場結婚と寿退社がセットで考えられていたような時代は、だんだんと遠くなりつつある。ただ、昭和から平成、平成から令和へと年号は移り変われど、サラリーマン文化は(男女問わず)人びとの規範意識に影響を与えているだろう。わたしたちはいったい、「会社」で働きながら、あるいは働く人の傍らにいながら、日々の暮らしのなかでどんな欲望を抱いてきたのだろう。
今回の課題図書は鈴木貴宇著『〈サラリーマン〉の文化史 あるいは「家族」と「安定」の近現代史』(青弓社、2022年)と、五十嵐彰・迫田さやか著『不倫―実証分析が示す全貌』(中公新書、2023年)。オーディエンスとして足を運んでくれた著者の鈴木貴宇さん、サラリーマン漫画研究で知られる真実一郎さんとともに、サラリーマン文化をめぐる解像度が一段と高まる、そんな議論がかわされた。
text by Fumihisa Miyata
研究者にとっても謎、当事者にとっても謎
工藤 今日は諸事情により、普段登壇しているコクヨ ヨコク研究所所長の山下正太郎がいないのですが、本当に嬉しいことに、参考図書に挙げている『〈サラリーマン〉の文化史』の著者である鈴木貴宇さんが会場にいらしてくださいました。
若林 「会社の社会史」というシリーズは外部からの反響がほとんど聞こえてこないまま6回目を数えていますので、鈴木さんがお運びくださったこと、とてもありがたく存じます。恐れ入りますが、フロアに向けて自己紹介をいただいてよろしいでしょうか。
鈴木 はじめまして、鈴木と申します。実はこの場にうかがっていいものかどうか迷ったんです。イベント告知を見つけた『〈サラリーマン〉の文化史』担当編集者が知らせてくれたんですが、もしかしたら著者抜きでこっそり開催したいのかもしれないし、どうしようかと(笑)。ただやはり、みなさんがどのように拙著を読んでくださったのか、ぜひ聞いてみたいと思い、足を運んだ次第です。よろしくお願いいたします。
畑中 いままでにない回になりそうですね。さて、どのあたりから入っていきましょうか。
若林 鈴木さんのご著書はものすごい情報量の多さでして、どんな感想を抱いたのか、フロアの方にご感想をうかがうところから始めてみたいですね。読んだ方はいらっしゃいますかね、(目の前の男性に)いかがでしたか?
男性A 全体を精読できているわけではないのですが、とても面白かったです。実はわたし、真実一郎と申しまして、『サラリーマン漫画の戦後史』といった本を書いている者でして……。鈴木さんの今回のご著書で参考文献に挙げていただいているということもあって、今日は楽しみにしてきました。
鈴木 えーっ、真実一郎さん!? お会いできて嬉しいです!
男性Aこと真実 こちらこそ、お目にかかれて光栄です。本についての議論を聞きにきたのですが、まさか著者の鈴木さんと直接お話しできるとは思っていませんでした。
若林 サラリーマン研究の大家のおふたりがこの場にいらっしゃるということですので、ここからのトークをお任せしてもいいかもしれません(笑)。
真実 いえいえそんな、恐縮です……。ともあれ鈴木さんの『〈サラリーマン〉の文化史』の何が面白いかといいますと、サラリーマンに対して徹底して客観的であろうとしていて、だからこそ深掘りできているというところです。サラリーマンがサラリーマンの研究をすると、当事者のリアリティは滲みつつも、どうしてもバイアスがかかってしまうのは免れません。一方で鈴木さんは、そうした“愛”に基づかずに対象を見つめる研究者の方だからこそ、冷静な学者の視点でサラリーマンの世界を深く探究されている。あまり他に類を見ない書籍だと感じました。
鈴木貴宇|Takane Suzuki(左) 東邦大学准教授。専攻は日本近代文学、日本モダニズム研究、戦後日本社会論。単著に『〈サラリーマン〉の文化史 あるいは「家族」と「安定」の近現代史』、編著に『社会主義リアリズムの系譜』、共著に『高度経済成長の時代』などがある。
工藤沙希|Saki Kudo(中央左) 本誌編集部/コクヨ ヨコク研究所研究員。「選べなさ」「社縁」「現代私祭」などへの関心を軸に、民俗学的な視点でのフィールドワーク、聞き取り、参与観察などの質的調査を中心とした社会研究に取り組む。
畑中章宏|Akihiro Hatanaka(中央右) 民俗学者。著書に『21世紀の民俗学』『廃仏毀釈:寺院・仏像破壊の真実』『忘れられた日本憲法:私擬憲法から見る幕末明治』『今を生きる思想 宮本常一:歴史は庶民がつくる』など。
若林恵|Kei Wakabayashi(右) 編集者。黒鳥社コンテンツ・ディレクター。元『WIRED』日本版編集長。2022年7月リニューアルした「WORKSIGHT」のディレクションを務める。著書に『さよなら未来』『週刊だえん問答』シリーズなど。
真実一郎|Ichiro Shinjitsu(写真外) サラリーマン兼ライター。2010年に『サラリーマン漫画の戦後史』(洋泉社新書y)を上梓。2018年に『サラリーマン漫画の戦後史(改訂版):昭和・平成を越えていけ』を電子書籍で刊行。
鈴木 著者冥利に尽きます。写真や漫画、映画、文学作品などの虚構、いわゆるフィクションを分析しながらサラリーマンと社会状況に迫る、という手法をとっている本でして、その意味でもみなさんがどう読んでくださったのか、どうぞ忌憚なきご意見を頂戴できればと思っています。
若林 実際の内容に入る前に、おふたりはそもそも、なぜ日本のサラリーマンに着目するようになったのですか。
鈴木 わたしは小学校から高校まで、日本にいなかったんです。父の仕事の関係で、小学校時代はシンガポールで、中高はアメリカで過ごしました。そうして海外におりますと「あ、あの人は日本人だな」とわかる人たちがいて、それがサラリーマンなんですね。アメリカだったら中国や韓国の人もいるのに、何でしょうか、独特のハビトゥスといいますか振る舞いによって「日本から来たおじさん」だとすぐわかる。すごく不思議で、日本社会のことを知りたいと思ったきっかけにサラリーマンの存在があるんです。
畑中 海外においても、他国からのビジネスマンと、日本から来たサラリーマンは雰囲気が違うんですか?
鈴木 まったく異なりますね。抽象的な言い方になりますが、例えば中国や韓国から来ている人たちは一個人に見える一方で、日本から来ている駐在員は会社を背負っている感じがします。わたしはそんなサラリーマンを見て「あの人は銀行だな」「商社だな」「保険だ」「政府関係者だ」などと見分けていたわけです。我ながらかわいくない子どもですが(笑)。そうしたサラリーマンのあり方は、どんな社会を背景にしているのだろうと興味をもっていったんですね。
工藤 真実さんはいかがですか?
真実 わたし自身が日本の会社のサラリーマンなんです。業務のなかで外資系のクライアントと仕事をすることがあるのですが、相手が日本人のときは上手に業務をまわすことができていたんですね。しかしあるとき、仕事相手がみんな外国人だったことがあり、従来のやり方がまったく通用しないという事態に直面して、ものすごく衝撃を受けたんです。そこで、海外のビジネスマンと日本のサラリーマンというのはまったく違うんだ、いったいサラリーマンって何なのだろうと考え、自分事化し、ルーツを探すようになりました。そうした立場で、今日はみなさんの議論を拝聴したいと思っています。
若林 ふと思い出したのですが、この「会社の社会史」というトークシリーズを始めたとき、ある感想をもらったんです。それが「テーマ的には面白いけれど、どこに需要があるのか」というご意見でした(笑)。深く考えるきっかけがなければ、会社勤めの人は業務後に会社の話なんかしたくも聞きたくもないでしょう。自らの属性を掘り下げるインセンティブや楽しみはあるのかと。そう考えると、鈴木さんのご著作はどんな方が読んでいるのでしょうか。
鈴木 わからないですね……(笑)。海外の研究者からは面白がってくれている声が届いています。ただ、海外の研究者が日本のサラリーマンに焦点をあてる場合、たいていは日本人男性のマスキュリニティ、それこそ買春ツアーなどで問題になったような男性性についてなんですよ。
若林 今回『〈サラリーマン〉の文化史』に加えてもう1冊参考図書に挙げたのが『不倫』という本でして、問題意識の底流にあったのは、まさにいま鈴木さんがおっしゃったようなマスキュリニティなんですね。鈴木さんのご著作でも自由恋愛や立身出世へと欲望が発動されていく様子について書かれていますが、わたし自身も海外駐在員の息子ということもありよくわかる話で、飲み会も含めた体育会っぽいサラリーマン文化に対して強い拒絶があります。ただし、ある種の性欲も含めた欲望というものがサラリーマン文化や日本社会を構成していった回路であるというのもまた、おそらくは事実だろうと感じていて、そうした観点のもとで『〈サラリーマン〉の文化史』や『不倫』を読んだところがあるんですね。『不倫』はそうした歴史意識よりは、とことん実証主義的な内容であることに価値のある1冊ですが。
工藤 『不倫』は、社会学者の五十嵐彰さんと経済学者の迫田さやかさんのご著書で、ごく最近である2020年の大規模な量的調査の結果をまとめたものですね。驚くべき数字として、不倫経験のある男性の割合がなんと半数にのぼるという……。他方の女性は3割に満たないぐらい。既婚男性は既婚女性より職場での出会いが比較的多いというデータも、今回のトークにつながるかもしれません。
若林 実は鈴木さんのご著作の端々にもこうした性的なトピックは顔を出すのですが、そこに触れるためにも、わたしの乱暴なサマリーではあるのですが『〈サラリーマン〉の文化史』に沿って日本の近代化以降の流れをまとめたいと思います。そもそも「近代日本の出発期の立身出世とは『書生』を終えて『お役人』になることであった。『官吏=立身出世』という図式は明治期の一八八〇年代まで続く」というところから始まるのですが、日清・日露戦争、第一次世界大戦を経て日本の資本主義および実業界が発展するなか、いよいよサラリーマンの時代が訪れます。
立身出世への選択肢に「官吏」以外のもの、すなわち「銀行・会社員」という〈サラリーマン〉層の構成を多く占める職業が定着する。(中略)そして「知識階級」が増加した一九二〇年(大正九年)以降、〈サラリーマン〉という用語も階層も普及することになる。
引用箇所は前後しますが、鈴木さんはこのようにも書いておられますね。
好景気のおかげで高利潤を出していた民間企業は、彼ら高学歴エリートに高給を約束する魅力に満ちた職場へと変わり、一獲千金の夢を求めた青年は官途に就かずに「会社銀行員」、すなわちサラリーマンになることを選んだ。(中略)大戦景気に沸いたこの時期は「日本のサラリーマンにとってのベル・エポック」といわれるゆえんである。
畑中 「よき時代(ベル・エポック)」のなかで、いまのわたしたちもよく知るところのサラリーマンが登場してくるわけですね。
1900年頃の早稲田大学の学生たち Photo by Buyenlarge/Getty Images
サラリーマン(をめぐるシステム)はつらいよ
若林 サラリーマンたちは消費活動も謳歌していくわけですが、しかしここで、やはりわたしたちがよく知るサラリーマンの「つらさ」も滲んでくるんです。
サラリーマンの需要が高まった結果、高学歴を得るためにこの時期から受験戦争が過熱する。(中略)「就職試験」に通過しても、度重なる受験で疲弊した青年たちにはもはや野心や大望を抱く余裕はなかった。こうしてここに「没落する中流階級」(森本厚吉)にして無気力なサラリーマンが出現する。金銭が与える刹那的な消費の快楽は、彼らにとってせめてもの自己回復の手段でもあった。(中略)
自己回復の手段であるはずの消費生活が、サラリーマンにさらなる呪縛──世間体という他者の視線による呪縛──をかけてしまう。(中略)かつては社会的地位の象徴だった洋服が、一九一五年(大正四年)頃には「らしさ」という規範を凝縮した束縛へと変わる。
現代を生きるわたしたちにとっても実感できる話ですよね(笑)。先ほど述べた性的なトピックも、この流れを押さえるとよく理解できるんです。『〈サラリーマン〉の文化史』を読んでいると、例えば明治期に日本が近代化していく過程において、「理想の佳人」(妻)を娶って「スウィートホーム」(家屋)を手に入れることへの欲望が台頭してきたことがわかります。これについて鈴木さんは、社会学者・見田宗介さんのことばを引用しつつ、次のように述べています。
文明開化によって解放された欲望は、西洋文明という「新文明」を象徴するモノへ無批判的に向かうことになる。見田は「金銀の鎖附きの時斗(とけい)を領(えり)に懸け秀麗なる服飾をせざれば、金玉のある男とは見えぬ」という当時の俗謡を例に、洋装に代表される西洋風の文化への志向が「新しい社会に適応するシンボル」として機能したとする。だが、この俗謡が鋭く衝いたことは、西欧化=近代化に失敗したものは「男性性」をも喪失せざるをえない、という「公的」な出世(官吏としての成功)と「私的」な成就(恋愛の達成)が不可分に癒着している点ではないだろうか。日本資本主義がまだ発達段階にあった日露戦争前には、官吏は「男の中の男」だとされていた。
官吏をサラリーマン的なあり方の先駆と見ているわけですが、こうした「公的な出世」と「私的な成就」がセットになった欲望は、いわば「会社」と「家」がセットになった規範意識となって、その後の日本社会でかたちを変えながら続いていきます。例えば鈴木さんが引用している『主婦之友』1937年8月号付録「娘と妻と母の衛生読本」には、次のような驚くべき注意書きがあるそうです。
御主人に出世して貰いたい方や立派な仕事をさせたい方は、エネルギーを乱費させぬように注意することは、奥様としての資格の大切な条件でありましょう。
鈴木 夜、奥さんは程よくエロティックになりなさい、というとても変な記事で、見つけたときは思わず笑ってしまいました。夫が他の女の子に目移りしないよう、妻は所帯じみてはいけないし、しかしあまりエロティックだと会社の仕事に差し支えが出るから適度に、という。ものすごく難しいことを要求されている。
若林 現在は状況が変わってきているとは思いますが、かつては妻の候補を会社で見つけ、いまは先述のとおり不倫相手も会社で見つけるわけですよね。果てはこのトーク前、わたしは「愛人手当を経費で落とせるか」というようなネット記事まで目の当たりにしてしまいました。キャバクラの費用も接待交際費として計上されてきたようなビジネス界の土壌を振り返ると、「会社」やサラリーマン文化というものは性欲をめぐるひとつのシステムなのではないか……という仮説まで頭に浮かび、暗澹たる気持ちにはなります。
畑中 他方で、これもまた鈴木さんのご著作にあるように、1920(大正9)年以降に「サラリーマン」ということばが定着しつつも、昭和初期には当事者たちに閉塞感が満ちていたわけでしょう。増加した「知識階級」の一画を占めつつも、不景気のなかでの階層分化を乗り越えようとする「勇気あるインテリゲンチャ」と、資本主義社会の現実を追認していく「蒼白きインテリ」に分裂していくなかでの八方ふさがり感がある。その行き止まり感は、すこし後の時代になりますが、きちんと指摘されてもいました。わたしは今回青空文庫で、日本共産党員の文学者として知られる宮本百合子が1937(昭和12)年に発表した「若き世代への恋愛論」という文章を見つけたんですが、面白いんですよ。
地道な若い下級サラリーマンや、職業婦人の間に、今日はこんな世の中だからよい恋愛や結婚は望んでも駄目だという一種の絶望に似た気分があるのも事実だと思う。青年たちは、自分たちの薄給を身にこたえて知り、かつ自分の上役たちにさらわれてゆく若い女の姿を見せつけられすぎている。職業婦人たちは、それぞれの形で、いわゆる男の裏面をも知らざるを得ない立場におかれている。私たちの新しい常識は、職場での結合をのぞましいものと告げているのだが、日本の社会の現実で、愛情の対象を同じ職場で見出すことはほとんど絶対に不可能に近い。
若林 「自分の上役たちにさらわれてゆく若い女の姿を見せつけられすぎている」というのは、にわかには想像しがたいですが、おぞましい光景ですね。
畑中 鈴木さんは『〈サラリーマン〉の文化史』で、劇作家・岸田國士がサラリーマン家庭を描いた戯曲『紙風船』について論じておられますが、この戯曲が発表されたのは1925(大正14)年。岸田は後に、大政翼賛会の文化部長となりますね。宮本の文章を踏まえると、昭和10年代の日本社会では国家主義者と、労働者と連帯していく社会主義者のあいだで、どちらの陣営がサラリーマンをとりこむことができるのか争われていた、という見方もできるのかもしれません。
(上)1920年代前半の東京駅前の様子 Photo by Joseph Kraus/picture alliance via Getty Images (下)1920年頃の芸者たち Photo by Keystone-France/Gamma-Rapho via Getty Images
転がる紙風船、文化住宅という夢
工藤 岸田の『紙風船』に関する記述を、わたしはとても面白く拝読しました。「目白文化村」に住む結婚1年目の若夫婦が主人公で、そのふたりの会話によって進む戯曲ですが、夫婦の固有名詞が明示されないんですよね。「夫」と「妻」としか示されないふたりの会話が続くわけですが、印象的なのが鈴木さんも触れているこのやりとりです。
妻 あたし、日曜日がおそろしいの。
夫 おれもおそろしい。
夫婦は近代家族の規範を「らしく」生きようとしながら日常を送っているわけですが、日常というのは、平日のサラリーマンのルーティーンから逸脱した時間であるわけですよね。夫はただのひとりの男であり、勤めから帰る夫を待つ妻もひとりの女に過ぎない。そんな社会的属性から自由になった時間が訪れたとき、向き合うふたりのあいだには何ら先行するイメージは存在せず、不毛な状態が訪れる、と。最後のシーンも印象的ですね。子どもがいないふたりのあいだに、庭の外から突然「紙風船」が転がってくる。風船を飛ばしてしまったらしき女の子のみ、「千枝子」と名前が記されているのですが、妻と夫があらあらと風船とともに女の子のほうへ歩み寄っていくところで終幕に至ります。近代家族としてのふたりの関係がうまくいかない遠因が「不在の子ども」にあったというのが鈴木さんの分析ですね。
鈴木 この分析について大学の授業で触れると、女子学生が強く反応します。先ほどの『主婦之友』の引用は、『紙風船』発表から12年後の1937年の記事ですが、しかし描かれている内容はよく似ていますよね。他人から自分たちがどう見えるのか、近代家族をまっとうできているのかどうかということを気にする社会的な規範の原型は、おそらく大正時代にあるのだろうと思います。
工藤 大正期に「文化住宅」が出現したことにも、鈴木さんは触れていらっしゃいますね。借地の上に建てる持ち家としての小住宅であり、応接間の籐椅子や、当時流行した円本(全集)といったものに象徴されるモダンな暮らし、つまり「近代の夢」としての「文化住宅」。『紙風船』の若いサラリーマン夫婦には、経済的になかなか手が届かないわけですが、しかしそうした「近代の夢」が彼らの意識をとらえていることにも言及されています。
畑中 戦後へと時計への針を進めると、『銀行員の詩集』を鈴木さんが論じていらっしゃるのも気になるポイントです。全国の銀行員の詩作品を集めて1951(昭和26)年に第1集が、その後1960(昭和35)年までに計10冊が刊行されたという詩集です。のちに国民的詩人となった、日本興業銀行勤務の石垣りんの詩も収録されたようですね。
鈴木 東京メトロでよくポスターを見かける、メトロ文化財団が詩を一般公募している「メトロ文学館」や、「伊藤園 お~いお茶新俳句大賞」の原型とでもいえるようなものですね。プロでないということはもちろん、特段文学好きでなくても、普通の人が詩句に取り組んでいく、その先駆けとなるような試みです。当初はいまでいうところのメガバンクの組合が主体なのですが、やがて地方の小さな銀行などへも波及していきます。女性の組合員が多かったというのも特徴ですね。
畑中 後に戦後を代表する詩人となった中村稔による、当時の非常に厳しい評にも鈴木さんは触れていますね。ハンセン病患者が書いた詩に比して、銀行員たちの詩には「労働者意識などとは言つても、そんなものは、世間一般の貧しさの前で、およそ影がうすい」と。ちょうど先日も国立ハンセン病資料館で展示が行われたように、当時からハンセン病患者による詩作の実践があったわけですが、それと銀行員の詩作を比べて、後者は無個性だと言っているんですね。
鈴木 その詩作品に銀行員としての必然性はあるのかと言っているわけですよね。石垣りんぐらいになれば、もちろん銀行のことを書いている詩もありつつ、詩人個人としての力が突出しているんですけれど……。ただ、「メトロ文学館」にしても「お~いお茶新俳句大賞」にしても、個性が突出していない、ということが逆に面白いように感じます。
畑中 おそらくそこが「サラリーマン」や「会社」ということを考える意味につながるし、いまっぽいテーマ性を帯びるところでもある気がします。銀行のことを詩にしない、というある種の無個性性とでもいいますか。「会社の社会史」に取り組むということは、そうした無個性性にも向き合っていくことなのかもしれません。
鈴木 無個性性にもつながるかもしれないのですが、わたし自身は、サラリーマンというのはある種の「着ぐるみ」だと思っている人間なんです。システマティックに構築されている「着ぐるみ」だから、着ることも脱ぐこともできるはずなんですよ。例えば、男性がよく「妻のため」「家族のため」に働いていると口にしますけれど、サラリーマンというのが着脱可能な「着ぐるみ」だと認識できれば、そうした社会的な規範の外で「自分のため」に働くということはきっと可能だと感じています。『〈サラリーマン〉の文化史』は、サラリーマンは何のために生きているのか、生きうるのかということを考えるきっかけになればと思って書きましたし、今回みなさんの議論を聞いていて、その思いを改めて強くしました。ありがとうございました。
(上)夫婦と子どもふたり、女中ひとりという構成の、1930年代の家族の集合写真 Photo by H. Armstrong Roberts/ClassicStock/Getty Images (下)撮影時期不詳、20世紀後半と思しき東京の酒場のサラリーマン Photo by H. Christoph/ullstein bild via Getty Images
【近日発売・新刊のご案内】
書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]20号 記憶と認知症 Memory/Dementia』
わたしたちは他者と記憶を共有している。だからこそ集団のなかで大きな物語を描くことができ、他者から自分であることを認められ、自らの生活を営むことができている。認知症をもつ人を抱えた高齢化社会、国家や地域社会の衰退による集合的記憶の喪失など、「記憶の共有」をめぐる社会問題が浮上しつつあるいま、オランダとフランスでオルタナティブな社会実践を試みる、認知症や精神疾患のケアの現場等を本誌編集長が取材。約90頁にわたる取材旅行の省察と見聞録のほか、ルネサンス期の情報爆発と記憶術を研究する桑木野幸司氏、レバノン内戦の都市の記憶とその傷跡をテーマに音楽作品を制作したベイルートの音楽家・建築史家メイサ・ジャラッド氏へのインタビュー、記憶をめぐるブックガイドを収録。記憶と認知症を手がかりに、来るべき社会のための態度や今日的な問いについて思索する。
■書籍詳細
書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]20号 記憶と認知症 Memory/Dementia』
編集:WORKSIGHT編集部
ISBN:978-4-7615-0926-2
アートディレクション:藤田裕美
発行日:2023年8月25日(金)
発行:コクヨ
発売:学芸出版社
判型:A5変型/128頁
定価:1800円+税
次週8月15日のニュースレターはお盆のためお休みです。次回8月22日のニュースレターは、わたしたちの身体やあらゆる生物に流れる電流「生体電気」にフォーカス。生体電気で記憶・認知・身体を操作できる未来はもうすぐそこまで迫っています。しかし、人類にとって夢のようなテクノロジーは、アイデンティティの喪失や格差拡大などの問題を引き起こす可能性も。数々の実験結果やディストピア映画を引き合いに〈電気×人間〉の光と影を考えます。お楽しみに。