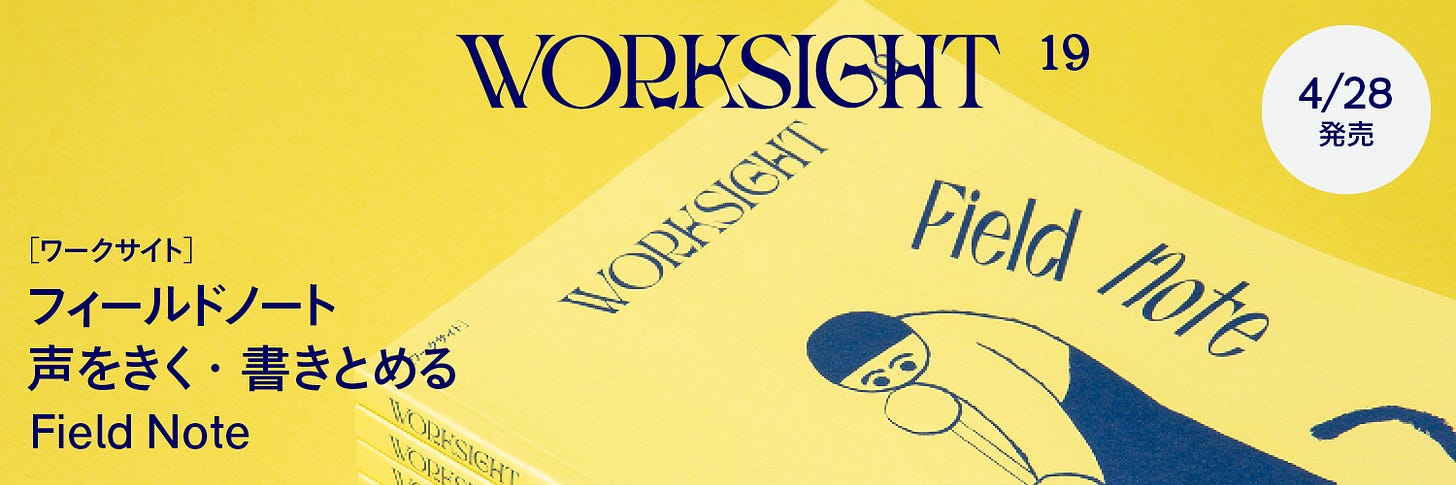少しずつ缶につめる、ファブリケーション飲料の未来:町工場CAN-PANYの充填室より
2023年5月、清澄白河にオープンした〈CAN-PANY〉。蒸留家として千葉の緑深き地で〈mitosaya 薬草園蒸留所〉を率いてきた江口宏志氏が、都市部で「ノンアルコール」「缶」「小ロット」を重点に置く工場を立ち上げたとあって話題だ。その飲料開発や製造・充填という営みは、ソバーな老若男女のみならず、ファブリケーションのひとつのモデルとして小規模な事業者たちと思わぬ縁を結び始めている。
「ノンアルコール飲料の製造・充填を行う都市型のボトリング工場です」と、〈CAN-PANY〉のWebサイトでは謳われている。「CAN-PANYは、小ロットから誰もが使うことのできる充填工場です」「CAN-PANYオリジナルの飲料の他、原料の加工から製造、充填、出荷、販売まで対応し、小規模から行える委託製造(OEM)や委託ブランド構築(ODM)を承ります」と、文言は続いていく。ノンアルを中心に独自の飲料を開発・製造するほか、小ロットで「缶」に飲料をつめたいという外部の人でも利用することが可能な場なのだという。
千葉県大多喜町の薬草園跡地に〈mitosaya 薬草園蒸留所〉を構え、同敷地内に居を構えながらボタニカルなクラフト蒸留酒を手がけてきた江口宏志氏。もともと自然派として知られてきたが、世のノンアルコール需要の高まりのなか、アルコール以外の飲料においてもそのナチュラルな姿勢を模索できるのではないかという思いがあったという。偶然にも東京・江東区に場所を確保できた江口氏が2023年5月、新たにオープンした拠点〈CAN-PANY〉は、大多喜町とは対照的に都市型の缶飲料充填場であり、町工場と呼ぶには異質なすがすがしさを清澄白河の住宅街で放っている。江口氏、そしてレシピ開発チーフのJUNERAY氏に話を聞くと、「充填」という行為を介し、小ロット生産によって可能になる、缶飲料のプロトタイピングの場としての側面が見えてきた。
photographs by Kaori Nishida
interview and text by Saki Kudo/Fumihisa Miyata
「クラフト」ではない感覚としてのボトリング
──千葉県大多喜町の〈mitosaya〉と比べてかなり都心寄りの立地ですが、なぜこの場所を選ばれたんでしょう。
江口 この建物は、〈mitosaya〉の共同運営者でもある株式会社WATの石渡康嗣さんが以前にイベントスペースとして使っていた場所でした。コロナを機に、なにか催しとは別のことをしようと考え始めたのが転用のきっかけです。
──奥まで筒抜けというか、文字通り「透明」性が強い空間ですね。
江口 〈CAN-PANY〉として設備と内装をリニューアルしてからは、原料から製造工程、働く人間まで、何も隠し事がないことを示すような、外からも丸見えな設計になっています。
道と場内はガラスで、室内もドリンクインスペースとファクトリーはビニールカーテンで区切られていることによって、表から奥まで透明度の高い設計となっている〈CAN-PANY〉。ブックショップ〈Utrecht〉の運営を経て蒸留家として活躍してきた江口宏志氏(下写真右)と、ライターやフローリストなどとして幅広く活躍し、〈CAN-PANY〉ではレシピ開発チーフを務めるJUNERAY氏に話を聞いた。
──建築家やデザイナー、画家などの同志が寄り合って生まれ、職住近接で酒造を行う〈mitosaya〉は、かつてウィリアム・モリスのほか画家や建築家、数学者たちが集ってアーツ・アンド・クラフツ運動の中核を担った「モリス商会」のような性質をもった場のように感じられます。今回都市部で「缶飲料」に取り組む〈CAN-PANY〉は、まさに company(商会、仲間、会社)の語を背負いつつも、新たな場づくりを目指していますね。
江口 〈mitosaya〉の蒸留所はわたし自身の自宅や農園と隣接しているし、1箇所で完結できる場所です。一方でこの場所は、原料の引き合いや、製品をつくりたいと言ってくれる人がいなければ、何もできない。それで最初に「アーバンボトリングハブ」なんてサブタイトルを考えたりもしていたんですが。
JR 薬草園でもあり工程が完結した〈mitosaya〉とは違って、誰かに何かをもち込んでもらわないと何も出てこない、入力がないと出力もされないような仕組みです。そのハブとしての変換の部分をわたしたちがやっているだけ、というか。ドリンクのレシピ開発もそうで、わたしがなにかイチからつくっているというより、かたちを変えているだけです。例えば届いたレモン1個から取れる果汁と皮の重さって決まっているので、それを余らせずに、かつ保健所の衛生要件も満たして......と考えていくと、自分で好きに決められることって多くないんですよ。そういう意味であまり「クラフト」という感覚ではないように思います。
──ここ清澄白河の周辺は新興の醸造所・蒸留所、焙煎所なども多いエリアですが、影響はありますか。
江口 それこそ近隣のワイナリーさんから、自前の飲料を缶へ充填する相談を受けるようなこともあります。思えば、例えば板橋にも "製本村" と呼ばれるエリアがあり、紙を切る所、製本する所、貼り付ける所があって、近所の工場でそれぞれが役割を担っていますが、町工場って本来そういうものですよね。〈CAN-PANY〉をこの場所でオープンしたのは偶然ですけど、結果的にはそれに近いことができるようになるかもしれません。
──なるほど。JUNERAYさんは〈CAN-PANY〉のChief Recipe Developer(レシピ開発チーフ)としての抜擢ということですが、どういう経緯で参加されたんでしょうか。
JR 以前は花屋とバーで働いていて、ワインエキスパートやSAKE DIPLOMA、ビアテイスターの資格ももっています。以前、蒸留器を自作してその辺りに生えている野草などを蒸留してドリンクをつくる、という記事をWEBメディアに書いたんです。その後に江口さんたちから声をかけてもらって、熊本・阿蘇山の天然水を使ったノンアルコールドリンクの開発に加わったのがきっかけです。
江口 完成度の高いドリンクをつくる優れたバーテンダーさんはたくさんいますけど、彼女が素晴らしいのはそれとは別の軸で、自前の感覚を的確にアウトプットできるところですね。
──こうしてお話をうかがっていても、〈CAN-PANY〉という組織にはあまり上下関係はなさそうですね。
江口 そうですね。人数もそう多くありませんし、工場長、プロジェクトマネージャーなどの各担当者が、自分の持ち場でフラットに役割を担っています。
汎用型の「缶」だからこその工夫
──欧米を中心に”sober(しらふの)”ということばも広がり徐々に日本でも受容されるなか、実はWORKSIGHT編集部も、こうした潮流には継続的に関心を抱いてきました。そんな折に〈CAN-PANY〉さんの取り組みを知り、強く興味を抱いたという経緯もあります。
江口 わたし自身は、食事中にノンアルコールを選ぶ人間ではないんです。ただパーティーなどでケータリングをやると、場合によっては半分以上の人がノンアルコールの飲み物を取っていくんですよ。〈mitosaya〉は薬草園だった場所でお酒をつくっていますが、立ち返ってみれば酒造自体が目的ではなくて、自然のものをかたちにする上でお酒ではない選択肢もあっていいと思います。ただ、酒類ではなく清涼飲料水というくくりになった瞬間に、法令基準で求められる設備要件も違ってくるので、いまの〈mitosaya〉の蒸留所の環境でノンアルコール飲料をつくるのは少し無理があったんですよね。
JR アルコールってそもそもが手を消毒できるくらい殺菌作用があるものですから、殺菌要件はアルコール飲料のほうがゆるいんです。
──ノンアルコール飲料をつくる際に、酒のアルコールを後から抜く方法もあると聞きます。
JR 海外で普及しているノンアルコールビールのような、一度アルコール飲料としてつくってからアルコールを抜く手法って、実はすごく電力がかかるんですよ。だからわたしたちとしては、最初からアルコールを入れずに美味しいドリンクがつくれるならそのほうがいい、という考えです。
──実際に、この取材の時点で1カ月、運営されてみた感触はいかがですか。
江口 ありがたいことに、わたしたちが思いつくような協働の話はだいたいいただいているんじゃないか、というくらいいろんなところからお声がけがあります。コーヒー、お茶、CBD、クラフトコーラ、余剰フルーツ......例えばそれらを基にわたしたちがレシピをつくり、いろんな店舗やイベントで提供するといった具合ですね。でも、まだまだ設備もスペースも含めて現時点でやれることは限られているなと感じます。アルコールって、飲料にするにあたって香りを抽出するのにも保存性を高めるのにも、ものすごく適しているんです。そのアルコールを使わないベストな代替の方法を、例えば一回凍らせたものをバラバラに分解して成分を抽出するというように、学びながら試している段階です。
──難しいものですね。
JR はい。スパイスやハーブなどの香り成分のほとんどは、油とアルコールにはよく溶けるんですが、水に溶けるものはすごく少ないんです。蒸留酒のジンだとよく香る原料も、いざノンアルコールでつくると全然香らないか、変質してしまったりする。一気に解決しようとすると大量に原料が必要になってしまうので、そうではない道を探るのは課題のひとつですね。「缶」にまつわる要件も重要です。
──缶の内容物の要件については、先ほど充填室を見学している際も、スタッフの皆さんが重要なトピックとして話してくださいました。
JR pH値が細かく決められていたり、塩分が入ってはいけないという決まり[※]があったりして、例えば余韻を出すために塩を使いたい場面があっても、それができない。ならば、どうするか、ということですね。あと、テイスティングにおいて味覚や嗅覚だけではなく、触感にあたる「マウスフィール」ということばがあります。例えばアルコールによる刺激、ワインの渋みなどもそうです。こういう余韻や後味、食感の良さって、ノンアルコールドリンクの制約のなかだとすごく表現がしづらいんです。考えた末に、山椒で少し辛味を効かせたり、生姜やチリを一緒に合わせてみたりしながら、模索しているところです。
──大手の飲料メーカーだと液体に合わせて缶自体を設計する一方で、〈CAN-PANY〉では缶の仕入れ元である東洋製罐株式会社の汎用型にpH値や内容物を合わせているとのことですが、独自に「缶」そのものをつくろうとされたことはありますか?
江口:いえ、やはりそこまでは。〈mitosaya〉では蒸留酒のガラス瓶をつくりましたし、〈CAN-PANY〉でも一部は瓶への充填もしていますが、缶や瓶などの容器の製造は金型ありきで、まず必要な型を製作するだけで数百万円かかってしまいます。工場を稼働するのも1日単位なので最低ロットでも相当な数になりますから、難しい部分はあります。わたしたちが手をかけているのは缶の「ラベル」のほうですね。缶の中身が見えない分、原材料をしっかり見せることを考えています。だからこの商品だと、普段は裏側に小さく載っている成分表示・原材料表示がラベルの表面に来ている。工場の内装の透明な見通しと同じように、実際の中身が見えない缶でも、飲料に使われている良い原材料が透けて見えるような設計になっています。
[※]缶の腐食を防ぐために酸や塩分の添加が制限されており、清涼飲料水においてはpH4.0未満以下の場合中心部温度65℃で10分の殺菌、pH4.0以上の場合中心部温度85℃で30分の殺菌などの加熱殺菌条件が法令で定められている。CAN-PANYの設備では水道の最高温度が75℃のため、飲料はpH4.0以下に抑える必要がある。
小ロットのプロトタイピング
──ノンアルに限らず、そもそも飲料を生産する上でのハードルには、どういうものがあるのでしょうか。
江口 一番大きいのはやっぱりロットの話です。飲料工場にお願いしようと思うと、その工場のラインを一日単位で変えてつくってもらわないといけないので、最低でも何万、何十万本からという話になるし、その分の原料も用意して、売るための仕組みを考えて......というと、どうしても大規模な生産になってしまう。〈CAN-PANY〉では場合によっては、そうした飲料工場より2桁ロットを減らして開発をオーダーできる、というぐらいの規模感なんです。
──大きなメーカーの生産ラインでは難しい規模ですよね。
JR 例えばそこに置いてあるドライフルーツは、量り売りのお店から賞味期限が近い在庫分を材料として使ってほしいともち込まれたものです。「この夏に売れなくなる量だけで何かつくれませんか?」というような、小規模のアップサイクルの話ができるメリットがあります。
江口 逆に言うと、わたしたちから「これだけの量の原材料をください」とリクエストすることは難しいんですよね。実際に飲料の製造と充填をやってみると、各所で行われているノンアルコール缶飲料の開発が、大規模にならざるを得ないことも理解できます。小ロットだとやはりコストが高くついてしまう点は否めません。ただ、別に、何でもかんでもここでつくる必要はないとも思っているんですよ。
──と、いうと?
江口 例えば、〈CAN-PANY〉でレシピを開発して、原料の入手経路も手配できた、ありがたいことに売り先もある、というところまでたどり着けたら、うちでつくらず大きい工場で生産してもいいと思うんですよ。ここはつくる場所でもあるけど、別にここでつくることが絶対条件ではない。
──プロトタイプの開発の場でもあると。
江口 そうですね。最初から大きな予算を組んだ状態でプロトタイプをつくるのは、ちょっと怖いじゃないですか。だから、はじめだけ〈CAN-PANY〉で、というやり方はありだと思います。そもそも〈CAN-PANY〉を計画する初期の段階から、メイカーズムーブメントにおける3Dプリンターのような機能をもつ場になる、という話は出ていました。〈CAN-PANY〉におけるレシピは、3Dデータの設計図にあたるものだと思います。また、飲料の製造にまつわる「原料の確保」と「レシピの開発」、「製造と充填」、そして「販売」という工程をバラバラにできれば、物理的な距離も経済的な規模も移動しやすい。例えばレシピだけなら国をまたいで行き来させるのも簡単ですから。
JR 実は比較的規模の大きい企業からも、まずは社内向けに数百本だけつくってみたい、という相談をいただくことがあるんです。それを踏まえて、いけそうと判断したら生産を拡大していきたい、というような。
江口 そういったお話が、かなりあるんですよね。缶にコーヒー豆を入れたいとか、土と植物の種を入れたいとか、新しいアイデアがもち込まれる状況に、自分たちでもびっくりしています。
「しらふ」が解き放つ場
──お話をうかがっていると、改めて、〈CAN-PANY〉は「ノンアルブランド」という押し出し方とは少し違うと感じます。
江口 はい。オリジナルのノンアルコール飲料もつくってはいますけど、〈CAN-PANY〉の一番大事な部分はやはり、この場所で行われる「充填」という機能なんです。
JR もちろんノンアルのドリンク自体は、もっと広まると思っています。個人的な話ですが、友人にアルコールアレルギーの人も多くて。食事に行くとアルコールのメニューって膨大なのに、ソフトドリンクのメニューってごく僅かじゃないですか。果たしていつまでその割高の烏龍茶を友人たちに飲ませ続けるんだ、という思いを抱きながら、日頃のレシピ開発にあたっているところもあります。もともとお酒がすごく好きだけど子どもが生まれるから控えているとか、地方や郊外に住んでいて帰りが車だから飲まないという人もたくさんいるはずです。食事の場での「ソフトドリンク」の幅が従来狭かったことがおかしいくらい、本来は需要があるはずなんです。
──〈CAN-PANY〉もそうですが、"ノンアルコール" というカルチャーがもつ空気というか、磁場のようなものもあると感じますが、いかがでしょうか。
JR よくわかります。アルコールが主体のコミュニティってどうしても排他的になってしまいますけど、ノンアルコールが中心だと、例えばこの建物の隣が保育所なんですが、そのお子さんたちでも入ってもらえますよね。近所のおばあさんが、「ここは何なの?」と言いながら入ってきてくださることがあります。
江口 そういう空間でありたいですよね。下校途中の生徒さんたちや、その保護者の方々にも気軽に入ってみてほしい。そういう場を目指しています。
JR 例えば、学校帰りの中学生に溜まってもらいたいです(笑)。子ども向けのドリンクもつくりたいと思っていますし。
──お酒やバーカルチャーはこれまで "大人" のものであったわけですが、そうでない開かれ方を模索されていると。
江口 はい、オーセンティックなバーの内装も踏襲していません。飲み物も変わればお客さんも変わるし、お客さんが変われば、皆さんにとって心地良い空間も変わるはずですから。
次週7月18日は、去る4月27日に東京・渋谷で開催された「Agile Governance Summit」に登壇するために来日された、アメリカの先鋭的運動体「RadicalxChange Foundation」のプレジデント、マット・プルーウィットさんのインタビューを配信。「私有」制度を組み替え、資本主義のオルタナティブを構想する、シリコンバレー発の反シリコンバレー思考の最先端を学びます。お楽しみに。