すべて「半開き」がいい──全生新舎・野口晴哉記念音楽室というコモンズ【「場」の編集術 #04】
日本の整体の第一人者・野口晴哉は、生前、自邸に独自の音響設計を施した音楽室を構えていた。その空間はいま、孫の野口晋哉氏の手によって、リスニングスペースとして活用されている。だがこの場所は、音楽鑑賞のための空間にとどまらない。身体感覚を媒介に、野口晴哉が遺した思想と遺産を現代に開き直す、横断的かつ革新的な試みが進行している。
故野口晴哉が生前に設計・使用していたリスニングルーム「野口晴哉記念音楽室」
東京都狛江市。表通りに看板はない。Webサイトも存在しない。住所を頼りに路地を進むと、そこに広がるのは鬱蒼とした木々に囲まれた、昭和の趣を残す古い邸宅の門構えだけだ。しかしここ数年、晴風学舎・狛江稽古場の敷地内にある「野口晴哉記念音楽室」には、鋭敏な嗅覚をもつ編集者、アーティスト、そして自身の身体感覚に渇きを覚える人びとが、吸い寄せられるように集まり始めている。
ここはかつて、日本の整体の創始者であり、思想家でもあった野口晴哉(1911–1976)が過ごした「終の棲家」である。彼が遺した約55畳の土蔵造りの音楽室には、ドイツ・シーメンス社のオイロダインや、米国ウェスタン・エレクトリックの巨大なホーンといった、オーディオ史における名機が鎮座している。
だが、ここは単なるヴィンテージ・オーディオの保存館ではない。また、整体という特定の身体技法を教えるだけの場でもない。野口晴哉の孫にあたり、現在この場所を保存・継承する「全生新舎」(ぜんせいしんしゃ)の主宰・野口晋哉氏は、この音楽室を「編集と翻訳の稽古場」であると定義する。情報が過多となり、あらゆる体験が消費され尽くそうとしている現代において、人間が本来もっている「生の感覚」や「身体性」を取り戻すための環境とは、いかにして設計可能なのか。そのヒントは、晋哉氏が語る「半開き」という奇妙なことばのなかに隠されていた。
interview by Shotaro Yamashita, Sho Kobayashi, Hidehiko Ebi
text by Shotaro Yamashita
photographs by Kaori Nishida
野口晋哉|Shinya Noguchi 「全生新舎」主宰。晴風学舎・狛江稽古場に残された「野口晴哉記念音楽室」を拠点に、音楽鑑賞会や対話の場を運営する。晴風学舎技術研究員を務めながら、整体の専門用語や技法に閉じないかたちで、野口晴哉の思想を現代に継承する試みを続けている。
半開きの身体論
「よく、どんな体がいい体なんですかと聞かれるんです。わたしは迷わず答えます。『半開き』の状態こそが、一番いい体なんだと」。取材が始まって早々、晋哉氏はそう切り出した。
一般に整体と聞けば、調整や代替医療といったイメージをもつかもしれない。しかし氏の口から語られたのは、健康法や養生法ではなく、身体における「可動性」(モビリティ)の条件についての洞察だった。「緊張しっぱなしの体は固まって動きません。逆に、リラックスしすぎて弛緩しきった体も動けない。多くの人はストレスでガチガチになるか、癒やしを求めて脱力しきるか。その二元論を行き来しているだけなんです」
現代のウェルビーイングの議論は、いかに緊張を取り除き弛緩させるかに終始しがちだ。オフィスは緊張、カフェは安らぎというように、都市機能もON/OFFの切り替えスイッチとして設計されてきた。しかし晋哉氏が提示する「半開き」とは、そのスイッチを無効化する概念だ。「緊張と弛緩が同居し、ある種の『拮抗関係』になっている状態。これこそが、いつでも次の動作に移れる最も動ける体なんです。互いが引っ張り合い、ギリギリのところで釣り合っている。『拮抗』という動的な不安定さこそ、生命の本来の姿なんです」
このことばを「場」や「組織」に置き換えたらどうなるか。完全に管理された組織(緊張)は硬直化し、安心感に浸りきったコミュニティ(弛緩)は腐敗していく。晋哉氏の言う「半開き」の組織とは、安心と不安、規律と自由が常にせめぎ合っている状態を指す。それは決して居心地が良いだけの空間ではないが、その微細なバイブレーションがあるからこそ、場は呼吸し、予期せぬ事態に即応できるのだ。
全生新舎も、この「半開き」の実践の場である。Googleマップに住所は登録されておらず、かつ予約制で参加するという個人の生活空間でありながら、見知らぬ他者を受け入れ、音楽や対話を通じて公共的なコモンズとしての機能も果たす。「組織も社会も国も、たぶん『半開き』な状態が一番いいはずなんですよ。だって体がそうだから」。そのことばの射程は、都市計画やデザインの根幹を揺さぶる。
こうした「半開き」の状態を目指すために、晋哉氏が重視するのが「体育」というアプローチだ。祖父・晴哉が創始した整体のルーツを、治療のような代替医療ではなく、文字通り「体を育む」ことにあると説明する。「そもそも整体は『体育』という名でスタートしたんです。それは治療や調整よりも、『編集』ということばがピッタリくる。日常で行っている動作を少し工夫して変えていくことで、体自体を育てていくんです」
例えば、「お茶を飲む」という何気ない動作ひとつをとっても、その実践は可能だという。「口に含んで体のなかに入れたとき、その水が食道を通っていく余韻を感じ入ろうとしてみる。すると、その余韻が体のなかに広がったり、収縮していったりすることを経験します。日常で行なっている営みを、より創造的なものとして、一つひとつの身体的経験に位置づけていく。すると、少しずつ体の捉え方が変わってくる。頭ではなく、経験が主体になって『体』が育っていくんです」日常の経験を通じて、身体を再編集していくこと。この思想は、身体という枠を超え、彼が運営する「場」の設計にもそのまま接続されている。
狛江稽古場の入り口(上)と縁側(下)。1958年、野口晴哉は妻・野口昭子ら家族とともに、稽古場兼自邸として拠点を狛江に移した
結び目だけを見せる
「本質を言いさえすれば、人は耳を傾けてくれる。わたしたちはどこかでそう思い込んでいる節があります。でも、そんなことはまったくないんです」晋哉氏は、自身が身を置く整体の世界、ひいては専門家コミュニティが陥りがちな罠について、鋭い自己批判を展開する。野口整体という深遠な身体哲学を受け継ぐ彼にとって、その本質を伝えることこそが使命であるはずだ。しかし、彼は逆説的なアプローチをとる。「本質を語らない」ことによって、本質を伝えようとしているのだ。
「本質を言い切ってしまった瞬間、それは情報として処理され、カテゴリーのなかに収納されてしまいます。『ああ、健康法ね』『調整して自然治癒力を高めるってことでしょ』と。理解された瞬間に、人の思考も身体も止まってしまうんです」人間は、未知のものに出会ったとき、不安を感じる。その不安を解消するために、既知のレッテルを貼り付け、分類し、わかったことにしたがる。しかし、それは死んだ知識のコレクションに過ぎず、生きた体験にはなり得ない。だからこそ、晋哉氏は「編集」という手法を用いる。
「本質の周りにある『フック』みたいなものを大量に生産していったほうが、人に届くと思うんです。だからここは、聴くとか、見るとか、味わうとか、そういう誰もが日常的に行っている動作にほんの少しの工夫をすることで、別の日常へと変容する経験を提供しているつもりなんです。そういう経験を通じて、わたしたちのやっていることの本質に少しでも触れていただけたらなと思って運営しています」
防音設計が施された音楽室(上)。壁面に埋め込まれた、縦約3m×横5m超の巨大スピーカーシステムと、音を拡張させる半円形のコンクリート響板が存在感を放つ。室内にはSP盤再生に用いられてきた蓄音機(下)をはじめ、オーディオマニアを唸らせる名器が揃う
全生新舎で開催されるイベントの数々は、一見すると脈絡がないように見える。ヴィンテージ・オーディオを使った、古典邦楽からアヴァンギャルドのレコード鑑賞会、声を主体としたSP盤を聴く会、映画上映、温泉とイワナと野口整体、「ハラノムシ」と「明治維新」についての対談など。そして、2025年11月に同じ敷地内にオープンしたブック&カフェ「坐坐奔奔」(ざざほんほん)における選書。これらはすべて、野口整体という本質の周囲にちりばめられた、計算された「フック」である。受け手は知らず知らずのうちに、野口晴哉が探究した「生」(いのち)の深淵へと引きずり込まれていく。晋哉氏はこれを、「結び目を見せる」と言い表した。
「例えば、『あなたの腕はここからここまでです』『頭はこれです』と定義してしまうと、体はバラバラのパーツになって動かなくなる。でも、ここに関節という『結び目』があるじゃないか、と示す。すると、腕や胴、脚といった身体の各部分が互いに関係づけられ、連動しながら自然に動き出すんです。人間の体はそういうふうにできている。場所も同じです」
結論を急がず、正解を教えず、ただ「結び目」だけを提示する。それは、現代の教育やメディアが失いつつある待つ姿勢の復権でもある。すぐに役立つソリューションを提供するのではなく、受け手の身体が勝手に反応し動き出すまでの「余白」をデザインすること。それこそが、晋哉氏の考える「編集術」の要諦なのだ。
このアプローチは、来訪者たちに「創造的な誤読」を許容する。かつて作家の五味康祐は、野口晴哉のオーディオシステムを聴き、整体師としての側面ではなく、音の芸術家としての側面を発見し、世に知らしめた。それはある種の誤読かもしれないが、その誤読があったからこそ、野口晴哉の哲学は整体業界という狭い枠を超え、文化的な広がりをもつに至った。全生新舎はいま、再びその「誤読の豊かさ」を取り戻そうとしている。「本質を言わないメディア」としての場所。そこでは、訪れる人それぞれが、ちりばめられたフックを手がかりに、自分だけの物語を編集し始めるのである。
音楽室に隣接し、窓越しに屋敷の庭を見渡すことができる和室に「坐坐奔奔」はオープンした。全生新舎から独立した別プロジェクトでありながら、本というメディアを通して、野口晴哉の思想を指し示す「結び目」を体感する場として構想されている
閉じたことばとの闘い
晋哉氏がこれほどまでに編集や翻訳にこだわる背景には、彼自身が身を置いてきた整体の世界に対する、強烈な危機感がある。「わたしが以前所属していた整体協会は、入会のハードルが非常に高く、紹介者が2人いないと入れないような、すごく閉じた世界で展開してきました」
高度な専門性をもつコミュニティは、必然的にその内部だけで通じるジャーゴン(専門用語)を発達させる。それは効率的なコミュニケーションを可能にする反面、外部との断絶を生む諸刃の剣だ。「閉じた世界では、ジャーゴンだけで会話が成立してしまいます。そうすると、外の人に向かって語ることばが失われていくんです。会話の仕方を忘れていってしまう。その結果、場はどんどん閉鎖的になっていく」
そして、「野口整体」ということば自体が一般名詞化し、限定的な意味として流通され、特定のカテゴリーの中でのみ消費されるジャーゴンとなってしまった。「野口整体」といえば、「治療術」「調整」「天才技」「効く/効かない」などとカテゴライズされてしまうように。晋哉氏は、この「ことばの死」に抗うために、新たな団体「晴風学舎」を、父と弟と共に設立した。彼が行っているのは、野口晴哉の思想を、整体の専門用語を使わずに、現代の人びとに伝わることばへと「翻訳」する作業だ。それは、場の「編集」のその先にある、思想を別の文脈へと渡していくための営為である。
この試みには、晋哉氏の父・野口裕之氏という先駆者がいる。「父は、整体の三本柱である『愉気』(ゆき)、『活元』(かつげん)、『錐体外路系』(すいたいがいろけい)といった専門用語を、それぞれ『触れる』『動く』『他者と出会う』という一般的なことばに置き換えて説明し始めました」
この翻訳作業に対して、一部の保守的な内部勢力からは「晴哉先生はそんなことは言っていない」と猛反発を受けた。しかし、ジャーゴンの外にあることばを使わなければ、その知恵は社会に共有されず、いずれ孤立して消滅してしまう。「父も孤独に闘っていましたが、それは画期的な翻訳でした。『触れることって、いいことなんだ』と、誰もが直感的に理解できることばに置き換えたんですから」
全生新舎が、突飛なテーマを扱うのも、すべてはこの脱・ジャーゴンのための戦略である。「整体」という看板を掲げれば、整体に興味がある人しか来ない。しかし、いい音や面白い本という普遍的な入り口を用意すれば、そこには多様な人びとが集まる。そこで交わされる対話は、専門用語に頼らない、生きたことばによるコミュニケーションとなる。
「組織も社会も、ことばを失ったら終わりです。だからわたしは、ここを『半開き』にして、常に外の風を入れ続けたい。そうしないと、腐ってしまうから」。専門性と公共性の断絶は、整体の領域に限らず、アカデミア、アート、あるいは企業のR&D部門など、あらゆる専門家集団が直面している課題だろう。「怒られる」ことを恐れずに翻訳を続けること。それこそが、ナレッジを社会に還流させるための唯一の方法なのかもしれない。
しかし、既存のカテゴリーを拒絶し、何者でもない場所であり続けることには、現実的な痛みも伴う。晋哉氏は、全生新舎の運営資金について「家族を困惑させるほど、全財産を注ぎ込んでいるんです」と苦笑した。当然、公的な助成金の申請も試みているが、結果は芳しくない。その理由は明白だ。「助成金の応募はしているんですが、毎回外れちゃうんです。評価されるためには、『ここは音楽の場所です』とカテゴライズしなきゃいけない。でも、それが一番苦手で」
音楽も聴くし、身体の話もするし、本も読む。その横断こそが価値なのだが、縦割りの社会システムにおいて、横断するものは所属不明として処理される。予算は音楽振興や地域福祉といった縦の財布からしか出ないため、その隙間にある全生新舎には落ちてこないのだ。「収集家も、音楽ファンも、それぞれ縦で固まる。そうしないと安心できないから。全部同じだと言っても、全然理解されないんです」
助成金が下りないという事実は、逆説的ではあるが、全生新舎が既存の枠組みに収まらない新しい公共性を獲得していることの証明でもある。理解され、カテゴライズされ、予算がつくような場所であれば、それはすでに「半開き」ではない。制度的な孤独を引き受けながら、それでもなお場を開き続けること。晋哉氏の言う自律とは、そのようなヒリヒリするような摩擦の上に成り立っている。
取材を敢行した2025年12月6日、音楽室では『音響・環境・即興:松籟夜話──〈耳〉の冒険』(カンパニー社)の刊行を記念したリスニング&トークイベントが行われた。フィールド・レコーディングや即興演奏など、著者である福島恵一氏・津田貴司氏がセレクトした音源は、夜遅くまで会場に響き渡っていた
感覚の再配線
全生新舎での時間は、わたしたちが慣れ親しんだ音楽体験とは決定的に異なる質をもっている。いわゆるライブハウスやクラブといった既存の音楽ベニューは、大音量を浴び、酒を飲み、熱狂のなかでストレスを発散する「消費空間」としての側面が強い。それは非日常への逃避であり、一時的な解放だ。
しかし、晋哉氏がこの場所で目指しているのは、消費でも逃避でもない。むしろ、乱れた身体感覚を本来の状態へと戻すための、「古を稽む」時間である。「世の中にある音楽ベニューとは、やっぱり役割が違うと思うんです。音楽を楽しむとか、大音量を浴びるとか、社交するとか、そういう目的の場所ではない」
全生新舎で起こる最もドラスティックな変化は、やはり「身体」そのものに訪れる。晋哉氏は、この場所で良質な音が鳴り響いたとき、人間の知覚に奇妙な現象が起こると語る。「いい音が鳴り始めると、耳がどこかに移動していくような感覚を抱くんです。聴覚という機能が、身体全体に分配されていく。例えば、腕で聴いているような感じにもなるし、指先で聴いているような感じにもなる」
現代社会において、わたしたちの身体は完全に分業化されている。「見る」のは目、「聴く」のは耳、「考える」のは脳。それぞれの器官がスペシャリストとして独立し、情報は断片化されて処理される。晋哉氏はこういった「頭の専門家と腕の専門家が分かれている状態」を、不自然なことだと指摘する。全生新舎の音楽体験は、この分業体制を解体する。シーメンスのオイロダインから放たれる圧倒的な音の波動は、鼓膜だけでなく皮膚を、骨を、そして内臓を震わせる。そのとき、聴覚は局在性を失い、全身的な「触覚」へと統合されていくのだ。
「一緒にイベントをやっているDJ/選曲家のChee Shimizuさんは、音を聴くときに目をカッと見開いたまま、どこにも焦点が合っていない状態で凝視するんです。『音が目に届いて、シュワシュワしてくるのを味わっている』と言うんですね」。一方、晋哉氏自身は、深い集中(ゾーン)に入ると目を閉じることで、「下腹のところに浮き輪みたいなものがフワッと出てきて、お風呂に浸かっているような感覚になる」という。
視覚で聴くこと。腹部で聴くこと。ここでは、「聞く」(Hearing)と「聴き入る」(Listening)の境界だけでなく、五感の境界そのものが溶解し、身体感覚の再編集が行われている。そして、この感覚の変容は、個人の内部で完結するものではない。
晋哉氏は、かつてある小さなレコード店で体験した瞬間についてこう振り返る。「その場にいる人たちの耳が、全部同じ方向を捉え始めた瞬間があったんです。茶室にいるような静けさのなかで、聴覚が一点に集まってくる。自分と他者がひとつになるような経験でした」イヤホンで遮断された個室的な音楽体験ではなく、同じ空間で空気を共有し、他者の気配を感じながら音に没入すること。そこで生まれるのは、「集団的な感覚の共鳴」だ。
隣の人が喜んでいれば、自分も嬉しくなる。誰かの集中が深まれば、場全体の深度も増す。「半開き」の身体たちが、音を媒介にして緩やかにつながり、ひとつの巨大な受容体となって響きを味わう。全生新舎が目指しているのは、こうした「共振する身体」の回復にほかならない。
イベント開催中、晋哉氏は来場者とともに、音楽室の後方で何度も音楽を聴き入っていた
「入りにくさ」という名の倫理
しかし、このような繊細で濃密な場を維持するためには、ある種の防御壁が必要となる。全生新舎が、あえて「入りにくい」場所として設計されている理由はそこにある。「入り口は怪しい路地だし、完全予約制だし、告知文には小難しいことが書いてある。これらはすべて、意図的なフィルタリングなんです」
開かれた場所というと、誰でも無条件に受け入れるバリアフリーな空間を想像しがちだ。だが、無防備な開放は、場の空気を希薄にし、時に破壊してしまうリスクを孕む。晋哉氏が目指す「半開き」とは、無防備になることではない。外部との接続を保ちつつも、内部の質を守るために、境界線を慎重に管理することだ。
その管理のあり方は、玄関に象徴的に表れている。「うちの玄関を見ると、お客さんの靴がすごく綺麗に並んでいるんです。それを見て『今日は大丈夫だな』とわかる。外から内に入る時、人は集中のモードを変えなきゃいけない。靴の揃え方は、その儀式ができているかどうかのサインなんです」
参加者は、予約という手間をかけ、難解なテキストを読み、路地を歩いてたどり着く。そのプロセスのひとつひとつが、来訪者の心身を、その場に身を置くためのモードへとチューニングしていく。晋哉氏は、予約メールのやり取りにおいて必ず一言、個人的なことばを添えるという。それは事務的な手続きではなく、すでに始まっている「関係性の編集」だ。この手間をかけることで、ドタキャンを防ぐだけでなく、当日その場に現れる人間が、単なる「消費者」ではなく、場の形成に寄与する「参加者」へと変貌する。
「空間に立ち入るまでのプロセスを、ちょっとだけ面倒にさせることも『半開き』の一部なんです。自分自身が何かを受け取るためには、関係性を構築するための準備が必要だから」。現代のサービスは、いかにユーザー体験をスムーズにし、摩擦をなくすかに腐心している。しかし全生新舎は、あえて摩擦を残す。その摩擦こそが、参加者の能動性を引き出し、場に対するリスペクトを醸成するのだ。優しさとは、安易に手招きすることではない。時には高い敷居を設け、それを跨ごうとする意志をもつ者を、最上の音と空間でもてなすこと。それが、晋哉氏の考える場の倫理なのである。
共振するコモンズへ
「緊張と弛緩の拮抗」という身体論から始まり、「本質を言わない」編集術、そして「入りにくさ」による場の保護へ。全生新舎・野口晴哉記念音楽室の取り組みを紐解いていくと、そこには新たな社会を構想するための実践的なヒントが詰まっていることに気づく。
晋哉氏は、「縦割り」ではなく「横に貫く」ことの重要性を説いた。整体、オーディオ、文学、自然。これらを専門ジャンル(縦軸)として掘り下げるのではなく、人間の「生」という視座(横軸)で串刺しにする。そこでは、専門家と素人、演者と観客、ホストとゲストといった固定的な役割は融解し、全員が共通項を通じて対等に関わり合う。
今後、全生新舎のような、音楽を聴くための場はどのように増えていくべきかと伺った際、晋哉氏は次のように答えた。「音楽を聴くだけが目的ではない、横に貫くことで新しいものが生まれる場が増えてほしい。そうした営みのなかから、文化は生まれると思うんです」。
全生新舎は、完成された博物館ではない。野口晴哉が次代に遺したものを受け継ぎながら、常に未完成のまま、時代に合わせて呼吸を続けている。真空管アンプは熱をもち、レコード針は溝をトレースし、人びとは集い、そして散っていく。その営みそのものが、野口晴哉が提唱した、すべての生命力を使い切って生きる「全生」の実践にほかならない。効率や正解を追い求める社会のなかで、わたしたちは身体を固くし、息を詰めて生きていないだろうか。もしそう感じるならば、狛江の路地裏にあるその扉を叩いてみるといい。そこには、あなたの身体がまだ知らない、あるいは懐かしく思い出す、「半開き」の自由な響きが待っているはずだ。
【WORKSIGHT SURVEY #37】
Q:場の運営において、入り口は広く開くべき? あえて狭めるべき?
野口晋哉氏は、誰にでも無条件に開くのではなく、予約制や告知文などを通じて、間接的に場の規範を守るあり方を選んでいます。場の運営において、入り口は広く開くべきか、意図的に狭めるべきか、どちらをより重視すべきだと思いますか? みなさんのご意見をぜひお聞かせください。
【WORKSIGHT SURVEY #36】アンケート結果
メイド・イン・ジャパンを売るということ:ある陶器商が見た欧州のポストクールジャパン(1月13日配信)
Q:「メイド・イン・ジャパン」には、まだ発見されていない可能性がある?
【可能性がある】純喫茶でわたしが頼んだサンドイッチを外国人が勝手に撮影していたので、日本の昭和っぽいサンドイッチは需要があるように思う。特に卵焼きのサンドイッチは恒久的に受けそうな気がする。
【可能性がある】予感があるのはお菓子のクオリティの高さです。年齢を問わず受け入れられる懐の深さがあると思います。手焼きのせんべいは日本でも見られなくなりましたが、パフォーマンスとローカライズした味付けなど、日本人も気が付かない可能性があるのではないでしょうか。
【可能性がある】There are still many unique and innovative products in Japan waiting to be discovered, especially in niche areas such as traditional crafts and modern technology. The continuous evolution of Japanese design and craftsmanship keeps this potential very much alive.
【第5期 外部編集員募集のお知らせ】
WORKSIGHTでは2026年度の外部編集員を募集しています。当メディアのビジョンである「自律協働社会」を考える上で、重要な指針となりうるテーマやキーワードについて、ニュースレターなどさまざまなコンテンツを通じて一緒に探求していきませんか。ご応募お待ちしております。
募集人数:若干名
活動内容:企画立案、取材、記事執筆、オンライン編集会議(毎週月曜夜)への参加など
活動期間
第5期 外部編集員:2026年4月〜2027年3月(予定)
年間を通じて継続的に活動に参加していただける方を募集します。単発・スポットでの参加は募集対象外となります。
募集締切:2026年2月18日(水)18:00まで
応募方法:下記よりご応募ください。
【イベント情報】
今週土曜開催!
〈メイド・イン・ジャパン〉を欧州でどう売るか?
1月13日(火)配信のWORKSIGHTニュースレター「メイド・イン・ジャパンを売るということ:ある陶器商が見た欧州のポストクールジャパン」のインタビューに登場し、英国の陶器商「Doki Limited」のメンバーとして活動する大谷臣史さんを招いた特別セミナーを、1月24日(土)に東京・渋谷の「(PLACE) by method」で開催いたします。
大谷さんのヨーロッパでの”行商”のノウハウをレクチャーしていただきつつ、国内外であらゆるモノにまつわる仕事に携わってきたバイヤーの山田遊、WORKSIGHT編集長の山下正太郎、そして本記事の制作を担当した黒鳥社の若林恵の4人とともに、これからの「メイド・イン・ジャパン」の可能性を考える特別講義。海外展開を目指す、ものづくり・飲食・小売関係者は聞き逃せないレクチャー+トークイベントです。奮ってご参加ください!
【特別レクチャー】
〈メイド・イン・ジャパン〉を欧州でどう売るか?
講師:大谷臣史
ゲスト:山田遊(Method)・山下正太郎(WORKSIGHT)
司会進行:若林恵(黒鳥社)
日時:2026年1月24日(土) 16:00〜18:00
会場:(PLACE) by method(東京都渋谷区東1-3-1 カミニート14号)
定員:30名
参加費:無料
次週1月27日は、文化的かつグローバルなモチーフである「ヴァンパイア」がいかにして誕生したのか、歴史学の視点からひも解くインタビュー記事を配信します。18世紀のハプスブルク帝国で、死者の蘇りをめぐる報告書が国家的な問題として公式に記録され、やがて現代のヴァンパイア像へと姿を変えていくまでの過程とその謎を、歴史学者アーダーム・メーゼシュ氏に伺います。お楽しみに。















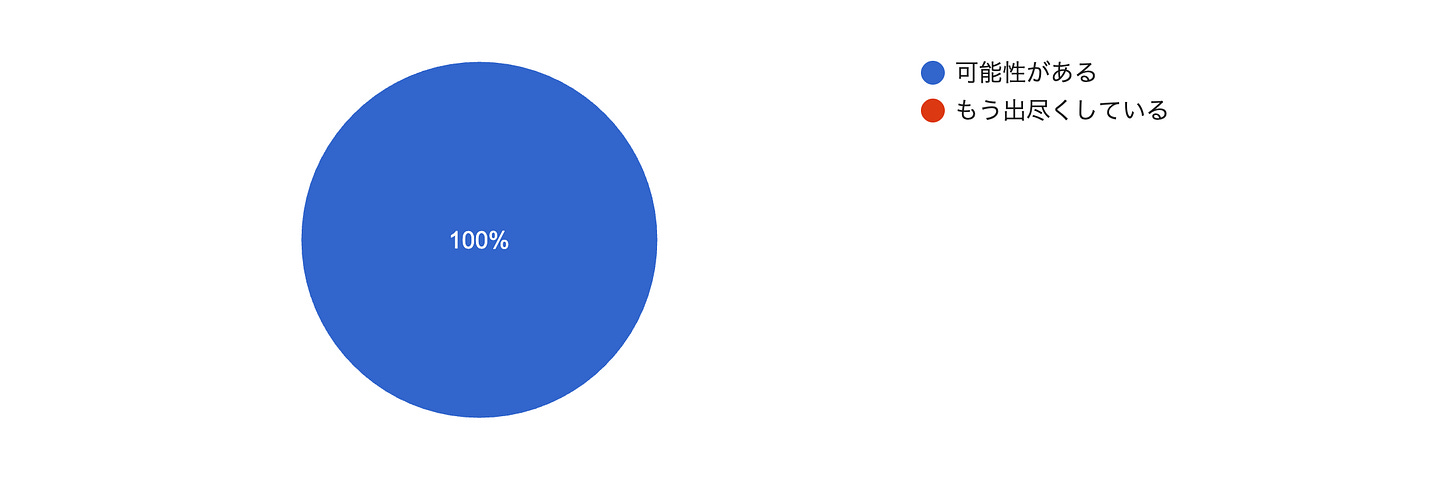

大変素晴らしいポスト、ありがとうございました。『「共振する身体」の回復』など、一つ一つの言葉がとても深く同時に心地よい余白を持っていて、本当に読ませていただき良かったと思う内容でした。