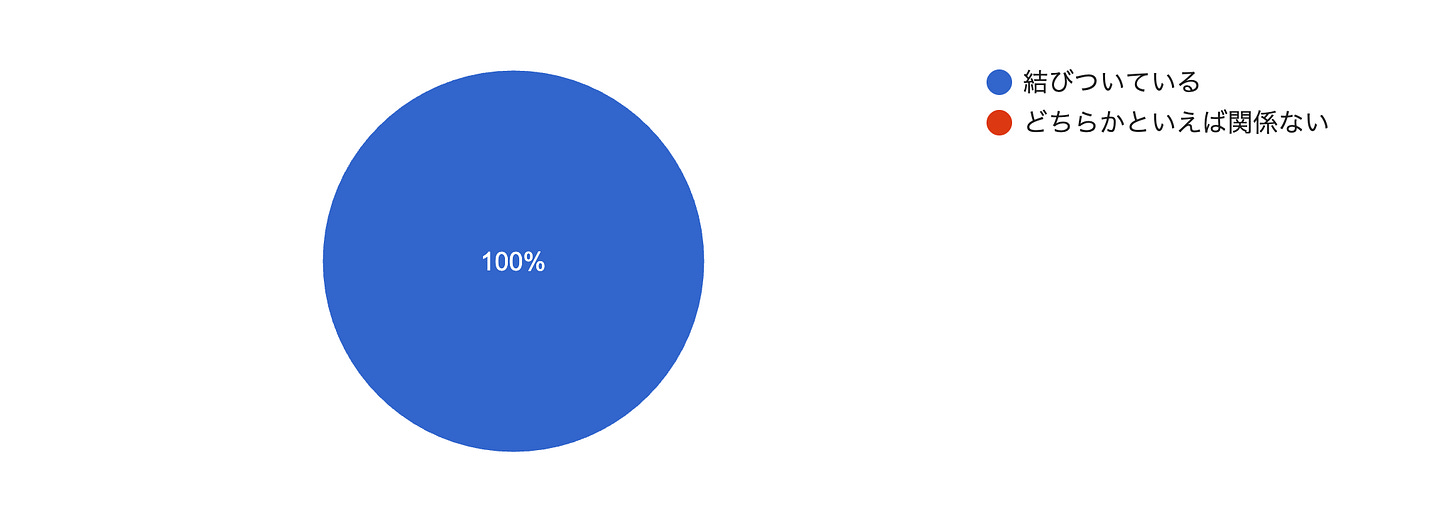大人が知らない有名中国企業: ルービックキューブを革新する「GANCUBE」の正体
「ルービックキューブ」にまだイノベーションの余地があったことを、いったい誰が想像しただろう。そして現在の日本の子どもたちもこぞって欲しがる最先端キューブが、中国企業によってつくられたものであることを誰が知っているだろう。かつての「おもちゃ」を「高級競技用アイテム」へと変貌させた、知られざる先端企業「GANCUBE」の正体とは?日本メディアによる初インタビュー。
2025年8月、GANCUBEより発売された最新モデルの魔方「GAN16 Maglev Max」
この10年、「ルービックキューブ」はかつての知育玩具から驚くべき進化を遂げ、いまや世界的な競技カルチャーとして広がりを見せている。その中心にいるのが、中国・広州を拠点とする「GANCUBE」だ。玩具から競技用デバイスへの進化、スマホとの連動機能、滑らかな操作性や精密な設計など、既存のキューブをあらゆる側面からアップデートしたことで、GANCUBEの製品は世界中のトップ選手に愛用されるだけでなく、日本の子どもたちにまで浸透している。
ルービックキューブをやったことのある大人は、せいぜい1〜2面を揃えられれば上出来といったところだったが、いまは違う。YouTube上にある教則動画やアプリなどのおかげで、多少の訓練は要するものの、小学生が6面揃えることは当たり前となった。そのことによって、かつて、おもちゃとしてルービックキューブで遊んでいた子どもたちは、タイムトライアルを競うことのできる「競技者」へと変貌した。メディアの変化がもたらしたこの劇的な市場の変化によって、「競技用」キューブは、ニッチな「上級者用アイテム」ではなく、初心者にも広く求められる「マストアイテム」となった。
現在GANCUBEは世界最大のキューブ企業として、主に子どもたちの間で広く親しまれているが、その企業の内実を知る人は少ない。日本を代表するバイヤーでmethod代表の山田遊とWORKSIGHTコンテンツディレクターの若林恵が、本国のCMOと海外ブランディングマネージャーに、知られざる有名中国企業の実態を聞いた。
interview by Yu Yamada and Kei Wakabayashi
text by Kei Wakabayashi
photographs courtesy of GANCUBE
創業者は元チャンピオン
──日本の小学生の間で「ルービックキューブ」はいままた人気でして、ある小学生に誕生日プレゼントに何が欲しいかを聞いたら「GANのキューブが欲しい」と言われたことがあったんです。「なにそれ」と調べてみたら、1万5千円もする非常に高価なものでさらに驚きました。日本の子どもたちの間で「GANCUBE」という会社名はそれなりに知られているのですが、多くの大人はルービックキューブがこの10年で驚異的な進化を遂げていることも知りませんし、ましてそのドライバーとなってきたのが中国企業だということも知りません。そこで今日は、「GANCUBE」という会社がどのような会社で、どのような考えでビジネスをされているのか詳しく伺いたいと思っています。
はい。よろしくお願いします。
──まずは、会社が設立されたのはいつで、現在従業員はどのくらいいて、規模はどの程度かを教えていただけますか。
当社は2014年に広東省の広州市で設立され、昨年10周年を迎えました。創業当初は非常に小規模でしたが、現在では従業員数が約500人、年間の生産額がおよそ3億元、日本円でおよそ60億円規模にまで成長しました。設計から研究開発、生産、製造までを自社で一貫して行っており、広東省に研究開発部門と工場をもっています。広東省は玩具や電子製品を含む多くの産業が集積している地域で、その地の利を活かして、当社は競技用魔方(キューブ)、いわゆる「スピードキューブ」(何秒で6面を完成するかを争うタイムトライアル)の分野で世界最大規模の生産拠点を築いています。
──500人の従業員がいるとのことですが、どの部門が一番多いのでしょう。
一番多いのは生産・製造部門です。製品をつくる工場の人員が大きな比率を占めています。当社は広東にふたつの工場をもっています。最初は広州市南沙区に工場を設立しましたが、事業が拡大し、2024年には順徳の産業区に大型の工場を新たに建設しました。現在は2拠点体制で運営しています。
──創業者について詳しく教えてください。お若い方と伺いましたが、いまは何歳くらいなのでしょうか。
創業者の江淦源(ジャン・ガンユエン)は、今年40歳です。彼は中国で最初期のプロのスピードキューブ選手のひとりで、中国の国営放送「CCTV」が主催した全国魔方大会でチャンピオンにもなった人物です。もともとは上海の同済大学で土木工学を学び、卒業後は国営の土木建設企業に勤めていましたが、幼少期から夢中になっていたルービックキューブへの情熱を捨てきれず、安定した道を捨てて自ら会社を設立しました。大学で培った工学的な知識は、後に「魔方」の設計に大きく役立っているのだと思います。
──会社を立ち上げる際には、いわゆるスタートアップのように投資家から資金調達をしたのでしょうか。
いいえ、外部からの資金調達は行っていません。すべて自己資金でゼロから始めました。2014年から2016年の間は製品をつくって販売し、その利益を生産に投資するというかたちで事業を回していました。当時は小規模な販売会社のような存在でしたが、少しずつユーザーに認められ、売上が増えたことで規模を拡大できました。2016年頃からは本格的にブランド戦略に取り組み、マーケティングやトップ選手との契約に力を入れるようになっています。
各面正5角形・12面体で構成された魔方「GAN Megaminx Maglev」
──GANCUBEの製品は一般的なルービックキューブに比べて非常に高価格帯です。なぜそれほど高い価格で販売できるのでしょうか。
当社は、魔方(ルービックキューブ)を「おもちゃ」ではなく「競技用デバイス」として位置づけているからです。一般の靴とトップアスリートが使う専用シューズが違うように、わたしたちは「魔方」を競技のための道具として設計しています。そのため、内部の構造や素材が従来の製品とはまったく異なります。さらに研究開発に大きな投資をしており、世界で200件以上の知的財産特許と60件の技術関連特許をもっています。これらの技術を融合させることで、ユーザーがより高いパフォーマンスを発揮できる製品を提供しています。その結果、価格は高くなりますが、ユーザーは品質に対してプレミアムを払う意欲があります。そして、その収益を再び研究開発に投資することで、さらなる革新を生み出すという好循環を実現しています。
──技術の進化についても教えてください。
大きく分けてふたつの方向性があります。ひとつはスピードキューブとしての進化です。従来の魔方はシンプルな構造でしたが、当社は内部にバネやテンション機構を組み込み、さらにマグネットを導入しました。磁石の力でパーツの位置を安定させ、よりスムーズに回転できるようにしたのです。その後、磁力を段階的に調整できる仕組みや磁気浮上(Maglev)技術を導入し、摩擦やブレを大幅に減らしました。現在では、ユーザーが従来よりも簡単に自分に合った設定に調整できるようになっています。
もうひとつはスマート化です。2017年にセンサーとBluetoothチップを組み込み、2019年にスマート魔方を発売しました。専用アプリと連動し、回転の動きをリアルタイムで記録・分析できるほか、遠隔での対戦や学習指導も可能になっています。
初心者向けのシンプルな磁力スピードキューブ「GAN356 M E」
プレイヤー・ファーストの開発思想
──GANの設立当初の状況についてもう少し聞かせてください。2014年に会社を立ち上げられたと伺いましたが、当時の環境や業界の雰囲気はどのようなものだったのでしょうか。
2014年というのは、まだ中国国内でスピードキューブが、いまのように広く普及しているわけではありませんでした。当時、多くの人にとっての「魔方」はあくまで「子どものおもちゃ」であり、せいぜい頭を鍛えるための知育玩具という認識にとどまっていました。ですから「競技用の道具」としての需要はまだ非常に小さく、ほとんどのメーカーはその領域に注目していませんでした。江はその状況を非常に歯がゆく思っていました。自分自身が競技者であり、日々練習をしているなかで「既存の製品では限界がある」と痛感していたのです。
実際、当時の「魔方」は内部構造がシンプルで、速く回そうとするとすぐに引っかかってしまい、スムーズに操作することができませんでした。トップ選手たちはそれを補うために自分で改造したり、潤滑油を注入したり、バネを入れ替えたりして工夫していました。江もそうした改造を繰り返しながら練習していましたが、やはり根本的に「製品そのものが競技用としてつくられていない」という限界を強く感じていました。そこで「ならば自分でつくろう」と決意したわけです。
──その時点で、周囲からは無謀だと言われたりはしなかったのでしょうか。
もちろん「そんな小さな市場でビジネスになるのか」と心配する声はあったと聞いています。家族や友人からも、国営企業を辞めてまで挑戦するのはリスクが大きいと言われました。しかし江自身は「たとえ市場が小さくても、真に必要とされるものをつくれば必ず評価される」という信念をもっていました。彼が最初につくったチュートリアル教材も、当時は誰も手をつけていなかったものでしたが、多くの初心者や競技者に歓迎され、インターネットを通じて瞬く間に広がりました。その経験が「小さな市場からでも始められる」という確信につながったのです。
──なるほど。
最初は本当に小さな規模で、江が直接工場に足を運び、生産ラインの人たちと一緒に試作を繰り返しました。当時は外部の投資もなく、資金的にも余裕がなかったので、試作品の数も限られていました。ひとつの設計を試してみて、思うような性能が出なければまた改良し、ということを地道に繰り返したのです。時には工場の人に「そんな細かい仕様変更をしても大差はない」と笑われることもありましたが、江は一歩も譲りませんでした。競技者としての経験から「このわずかな差が記録を左右する」と確信していたからです。
──その経験が、いまの高品質につながっているのですね。
まさにそうだと思います。当社の文化の根底には「競技者の視点」が常にあります。江自身が選手だったからこそ、妥協を許さずに細部までこだわり抜く。そうした姿勢が社内にも受け継がれていて、開発部門の人材にも「ユーザーはどんな感覚を求めているか」を徹底的に考えさせています。単なる製造技術や数値だけでなく、実際に指先で回したときの手触りや滑らかさをどう再現するかという部分まで突き詰めるのです。
──ユーザーの感覚にそこまで寄り添うのは大変ですね。
ええ、だからこそわたしたちはトップ選手と密に連携しています。現在、世界中で100名以上のトップ選手と契約していますが、彼らは単なる広告塔ではなく、実際の開発パートナーなのです。新しい試作品ができると彼らに送り、何百回も回してもらい、細かいフィードバックを受けます。「この角度で引っかかる」「この磁力では強すぎる」など、競技者だからこそわかる感覚を集め、それを開発に反映させます。そうしたプロセスを何度も繰り返すことで、ようやく製品が完成するのです。
──つまりGANの製品は、競技者とともにつくられていると。
その通りです。だからこそ、一般のユーザーにとっても「使いやすい」と感じられるのだと思います。初心者がGANのキューブを手にすると、「なぜか回しやすい」「すぐに上達した気がする」と感じることが多いのですが、それは競技者の要求水準を満たすよう設計されているからです。トップ選手が満足する製品は、初心者にとっても快適なものになる。そこに普及の広がりが生まれているのだと思います。
2024年、遼寧省実験中学(Liaoning Province Shiyan High School)で開催された、GANCUBE主催の「魔方」大会
──競技用市場は、実際には広がっているのでしょうか。
明らかに広がっています。その背景にはWCA(World Cube Association)の存在があります。WCAは世界中で公式大会を開催しており、10年前は年間200大会程度でしたが、現在では年間2700大会が開催されています。参加者が増えることで競技人口が拡大し、それに伴って高性能な「魔方」の需要も高まりました。かつて創業者が国内チャンピオンになった頃の最速記録は十数秒でしたが、現在の世界記録は3.05秒です。デバイスの進化が競技の記録を大きく押し上げてきたのです。
──GANCUBEのユーザーはどんな年齢層の人たちなのでしょう。
グローバルでは10代から20代の子どもや若者が中心です。欧米では高校生から大学生くらいが多く、中国では教育プログラムの一環として小学生や幼稚園でも取り入れられていますので、もう少し若いユーザーが多くなっています。算数や論理的思考を鍛える教材として活用されることが多く、低年齢層にも浸透しています。
──研究開発を担う人材についてはどうでしょうか。
創業者の江自身が現在も研究開発責任者を務めています。開発部門は理工系のバックグラウンドをもつ人材や玩具業界出身の人材が多いですが、当社の強みはトッププレイヤーが多く在籍していることです。開発者自身が競技者であるため、試作品に対して実践的で価値のあるフィードバックを提供できます。過去にはMax Park選手、現在はFeliks Zemdegs選手など、世界的なチャンピオンとも協力してきました。
GANCUBEの製造基地の見学ツアーにて、子どもたちがレクチャーを受けている様子
──2024年には直営店もオープンされていますね。
広州と上海に直営店を2店舗オープンしました。展示や販売だけでなく、DIYゾーンや対戦ゾーン、教育研修機関との連携ゾーンを備えています。DIYゾーンでは自分だけのカスタム魔方を制作できますし、対戦ゾーンではオンライン・オフラインで対戦できます。教育連携ゾーンでは初心者から上級者まで段階的に学習できるプログラムを提供しています。直営店は単なる販売の場ではなく、体験やコミュニティの場として機能しています。
──日本への展開についてはどう考えていますか。
1〜2年以内に海外の直営店の展開を検討しています。まずは中国国内で運営モデルを確立し、収益構造と運営ノウハウを安定させた上で、海外にもっていきたいと考えています。その前段階として、ポップアップストアや大会と連動した出張型のイベントを積極的に検討しています。日本市場は非常に可能性があると感じています。
──中国企業が強い理由はどこにあると思いますか。
第一には製造力が挙げられると思います。中国は産業チェーンが完備されており、スピード感をもって製造できます。第二に人材です。WCAのトップ50には中国選手が多く含まれており、その層の厚さが製品開発に直結しています。製造力と人材力、このふたつが中国企業の強さの源泉だと思います。
──日本市場への展望について、具体的にどうお考えですか。
日本市場は非常に可能性があると見ています。理由はいくつかあります。まず、日本ではすでに子どもたちの間でGANの名前が知られており、ブランド認知が自然に広がっている点です。多くの親御さんは「子どもがGANを欲しがる」と聞いて初めてその存在を知りますが、実際に購入してみると「従来のキューブと全然違う」という感想をもたれます。この体験は口コミを通じてさらに広がっていきます。
また、日本は教育や知育に関心の高い社会です。魔方は論理的思考力や集中力を鍛える教材として非常に相性がよい。中国で成功している教育プログラムを日本に導入すれば、多くの学校や塾、家庭に受け入れられると考えています。特にスマート魔方は「学習効果をデータで確認できる」という強みがあるので、日本の保護者層にも響くはずです。
──海外展開における課題はどのあたりでしょうか。
課題となっているのは、スマートキューブをいかに普及させるのかという点です。中国では売上比率で40〜50%がスマートですが、海外ではまだ10〜20%にとどまっています。理由のひとつは「体験の不足」です。スマートの魅力は実際に触ってアプリと連動させてみないと伝わりにくい。ですから、海外ではまず体験イベントやポップアップストアを通じて「スマートとは何か」を知っていただく必要があります。
もうひとつは競技文化の浸透度です。中国ではWCA大会への参加者が年々増え、競技者層が厚くなっています。これがスマート魔方の需要を押し上げています。しかし海外では競技人口が地域によって偏っており、必ずしも全国的な盛り上がりがあるとはいえません。そのため、教育分野との連携やコミュニティ形成を並行して進めることが重要です。
──社員の方々ご自身は、どのくらいの時間で6面を揃えられるのですか。
わたしは50秒くらいで、社内では遅い方です(笑)。ただ、入社当初はまったくできなかった人でも、3カ月も練習すれば大体解けるようになります。研究開発やITの部門にいる社員は練習熱心で、朝から100回以上解くこともあります。職場全体が「魔方に親しむ文化」をもっていると言えると思います。
──なるほど。最後に、日本の読者に向けてメッセージをお願いします。
GANの魔方は、単なるパズルや玩具ではありません。競技者のための道具であり、学習の教材であり、世界中の人とつながるためのツールです。日本では「昔のパズル」というイメージがまだ強いかもしれませんが、魔方はすでに進化を遂げています。内部機構は劇的に改善され、スマート化によって新しい学習体験や競技体験が可能になりました。
これから日本でも、体験イベントや教育プログラムを通じて、魔方がもつ新しい価値を伝えていきたいと考えています。CEOの江自身が、もし機会があれば日本で講演を行い、直接その理念を語りたいと思っています。魔方はひとりで楽しむだけでなく、人と競い、学び、交流する文化でもあります。体験・対戦・学習を束ねた拠点づくりやイベントを通じて、魔方の価値をさらに広げ、世界中で「当たり前の文化」にしていきたいと考えていますが、その豊かさを日本のみなさまと共有できる日を楽しみにしています。
【WORKSIGHT SURVEY #23】
Q. 「イノベーション」は、さまざまな領域で、まだまだ起こせる?
イノベーションなんてもはやないだろうと誰もが思いこんでいた「ルービックキューブ」を鮮やかにアップデートし、新たな市場を開拓した「GANCUBE」。このようなイノベーションは、他の領域でもまだまだ起きうるのでしょうか? 起きうるとしたらどんな領域や商品に、その可能性はあるのでしょう。みなさんのご意見をお聞かせください。
【WORKSIGHT SURVEY #22】アンケート結果
矛盾に気づくのはずっと後:ポルトガルの賢者、ペドロ・コスタかく語りき(9月30日配信)
Q:自分の仕事は歴史と結びついている?
【結びついている】シスジェンダー女性として権力のある立場でケアの仕事の現場にいる自分にとって、これまでも、いまも、これからも、自身の仕事が歴史と結びついていないとは言えないと思う。
【結びついている】歴史を紡いできた生活、文化やそれを包括する地域とつながる仕事をしていると考えているから。
次週10月14日は、WORKSIGHT編集長・山下正太郎が新しい場のあり方を探るシリーズ企画「『場』の編集術」第3弾を配信。東京や京都からカイロ、チェンマイまで、国内外を横断して多彩な編集的実践を積み重ねてきた「for Cities」共同設立者の石川由佳子さんと杉田真理子さんへの取材から、誰もが主体的に関わることのできる都市のかたちについて考えます。お楽しみに。
【リサーチャー募集のお知らせ】
WORKSIGHTの発行母体である「ヨコク研究所」の傘下にある、新しい働き方・働く場を探求する「ワークスタイル研究所」では、現在リサーチャーを募集しています。特に統計調査やデータ分析の専門知識をおもちの方を歓迎します。奮ってご応募ください。
業務内容:
主に大規模アンケート調査を通じて、社会動向を明らかにする業務【調査設計】デスクリサーチやヒアリングに基づいた調査目的・仮説の構築
【解析】基礎分析や多変量解析、モデリングを扱うデータ解析
【可視化】情報の可視化およびレポートの作成
【発信】セミナーやメディアなどを通じた社内外へのリサーチ発信
応募方法:
下記よりご応募ください