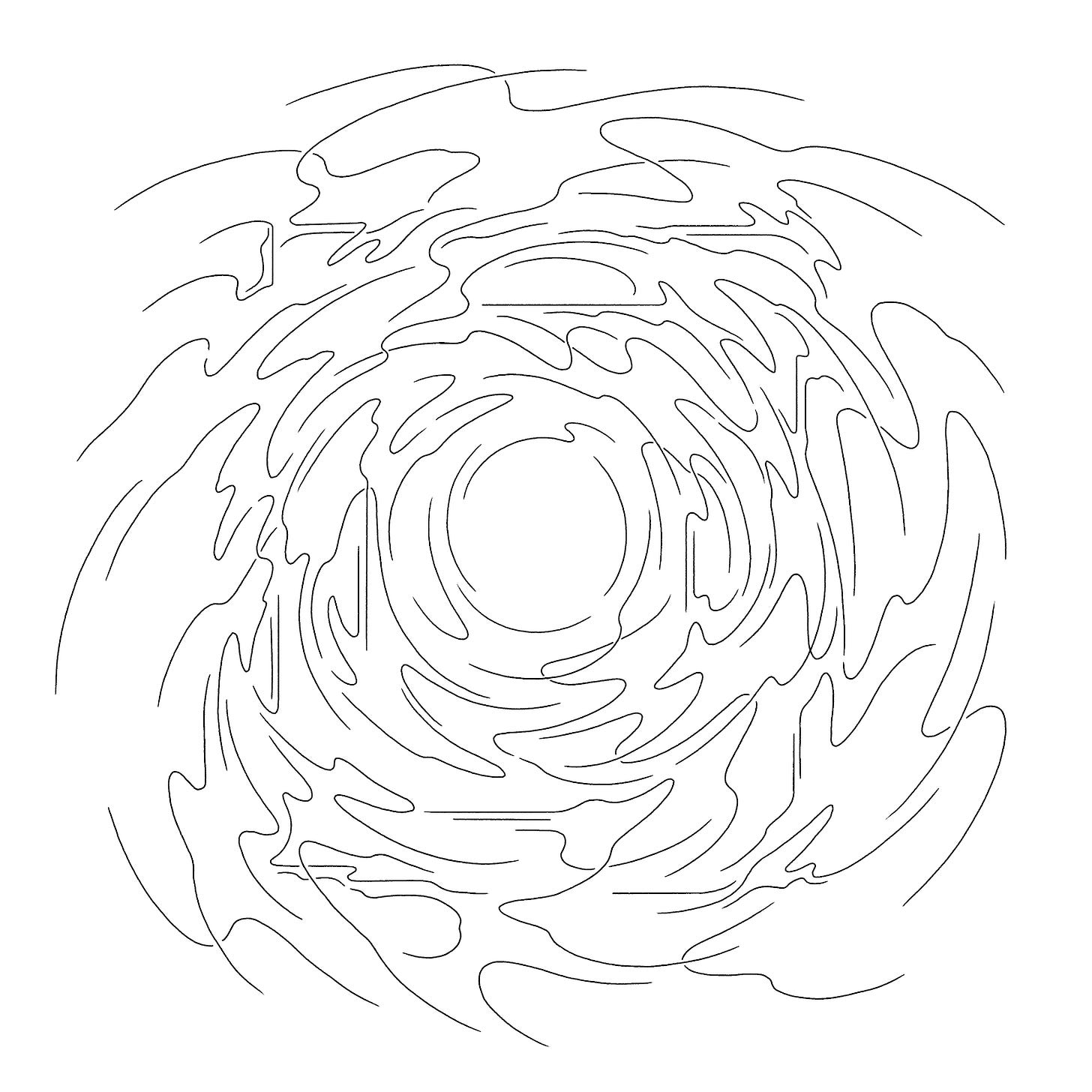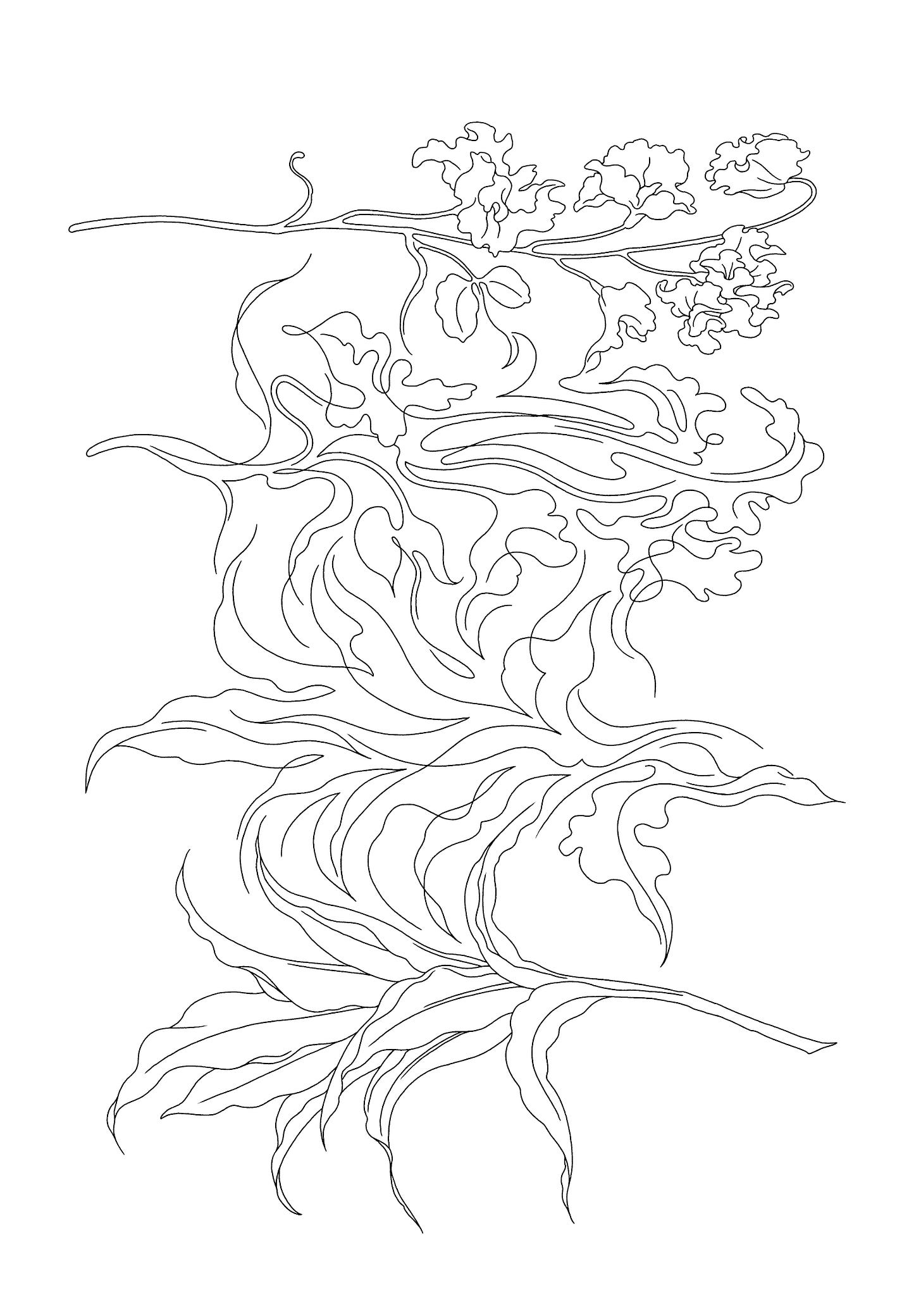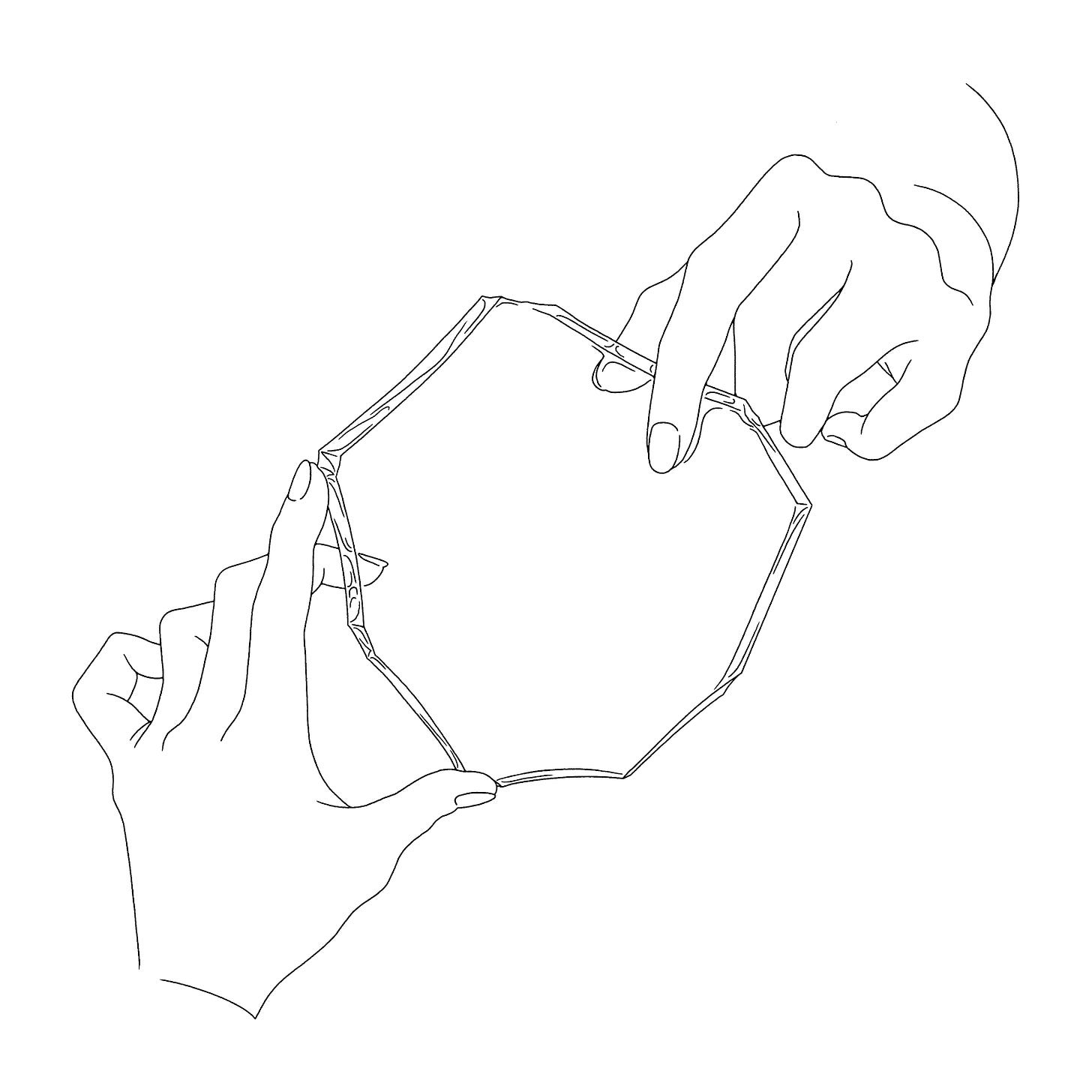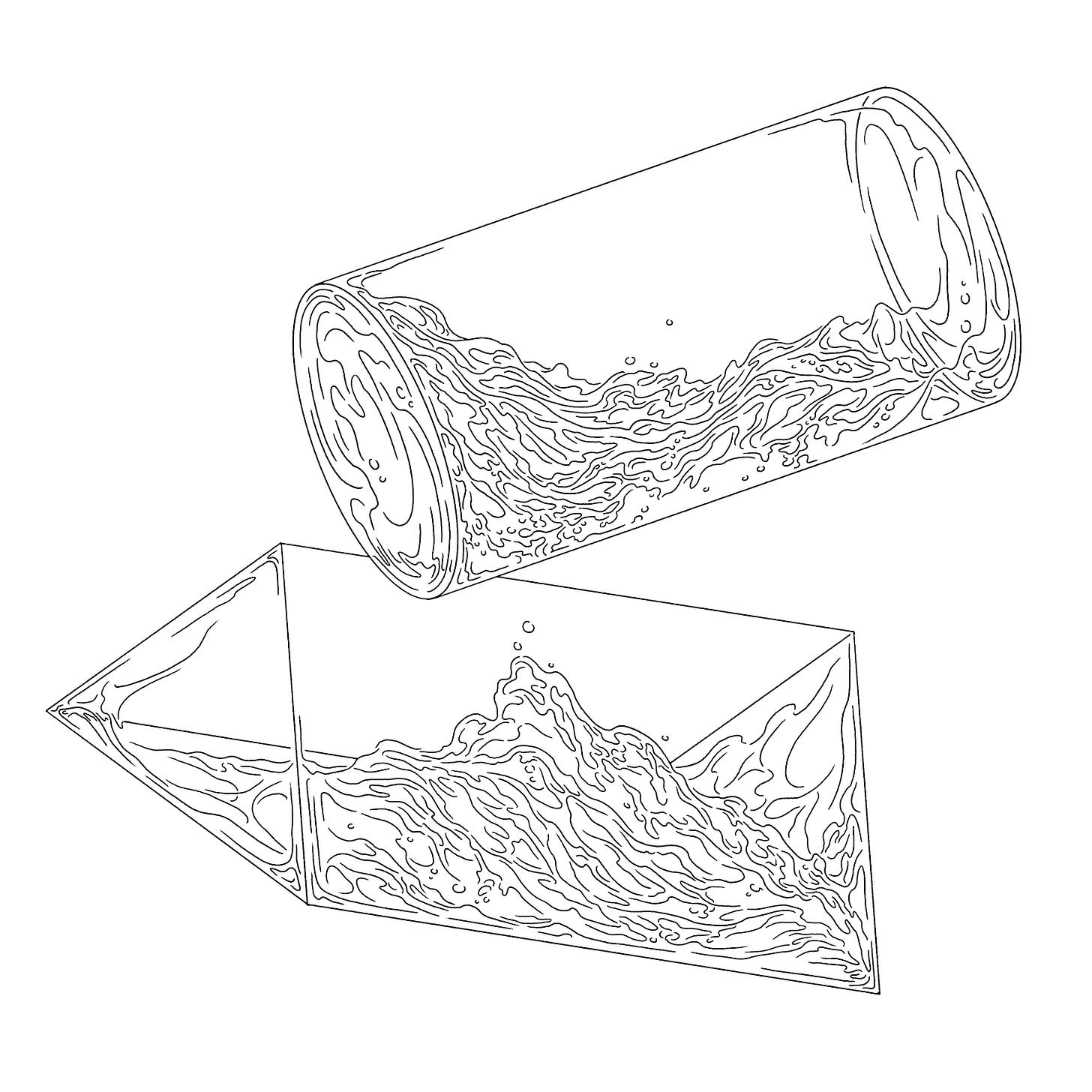この言葉でしかありえない:ウィトゲンシュタインと詩の理解【WORKSIGHT 21号「詩のことば」より】
「詩がわからない」と言う人が考える「わかる」と、「詩がわかる」と感じている人の「わかる」はそもそも違う──。わたしたちはどのようにして言葉を選び取っているのか。「詩のことば」の何が日常言語と異なっているのか。言葉の哲学者・古田徹也との対談を通して、ウィトゲンシュタインの言語論から「詩のことば」の秘密に迫る。鍵となるのは"しっくりくる"感覚だ。
「詩がわかる」とはいったいどういうことなのか。「言葉を理解する」ことを哲学し、意味の伝達にとどまらない言葉の側面を探求した天才哲学者、ルートウィヒ・ウィトゲンシュタイン。その言語論を紹介した入門書『はじめてのウィトゲンシュタイン』や、第41回サントリー学芸賞を受賞した『言葉の魂の哲学』のほか、最新刊『謝罪論』も話題の哲学者・古田徹也氏との対話を通して、「詩がわかる」の正体を解き明かす。「詩のことば」の秘密を知れば、詩を読むのがきっと楽しくなる──。プリント版最新号『WORKSIGHT[ワークサイト]21号 詩のことば Words of Poetry』より転載してお届けします。
interview & text by Kei Wakabayashi
illustrations by Saki Souda
しっくりくることばを探して
古田徹也との対話・ウィトゲンシュタインと詩の理解
置き換えられない言葉
──このたびのインタビューは、「詩のことば」という特集の巻末に掲載されます。この特集で、古田さんにお話をお伺いしたかったのは、古田さんのご著書『言葉の魂の哲学』や『はじめてのウィトゲンシュタイン』で書かれたウィトゲンシュタインの言語論が、「詩」というものを考える上で大きなヒントになると思ったからです。ここではウィトゲンシュタインおよびカール・クラウスの言語論を概説していただきながら、詩というものの不思議に迫ることができたらと思っています。
話が大きいので、どこから始めたものか難しいですね。
──ですよね。まずは、詩を考えるにあたって、ウィトゲンシュタインの言語論をもち出すことが果たして妥当なことなのかどうか、そこからお伺いするのはいかがでしょう。
そうですね。まず、ウィトゲンシュタインという人は、「言葉の意味」あるいは「言葉の意味を理解する」ということについて極めて根源的な洞察を行った哲学者です。ご存じの通り「言葉」は彼の議論の根幹をなす問題でしたが、その言語論の中心には、言葉というのはそれ自体に意味が宿るものではなく、むしろ「使い方」に意味が宿るものだとする考えがありました。
──はい。
ちなみにウィトゲンシュタインの探究は、『論理哲学論考』に代表される「前期ウィトゲンシュタイン」と、『哲学探究』に代表される「後期ウィトゲンシュタイン」と、時期によって大まかに分けられます。「言葉の意味は使い方に宿る」という見方は前期にも後期にも共通していますが、「意味は使い方に宿る」という考えについて「本当にそれだけなのか」と疑い出したところから、「後期」のウィトゲンシュタインの探究は始まっています。つまり、言葉をうまく使えていれば、それだけで「言葉を理解した」と言っていいのか、と考え出すわけです。そのことを考えていくにあたって、ウィトゲンシュタインは「詩を理解する」とはいったいどういうことかを論じています。彼はこう書いています。
ある詩の言葉が、対応する決まりに従って別の言葉に置き換えられたとしても、その詩は本質的には変わらないなどとは誰も思わない
我々が文の理解について語るのは、それが、同じことを述べている別の文に置き換えられるという意味においてであるが、しかしまた、それがいかなる文にも置き換えられないという意味においてでもある。(ある音楽の主題を別の主題で置き換えることができないのと同様に。)
ある場合には、文の内容は異なる文に共通なものであるが、別の場合には、その言葉だけがこの配置のなかで表現している何かなのである。(詩の理解)。
──どういうことでしょう。
ここでウィトゲンシュタインは「言葉を理解する」ということのなかに相反するふたつの側面があると語っています。ある言葉の「意味」を他の言葉によって置き換えることができるという側面と、言葉を置き換えた途端に「意味」が台無しになってしまう側面があるということです。例えば、あるジョークを別の言葉で解説してしまうと、ジョークの面白みは死んでしまいますよね。同じように、詩をパラフレーズして置き換えたら、やはり詩は死んでしまいます。
──たしかに。
これは『言葉の魂の哲学』のなかで使った例ですが、「せつない」という言葉の意味を聞かれたら、わたしたちは「胸が締め付けられる気持ち」という意味だとか「やるせない」「しんみりする」「かなしい」といった意味だと答えます。普段の生活のなかで意味を伝えるのであれば、こうした言い換えで事足ります。ところが、いま自分が「せつない」思いを感じていたとして、その「せつない」を「胸が締め付けられる気持ち」や「かなしい」といった言葉に置き換えてしまったら、なんだかしっくりこない、ということが起こりえます。
──わかります。そこは勝手に言い換えられては困ります。
ウィトゲンシュタインは「言葉を理解する」ということには、このようにふたつの背反する側面があって、彼はその両方を見渡した上で「言葉を理解する」ということを捉えなくてはならないと考えました。論理学の言語とは違って、わたしたちが普段使用している「自然言語」には「固有の魂」があると彼が語るときに問題になっているのは、ふたつの側面のうちの後者の「置き換えのできない言葉を理解する」という「理解」のあり方が、論理学の言語のみならず、わたしたちの日常においても十分に検討されてこなかったということです。
それは向こうからやってくる
──いまのお話は「詩」をめぐってよく交わされる議論をきれいに整理してくれているように思います。詩になじみの薄い人はよく「詩はわからん」「意味がわからん」とぼやく一方で、詩が好きな人は「理解しようとしなくていいんだ」といった言い方で、詩の魅力を説明しようとします。このやりとりは基本どこまでいっても平行線です。
ウィトゲンシュタインに倣って見ると、そのやりとりの混乱は、彼が論じたように「言葉の理解」には背反するふたつの側面があることから生じている混乱、すれ違いだと説明することができるかと思います。「詩がわからない」と言っている人が考えている「わかる」と、「詩がわかる」と感じている人の「わかる」は、そもそも違う。ウィトゲンシュタインが指摘したのは、まさにそのことなんです。
──面白いです。それにしても、言葉が「しっくりくる/しっくりこない」というのは、それこそしっくりくる説明ですね。
ウィトゲンシュタインは、このことをかなり突っ込んで探究していまして、わたしも『言葉の魂の哲学』のなかで「しっくりくる言葉を選び取る」ことについて、相当ページを割いて論じました。
──はい。
ウィトゲンシュタインがここで何を考えようとしたかを簡単に説明しますと、わたしたちがどうやって「しっくりくる」を判断しているのかということです。彼は、まずこう問いを立てます。
言葉の馴染み深い表情。言葉がその意味をみずからのうちに取り込んでおり、その意味の生き写しになっているという感覚。──そうしたことすべてと無縁であるような人々が存在するかもしれない。(そのような人々には、自分たちの言葉に対する愛着がないだろう。)──ところで、そうした感覚は我々の場合にはどうやってあらわれるのだろうか。──我々が言葉を選び、それを評価する仕方のなかで
──そう言われてみると、なんで「しっくりくる」と感じるんでしょうね。やっぱり自分のなかにそれと響き合う何かがあるからなんでしょうか。
そう思ってしまいますよね。ところがウィトゲンシュタインは、その考え方を否定します。
──そうなんですか。
そうなんです。「しっくりくる言葉を選び取る」という実践について彼はこう考えます。言葉が選び取られる前に何らかの神秘的な実体が存在していて、それと個々の言葉を突き合わせて「これはしっくりくる」「これはしっくりこない」といったふうに判断しているのではない、と。じゃあ、いったいどうやってそれを選び取るのか。彼はこう説明します。
『適切な』言葉を、私たちはどうやって見つけるのか。私はどうやって、様々な言葉のなかからそれらを選び取るのだろうか。確かに私は、微妙なテイストの違いに基づいて言葉同士を比較しているかに見える。これはあまりにも……過ぎる、これこそ適切なものだ、という風に。
しかし、これらの言葉がなぜしっくりこないのか、常に判断したり説明したりする必要はない。それは単にまだしっくりこないという以外の何ものでもない。私はさらに探すが満足しない。最後に私は安らぎを覚えて満足する。探すとはまさにこのようなことであり、見出すとはまさにこのようなことなのである
──「しっくりくる」言葉と出会うまで、あれこれ言葉を入れ換え続けるしかない、ということですか。
ウィトゲンシュタインが、この議論のなかで強調しているのは、最終的にしっくりくる言葉が見いだされるまでの導きとなるのは、言葉から言葉への連想と「しっくりこないという感覚」以外の何ものでもない、ということです。そして大事なのは、しっくりくる言葉がいったん出てくると、それはそうでなくてはならない、極めて自然なものとして感じられるということです。
──「しっくりくる」というのは、それが自然に感じられるということでもあるというのは、実感的にもわかります。
例えば「閑さや/岩にしみ入る/蝉の声」という松尾芭蕉の句がありますが、ここには、何も奇をてらったところはありません。とても自然です。けれども「蝉の声」が「岩にしみ入る」ところに「閑さ」を感じるというのは、よくよく考えてみると実に驚きに満ちた発見ですよね。蝉の声に閑さを感じるわけですから。でも、とても「しっくり」くるわけです。
──ほんとですね。
『言葉の魂の哲学』のなかで、ウィトゲンシュタインに大きな影響を与えたとされる批評家・戯曲家・文筆家のカール・クラウスの言語論を紹介しましたが、クラウスは「言葉がしっくりくる」というこの感覚を「創造的必然性」と呼んでいます。
──創造的必然性?
クラウスは詩における「韻」について論じていますが、韻を踏むという行為は、発音が似た言葉を選ぶわけですから、意味やコンテクストを逸脱していく可能性を孕んでいます。言うなれば、言葉と言葉に偶然的な結びつきを与えるものとして作用するわけです。けれども、ある言葉と言葉が実際に韻を踏んで、それが豊かな意味の広がりをもたらす効果を発揮したなら、それぞれの言葉は韻を踏むのに「はじめからふさわしかった」ものとして、つまりその結合は必然性があったものとして立ち上がってきます。クラウスが「創造的必然性」という言葉で説明しようとしたのは、言葉のそういう立ち現れ方です。
──言葉と言葉の偶然の結びつきが、あたかも必然性があったように感じられる、と。
はい。クラウスは、言葉のそうした作用を必ずしも詩のなかにのみ認めているわけではなく、例えばわたしたちが言葉を用いるあらゆる場面で、これは発現するとしています。クラウスの説明を、自分の本のなかから引用しますと、こんな感じです。
その一例として彼は、時事問題について語られる手短な批評(グロッセ)について取り上げている。卓抜な批評の言葉に触れたとき、人はときに思わず膝を打ち、これぞ自分が言いたかったことだと感じる。もちろん、その言葉は、当該の批評がなされたときに初めて生まれ、人々の耳や目に初めて入った言葉である。だからこそ人は虚を突かれて驚き、感心するわけだが、にもかかわらず、同時に、その言葉はしっくりくるものとして受けとめられる。自分が以前から思っていたことをうまく表現してくれた、そう人に感じさせるのである
──これは、おそらく誰もが体験したことのある感覚ですね。
そうだと思います。ここで注意すべきは、自分が何かを感じていたことが、言葉が選び取られた後になって初めてわかるという点です。つまり、ある言葉が生まれることによって、それが生まれる以前のものの見方や感じ方、考え方が明らかになるわけです。言葉の創造的必然性というのは、あらかじめ必然が用意されているのではなく、その言葉が見いだされることによって初めて「自分が以前から思っていたこと(感じていたこと、見ていたこと等)」が、遡及的に浮き彫りになるという、ある意味パラドキシカルな構造をもっているというのが、クラウスの見解です。「しっくりくる」は、いわば、向こうからやってくるんですね。
──なるほど。ある文章を読んで、「これこそまさに前から自分が感じていたことだ!」と思うことはよくありますが、本当に自分がそれを感じていたかどうかは、振り返ってみると確かに怪しいです。でも、「しっくりきた」ということが感じ取れた以上、何か感じていたことはあったということにもなるわけですが、でも、それは後になってからしかわからない。「これこそ自分が前から感じていたことだ!」という言い方は、常に後出しジャンケンにしかならないとは感じていましたが、それが言語のひとつの性質だと言われると、なんだか安心します。
クラウスは、ウィトゲンシュタインと同様に、言葉にはふたつの側面があると語っています。それは思考内容などを伝える「伝達」の働きと「それ自体がかたちを成す」、つまり「形成」の働きです。クラウスによれば言語をめぐる探究は、前者の働きに価値を置こうとするものと、後者に重きを置こうとするもののふたつに大別されます。そして彼は、これまでの言葉の探究は前者の価値に重きを置きすぎていて、「それ自体がかたちを成すもの」としての言葉の価値の側面が顧みられてこなかったと指摘します。これは、ウィトゲンシュタインが「言葉の理解」をめぐってふたつの側面があると指摘したことと重なり合う議論だと言えます。
生活と言語ゲーム
──今回の特集において、ひとつ興味の焦点としてあるのは、「詩」と「生活」との関わりです。「生活詩」という言葉がありますが、この言葉には「生活」のなかにある言葉を使って「生活者」の実感なり心情なりを映し出すといったニュアンスが込められています。ここには詩や言葉というものをめぐる大きなすれ違いが潜んでいるようで、クラウスが指摘した通り、「生活詩」というコンセプトにおいても、あくまでも「伝達」に重きが置かれてしまっている感じがします。
「詩がわかる/わからない」を言葉の伝達性において捉えて、生活のなかの「わかる」言葉で誰にでも「わかる」詩を書く、というニュアンスが「生活詩」という言葉のなかに感じ取れるということですよね。
──はい。ただ、ここで厄介だなと思ったのは、『はじめてのウィトゲンシュタイン』のなかで、ウィトゲンシュタインを理解するキーワードのひとつとして、古田さんが「生活」という言葉を取り挙げていらっしゃる点です。とはいえ、「誰にでもわかる」という意味での「生活」や「日常性」と、ウィトゲンシュタインが語った「生活」とは実際は似て非なるものといいますか、むしろ真逆のベクトルをもっている言葉のように思えるのですが、いかがでしょうか。
後期ウィトゲンシュタインが語った非常に重要な言葉に「言葉は生活の流れのなかではじめて意味をもつ」というものがあります。ここでウィトゲンシュタインが語っているのは、言葉というものは、人びとがそれを使ってきた長く複雑な歴史をもっていて、いわば膨大な「使用例」の集積としてあるということです。別の言い方をしますと、言葉の意味というものは「生活の流れ」のなかの膨大なやりとりのなかでそのつど定まってきたもので、ある記号が、生活のなかで使用され特定の役割を果たすその具体的な状況こそが、記号を「意味ある言葉」に変えるということです。
──ふむ。
ウィトゲンシュタインの有名な用語に「言語ゲーム」というものがありますが、彼はそれを「言葉と、それが織り込まれた諸行為の全体」と説明しています。つまり、言葉というものは、それ自体に意味や本質が宿るようなものではなく、長い時間をかけてかたちづくられてきた生活のあり方、生活の一定の流れを背景にした、そのつどの活動や実践のなかでしか意味を成さないというのが、ウィトゲンシュタインが考えたことでした。彼はこんな言葉で「言語ゲーム」というものを説明しています。
『言語ゲーム』という用語はここでは、言葉を話すということが活動の一部分、あるいは生活形式(Lebensform)の一部分であることを際立たせるべきものである
命令し、質問し、語り聞かせ、おしゃべりすることは、歩き、食べ、飲み、遊ぶことと同様に、我々の自然誌に属している
─「自然誌」という言葉は面白いですね。つまり、言葉は、ある意味、わたしたちを取り巻く「自然」として観察されなくてはならない、ということでしょうか。
「言語ゲーム」という用語に込められたニュアンスは、それが日々生まれながら刻一刻と変化するもので、途方もない多様性をもち、生成変化するダイナミズムや可塑性を内包しているということです。こうした考えは、従来の哲学に対する批判としての側面が強くありました。それまでの哲学において重視されてきた「◯◯とは何か」という「普遍的」な「本質」を探り当てようとする問いの立てかたに対する異議申し立てでもあります。彼は、こう書いています。
哲学者たちがある言葉を用いて──「知識」、「存在」、「対象」、「自我」、「命題」、「名」といった言葉を用いて──物事の本質を把握しようとしているとき、人は常に次のように問わなくてはならない。いったいこの言葉は、その故郷となる言語のなかで、実際にそのように使われているのか、と。──
我々はこれらの言葉を、形而上学的な使い方から日常的な使い方へと連れ戻す。
ここだけ読むと、哲学者の言葉使いを、ある意味超越的な位置から引きずり下ろして、民衆や大衆に返そうという保守主義的な物言いだと誤解されてしまいそうですが、彼の言語論にはそうした階級闘争的な視点はありませんし、人類学のように文化を相対的に捉えるという観点も強くはありません。実際、彼は「社会」や「文化」といった言葉を『哲学探究』のなかではほとんど使っていません。むしろ彼が疑うのは、物事の「本質」や「普遍的な規則」といったものを措定しようとする考え方そのものです。
現象の背後に何も探してはならない
彼が、ここで「自然誌」という言葉を使っている背景には、詩人ゲーテが唱えた「形態学」という用語が大きく影響を与えています。ゲーテは植物を観察するなかで、有機体の個々の形態を「動的に関係し合う全体」において捉えることを提唱しています。彼はこう語っています。
……あらゆる形態、とりわけ有機体の形態を観察すると、変化しないもの、静止しているもの、他と関係していないものなど何ひとつ見出せず、むしろ、あらゆるものは絶えざる運動のなかで揺らいでいることに気づく
簡単に言ってしまえば、ウィトゲンシュタインは植物がお互いに連関しながら変態=メタモルフォーゼを絶えず繰り返していくさまを、言葉というものを考える上でのひとつのモチーフとしたわけです。ただ、ゲーテとウィトゲンシュタインとを決定的に分かつのは、ゲーテが、そうやってネットワーク化しながら変態を繰り返していく植物の変化の背後に何らかの「原型」を見てとり、そこに原初的な「本質」を見いだしたのに対して、ウィトゲンシュタインは、目の前の現象の背後に何らかの「本質」「謎」が隠されていると考えてしまう欲求をキッパリと否定した点です。ウィトゲンシュタインは、ゲーテの次のモットーを引用していますが、ウィトゲンシュタインは、ある意味ゲーテ本人よりもこのモットーに忠実でした。
現象の背後に何も探してはならない。現象それ自体が学説なのだ
──めちゃくちゃかっこいいですね。
ウィトゲンシュタインは、現象の背後に隠されている謎や秘密はないというわけです。そうだとすると、わたしたちの目の前で起きている現象は何かということになりますが、わたしたちは、目の前で起きていることを、ある固定化された特定の「像」の下に見ているだけで、その異なる側面を見落としているというのが、彼の考えになります。だいぶ端折ってお話ししていますが。
──つまり、わたしたちは、世界を無垢な自然の状態で把握することができない、ということですよね。ある意味、言葉というものがわたしたちと世界の間にあって、言葉というレンズを通してしか世界を見ることができないといいますか。
ウィトゲンシュタインが言葉は生活そのものであると語り、それを観察することを「自然誌」と呼んだのは、言葉が世界そのものの一部であるという意味においてです。であればこそ彼は、言葉がわたしと世界を隔てている膜のようなもので、それを取っ払ったら無垢な世界を見ることができるとは考えませんでした。ウィトゲンシュタインにとって言葉は世界の重要な一部分なんです。それを取り払ってしまえば世界の大きな一部が失われてしまいます。こうした観点からウィトゲンシュタインは、言葉を人間のコントロールを凌駕するものと捉えていました。あるいはクラウスは、言葉を「巨大な有機体」と言い表してもいます。
また、ウィトゲンシュタインは「像」(Bild)という用語を独特な使い方をしています。『はじめてのウィトゲンシュタイン』は、この用語を説明することにかなりの紙幅を費やしています。「像」は「何かのイメージで物事を捉えるということ」を指しています。ここでいう「イメージ」は必ずしも具体的な視覚イメージに限ったものではありません。ひとつひとつの言葉やそれが連なった構文などには、それぞれ固有の──とはいえ絶えず流動している──「像」があるわけです。そして、ウィトゲンシュタインは、わたしたちは普段、そうした特定の「像」によって囚われになっていると考えます。
──ふむ。
わたしなりの言葉で言い直しますと、ウィトゲンシュタインの言語論は、いわば「概念の文法」を観察することを促すものです。ここでいう文法は、わたしたちが生活の流れのなかで個々の概念などを学び、ちゃんと意味が通るように使う際に従っている秩序のことです。
例えば、「痛み」という概念を例にすると、その概念のなかには「痛みは他人と分かち合うことができない」「痛いと人は顔をしかめる」「痛みには始まりと終わりがある」といったさまざまな内容が含まれていますが、それらのことは当たり前すぎて、わざわざ誰も目を向けません。ウィトゲンシュタインは、そうした当たり前をよく見ていくことこそが哲学の営為だと論じました。それこそが、先に挙げた「形而上学的な使い方から日常的な使い方へと連れ戻す」という言葉の主旨です。
その意味でウィトゲンシュタインの言語論は、簡単に言ってしまいますと、わたしたちが「当たり前」としてそのなかで生きている「像」や「文法」に、どう揺さぶりをかけることができるのかをめぐる探究だとも言えます。ちなみに『いつもの言葉を哲学する』という本は、そうした揺さぶりを、実生活のなかにある言葉を通じてわたしなりに実践するつもりで書いたものです。
──先ほど挙げられていた「〇〇とは何か」という問い自体が、ひとつの「像」もしくは「文法=秩序」であって、その「像」から抜け出すためには、その「像」自体を観察しないとだめだ、と。
「〇〇とは何か」がひとつの「像」でしかないのであれば、わたしたちが世界を把握するためには、その「像」自体を批判的に観察し、「〇〇とは何か」という構文そのものに懐疑的にならなければなりません。でもこれはやろうとするととても難しいもので、放っておくとつい「〇〇とは何か」という問いに戻ってきてしまいます。
ChatGPTと吉岡実
──余談めいた話ですが、最近インターネットを使った「検索」のワークショップを企画したんです。例えば「いまアメリカで一番イケてる映画監督を検索せよ」といったお題で参加者の方々に検索してもらったりしたのですが、興味深かったのは、「イケてる」という言葉の「意味」や「定義」あるいは「本質」を検索しようとする人が少なからずいたことです。ところが、このアプローチはどこにも行き着かないんですね。というのも、インターネットの検索は、基本言葉の使用例を統計的にランキングしたものにすぎませんので、アプローチとしては、むしろ「イケてる」の言葉がどういう言葉と並んで頻出するかを見ていくべきものなんですね。
ChatGPTについても同じことが言えそうですよね。おっしゃる通り、そこに現れる文章なり検索結果は統計に基づくもので、言うなれば言葉と言葉の間の距離を測っているわけですね。そういう意味でインターネットや大規模自然言語処理は、まさに「背後に何も探してはならない」現象と言えるかと思います。特に言語AIは、そのままウィトゲンシュタインの議論に馴染むもので、生活のなかの膨大な使用例を統計的に配列した「言語ゲーム」と言えますし、わたしたちが生きている生活の流れのなかでつくられた「像」や「概念の文法」の現れだと見ることもできるかと思います。
ただ、ChatGPTを考えるときに重要なのは、ここまで見てきたように、言葉には「置き換えができるもの/できないもの」あるいは「伝達/形成」というふたつの側面があるということです。わたしたちはとかく「意味の伝達」という側面においてからのみChatGPTを論じてしまいがちですが、「形成」という観点、あるいは「しっくりくる言葉を選び取る」という観点から見ると、また違った論点を取り出すことができるのかもしれません。
──「AIに意志はあるのか」「AIは思考しているのか」といった問題は、だいたいが「意志とは何か」「思考とは何か」といった本質論に陥りがちですが、ウィトゲンシュタインはいわば、この問題を考えるための別のアプローチの仕方を100年近く前にすでに考えていたとも言えそうです。
ChatGPTというものを前にして誰もが何ともいえないモヤモヤに直面しているいまであればこそ、ウィトゲンシュタインにとって言語というものがなぜ重大なテーマとして設定されたのかが、より強いリアリティをもって感じることができますね。
──今日インタビューにお邪魔する道すがら「現象の背後に何も探してはいけない」というゲーテのモットーを唱えながら、道ゆく車や街路樹を眺めていたのですが、そうやって辺りを見回してみると、詩が立ち上がってきそうな予感がしてきました。ただ、それは必ずしも街路樹を単に「記述する」ことではないのだな、という感じもしました。
ウィトゲンシュタインは、ある「像」から抜け出すためには、別の「像」を探す、あるいは発見して、元の「像」と比較することが大事だとし、それこそが創造的な営為だと語っています。さまざまな「像」の可能性を検討し比較を重ねていくことは「しっくりくる言葉を選び取る」営為と似ているところがあります。「しっくりくる」まで、とにかく可能性を検討するわけです。
──この特集のために石垣りんの『朝のあかり』というエッセイ集を読んでいたのですが、こんなことが書かれていました。例えば詩を見て虹を感じたとします。そのとき、人は「詩は虹を書くことだ」と考えてしまいます。でも、「どうもそうではないらしい」。「虹をさし示してる指、それがどうやら詩であるらしい」。
うまいことをおっしゃいますね。先の芭蕉の句ではないですが、しっくりくるものと出会うと、それがあたかも自然に感じられます。と同時に「あっ」という驚きがありますよね。加えて、そこには何らかの新しい意味や価値がつけ加えられているわけでもない。「それそのものとして見る」という行為なんですね。「理解している通りに理解する」といいますか。ウィトゲンシュタインは、生活のなかにある言葉を、それ自体が「驚くべきもの」であるということを語っていたのだと思います。
わたしたちは学校で言葉の扱いかたを学ぶとき、常にその背後に必ず「メッセージ」があるという前提で学びます。それがいかにつまらないことかと感じたのは、わたしの場合、吉岡実の詩に出会ったときでした。「この言葉でしかありえない」という感覚を、吉岡実の詩で初めて深く納得しました。それをそれとして味わう以外の読み方がないという感覚ですね。それによってひとつ呪縛が解けたと感じたことを覚えています。
──芭蕉の詩句に「メッセージ」を読み取るのはナンセンスですよね。詩という現象の背後に何も探してはいけない、ということですね。
詩をまるで自然の景色を眺めるように見る。そこに言葉が揺らぐのをただただ見る。そういうことかなと思います。『はじめてのウィトゲンシュタイン』を執筆した際にも、机の上に吉岡実の詩を置いていました。ウィトゲンシュタインについて執筆しながら、時折詩集を開くと、そこにウィトゲンシュタインの言語論が実践されているように感じていました。『絶版本』という書籍の企画で、吉岡実の詩について書かせていただいたことがあるのですが、そこでこんなことを書きました。
そこに隠されているものは何もない。深遠なメッセージも、奇抜なイメージも、巧妙な寓意も、そこにはない。あるのはただ、言葉のかたちそのものだ
古田徹也|Tetsuya Furuta 1979年、熊本県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科准教授。東京大学文学部卒業、同大学院人文社会系研究科博士課程修了。専攻は、哲学・倫理学。『言葉の魂の哲学』で第41回サントリー学芸賞受賞。その他の著書に『それは私がしたことなのか』(新曜社)、『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』(角川選書)、『不道徳的倫理学講義』(ちくま新書)、『はじめてのウィトゲンシュタイン』(NHKブックス)、『いつもの言葉を哲学する』(朝日新書)、『このゲームにはゴールがない』(筑摩書房)、『謝罪論』(柏書房)など。
【新刊のご案内】
Photo by Hiroyuki Takenouchi
書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]21号 詩のことば Words of Poetry』
言葉という情報伝達手段でありながら、普段わたしたちが使うそれとは異なるかたちで世界の様相を立ち上げる「詩のことば」。情報過多社会において文化さえも消費の対象とされるいま、詩を読むこと、詩を書くこと、そして詩の言葉にこそ宿るものとはいったい何なのか。韓国現代詩シーンの第一人者であり、セウォル号事件の被害者に寄り添ってきたチン・ウニョンへのインタビュー、映画監督・佐々木美佳による詩聖・タゴールが愛したベンガルでの滞在記、詩人・大崎清夏によるハンセン病療養所の詩人たちをめぐる随筆と新作詩、そして哲学者・古田徹也が語るウィトゲンシュタインの言語論と言葉の理解など、わたしたちの世界を一変させる可能性を秘めた「詩のことば」について、詩人、哲学者、民俗学者、建築家などのさまざまな視点から解き明かす。
【書籍詳細】
書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]21号 詩のことば Words of Poetry』
編集:WORKSIGHT編集部
ISBN:978-4-7615-0928-6
アートディレクション:藤田裕美
発行日:2023年10月20日(金)
発行:コクヨ
発売:学芸出版社
判型:A5変型/128頁
定価:1800円+税