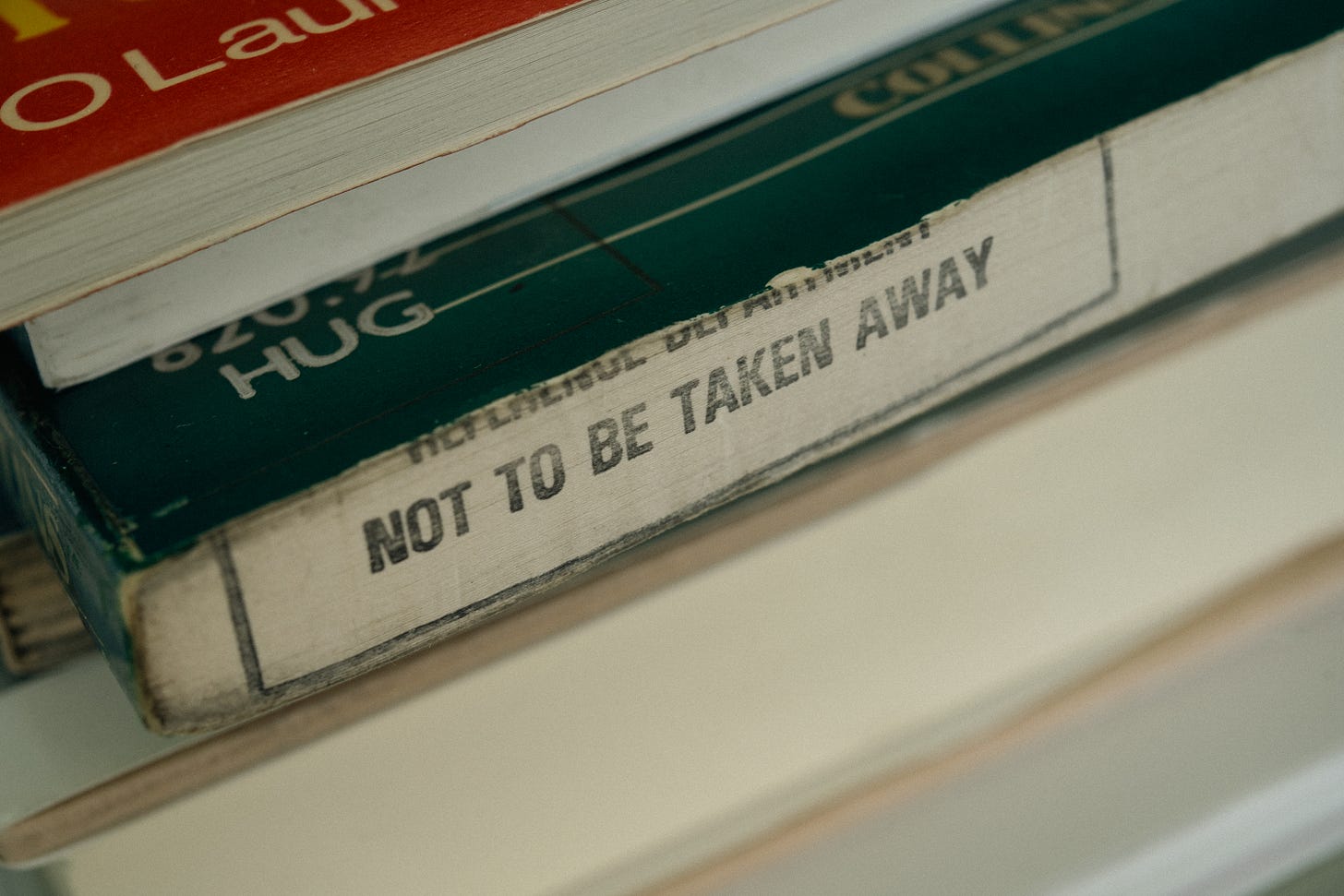「起源」ばかり問わないで:カリブ海思想研究者・中村達との語らい
無意識バイアスが反省されつつあるなか、知の枠組み自体を鋭く問い、揺らがせる“変化の思想”がある。その思想を学び、自身も変化したと語るのが『私が諸島である:カリブ海思想入門』の著者・中村達だ。人気ゲーム『Outlast 2』やディズニー『リトル・マーメイド』、デヴィッド・グレーバーの批判的検討から、カリビアン・フェミニズムやカリビアン・クィア・スタディーズまで。カリブ海思想の水平線は、限りなく広い。
「なぜハイデガーでなければならない? なぜラカンでなければならない?」「僕たちにだって思想や理論はあるんだ」──。2023年12月に刊行された『私が諸島である:カリブ海思想入門』(書肆侃侃房)の本論冒頭、そして書籍の帯にも引かれているのは、著者である中村達が指導教員ノーヴァル・エドワーズ、通称ナディからかけられたことばだ。2015年、西インド諸島大学へ留学した中村が、西洋の文学理論や哲学を援用しながらカリブ海の文学を分析した論文を見せた際の、短くも強烈な一言だったという。
カリブ海の思想と聞けば、遠いものだと感じるだろうか。いや、その実態を知れば、文化が分かちがたく混じりあって変化していく様相を描き出す思想は、現代社会の深奥を抉るものなのだとむしろ近しさを覚え、共感を抱くはずだ。そして同時にカリブ海思想は、そのように普遍的な思想として自らを消費しようとするものを、注意深く牽制してもいる。つまりカリブ海思想に触れ、考えるということは、今回インタビューした中村が実感してきたように、わたしたちが生きる世界の可能性と複雑さに身を浸すということなのかもしれない。
photographs by Kaori Nishida
interview and text by Fumihisa Miyata
中村達|Tohru Nakamura 1987年生まれ。千葉工業大学助教。英語圏を中心としたカリブ海文学・思想を専門とする。西インド諸島大学モナキャンパス英文学科の博士課程に日本人として初めて在籍し、2020年PhD with High Commendation(Literatures in English)を取得。2023年12月、『私が諸島である:カリブ海思想入門』を上梓。主な論文に、 “Peasant Sensibility and the Structures of Feeling of "My People" in George Lamming's In the Castle of My Skin”(Small Axe, 2023)など。
欧米の理論という「ナイフ」
──「2015年に日本の大学院を飛び出るように満期退学した私は、(中略)カリブ海にある西インド諸島大学への博士課程留学を決意し」、キャンパスのひとつがあるジャマイカへと旅立ったと、『私が諸島である』の序章にあります。中村さんはなぜ、カリブ海思想へ足を踏み入れたのでしょうか。
そもそも日本で大学院に入ったときは研究者を目指していたわけではなく、高校で英語教員になろうと思い、その鍛錬のためという意識でした。学部生の頃から学んでいたのも、ヴァージニア・ウルフやE・M・フォースターなどの、イギリスのモダニズム文学です。卒業論文や修士論文こそ、トリニダード・トバゴ出身の作家、V・S・ナイポールについて書きましたが……。
──ノーベル文学賞受賞作家であるナイポールですが、西洋の価値観を内面化してしまっており、カリブ海に創造的な歴史を見いだすことができなかった書き手として、現地の思想家たちの間では批判的に言及されているようですね。
カリブ海でナイポールは「すごい作家なんだけれど……」と微妙な受け止められ方をしているということは後にわかったことで、当時のわたしは、そんな視点は一切もち合わせていませんでした。ナイポールを考えるといっても、ホミ・バーバの「ミミクリー(模倣)」という概念をはじめとした欧米中心の文学理論や、すこしかじった西洋哲学をもとに論じるというもの。カリブ海思想を学ぶことをめぐる使命感も何もなく、人文系の若い子にありがちな、理論にかぶれた人間だったのです。
──そうだったんですね。
そうするうちに日本で博士課程に進み、高校の教員になる気持ちもいつの間にか薄れるなかで、きちんと探究するべきものとして浮かび上がってきたのがカリブ海文学・思想でした。とはいえそんなことを研究できる環境はなく、独学で進めるうちに、やがて日本を飛び出すことになったのです。いろいろと理由はあったのですが、日本の研究者でひとりぐらい、カリブ海のジャマイカでPhD(博士号)を取るような人間がいても面白いんじゃないか……正直にいえば、それぐらいの心持ちでした。
──中村さんが最初に見せた論文を、やがて恩師となるナディが批判した所以がわかりました。
日本でインストールされたOSしかわたしのなかにはなかったにもかかわらず、「カリブ海文学を“調理”できる方法はすべて理解した。これ以上の調理法は知らない」というぐらいの気持ちでいました。しかしナディにしてみれば、日本でわたしが身につけてきたのは、欧米のアカデミアのなかで多くがそぎ落とされ、失われたものだったのです。彼はカルチュラル・スタディーズの著名な研究者であるポール・ギルロイの『ブラック・アトランティック』も、欧米の枠組みにおいて黒人文化を論じている、というように公然と批判する人でした。生涯をかけて、カリブ海という世界で生まれた知を研究してきたナディから見れば、わたしはまさに悪しき意味において典型的な人間だったのだと思います。
──中村さんご自身にとって、すべてがガラッと転換する瞬間だったことと思います。
そのときに痛感したのは、「切れ味鋭い論考」というような表現をされる文章であっても、その切れ味というのは欧米の知識や権威に任せて無差別に切りつけているだけなのではないか、ということでした。その地域が積み上げてきた調理法に則るのでもなく、欧米から輸入した便利なナイフで、問答無用で切りつけているような……。これではだめだ、と衝撃を受けました。まったく違う方向をナディに教えてもらい、そこから5年にわたる学びの日々が始まったんです。
──「まったく違う方向」ですか。
『私が諸島である』のなかで、カリブ海思想におけるひとつの転換点となった、パジェット・ヘンリーによる2000年刊行の名著『キャリバンの理性』に触れた個所があります。ヘンリーは、こう書いているんです。カリブ海の人びとが自ら生み出しているものにまず目を向けなければならない、ということを強烈なまでに考えさせてくれる一節ですね。
もし我々が、我々の自己形成に関わる文化的側面の主導権を取り戻そうとするなら、西洋から輸入し続けている哲学的人類学、倫理学、存在論、認識論、その他の言説を、我々自らの手で耕し、生みださなければならない。今こそ、このような哲学的依存関係を断ち切るべき時なのだ
2022年6月から2023年5月までのweb連載時から話題になっていた内容に、大幅な加筆修正を経て刊行された『私が諸島である』。デザインは、グレゴワール・シャマユー『統治不能社会:権威主義的ネオリベラル主義の系譜学』(信友建志訳、明石書店)や、作曲家である藤倉大がアルテス・パブリッシングから出している著書などの装幀を手がける、木下悠によるもの。
単なる“ごちゃ混ぜ”ではない
──特に1980年代以降、日本でもクレオール論をはじめカリブ海思想はさまざまに紹介されてきましたが、『私が諸島である』はweb連載時から斬新な構成で評判を呼んできました。クリストファー・コロンブスがカリブ海の群島にたどり着き、双方が遭遇した1492年以降、西洋視点で紡がれてきた知の体系を「解呪」しようとしてきた現地の思想を、クリアに紹介しています。さらに書籍化にあたっての加筆では、カリビアン・フェミニズムやカリビアン・クィア・スタディーズといった、日本ではほとんど紹介されてこなかった領域について、熱のこもった筆致で詳説しておられますね。
連載時に書いていった内容も非常に重要ではあるのですが、加筆した部分がないと、先行する日本語文献や書籍と似たような、従来のカリブ海思想を紹介する内容になってしまうかもしれない、とも感じていました。キューバ人理論家のアントニオ・ベニーテス=ローホーは、「クレオライゼーション」の「唯一の法則は変化である」と述べていますが、カリブ海思想を紹介するならば、常に起きているその「変化」を前面に押し出しながらこの本を終えたいと思ったんです。
──前提として、カリブ海思想においてよく語られる「クレオライゼーション」ということばは、どうとらえればよいでしょう。
「クレオライゼーション」とは、多様な文化や人種が接触し変化していくカリブ海特有の経験を示す隠喩として、現地のさまざまな思想家や作家が用いてきた概念ですが、カリブ海の外では、いわゆる “ごちゃ混ぜ”の状態として一般的な理解がなされてきてしまっているように思います。しかし、「クレオライゼーション」を単なる混淆性として理解してしまっては、従来エドワード・サイードやホミ・バーバといった、欧米中心のポストコロニアリズムの思想家たちによる「雑種性」の議論へとカリブ海の経験を収奪してしまってきた流れと同じことになってしまうのです。
──植民地主義を批判するポストコロニアリズムも、あるいは近年議論の進んできた「惑星思考」という一見包括的な知の枠組みについても、いずれも西洋中心的な「思想的搾取」だったのではないかというのが、本書の論旨ですね。そこから如何に脱するか、知の「脱植民地化」を果たしていくのか、カリブ海の思想家たちが苦闘してきた歩みが紹介されていきます。
バルバドスの歴史学者・詩人のカマウ・ブラスウェイトは、もともとカリブ海において旧世界に由来し新世界に生まれた人間を指していたクレオールということばの形成過程にも、植民地としての経験が刻まれているという議論を展開しています。そして、カリブ海のクレオライゼーションは「文化変容」と「文化相互作用」という、ふたつの変化の過程からなるとしている。やはりここには、クレオライゼーションは単にゴチャゴチャの混淆状態を指すのではなく、カリブ海が植民地として経験してきた歴史が強く影響しているという思想が息づいています。今回『私が諸島である』を書くにあたって、カリブ海の思想家たちが紡いできたことば、そして知識の総体を、とにかく印象づけていきたいと思いました。各章のはじまりを、カリブ海の人びとのことば、いわば“声”の引用にしていることも多いんですね。わたしの“声”は、本当に部分的にしか入れていないんです。
カリブ海を消費するカルチャー
──アカデミズムの領域のみならず、人気ゲーム『Outlast 2』などにも同様の危うさがあるというのは、本書のハッとする指摘です。ガイアナで1978年に発生したカルト宗教集団による集団自殺をモチーフにしたゲームであり、同様のエンタメ的な消費はよく行われているにもかかわらず、現地でその地域的トラウマを「回復」しようとしている言説や文芸表象には目が向けられていない、と。
つくづく思うのは、カリブ海というのはその歴史を通してずっと、誰かが自分の欲望を映し出す鏡、欲望を垂れ流す器として利用され続けてきた、ということです。『Outlast 2』にしても、あれだけ衝撃的な事件が起きた歴史があるにもかかわらず、素材として利用して「面白かったね」と享受したら終わりなのか、と疑問に感じます。他にも例えば、2023年に話題になったディズニーの実写版映画『リトル・マーメイド』に関しても、思うところはあります。
──主人公である人魚のアリエルを、黒人の女性が演じた『リトル・マーメイド』ですか。
カリブ海を想起させる王国を舞台に、たしかに黒人の人魚が主人公となっており、「フェミニズムへの目配せがある」というような論評もされました。しかし、それは誰による、誰のためのフェミニズムなのでしょうか。それはディズニーが見せたいフェミニズムにすぎないのではないか。人魚が恋をする人間の王子は白人であり、それはカリブ海の歴史においては白人プランター(入植者)に恋をする描写に等しいわけです。
──なるほど……。
そうした作品をフェミニズムの観点から論じる人たちが依拠しているのは欧米のフェミニズムであり、例えばジャマイカのフェミニストであるキャロリン・クーパーのような人たちの言説に触れられることはほとんどない。カリブ海は、外側の人たちが見たいものを自分勝手に見る舞台にされてきているというのは、まさに現在起こっている問題だと感じます。
(上)『Outlast 2』のトレイラー。ヒット作となったホラーサバイバルゲーム『Outlast』のシリーズ第2弾としてつくられた本作は、1978年にジム・ジョーンズを教祖とする人民寺院が、ガイアナの通称“ジョーンズタウン”で起こした集団自殺をモチーフとしている。 (下)2023年の実写版『リトル・マーメイド』の本編プレビュー。人魚アリエル(ハリー・ベイリー)は、命を救ったエリック王子(ジョナ・ハウアー=キング)に惹かれていく。
どこまでも変化すること
──『私が諸島である』の終盤で紹介されるカリビアン・フェミニズムや、新世代のカリビアン・クィア・スタディーズは、まさに既存の価値観に挑む動きです。西洋の理論を批判的に乗り越えようとしながら、従来カリブ海思想を紡いできた男性たちへも反駁する、二重の批判になっています。このインタビューでも言及されたブラスウェイトは、クレオライゼーションを支えるアフリカ文化を、海に「沈み込んだ母」と表現しているようですね。それは奴隷たちが文化を密かに生き延びさせてきた抵抗戦略を語ることばでありながら、女性たちを男性主導の文化を支える受動的な役割へ押し込めている。植民地主義を糾弾し、日本でも多くの読者をもつフランツ・ファノンもまた、名著とされる『黒い皮膚・白い仮面』のなかで非異性愛者の実在自体を否定していると紹介されます。
わたしがPhDを取ったのは2020年のことですが、その段階では、男性のカリブ海作家についてしか論文では扱っておらず、口頭試問においてもジェンダーの観点を問われました。わたし自身、カリビアン・フェミニズムやカリビアン・クィア・スタディーズへと論がきちんと及んでいないというのは自覚していて、課題だと感じていたんですね。今回の書籍で、連載終了後に加筆した章こそが、そうした課題に応答しようとしたものでした。西洋に対してカリブ海から複数のフェミニズムを提示したり、包摂的な言説に見えて白人優位的なクィア・スタディーズを乗り越えようとしたりしている人たちが、実際に多くいます。そうしたカリビアン・フェミニズムやカリビアン・クィア・スタディーズの語り手たちは、この場でお話ししてきたようなカリブ海思想を、内部から変えようとしている人びとです。わたしは今回、書籍を出すならば、必ずその人たちの発言を紹介したかったですし、だからこそ加筆をしていったのでした。
『私が諸島である』で紹介される、さまざまな書き手たち。 (上)1947年、トリニダード・トバゴに生まれたカナダ人作家、マーリーン・ノービス・フィリップ。「像」(image)の頭文字を大文字化し「私」(I)を前景化した「私-像」(I-mage)という概念をもとに、西洋からの思想的搾取のもとにあったカリブ海の人びとの存在論的主権を訴えてきた。その議論は、カリブ海の女性たちの身体が置かれてきた社会的位置にまで及ぶ。 Photo by Patti Gower/Toronto Star via Getty Images (下)自身がゲイであることを公表している、1978年生まれのジャマイカ人作家・詩人、カイ・ミラー。カリブ海の一部では、植民地時代の負の遺産として同性愛が犯罪とされたままであり、ジャマイカではレゲエ文化も含めた大衆的な差別感情が問題視されている。ミラーは、命の危険を感じるほどの社会の空気を、文字通り投げつけられる石をタイトルに掲げた短編集『石の恐怖』で描いている。 Photo by Roberto Ricciuti/Getty Images
──本書中盤にかけて論じてきた内容を、いわば内部から批判していくような終わり方になっていますよね。この書き方を可能にしたものは、何なのでしょう。
先ほどすこし触れたように、そもそもの話として、カリブ海思想の語り口を変えていきたいという思いがわたしのなかにありました。日本でもフランス語圏のカリブ海思想や文学はよく読まれてきているのですが、だからこそといいますか、その理解が綺麗な“道”になってしまっているイメージがあるんです。まずはアフリカを神話化・理想化していった、エメ・セゼールらによる「ネグリチュード」という運動があり、その本質主義を乗り越えようとしたエドゥアール・グリッサンがいて、その思想に倣ったパトリック・シャモワゾーやラファエル・コンフィアンといった「クレオリテ派」がいる……という。クレオリテ派らによる宣言の書『クレオール礼賛』のように、クレオールは素晴らしいという議論のままに日本では消費されてきている感覚があります。
──インタビュアーであるわたしも、そのように理解してきました。しかし、そうしたカリブ海思想の男性論者の議論には、クレオリテ派が実は女性に抑圧的・攻撃的であったように、問題が含まれているというのもまた『私が諸島である』の論旨です。
これまでの“道”をなぞるだけではいけない、と思ったのです。カリブ海文学研究者であり、グリッサンの翻訳者としても知られるJ・マイケル・ダッシュは、グリッサンの思想には「皮肉なまでの自己内省」があるとしています。自己内省を繰り返しながら変化していくというその思想にクレオリテ派が倣っているというならば、性差別的な危うさを抱えたクレオリテ派を語ることをもってクレオールの議論を終えてはいけないはずなのです。再生産して権威化するのではなく、常に変化をしていくのが、カリブ海思想の姿なのではないでしょうか。
──変化していくことこそがクレオライゼーションであるならば、その本来の姿勢に則るのだ、と。2008年に刊行されたゲイ/レズビアン作家たちの論考アンソロジーが、『我々のカリブ海』と題されているのも象徴的です。それにしても、各国・地域の状況に焦点を当てるというのでもなく、より全体的、環カリブ海的な思想を目指すなかでこそさまざまな「回復」がなされるのだという現地の信念や動きは、どのように考えればいいのでしょう。
もちろん、カリブ海のなかでも国や地域によって、スペイン語圏やフランス語圏、わたしが研究している英語圏というようにことばも違いますし、奴隷制によってアフリカの人びとが、奴隷制に代わる年季奉公制においてはインドを中心にしたアジアの人びとが送り込まれていったように、状況もさまざまです。しかし、そのなかでもやはり、植民地支配という“共通の経験”が、現地の人びとを関係づけているわけです。そして、その“共通の経験”から解放されるためにこそ、環カリブ海という枠組みが重要になってくるんですね。
──“共通の経験”から解放されるためにこそ、共通の議論の土台を拡張していく、と。
カリブ海思想自体が、“共通の経験”から紡ぎ出されてきたものであるわけです。植民地支配を受けてきた我々が、その経験の只中から主体的につくり上げてきた思想があるのだ、だからこそこれからも、ともにやっていこう──そのように絶えず自己内省と変化を繰り返していく営みなのだと思います。
西洋中心主義批判だけが、カリブ海思想の役割か?
──カリブ海の思想を、どれだけ自分たちに引きつけていいものか、現代社会を相対化する思想として見ていいものか、悩みます。例えば文化人類学者デヴィッド・グレーバーは『民主主義の非西洋的起源について:「あいだ」の空間の民主主義』(片岡大右訳、以文社)でアテネに端を発する西洋の民主主義をめぐる伝統的ナラティブを相対化し、「アフリカやブラジルの農村コミュニティにおける平等志向の意思決定形態が、今日のほとんどの国民国家を支配している立憲的システムと少なくとも同程度に──また多くのケースではたぶんはるかに──この名に値する、と考えない理由など何ひとつありはしない」と述べていますが……。
どうなんでしょうか……直接の答えになるかはわかりませんが、ふと思うのは、グレーバーの議論はカリブ海を不利な立場に立たせるということです。グレーバーのこの著作の原題は、民主主義が「あいだ(in between)」の空間に現れる(emerge)という表現をしていますが、そうした起源をめぐる議論になると、カリブ海は不利な立場に置かれます。先住民のアラワク族は、植民者たちによる虐待と彼らがもちこんだ感染症によってほぼ絶滅に追い込まれています。つまり、西洋社会を相対化するための起源という議論自体が、まさしくカリブ海を他者化していく性質をもつのではないか。わたしは、起源=はじまりをめぐる議論はもういいじゃないか、と思います。どのような変化が常に起きているのか、ということのほうが、大事なのではないでしょうか。
──なるほど。自分たちを相対化するヒントを“外”に求めること自体にも、問題があるのかもしれないと内省せざるを得ません。
今回、わたしの本を読んで面白いと思ってくださる方のうち、西洋中心主義批判の文脈で興味を抱いてくださる方は多いだろうと想像します。ただ、それは必ずしもカリブ海思想が担うべきものでもないし、わたしが取り組むべき仕事でもないと思うのです。わたしがしたいのは、単にカリブ海思想を紹介する、ということなのです。
──西洋中心主義批判のコンテクストのみでカリブ海思想を見れば、それもまたひとつの搾取であり消費だ、と。
はい、そういうことなんです。西洋中心主義批判は、西洋中心主義の人たちが自分でやればいい、いや、自分たちの思想の不公平さを「解呪する」必要性に気づいてほしいと思っています。
──ガイアナ出身の作家ウィルソン・ハリスが、「カリブ海のクレオライゼーションの経験から生まれるクロス・カルチュラルな想像力」によって「ニヒリズムを凌駕」しようとしているという議論も紹介されていますが、現代に蔓延するニヒリズムに安易に結びつけていいのかどうか……刺激を受けながら躊躇します。
やはり、地域性をリスペクトするということに尽きるのではないでしょうか。ハリスがどのようにニヒリズムへの抵抗を含めた自身の思想を培ったかといえば、欧米のアカデミアに学んだのではなく、若い頃に政府の測量官となり、長い間アマゾンの奥地で日々を過ごしていたという経験から、知恵を編み出していきました。わたしたちは、そうした地域的な経験を踏まえてカリブ海思想をとらえるべきだと思います。「見たいものを見た」ということで終わってはいけない、と我が身を省みながら感じますね。そして、カリブ海思想自体が刻々と変化していく。わたしが語ることも変化していくことでしょう。
次週2月6日は、いよいよ明日1月31日刊行となる『WORKSIGHT[ワークサイト]22号 ゲームは世界 A–Z World is a Game』をより楽しむためのディープガイドをお届け。最新号の見どころはもちろん、誌面ではご紹介できなかった内容もまとめてお届けします。お楽しみに!
【近日発売・新刊のご案内】
photographs by Hironori Kim
書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]22号 ゲームは世界 A–Z World is a Game』
「21世紀はゲームの時代だ」──。世界に名だたるアートキュレーター、ハンス・ウルリッヒ・オブリストが語ったことばはいま、現実のものとなりつつある。ゲームは、かつての小説や映画がそうであったように、社会を規定する経済的、政治的、心理的、そして技術的なシステムが象徴的に統合されたシステムとなりつつあるのだ。それはつまり「ゲームを通して見れば、世界がわかる」ということでもある。その仮説をもとにWORKSIGHTは今回、ゲームに関連するキーワードをAからZに当てはめ、計26本の企画を展開。ビジネスから文化、国際政治にいたるまで、あらゆる領域にリーチするゲームのいまに迫り、同時に、現代におけるゲームを多面的に浮かび上がらせている。ゲームというフレームから現代社会を見つめる最新号。
書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]22号 ゲームは世界 A–Z World is a Game』
編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)
ISBN:978-4-7615-0929-3
アートディレクション:藤田裕美
発行日:2024年1月31日(水)
発行:コクヨ
発売:学芸出版社
判型:A5変型/128頁
定価:1800円+税
【第3期 外部編集員募集のお知らせ】
WORKSIGHTでは2024年度の外部編集員を募集しています。当メディアのビジョンである「自律協働社会」を考える上で、重要な指針となりうるテーマやキーワードについて、ニュースレターなどさまざまなコンテンツを通じて一緒に探求していきませんか。ご応募お待ちしております。
募集人数:若干名
活動内容:企画立案、取材、記事執筆、オンライン編集会議(毎週月曜夜)への参加など
活動期間
第3期 外部編集員:2024年4月〜2025年3月(予定)
通年の活動ではなく、スポットでの参加も可
募集締切:2月13日(火)正午
応募方法:下記よりご応募ください。