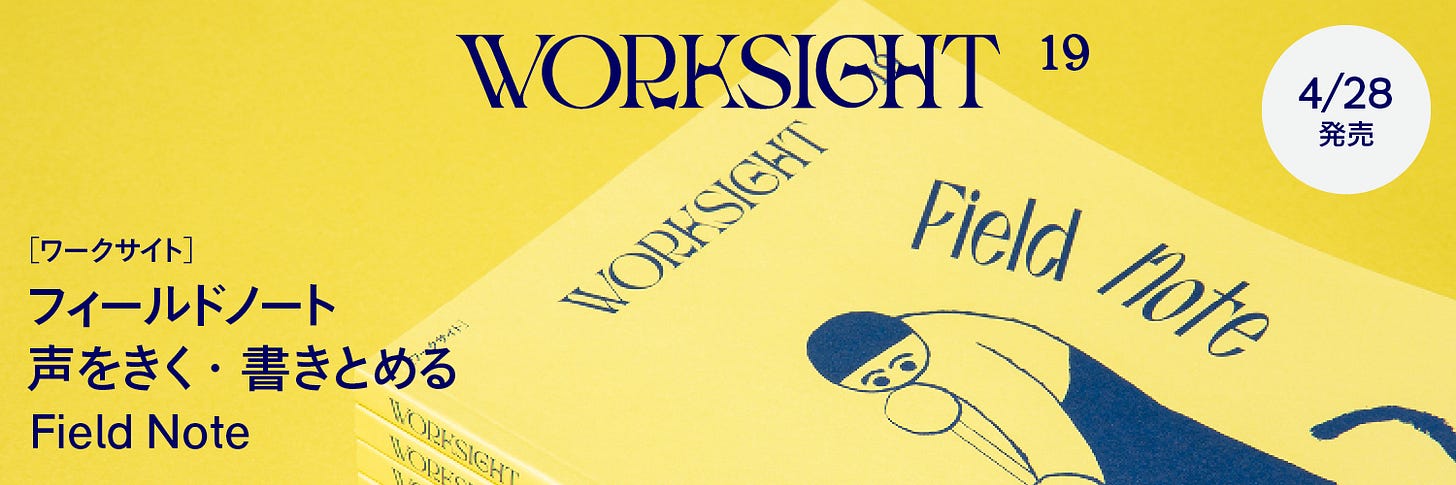バーチャルフォトグラフィーの、見たことのない写真:あるビジュアルの黎明
「Virtual Photography(バーチャルフォトグラフィー)」をご存じだろうか? 端的に言えば、ゲームをはじめとしたバーチャル空間で撮影した写真のことを指す。近年、このバーチャルフォトグラフィーがじわじわと盛り上がりを見せている。いったい、何が人びとを惹きつけているのか? 国内外の事例、それらをめぐる勃興期としての議論を踏まえながら、バーチャルフォトグラフィーの世界へとダイブしてみよう。
『Hogwarts Legacy』/ photo ©ELI THE WALKER
Instagramで「#virtualphotography」と検索すると300万件近くの投稿が出てくることから、バーチャル空間内で撮影した写真をシェアすることは珍しくない行為となっていることがわかる。バーチャルフォトグラフィーという呼称を知らない人でも、その作品のひとつは目にしたことがあるかもしれない(ゲーム内で撮影する写真は「インゲームフォトグラフィー(In-game Photography)」と呼ばれることもあるが、近年ではバーチャルフォトグラフィーの呼び名も広がっており、本稿ではその名称で記載する)。
近年の多くのゲームには、プレイを一時中断し、ズームや被写界深度、フィルターなどを設定できる「フォトモード」を標準的に備えたものが多い。PlayStationのようなゲームハードウェア側にも、スクリーンショットを撮る機能や写真をシェアする機能が搭載されているし、PCゲームのプラットフォームである「Steam」には各タイトルにプレイヤーが撮影した写真を共有できるページが存在している。また、多くのゲームメーカーはフォトコンテストを開催し、プレイヤーが積極的に写真を撮影することを推奨している。本稿では、「バーチャルフォトグラフィー」の歴史を簡単に紹介し、現在進行形で活動するバーチャルフォトグラファーの活動を紹介する。彼らの活動からはバーチャルフォトグラフィーがもついくつかの可能性が見えてくるだろう。
text by Koji Fukuda
不確かな起源、コロナ禍に旅立つゲーム世界
いくつかの事例から始めよう。いまやInstagramの登場により影を潜めてしまったが、それでも写真を撮るコミュニティでは根強く使われている写真共有サイト「Flickr」では、2022年から写真投稿時に「Virtual Photography / Machinima」というcontent type(Flickrでの検索時にフィルタリングできるカテゴリ)を選択できるようになっている。
それまでのcontent typeには「Photos / Videos」「Screenshots / Screencasts」「Illustration/Art / Animation/CGI」の3つしかなかったことから、Flickrがバーチャルフォトグラフィーをそれらに比肩するほど大きなジャンルとして認識していることがわかる(余談だが、Flickrはもともと開発していたオンラインゲームから写真共有機能を取り出してサービスとして提供したところから始まったそうだ。まさにバーチャルフォトグラフィー!)。
また、世界的なフォトエージェンシーであるGetty Imagesは、eスポーツ業界に参入し、『グランツーリスモ SPORT』の大会に現実のF1カメラマンを派遣し、撮影を行っている。
(上)Flickrにおけるバーチャルフォトグラフィーの紹介記事。(下)eスポーツの写真の潮流を紹介する動画
バーチャルフォトグラフィーはいまや、ゲームをプレイする人びとを中心に当たり前の行為となり、それに伴ってハードやソフト側の機能としても標準搭載されるようになってきている。また、Flickrのようなサイトで取り扱われるということは、現実の写真と同じような扱いをされ始めているとも言える。すでに、バーチャルフォトグラフィーの撮影を仕事にするカメラマンも出てきているのだ。
こうした盛り上がりをみせる「バーチャルフォトグラフィー」の来歴について、簡単に紹介していこう。正史めいたものはまだなく、海外ではいくつかの研究論文が存在しているものの、日本への紹介はこれからという段階だ。バーチャルフォトグラフィーについて、日本での数少ない文献のひとつは、メディアアーティスト・谷口暁彦による論考「ヴァーチャルなカメラと、それが写すもの」(『エクリヲ vol.11』収録)だ。
谷口は「バーチャルフォトグラフィーの起源」を明確にすることは困難だとしつつ、「プレイヤーがゲーム内で撮影行為を行い、それを介したコミュニケーションが活発化する時期」については明らかにすることができるという。ゲームにおける写真撮影の初期の例として挙げられるのは、1999年に発売された『ポケモンスナップ』だ。これは、いまや世界的に知られるポケモンを撮影して、その写真を評価することが目的のゲームである。撮影した写真をプリントするためのハードも発売され、写真を介したコミュニケーションが意図されていた。
次に谷口が最初期の例として挙げているのは、2003年にサービスを開始した『Second Life』だ。
『Second Life』はいまや「メタバースの元祖」的な存在として知られており(いまもサービスは継続中である)、「3Dで構成されたバーチャル空間でコミュニケーションするサービス」としては最初期のものである。
当時、Second Lifeをめぐるコミュニティではバーチャル空間内で撮影された写真を共有するサイトが存在していたらしい。つまり、現在のようにTwitterやInstagramで写真を共有するようなプレイヤーやコミュニティが存在していたということだ(ちなみに、先に触れたFlickrが「Virtual Photography / Machinima」を追加した際に公開したブログでは「Second Lifeで撮影され、コミュニティで共有されるコンテンツ」を念頭に置いていることが語られており、いまでもそうした文化やコミュニティは健在のようだ)。
2006年頃にはニューヨークを拠点に活動するアーティスト・Eva & Franco MattesによるSecond Lifeのアバターを撮影した作品『Portraits』(2006~07年)が制作されており、バーチャルフォトグラフィーをひとつの作品としてみる向きもこの辺りで生まれ始めたと言えそうだ。
また、バーチャルフォトグラフィーの先駆者として知られ、多くの作品を掲載するウェブサイト『Dead End Thrills』を運営するイギリスのビデオキャプチャアーティスト・Duncan Harrisが活動を開始したのも2007年頃であり、2003年から2007年辺りにコミュニティや商業写真、メディアアートなどさまざまな領域でバーチャルフォトグラフィーが登場してきたと谷口は分析している。
その後、TwitterやInstagram等のSNSの登場、YouTubeやTwitchでのゲーム実況の流行などにより、ゲーム内で撮影した写真や映像を共有することは当たり前になり、それに伴いハードやソフトもその需要に対応するようにバーチャルフォトグラフィーに関する技術を発展させてきた。
近年では、現実の風景を撮影する写真家がバーチャルフォトグラフィーを撮影し、それを写真集として出版する例も出てきている。その大きな要因は「コロナ禍」である(奇しくも谷口の論文が世に出たのは、世界が激変する直前の2019年11月のことだった)。
コロナ禍で渡航が制限された一部の風景写真家たちは、自宅からでも旅立つことができるゲームの世界に、撮影するための風景を探しに出ていった。
スイスの写真家Pascal Grecoは、コロナ禍によってアイスランドへの撮影旅行が中止となったことをきっかけに、いくつかのビデオゲームを購入したというエピソードをもつ。Pascal Grecoは、そのなかのひとつ、小島秀夫氏率いるコジマプロダクションによるゲーム『DEATH STRANDING』の舞台に惚れ込んだ。ゲーム内の風景には訪れる予定だったアイスランドを思わせる光景が広がっており、Pascal Grecoはその光景を写真におさめることに熱中した。そして、DEATH STRANDINGの世界のなかに存在するアイスランドらしい風景をおさめた写真集『Place(s)』を出版した。
現在は渡航制限も緩和され、再び風景写真家たちはさまざまな場所へ旅立つことができるようになったが、Pascal Grecoは継続してバーチャルフォトグラフィーの価値を広めるために活動しているという。
(上)Second Lifeは2023年、サービス開始から20周年を迎えた。(下)『DEATH STRANDING』/ photo ©Pascal Greco / Pascal Grecoの写真はウェブサイトのほか、本人のInstagramでも見ることができる
写真家になる「アクセシビリティ」の解放
ブラジル・サンパウロで活動するLeo Sangは、ゲームメーカーの依頼を受けてバーチャルフォトグラフィーの撮影を行う、商業的に活躍するバーチャルフォトグラファーだ。もともと、広告業界でのデザインや現実のライブ・イベントの写真撮影を生業としていたが、やがてバーチャルフォトグラフィーを仕事にするようになる。
Leo Sangは、そのきっかけは現実の写真家の「エリート主義」にあると、BBCのインタビューで語っている。
写真家は、第一に機材購入のために少なくない予算が必要となる。また、Leo Sangが拠点としているサンパウロで写真を撮影するのは危険が伴う。そのため安全の確保にコストがかかる。さらには、風景写真を撮影するためには旅行計画を万全にするための資金力が必要となる。つまり、現実の写真家として活動するためには想像以上のコストが必要になるのだ。
Leo Sangはそうした現実の写真家の活動の難しさに触れた上で、バーチャルフォトグラフィーの特徴的な点は誰もが同じ状況で始めることができる「アクセシビリティ」にあると語る。
最近では、オーストラリアのフォトグラファー兼ゲーム開発者のMatt Newellによる、デジタルで再現された世界中のさまざまな観光地を探検し、写真撮影することができるゲーム『Lushfoil Photography Sim』の発売が発表されている。
このゲームの紹介記事によれば、開発者のフォトグラファーとしての知見を活かしたデジタル一眼レフカメラのリアルな操作感が特徴だそうだ。このゲームをプレイすることで、プレイヤーは自宅にいながら「世界中の風景」を「デジタル一眼レフカメラ」で撮影できるというわけだ。
このゲームは、高度なフォトリアル表現をつくることができるゲームエンジンとして注目を浴びる「Unreal Engine 5」を使用して制作されたゲームである。
Unreal Engine 5のフルバージョンが使用できるようになったのは2022年のことであり、それを踏まえると、今後フォトリアルなバーチャルフォトグラフィーを撮影できるゲームが次々と登場することは容易に想像できる(バーチャルフォトグラフィーを含め特化したジャンルが近年のインディゲームで盛り上がっているのは、このように高品質なゲームエンジンが広く提供され、少人数でも開発できるようになったという背景も影響している)。
つまり今後は、お金をかけたり高い機材を買ったりしなくてもフォトリアルに再現された世界中の風景(もしくは現実にはあり得ないような風景)を家にいながら撮影できるようになる環境がより増えるということであり、まさしくLeo Sangが言及した「アクセシビリティ」という点で、写真撮影を始めやすい環境になってくると言えるだろう。
ゲームや映画など幅広くエンターテインメントを扱うアメリカとイギリスを拠点とするメディア「DEN OF GEEK」に掲載された、SNS上で活動するバーチャルフォトグラファーを紹介する記事では、Instagramで約57,000人のフォロワーをもつ @firstpersonshutter が紹介されている。
彼は、ナショナルジオグラフィックなどに投稿するフリーランスの写真家として活動することを夢みていたが、機材を買う経済的余裕がないため、バーチャルフォトグラフィーで写真の技術を磨いているという。
このように、写真撮影を生業にしたくても金銭的な余裕の問題で始めることができなかった人びとがバーチャルフォトグラフィーでキャリアを積むという例は、今後次々と登場してくるであろう。
『a plague tale requiem』/ photo ©Leo Sang / Leo SangのInstagramより
現実もバーチャルも撮る、国境も超える
東京在住の風景写真家・横田裕市も、コロナ禍によって仕事が減り時間ができたことを端緒にPlayStation®4用ソフトウェア『ワンダと巨像』でバーチャルフォトグラフィを撮影するようになった。やがて、横田が撮影した写真はインターネット上で話題となり、バーチャルフォトグラファーとしての活動を開始したと語っている。
現実で活動している写真家は、バーチャルフォトグラフィーのどのような点に魅力を抱いているのだろうか?
横田は『SWITCH Vol.40 No.3 特集 PlayStation』に掲載されたインタビューで、バーチャルフォトグラフィーの魅力として「時間や天候、アングルなどを自由自在にコントロールして撮影ができること」「現実世界では撮れないシーンが撮れること」「他のゲームプレイヤーが気づかなかった景色を提示できること」を挙げている。
バーチャルフォトグラフィーについて、現実の写真の代替ではなく独自の魅力を語っている点が印象的だ。これは現実での写真撮影を生業にしているからこその視点もあるのだろう。
確かに、太陽の位置や天候など刻々と環境が変わっていく現実の風景と、同じ環境を繰り返すゲームの世界における風景がまったく同じものだと言えるわけではない。しかし、それでも被写体に対して「ある意思やコンセプトをもって撮影する」という行為自体は、現実の写真もバーチャルフォトグラフィーも変わらない。
横田が同じインタビューでバーチャルフォトグラフィーを上手く撮るコツを問われ、回答した内容も、現実の撮影行為での撮影のコツと共通している面があると思われる。
まず構図を整え被写体を意識することですね、記念写真にはならないように。そして、光と影を意識して、余分な要素を省くこと、だと思います。
今後はバーチャルフォトグラフィーで写真の楽しさを知ったプレイヤーが現実の写真を撮り始めるということも十分に起こり得るだろう。
ここまで概観してきたバーチャルフォトグラフィーの盛り上がりは海外の事例が目立つが、国内でもコミュニティが生まれ徐々に盛り上がりつつある。
国内のバーチャルフォトグラフィーのコミュニティ「VPCONTEXT」はELI THE WALKER、Kemo、JUNの三者によって運営され、展示会やフォトブック等の制作を行っている。
バーチャルフォトグラファーとしての活動が日本でも紹介されているELI THE WALKERは世界的なバーチャルフォトグラフィーのコンテスト「The Virtual Photography Awards」に審査員として関わり、国内外で活躍している。
いまやあるゲームが世界中で共通してプレイされることは当たり前の世の中になっている。つまり、国境や言語すら関係なく世界中の人びとが同じ体験をして、同じ風景を眺めているということだ。
谷口の論考や「インゲームフォトグラフィーにおける観光写真に関する研究」という論考によれば、3Dで構成されたゲームをプレイすることは「旅」や「観光」との共通点を指摘されることがあるという。確かに、ゲームのなかの世界を探索し、そこで見つけた風景を写真としておさめ、共有する行為は現実の観光写真と非常によく似たプロセスと言えるだろう。
ただ、現実の観光と違うのは「プレイヤーたちがまったく同じ体験」をするという点にある。バーチャルフォトグラフィーのこうした特徴は、コミュニティにより強い結びつきを与えていると言える。
(上)PlayStation®4用ソフトウェア『ワンダと巨像』©2005-2018 Sony Interactive Entertainment Inc. / photo ©横田裕市 / 本文にもあるように、横田のInstagramでは現実世界の写真が多く並ぶ。(中)(下)それぞれ『DEATH STRANDING』/『Horizon Zero Dawn』/ ともにphoto ©ELI THE WALKER
VR機器を使って「瞬間」を撮る
2022年にバズワードとなり、一般に広く認知された「メタバース」。明確な定義は存在していないが、メタバースとして語られる多くのサービスに共通しているのは「3次元のバーチャル空間内でコミュニケーションを取ることができる」という点だ。そういう点で、オンラインゲームとの共通点が指摘されたり、先に触れたSecond Lifeはメタバースの先駆的な例として挙げられることが多い。
そして、そのなかに、プレイヤーがアバターを纏い、VR機器等を利用してバーチャル空間内でコミュニケーションを取る「ソーシャルVR」と呼ばれるサービス群がある(Second LifeはVR機器に対応しているわけではないが、ソーシャルVRはゲームよりSecond Lifeに近い存在と言える)。
その代表的なプラットフォームであるVRChatやcluster、Neos VRでは、VR機器使用時にプレイヤーがカメラを構えて写真を撮影することができる機能が備えられている。その影響か、こうしたプラットフォームでもバーチャルフォトグラフィーは盛り上がりを見せている。
ただし、ここまで綴ってきたゲームの「フォトモード」とは異なる点がある。それはVR機器を利用して撮影する行為はフォトモードのように画面を静止させることはできず、現実の写真撮影と同じように身体的な振る舞いを伴って撮影する必要があることだ。
また、被写体となる対象はゲームのようにプログラムされた同じ動作を繰り返すものではなく、撮影者と同じようにVR機器を使用してアバターを纏った生身の人間であることが多い。つまり、「バーチャル空間内で撮影する」という点では共通しているが、撮影対象のコントロールについての前提条件は少し異なっている。
近年では、サンリオによる音楽フェス「SANRIO Virtual Festival」、日産自動車によるバーチャルギャラリー「NISSAN CROSSING」、京セラによるバーチャル展示会「京セラレーザーコンセプト製品展示ブース」など、VRChat等を利用してバーチャル空間上で企業がイベントを行う事例も増えてきており、それらの様子を撮影するためにソーシャルVRにおけるバーチャルフォトグラファーの需要が増えてきている。
VRChatにおける日本のバーチャルフォトグラファーとして早くから活動しているえこちんに実際に話を聞いてみたところ、こうしたイベントだけではなくVTuberのポートレイトやアバターに着せるバーチャルファッションの撮影、ユーザーによる音楽イベント……などバーチャルフォトグラファーの需要は急激に増えているという。
また、「バーチャル空間上でコミュニケーションができる」という性質をもつソーシャルVRでは、フォトグラファーが同じバーチャル空間上に集まり、同じ時間を過ごしながら思い思いに撮影をするということが行われていたり、自身が撮影した写真を飾る展示会のバーチャル空間を制作し、広く公開するということも行われているという。
つまり、ソーシャルVR上では、ゲームと異なりバーチャルフォトグラフィーを介したコミュニケーションまで包括して行われているということだ。
えこちんはバーチャル空間での撮影から始め、いまでは現実でもカメラを購入して日々写真について研鑽しているそうだ。さまざまな世界にすぐに行けて、同じ興味をもつバーチャルフォトグラファーたちとすぐに議論ができる環境は、より多くの経験を得ることができ、それが現実/バーチャルでの写真の撮影技術の習熟に良い影響を与えていると話す。
Leo Sangはバーチャルフォトグラフィーのメリットは「アクセシビリティ」と話していたが、こうした話を聞くとソーシャルVRでの撮影をスタートとして、写真の技術を磨いていく層も今後どんどん現れそうだ。
(上)VRChatワールド『~京成電鉄 旧博物館動物園駅VR~ 「デジタル ハクドウ駅」by デジタル上野の杜』。 (中)VRChatワールド『ORGANISM (v1․0)by DrMorro』。(下)VRChatワールド『Coffee by amanek』 以上、すべて photo ©えこちん
「ある種の現実」を切り取る?
批評家・藤田直哉と哲学者・谷川嘉浩の対談「サブカルチャーは「反省」している?成熟したゲーム文化を読む」では「ゲームはシミュレーションである」というテーゼをめぐって議論が進む。
ゲームをはじめとしたバーチャル空間はシナリオから表現までさまざまなレイヤーでプレイヤーに「リアリティ」を感じてもらえるようにつくられている。なぜならそれらを楽しむためには「没入感」が必要だからだ。だからこそ、現実の一部をシミュレートすることでそうした感覚をもたらしている。
藤田 物語というのは、ある種、現実を構造化して、モデル化して、情報を縮減して、わかりやすくすることで我々に何かを教えてくれる装置だと思います。そして、ゲームの場合も、使命感を持った人たちが社会をモデル化して、何かを伝えようとしていることがあるわけです。たとえば、アメリカのデトロイトを舞台に、アンドロイドたちが「差別」される世界を描いた『Detroit: Become Human』などは完全にそうで、貧富の差、あるいは産業構造が転換することによって置き去りにされた労働者たちが反逆してきて、その中で差別が過激化してみたいな現状の問題をわかりやすく伝えてくれるものですよね。ラストベルトなどで、現実に起こっていることの寓話ですね。それはある種の啓蒙というか、教育的な意図で作り手がやっているんだと思います。
バーチャル空間とは、現実のある側面をシミュレートして表現された空間である。
バーチャルフォトグラファーの一部はバーチャルフォトグラフィーを撮り始めたからこそ「現実の解像度の高さ」に気づき、よく観察するようになったと述べる。
わたしたちが普段目にしている現実はあまりにも解像度が高いからこそ、限られたものしか認識できていない。逆に言えば、現実より解像度の低いバーチャル空間での経験こそが、現実のある側面に気づくきっかけをもたらしてくれることもあるということだ。
一方で、バーチャル空間でしか見ることができない空間表現も今後はどんどん生まれていくだろう。
1970~90年代にかけてのゲームの「ドット絵」が、「ピクセルアート」として再び世界中で注目され始めているように、フォトリアルなだけではないバーチャル空間の表現が、ひとつの空間表現として確立されることは想像に難くない。
空中都市や超巨大構造物などの現実のエッセンスを加味した現実にはあり得ない風景から、幾何学によって構成された色とりどりの抽象的な空間表現など、世の中にはすでに人の頭のなかをそのまま覗き込むかのような、カオスでバラエティに溢れたバーチャル空間が存在しており、それらの空間が多くの人びとを魅了している(魅惑的な幻想にこそ現実のエッセンスが抽出され描き込まれている、という議論もまた可能ではあるだろう)。
バーチャル空間自体が独立した空間表現として完成している場合であっても、その空間の作者自身も気づかなかった風景を切り取ったり、その空間で行われうる営みやアクションの可能性を示唆したりするなど、バーチャルフォトグラフィーが担う価値は無数にあるはずだ。
イギリスのメディア文化理論家/メディア・アーティストであるセス・ギディングスは論考「光なきドローイング:ビデオゲームにおける写真のシミュレーション」(翻訳:増田展大、『エクリヲ vol.9』収録)で、現代の現実のデジタルカメラがレンズを通して風景を直接写し取るものではなく光学的にシミュレーションを行いディスプレイに表現する装置となっていることに触れ、「(リアリティを生み出すために)シミュレーションを踏まえて制作されたゲーム」とは「カメラ自身」ではないかと述べている。
つまり、「バーチャル空間を探索し、そこで見た風景を撮影すること」は「デジタルカメラを現実の被写体に向ける行為」と変わらないということであり、それは、ある種の現実を写し取る行為だと言えるのかもしれない。
ゲームは世界でどんどん拡大する巨大な文化になりつつあるし、メタバースもバズワードとしての盛り上がりは落ち着きつつあるもののユーザー数は着実に増加している。そこで、育まれている「バーチャルフォトグラフィー」という文化が今後、現実にどのような視点をもたらしてくれるのか、注視していきたい。
次週8月8日は、イベントシリーズ「会社の社会史」より第2シーズン第3回「オフィスとサラリーマン 『サラリーマン』とは何ものなのか?」の模様をレポート。近代日本以降に出現したサラリーマン文化を紐解きながら、彼らの”つらさ”の正体に迫ります。お楽しみに。