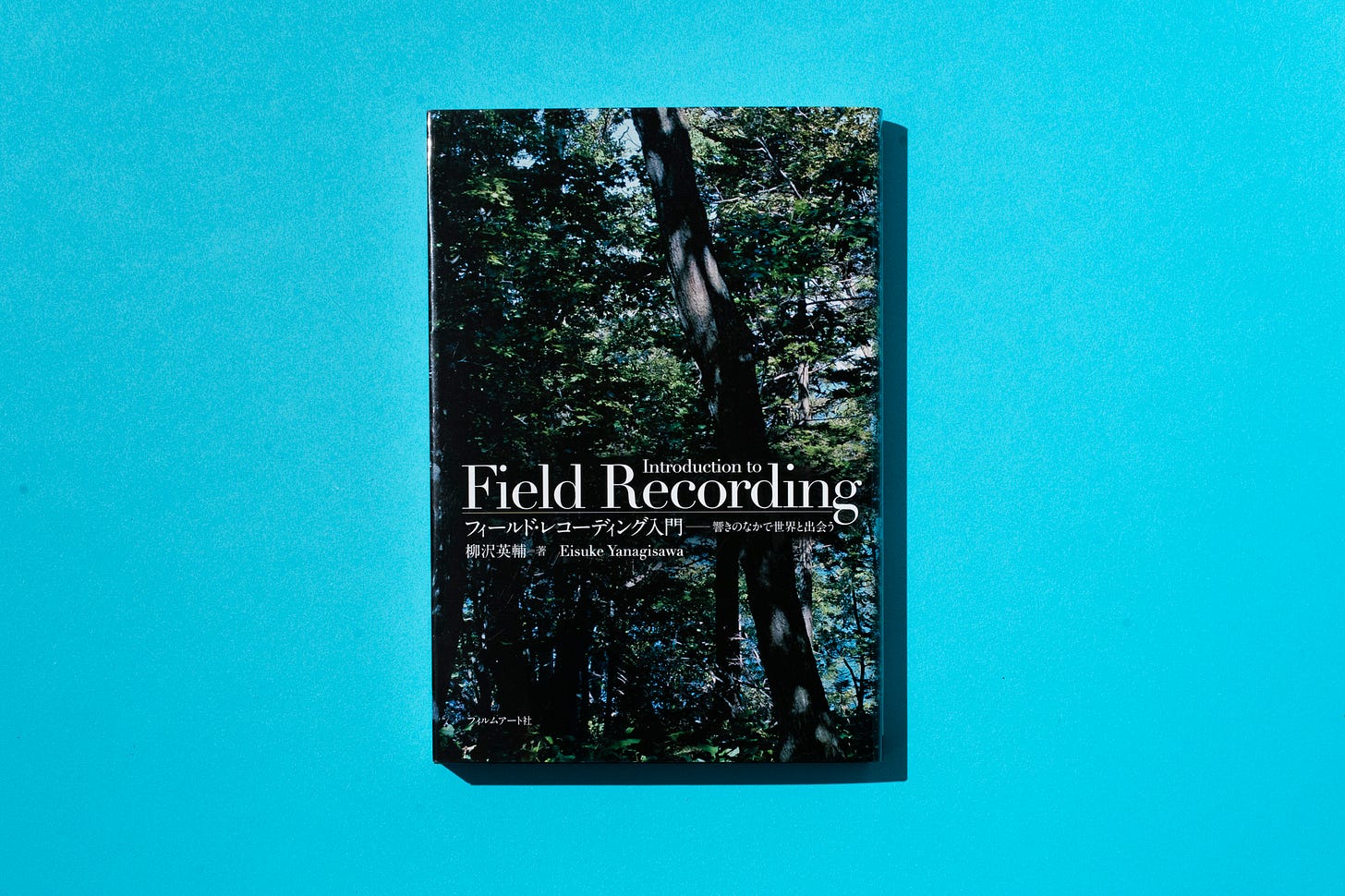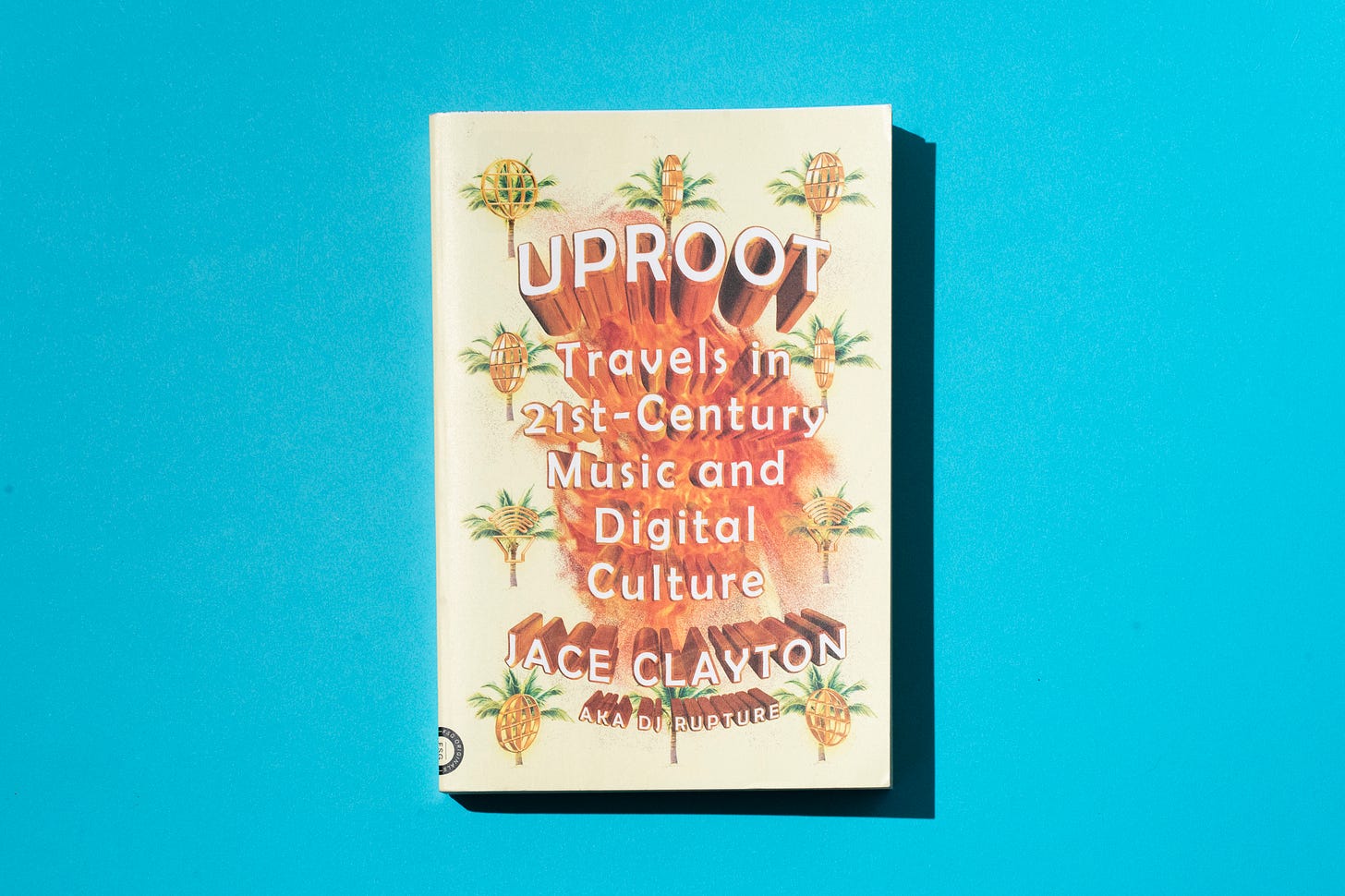音楽とテクノロジーと「つくる」をめぐる4つの断面|imdkm・選【つくるの本棚 #4】
これからの「つくる」を考えるべく、各界の識者が本を紹介する「つくるの本棚」。第4回は、音楽家へのインタビューや作品レビューなどを執筆するライター・批評家のimdkmさんに、音楽を「つくる」行為とテクノロジーにまつわる4冊を選んでいただきました。
音楽を奏でる、録音する、聴くという行為と密接に関わり合い、互いに発展してきたテクノロジー。その関係性に注目した著作は数多あれど、どちらか一方から他方を見るのではなく、音楽に批評的なまなざしを向けながら、それを取り巻くテクノロジーを支えるイデオロギーにも切り込んでいく読書とはどのようなものなのでしょう。
「つくるの本棚」第4回は、先日ZINE「音楽とテクノロジーをいかに語るか?」を編集・執筆されたライター・批評家のimdkmさんが、西洋音楽史/サウンドプロダクション/フィールド・レコーディング/植民地主義という異なる4つの視点から本をセレクトします。
text by imdkm
photographs by Yuri Manabe
【つくるの本棚 #4「音楽とテクノロジーと『つくる』をめぐる4つの断面」imdkm・選】
『音楽機械劇場』
渡辺裕|新書館
『サウンドプロダクション入門:DAWの基礎と実践』
横川理彦|ビー・エヌ・エヌ
『フィールド・レコーディング入門:響きのなかで世界と出会う』
柳沢英輔|フィルムアート社
『Uproot: Travels in 21st-Century Music and Digital Culture』
Jace Clayton aka DJ Rupture|Farrar, Straus and Giroux
先日、5月21日に開催された文学フリマ東京36にて、「音楽とテクノロジーをいかに語るか?」というZINEを頒布した(現在は電子書籍版をオンライン販売中)。タイトルの通り、音楽とテクノロジーの関係についてこころゆくまでひとりで調べ、考えたZINEだ。ふだん音楽関係のライターをしているものの、こんなふうに自分の関心に忠実にものを書いたのはずいぶん久しぶりかもしれない。
しかし、単に趣味に徹したなどとは毛頭思っていない。どれだけの人にわかってもらえるかはわからないけれど、音楽について考え、語るならば、テクノロジーの問題を避けて通ることはおよそ不可能だ。その一方で、あまりにその関係が密接で、かつ広範すぎるゆえに、丸腰で正面から向き合うこともまた不可能に思える。そんな質的・量的な困難さをなんとか乗り越えるための土台づくりとでも言うべきか。
例えば、音楽を奏でることにも、聴くことにもテクノロジーは関わっていて、それぞれの関わりが独自の広がりをもっている。それこそ、めまいのするような広がりを。さしあたり、今回のZINEで注目したのは前者。具体的に言うと、音楽を演奏したり、つくったりする行為にまつわるテクノロジーだ。その上で、テクノロジーが音楽に(あるいは音楽がテクノロジーに)いかなる影響を与えているのか。そもそも、影響を観察し、記述するにはどうすればよいのか。書籍やドキュメンタリーを含む25本のコンテンツガイドと、15ページにわたる年表、そして論考1本を通じて、そんなことを考えてみた。
ここでは、ZINEで取り上げたコンテンツのなかから、4冊の書籍をピックアップして紹介したい。
西洋音楽史から見る「音楽とテクノロジー」
『音楽機械劇場』(渡辺裕|新書館)コンサートに関わる制度史やレコードなどのテクノロジーの問題を中心とした「近代化」や「脱近代」の問題を取り上げてきた著者が、従来の西洋音楽史で見過ごされてきた「機械」に焦点を当て、音楽史の脱構築を試みる。ハイテク=「脱近代」という定式を疑うことで、音楽とテクノロジー、音楽とメディアの関係を考察。
その名の通り、「機械」を主題に近代から現代に至る音楽の姿をたどる一冊。著者は、1989年にサントリー学芸賞を受賞した『聴衆の誕生:ポスト・モダン時代の音楽文化』(春秋社、のち中公文庫)で知られる音楽学者の渡辺裕だ。二部構成のうち、第一部ではピアノの発展を中心とした19世紀の状況を、第二部では20世紀、特に蓄音機の登場以降の状況を紹介していく。面白いのは、これがいわゆる音楽史とも、技術の発展史とも異なるユニークな領域に光を当てていくところだ。ひらたく言えば、作曲家や楽曲を中心に記述される音楽の歴史と、めまぐるしく進む「改良」や「発展」によって語られる技術の歴史が交差する。すると、新しいテクノロジーが切り開く表現にクリエイティビティを刺激される作曲家や演奏家と、そうしたユーザーのサポートを追い風に姿を変えてゆく(あるいは消えてゆく)テクノロジーのありようが浮かび上がってくる。
その風景はいかにも不純で軽薄に映るかもしれない。例えば第一部で何度も登場するのがベートーヴェンとピアノの関係だ。当時最先端の楽器であり次々と改良が重ねられていたピアノに、ベートーヴェンがいかに食いつき、自作へのインスピレーションとしていったか。新しもの好きで、かつピアノのもてるポテンシャルを最大限に活かそうとする創作への貪欲さもある。次第に、悲劇の天才というイメージとはまた違う作曲家像が結ばれてゆく。あるいは、時代の徒花のように消えていった自動演奏楽器やバセット・クラリネットのような改良楽器への注目は、ともすれば「珍楽器」に対する好奇のまなざしと紙一重だ。
しかし、こうした不純さや軽薄さこそが、「機械」をタイトルにかかげて音楽史を語ろうとする本書が問おうとすることそのものである。いわく、
[…]それぞれの時代において楽器をめぐるテクノロジーがどのような状況にあったか、またそれがどのような社会的状況とかかわっていたかを視野に入れながら、作曲家の残した作品を見直してみるならば、従来の作品中心の「純粋な」音楽史によっては捉えることのできなかった新しい流れが見えてくるのではないだろうか。そのような意味では、楽器を媒介に作品を外の環境とかかわらせようとする「不純」な音楽史研究は、まさに「近代的」な音楽学研究のあり方への挑戦であると言っても過言ではないのである。(前掲書、p.20)
作品を軸にしても、あるいは作曲家の伝記的な記述を軸にしても見えてこない音楽史のかたちが、例えば楽器というテクノロジーの領域に着目することで見えてくる。音楽をめぐるオルタナティブな語りの可能性が開けてくるわけだ。本書はアカデミックな音楽学の文脈にあるが、同じことは現代のポップ・ミュージックにも適用できるだろう。かくも強固に思える作品やジャンルや作曲家という「くくり」を貫通させる可能性が、テクノロジーという切り口にはあるのだ。
本書は、テクノロジーを通じて音楽を考えるばかりではなく、現代日本とはまったく異なるパラダイムに属するテクノロジーのありようをたどり直す上で陥りがちな罠にも注意を促している。その意味で、「音楽とテクノロジーをいかに語るか?」という問いに対して、いわゆる近代以降の西洋クラシック音楽の側から、示唆に富む考察を提供している。
音楽制作の「現在」を知る
続いて、ベートーヴェンの時代から一気に飛んで、21世紀の現在へ。横川理彦『サウンドプロダクション入門:DAWの基礎と実践』は、著者が美学校で行っている講義をベースとしたコンピューターによる作曲入門書である。「DAW」とは、デジタル・オーディオ・ワークステーションの略称で、コンピューターによる音楽制作を行うための総合環境のことだ。読んで字のごとく、本書はDAWを使った音楽制作=サウンドプロダクションのノウハウを伝えることを主眼としている。
『サウンドプロダクション入門:DAWの基礎と実践』(横川理彦|ビー・エヌ・エヌ)ミュージシャン、バイオリニストの著者は、世界各地でDAWのワークショップを行った経験ももつ。本書の第1章では「DAWで音を聴く基本的な作法」として、環境づくりから音の確かめ方、またDAWのもつ可能性などに言及する。
しかし、本書は単に「使える」ノウハウ本にはとどまらない。実践とともに、現代において音楽はいかにして生産され、受容されているのかに対する理論的な考察も充実しているのだ。例えば、第1章の冒頭から少し引用してみよう。
ところで、現在私たちはどこで、どうやって音楽を聴いているのでしょうか? 私たちが聴く音楽は、ほとんどがスピーカーやイヤフォンを通じた再生音で、すでに録音された音を色々なメディアで聴いています。コンサートやライブで音楽家の生演奏を聴くという場合でも、歌はマイクを持ったシンガーの歌唱をPAスピーカーから聴いています。楽器の演奏者も、アンプから音を出したり、マイクで音を拾いPAスピーカーから音を出しています。歌手や演奏家から発せられる音をそのまま聴くという経験は、珍しい出来事になってしまいました。また、昨年のコロナ禍からの世界的な社会変化は、音楽経験=再生音となることをさらに推し進めています。こうした状況の中で音楽のクリエイターがまず持つべきクラフト(技術・力)は、「音を正確に聴き取れること」になっています。(前掲書、p.10)
きわめて簡潔ながら、レコーディング・スタジオや、そのソフトウェア版と言うべきDAWを用いた現代の音楽制作・音楽作品が前提とする「音楽経験=再生音」という前提について注意を促す鋭い文章だと思う。このような基本的な事項に始まり、テクノロジーにもとづく実践がいかに音楽のかたちを変えているかが、ノウハウに関する記述のなかに埋め込まれているのだ。
また、引用箇所でつくり手にとっての「聴く能力」の重要性を強調していることからもわかる通り、本書で示されるノウハウは、「つくる」ことと同じくらい「聴く」こと、しかも没入的なリスニングではなく、クリティカルに耳を澄ますことにつながっている。かつそれは、楽理的な分析とは異なる現代的な音楽制作のロジックに通じることで、近代的な知の枠組みでは消化しきれない領域に向き合う力をつける方法でもあるのだ。
そんなわけで、この本は「音楽をつくりたい」という人だけではなく、「音楽を分析したい、音楽について書きたい」と思う人にもぜひすすめたい。実際、第6章の「アーティスト研究」ではビリー・アイリッシュ、米津玄師、Yaeji、長谷川白紙が取り上げられ、コンパクトに的確な分析が行われている。
サウンドの世界から音楽を見る
次に取り上げるのは、ある意味でDAWとは対極にある実践、フィールド・レコーディングに関する本だ。フィールド・レコーディングとは、ざっくり言えばある場所や空間に存在する/した響きを録音する行為であり、その生産物のことでもある。DAWが音素材の操作に主眼が置かれているとすれば、フィールド・レコーディングは録音という行為や、録音物に封じ込められた響きや場の痕跡そのものに重きを置いている……とでも言おうか。しかし、どちらも録音─再生という響きの再生産をめぐるテクノロジーであるという点で、きわめて近接した領域でもある。
『フィールド・レコーディング入門:響きのなかで世界と出会う』(柳沢英輔|フィルムアート社)自然音、環境音、音楽まで、さまざまな録音対象を事例として扱い、著者はフィールド・レコーディングを、マイクロフォンを通して「世界」を再発見していく、実験的、創造的で可能性に満ちた実践であると語る。
本書の著者はいわゆる「ミュージシャン」ではない。フィールド・レコーディング作品をリリースもしているが、もともとはベトナムの少数民族が奏でる楽器・ゴングにまつわる音文化を調査する研究者だ。このことからもわかる通り、本書は必ずしも「音楽」という領域に限らない、広い「響き」の世界へ読者を誘う。むしろ「音楽」は、豊かな「響き」の世界の一部分に過ぎないとさえ言える。それゆえに、録音するにせよ、リスニングするにせよ、いわゆる「音楽」──クラシックであれ、ロックであれ、ヒップホップであれ──とはまた違う耳の使い方が要請されることになる。
結果として、フィールド・レコーディングに学ぶことは、「音楽」の聴き方や、「音楽」との向き合い方そのものを問い直すことにつながってくる。「音楽」の文脈から本書を読み解く意義はまさしくそこにあるだろうし、「音楽」のなかに潜む多様な実践に改めて目を向ける絶好の機会になるだろう。
さて、それではテクノロジーはフィールド・レコーディングにどのように関わるか? 先に述べたように、フィールド・レコーディングは録音テクノロジーと切り離せない。
筆者にとってフィールド・レコーディングとは、マイクロフォンを通して場所や空間の響きを観察し、記録する行為である。視覚的に捉えられがちな身の周りの環境やモノをさまざまなマイクロフォンを通して聴覚的に観察してみると、想像もしないような姿が現れることがある。身の周りの環境を録音機器というテクノロジーを通して観察・記録し、記録した音を聴くという実践を繰り返すことで、我々の身体と環境との関わり方や環境に対する認識そのものが変わっていくかもしれない。それはありふれた日常が驚きをもって再発見されるようなスリリングで刺激的な体験である。(前掲書、p.9)
本書には著者の経験にもとづく魅力的な記述や、フィールド・レコーディングの具体的なノウハウが詰まっており、読者を実践に誘うとともに、フィールド・レコーディングにおいて用いられるテクノロジーについて知る格好の資料にもなっている。そうした知に触れた上で耳を傾ければ、フィールド・レコーディング作品はいっそう豊かな世界を聴かせてくれるだろう。
テクノロジー、文化、植民地主義
最後に紹介するのは、DJ Rupture名義でのDJをはじめ多彩な活動を行うジェイス・クレイトンによる2016年の著作。
『Uproot: Travels in 21st-Century Music and Digital Culture』(Jace Clayton aka DJ Rupture|Farrar, Straus and Giroux)無名のDJだった著者は、2001年にオンラインに公開したミックス音源がきっかけで世界ツアーの機会を得る。21世紀のグローバル化した世界で、芸術制作における激変期に立ち会った経験と気づきから、巡った各国の音楽とデジタル文化の関係について知見を綴る。
デジタルテクノロジーの普及以後、ルーツから引き剥がされ、異なる環境と衝突し融合しながら育まれるハイブリッドな文化の諸相を記したエッセイであり、魅力的な旅行記だ。グローバル化、インターネットの普及、音楽制作や流通の現場へのデジタルテクノロジーの浸透といったトピックが、クレイトンの実体験に即しながら、豊富なエピソードとともに語られていく。とりわけ、現地のミュージシャンと交流しながら浮かび上がる、北アフリカやアラブ諸国、中南米における西洋的な音楽制作のテクノロジーの受容はきわめて興味深い。
こと音楽制作のテクノロジーという意味では、第2章「オートチューンがあればより良い自分をあなたに届けられる(Auto-Tune Gives You a Better Me)」が興味深い。そこで繰り広げられる、モロッコにおけるオートチューン受容をめぐる議論は、テクノロジーの受容が異なる文化間の交流と摩擦、そしてクリエイティブな転用をつくり出してゆく様をいきいきと描き出してゆく。
あるいは、第7章「道具(Tools)」では人気DAWのひとつFRUITYLOOPS(正式なプロダクト名はFL Studio)を題材としつつ、DAWによる音楽制作テクノロジーの世界的な標準化がもたらした功罪を検討してゆく。
クレイトンは非西洋の音楽にしばしば登場する複雑なポリリズムの表現に着目しながら、いかにDAWが西洋的なバイアスをもち、ポリリズムと相性が悪いか論じてゆく。エジプトはカイロで目の当たりにした儀礼音楽「ザール」のめくるめくリズムを想起しながら、クレイトンはこう述べる。「[…]ザールをデジタルに演奏したいと思っても、すんなりエンコードする方法は存在しない。ソフトウェアの観点からは、ザールは不可視だ。もしザールの伝統がデジタルの世界に躍り込むことができないならば、それはただただ消えゆくことになるだろう」(拙訳)。
そう、デジタルテクノロジーが音楽制作の主流となるいま、そのテクノロジーに翻訳できない文化は、そのまま消滅してしまう蓋然性が高い。もしかしたら翻訳の方法はどこかにあるかもしれない。しかし、わざわざカネにならない伝統文化のため、ソフトウェアに開発費を投じるテック企業が出てくる望みは薄い。
ここで提起されているのは、テクノロジーにおける植民地主義とでも言うべき問題である。DAWがもたらすテクノロジーの民主化は、そのテクノロジーが暗黙のうちに前提とする欧米中心主義的な文化観を他の文化圏にインストールすることと切り離せない。こうした認識は音楽に限らずあらゆる文化や産業、そしてテクノロジーをめぐって普及し、議論が行われているところだ。そんななかで、クレイトンは常にDJとして、ミュージシャンとして、観察者としてアンビバレントな関心を抱きながら、そうしたテクノロジーやデジタルカルチャーの功罪に対して介入を試みようとする。その活動自体興味深いものだが、ひとまずは本書の紹介をもって筆を置きたい。
imdkm ライター、批評家。ティーンエイジャーの頃からビートメイクやDIYな映像制作等ダンス・ミュージックに親しみ、自らビートメイクもたしなんできた経験をいかしつつ、広くポピュラー・ミュージックについて執筆する。著書に『リズムから考えるJ-POP史』(blueprint、2019年)。
次週6月13日は、イベントシリーズ「会社の社会史」より第2シーズン第1回「奉公・出世・起業:ビジネスで『身を立てる』ということ」の模様をレポート。日本人の「立身出世」観はどこから来たのか、その源流に迫ります。お楽しみに。
【WORKSIGHTのイベント情報】
WORKSIGHTイベントシリーズ「会社の社会史 -どこから来て、どこへ行くのか-」
第2シーズン 第3回 「オフィスとサラリーマン :『サラリーマン』とは何ものなのか?」
6月20日(火)19:00-20:30
WORKSIGHTが誠品生活日本橋とのコラボレーションでお届けするトークイベント「会社の社会史」。第2シーズン第3回を6月20日(火)に行います。
日本人にとって「会社」とはいったい何なのか。明治期に西洋よりもたらされたその概念を、日本人はどのように社会のなかに位置づけ、どのように我がものとしてきたのか。会社のあり方そのものが問われている現在、改めて日本人と会社をめぐる、わかったようでわからない関係性を民俗学者の畑中章宏さんとともに考え直す、〈経営民俗学〉という新たな試み。
今回のテーマは「オフィスとサラリーマン:『サラリーマン』とは何ものなのか?」。サラリーマンはいつ社会に登場したのか?オフィスへの通勤にはどんな意義があるのか?サラリーマンにおける「幸福」とは果たして何なのか?こうした疑問をめぐって、鈴木貴宇『〈サラリーマン〉の文化史──あるいは「家族」と「安定」の近現代史』(青弓社)、五十嵐彰・迫田さやか『不倫──実証分析が示す全貌』(中公新書)の2冊を手がかりに、現地参加するみなさんと一緒に、ワークショップ形式で考えていきます。
「会社」に関するもやもやを参加者とともに考える「会社の社会史」。現地でも、オンラインでも、皆さま奮ってのご参加をお待ちしています!
【イベント概要】
■日時:
2023年6月20日(火)19:00 - 20:30(終了時間は目安です)
■開催形式:
会場とオンラインの同時開催
会場|誠品生活日本橋内 イベントスペース「FORUM」(COREDO室町テラス2F)
オンライン|Zoomウェビナー
■参加費:
会場観覧|1,500円(税込)
オンライン|1,000円(税込)
■出演:
畑中章宏(民俗学者)
山下正太郎(WORKSIGHT編集長)
若林恵(黒鳥社)
工藤沙希(WORKSIGHT編集員/コクヨ ヨコク研究所研究員)
■定員:
会場観覧|30名
■主催:
誠品生活日本橋+WORKSIGHT
■アーカイブ配信につきまして
・イベントチケットご購入の方限定で、後日アーカイブを配信予定です。
・アーカイブ配信のみご希望の方はオンラインチケットをお申し込みください。
■お申し込み(リンク先にて会場観覧またはオンラインをご選択ください)