あなたの「道」は、わたしには見えない:文化人類学者・古川不可知との対話から
現代の都市では道に迷うことはあっても、道がなくて迷うことはあまりないだろう。だが山の「道」はまるで明滅するように、立ち現れては消え、また現出する。しかも、個々人の身体ごとに──。世界最高峰とされるエベレストの南麓、登山客がひしめく地域で、ポーターやガイドとして働く「シェルパ」たちの調査を続け『「シェルパ」と道の人類学』を著した文化人類学者・古川不可知氏に、「道」について尋ねた。
古川氏が主な調査地としているのは、ネパール東部・ソルクンブ郡クンブ地方というエリアだ。エベレスト登山/トレッキング観光の中心地として人びとが集う、標高3,000m超のその地域では、「シェルパ」と呼ばれる人びとが働いている。かつてはシェルパ族という民族の名称だったのが、いまでは登山客の荷物を運ぶポーターや、道案内をするガイドといった職業も指すようになっている。そうした「シェルパ」の世界に身を置き、話を聞き、ともに歩いてきた古川氏が考えている「道」のありようは、雨上がりの地面のように、多くの豊かな問いを柔らかく含み込んでいる。
photographs in the mountains by Fukachi Furukawa
photographs during interview by Kaori Nishida
interview and text by Fumihisa Miyata
古川不可知|Fukachi Furukawa 1982年、埼玉県生まれ。専門は文化人類学、ヒマラヤ地域研究。九州大学大学院比較社会文化研究院/共創学部・講師。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。著書に『「シェルパ」と道の人類学』、共訳書にR・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ:シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』など。2023年3月、登山ガイドステージⅠの資格認定を受けた。
山だからこそ見える「道」の特性
──山における「道」を探究されていらっしゃいますが、もともと登山好きだったのですか。
実はいまでも本格的な登山家とは言えないのですが、それでもこんなに頻繁に山に登るようになるとは、かつては想像していませんでした。大学で人類学を学び始めた学部生の頃、ぼんやりとではありますが、宗教的な対象も含めて“見えないけれどもリアリティがあるもの”に関心があり、修験道を調査したのが大きなきっかけでした。半年に1回ぐらい趣味で山に登る程度だったのが、ここから徐々に、山の世界に深入りしていくことになったんです。その後、いつかは大学院に戻ろうと思いつつ東京でサラリーマンとして働いていたのですが、たまたま読んだネパールの本にシェルパのことが書かれていた。修験道とよく似た儀礼を行っていることに気づき、興味を抱いたんですね。大学院に入った後、2010年8月に初めて、いまもメインの調査地であるクンブ地方を訪れました。
──実際に行ってみて、いかがでしたか。
ソルクンブ郡に行ってみて、険しい山間部でありながら世界的な知名度を誇る観光地でもあるところが面白いと感じました。大きな村の通りではいろんな国の言葉が飛び交い、土産物屋もあればバーもある。山間部の国際都市のような様相を呈していました。その上で、仕事で往来している「シェルパ」の人たちが、ずっと「道」を探りながら歩いていることに、強く惹かれていったんです。
──重い荷物をもつポーターは、仮に軽い傾斜であっても登山客のように直線的に登らず、ジグザグと歩いていくという話が『「シェルパ」と道の人類学』のなかに出てきますね。ガイドであれば、まるで家畜の放牧のように、登山客に適したルートを探りつつ歩かせ、また逆にガイドも歩かされているという話も書かれている。「シェルパ」の「道」の独特さが伝わります。
わたしにとっての「道」が他者にとっての「道」ではないということが、山のなかでは非常にはっきりするんですよね。例えば「シェルパ」の人たちが「あそこに道があるじゃないか」と言っても、わたしには氷の壁にしか見えないということがあり、逆にわたしが普通に歩いていける「道」はポーターが通れず、大きく回り道をすることもあるわけです。同じような物理的環境を前にしても、何が「道」であるか、そこにどんな「道」があるのかは、個々の身体によって異なる立ち現れ方をするのだということが、とても面白く感じられたんです。山であり、観光地であるという特性をもつ場所での調査から、立ち現れとしての「道」というものが見えてきて、これはより広く議論を敷衍させられるのではないか、と感じるようになりました。……とはいえ、やはり登山家ではないですし、調査は毎回とてもしんどいですが(笑)。
古川氏が「頼りにならない」と語った、「エベレストへの道」が矢印で指示された看板。雨風などによって、しばしば看板の向きが変わっているからだという。ちなみにインタビューの帰路、氏は地図アプリで次の目的地までのルートを確かめながら「実は方向音痴なんですよ……」と告白した。
僧院のあるタンボチェ方面へ向かう峠道。積まれた石に巻かれているのは、カタと呼ばれる祝布
エベレスト・ベースキャンプ手前、ゴラシェ(ゴラクシェプ)のロッジ集落とクンブ氷河
環境と完全に一体化しないために
──そうしたビジョンを言語化する上で、古川さんはティム・インゴルドの「天候-世界」という概念を、批判的に検証しつつ導入しています。
雨や雪といった天候、あるいは土砂崩れや氷河の流動などによって、ヒマラヤ山間部の「道」は刻一刻と姿を変えていき、「シェルパ」の歩行もまたそれに応じて変化していきます。インゴルドは、わたしたち有機体を含み込んで絶え間なく生成していく流動的な「天候-世界」を描いています。このビジョンは非常に魅力的で、わたしが調査している土地の状況の説明としてもよく馴染むのですが、一方でインゴルドは、天候と完全に浸透し合った有機体というようなものを理想化しています。世界と一体化したビジョンはたしかに美しいのですが、しかし山のなかで本当に人間が環境と一体化してしまったとしたら、それは個体にとっての死でしかありません。
──全体としての環境に本当に溶け込むとき、その有機体は死んでいる、と。
ですから「シェルパ」の人たちもわたしも、世界に対する自分の身体の境界というものを何とか確保しながら歩行し続けるわけです。わたしは、全体が個々の生に優先してしまうインゴルドの視座の危うさを確認しながら、生き延びていくために天候に抗しながら歩いていく個体にとっての「道」を示すべく、ドゥルーズ&ガタリの「アレンジメント」という概念を導入して論じてきました。身体が抵抗をともないながら移動していくのと同時に、環境中の予想外の要素や条件が組み合わさって、一瞬ごとに「道」が構成されていく……自己の身体が部分的に世界と浸透し合っては切り離されてゆくことによって「道」自体が動いている、というような議論ができれば、と。
──やはりそれは、職業としての「シェルパ」の視点を経るからこそ見えてくる話ですよね。ご著書を読んでいると、山のロマンなどとはむしろ無縁で、彼らがあくまで経済的な対価を得るための労働として、時に相当な苦労をともないながら山で働いていることがわかります。
登山家であれば、場合によっては「山で死ねたら本望だ」という人もいます。しかし「シェルパ」にとっては、率直に言えばふざけるなという話なのだと思います。金のためにやっているのだから、生きて戻ってこられなければ金がもらえないじゃないか、ということです。わたし自身はそんなに高いところまでは登れず、最高到達点でも標高6,000mにも満たないのですが、もっと高い8,000m級の山々で活動する「シェルパ」たちにインタビューする限りでは、やはりとてもシビアな判断を重ねていることが伝わってきます。どのように雪や風の状態を見切るのか、どうやってロープを張って「道」をつくっていくのか……その個々の身体はたしかに環境と相互に浸透し合っているのですが、しかし同時に彼らはその環境から自分をどうやって切り離すかという、切実な課題と向き合っているわけです。
近代国家のインフラの外で
──ここで語られる「道」は、近代国家が整備する道とは似て非なるものですよね。ご著書のなかでは現地の人びとが整備する車道にも触れられていますし、そうしたインフラストラクチャーとしての側面には、緩やかなグラデーションもあると思うのですが。
近代国家によって規格化された道は、標準的な身体に対して最適化されている、ということは言えると思います。そこからはみ出した身体を切り捨てがちだからこそ、バリアフリーが問題となるわけですよね。一方で山道は、誰にとっても不便です。慣れている「シェルパ」の人たちにとっても、ちょっと地面がぬかるむと進めなくなることさえある。安定した平面は見当たらず、その環境に適した身体というのも基本的に存在せず、だからこそ皆が自分と他人の身体をケアしていかなければなりません。例えば、わたしが下宿していたポルツェ村のロッジの「母親」から、わたしが通行するのが難しいと思われるルートに関して「道はない」と言われたことがあります。わたしのことをよく知っているからこそ、「君にとって道ではない」という意味合いで言ってくれるわけです。
──なるほど。古川さんの身体的な限界も想像し、見越しながら、「道はない」と表現されたのですね。
はい。彼女自身はガイドではないのですが、険しい山のなかでは、常に他者の身体をケアし、ともに歩いていかなければならないということですよね。こうした「道」のあり方から現代のわたしたちが学べることは、たくさんあるんじゃないかとも感じています。ちなみにわたしが現地で見た山間部の車道は、土砂崩れが起きて通れなくなった結果、放置されて別のルートがつくられる、ということさえあります。
──車道でさえ、短いタイムスパンで可変的な「道」である、と。
近代国家によって規格化された車道も、実はこうした側面をもっているのではないでしょうか。メンテナンスが必要であることはもちろん、例えば災害のような事象が発生したとき、そこがわたしの身体にとって通行可能な限りにおいて「道」であり続けるわけです。実は山のなかの「道」から連続的な存在といいますか、地続きであるように考えています。
福岡・天神に、標高60m台の「山」?
──ご著書には、山道の整備を「功徳」として行う民間人が出てきますね。一方で日本では、自治体が整備したり、山小屋の管理人が手を入れたり、さまざまなケースがあります。
ネパールでは「ビカス(開発/発展)」という概念が重視されていて、「シェルパ」としての生活も、そして山道の整備も、この「ビカス」と強く結びついています。観光客やお金が入ってくる山道を整備することは素晴らしいことだとされていて、宗教的なニュアンスも帯びた「功徳」という言説が、現地ではたびたび聞かれるんです。そもそも村人たちの生活道だったところを観光客が使っているわけですから、壊れたり崩れたりしたら自分たちで半ばオートマチックに修復していくようなところがある。一方の日本では、例えば山岳部の国立公園のような場所はかつて人が住んでいなかった場所も多く、半永続的に地域のコミュニティがメンテナンスしていく、という状況になりにくいまま現在に至ります。山小屋だけではリソースが足りず、最近では登山者の人たち自身に整備してもらうようなプロジェクトも立ち上げられてきており、わたしもその一部に関わっています。
──なるほど。同様に日本社会に引きつけて伺いたいのですが、近年は登山アプリが注目を集めていて、特に安全面での貢献が評価されてきています。「道」という観点からも興味深いものだと思いますが、いかがですか。
わたしも、いろいろと面白い論点や可能性がありそうだと感じています。日本で最も著名なアプリについて、ひとつポイントを挙げるとすれば、人がたくさん歩くルートは太い線になる仕様になっていることです。登山道というものは、そもそも人が歩けば歩くほど登山道として確立されていく──つまり、前の人が歩いていった足跡を後から歩く人が辿ることで道になっていくという側面があるわけですが、それがデジタルな空間においても「人が歩くと道になる」というかたちで実装されている点には、興味を引かれます。次から次へと人が辿り続けることで登山道であり続けるということが、デジタルのレベルでも表現されているということですよね。
──他者とともに「道」に織り込まれている時間や歴史の、表現の一端かもしれないということですね。
あと、これはアプリに限った話ではなく、「道」ともトピックはすこしずれるのですが、「山」の定義自体が揺れているのも興味深い現象だと感じています。例えば、福岡・天神には、「アクロス山」と呼ばれる地元では有名な「山」があるんですよ。
──都市部である天神に「山」ですか?
実際は、階段状になっている標高60m超の屋上庭園なんですけれども、屋上まで外階段で登れるようになっていまして、登山アプリ上では「山」と表記されているんです。ユーザーからのリクエストを受けて、こうした「山」が登録されることがあるそうです。
──わたしたちにとって、「山」の名づけや判定というのは、実はかなり恣意的なものだということでもありそうですね。
「山」とは何か、という問いは実は非常に難しいし、やはり感覚的な部分が大きいのだと思います。例えばヒマラヤにおいては、基本的に標高6,000mより低い山というのは、山じゃないんですよ。わたしが普段滞在しているポルツェ村は約3,800mですので、4,000mを越えても彼らにとっては丘のようなものなんです(笑)。
──標高4,000m近くでも、丘ですか……。
そうなんですよ、富士山(標高3,776m)より高いんですけれども(笑)。「シェルパ」の人たちにとって「山」というもののイメージは、自分たちの村から遠く、向こうに高くそびえていて、雪をかぶっているのが見える、というようなものであるわけです。重ねて言えば、このことは、何もヒマラヤに限った話ではありません。わたしがいまインタビューをしていただいているのは渋谷の三階建てビルの屋上ですが、ここまで上がってくる外階段も、登っているときの体感はもしかしたら「山」に近いかもしれない。しかし一歩引いてみれば全然「山」ではないわけです。同様に、わたしたちにとっては「道」だったかもしれませんが、他の誰かにとってはまったく「道」ではないかもしれない。やはり、こうした認識は相当に身体感覚に基づくものなのだと思います。
──今回こうしてお話ししてきて、「道」という対象は具体的なのにとても曖昧で、ローカルでありながら普遍性もあわせもつからこそ、語る難しさと可能性があるように感じました。
そもそも文化人類学という営みそのものが、フィールドワークにおいてわたしが経験したことからしか語ることができないという性質をもっていますし、同時にそれをどこか大きく人類の話として普遍化したいという欲望を抱えています。そこが大変なジレンマであり、難しいところでもある。ただ、「道」を考える際には、まさに個別の身体において「道」が立ち現れるということ自体は普遍化して語りうるのかな、と感じてはいるんです。
──なるほど。文化人類学的な困難を可能性へと転じていくものとしての、「道」の立ち現れということなんですね。
逆に言えば、万人にとって標準的な「道」などというものを疑い続けるということ、そんなものは存在しないんじゃないかと考えていくということでもあります。近代都市において排除されているものに目を向けるきっかけにもなるかもしれない。例えばわたしも、山から下りてネパール首都のカトマンズに戻ると、地面がすべて平らで逆に不安になるんです。山の「道」ではほぼすべての動作が登るか下りるかですし、目に見えているものもすべて斜めですので、そうした環境に慣れて都市部に戻ってくると、とことん平らなので逆に怖くなる。あまりに良心的な物言いになってしまうかもしれませんが、他の人にとっては別な世界が立ち現れているかもしれないと想像する、こうした思考を共有していくことによって、すこしだけ世界が優しいものになるんじゃないか、と思っているところです。
観光客の目的地としてエベレスト・ベースキャンプと肩を並べる、ゴーキョ付近の雪原の道
次週6月6日は、先日ZINE「音楽とテクノロジーをいかに語るか?」を編集・執筆された、ライター・批評家のimdkmさんによる「つくるの本棚 #4」をお届けします。音楽を奏でたり、つくったりする行為と関わるテクノロジー。相互の影響を観察し、記述した数ある書籍の中から、imdkmさんが選ぶ4冊とは──お楽しみに。
発せられているのにきこえていない「声」をきき、記録し、伝えていくことは、存外に難しい。世界が複雑化するなか、わたしたちはどのような態度で、人と、そして人以外の存在たちと向き合えばいいのだろうか。どうすれば、行為の一方的な「対象」としてではなく、相互的な「関係」を相手と築くことができるのだろうか。スケートボード、フィールドレコーディング、郷土料理、文化人類学、Chat-GPT……他者の「声」に耳を傾け、書き留めることの困難と可能性を探る。
【書籍詳細】
書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]19号 フィールドノート 声をきく・書きとめる Field Note』
編集:WORKSIGHT編集部
ISBN:978-4-7615-0925-5
アートディレクション:藤田裕美
発行:コクヨ
発売:学芸出版社
判型:A5変型/128頁
定価:1800円+税








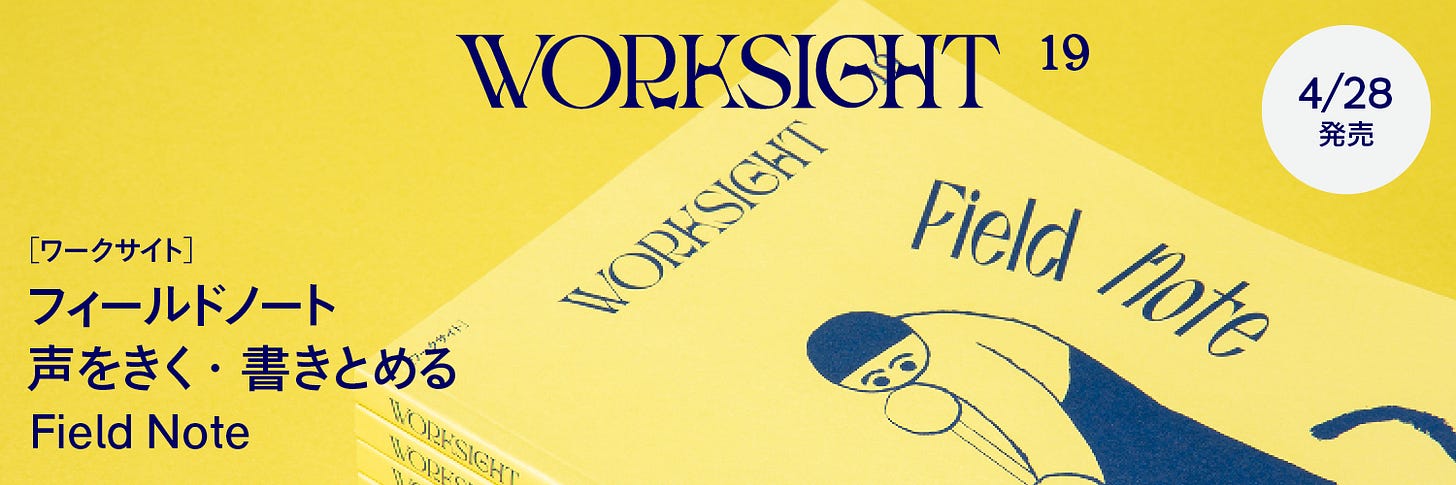
スキーで雪山を登り降りする山スキーを趣味とする私には身近に感じられる内容でした。雪の状態や体力に合わせて適切なジグザグを切って雪面を登り、後ろにはトレースという「道」が残る。他の人の「道」は参考になることも多いが、時として間違っていたり自分には向いていなかったり。そして雪が降れば、あるいは風が吹いただけで、たちまち道はリセットされる。著書を拝見したいと思いました。