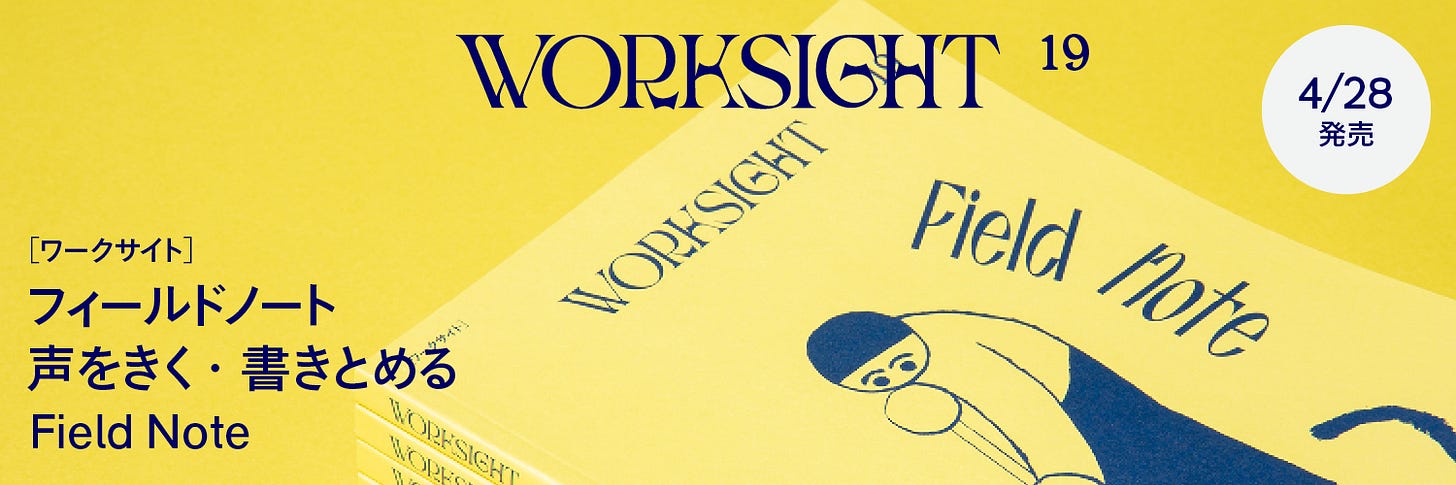趣味の3Dプリンターじゃ世界は変わらない── 新工芸舎と考える「ものづくりの民主化」の現在地
「ものづくりの民主化」を掲げたメイカームーブメント、Fabに多くの人が期待を寄せた2010年代の始まり。10年以上を経た現在、いったいどれほどものづくりはわたしたちに近づいただろうか。小さくあることへのこだわり、適量生産、新しい地域性など、デジタルファブリケーションの新しい可能性を模索する「新工芸舎」代表の三田地博史さんにお話を伺った。
クリス・アンダーソンが提唱した「メイカームーブメント」。どんな人でも、ものづくりを基軸にした起業家になれるし、誰でも自分がつくりたいものを作れる時代になったとされている。日本でも多くの場所にデジタルファブリケーションの拠点が生まれ、やろうとすればできる環境は整った。しかし、実際の自分たちの生活にどれほどの影響があっただろうか。趣味や日曜大工的なものづくりを超えて、デジタルファブリケーションがより社会に実装されていくためには何が必要なのだろうか。「ものづくりの民主化」の次の10年を考える。
photo courtesy of Shinkougei-sha
interview and text by Kakeru Asano/Shintaro Kuzuhara
自分自身として生き抜くためのデジタルファブリケーション
──まずは 「新工芸」とは何を指すのか、一般的なデジタルファブリケーションやFabと何が違うのか、教えていただけますか。
新工芸は、社会の行き過ぎたシステム化に対して、デジタルファブリケーションを用いた個人の主体的な創造性の回帰を目的にした思想や態度のことを指しています。2010年頃「メイカームーブメント」や「Fab」という概念が海外で生まれ、日本でも広まりました。僕も大きな影響を受けましたが、一方でわざわざ新しいことばを使ってしまったために本質的な議論や実践が深まっていないようにも思えました。横文字であるだけで、価値があるものに見えてしまったりしますから。
3Dプリンターをはじめとした技術(=デジタルファブリケーション)を用いるものづくりは、「工芸家」が設備や環境を整えながらものづくりと向き合い生計を立ててきたことと同じではないかと僕は思ったんです。デジタルファブリケーションを応用しながらも、人びとのなかで脈々と受け継がれてきた「工芸」あるいは「工芸家」でありたいとの思いを込めて「新工芸」と名付け、ものづくりと経営の調和を目指しています。
「新工芸舎」と名乗るようになったのは2020年。当時僕が所属していた3Dプリンターなどのデジタルファブリケーションツールの販売や導入を支援する株式会社YOKOITOの研究部門として始まりました。2023年4月にYOKOITOから独立し、合同会社 新工芸舎を3人で立ち上げたところです。
ぽってりした太い幹が特徴のテーブルランプ「BaobabLamp」
── なぜ独立することになったのですか。
「小ささ」を維持したまま、僕ら3人が生きていけるということを自分たち自身で実証することは、新工芸というコンセプトそのもの。僕にとって3Dプリンターとは、個人への主体性回帰の象徴なんです。
僕の学生時代はメイカームーブメントの全盛期でした。いくつものハードウェアスタートアップが、Kickstarterで驚くような資金を集めて、会社を立ち上げプロダクトをつくり、世界に広がっていった。当時は、大きな資本力でものを大量につくり、経済的な影響力をもつことへの憧れもありました。
ただ社会に出て、いろいろ経験を積んだり、いろんな人と会ったりするようになると、巨大な資本が動かす分業化された社会は人自体もシステムの一部として扱ってしまうことがわかってくる。情熱や高い視座で始まったとしても、組織が大きくなればなるほど、そこに集う人それぞれの創造性や主体性を削いでしまうのだなと。
次第に自分の興味は人が本来もつ創造性や生き方そのものに移っていきました。社会学や民藝、ものをつくることと人間の関係などの面からものづくりについて考えるようになったんです。
そういう視点で3Dプリンターと向き合ったとき、この技術があれば、焼き窯を手に入れた工芸家がそうであったように、大きな組織のなかに自分の名前を埋もれさせることなく主体性を維持したまま生きていけるんじゃないかと考えた。新工芸のステートメントを「人間としての主体性」に力点を置いて書いたのは、こういった思いがあったからです。
目の前に3Dプリンターがあって、それを使う技術がある。ならば、それでどうにか生き抜こう。泥臭く“自分たちで”商売をしてみようと。
趣味の“Fab”では、世界は変わらなかった
──新工芸舎のプロダクトといわゆるFabで生まれたプロダクトとの違いはどのような点にありますか。
インダストリアルデザインを学んでいた学生時代から3Dプリンターを購入してずいぶんと使いこんできました。ただ、世の中のメイカーフェアや3Dプリンターから生み出されるプロダクトを見ながら、何か違うと感じていた。人びとの創造性が刺激され、自由な表現の場になっているのは確かですが、それに参加する人のほとんどが趣味の領域を超えていないからです。平日に頑張って働いて、休日を使って3Dプリンターを楽しんでいる人に「本物」を求めてもしかたないですが、これは僕が考えていた「ものづくりの民主化」ではなかった。そこに良きデザインと暮らしに影響を与えるアウトプットが現れてこない限り、世界は変わりません。だからこそ、自身が会社員になってからもずっと、その可能性を模索し続けていました。
そんな試行錯誤のなかで生み出したのが、新工芸舎の代名詞となる「tilde(チルダ)」です。熱で溶かしてノズルから押し出した樹脂を積み上げていくFDM(熱溶解積層)方式のデメリットとされる積層痕をむしろ「表現」として活かす。これはデザインとして新しいだけでなく、造形時間を短くできるメリットもあるんです。素材や技術に真剣に向き合ったときに、ついに相応しい表現にたどり着くことができた。これはまさしく「工芸」だと思いました。これなら“Fab”の次に進めそうだ、と。
3Dプリンターのノズルの太さや着色の方法を変えることで、さまざまな表現を可能にするtilde
工芸、特に民藝とは、素材との対話と人びとの営みのなかから自然と生まれてきて長い時間をかけて結晶したものだと理解しています。それは、つくり手にとって無理なくつくり続けることができる仕事が、自然と生活の糧になっていくということでしょう。tildeを生み出す過程でも、つくりやすさ・日常でのニーズ・見た目の良さ、それぞれがバランスするポイントを探ってきたし、それは窯や素材と向き合いながら作品をつくって販売して生計を立てる陶芸家とマインドは同じなのではないかと思いました。3Dプリンターやデータと向き合いながら、民藝がもつ自然さを目指そうというわけです。
──tildeシリーズとして初めて発表したプロダクトはどのようなものだったのでしょうか。
会社員時代に温めたtildeのアイデアを磨き上げ、発表したボールペンtilde pen&pencilです。FDM方式で製造されたプロダクトとしておそらく初めて、世界的に知られるデザインアワードのiF Design Award2020を受賞しました。
3Dプリンターは一点物を比較的安価につくることができることがメリットですが、僕たちはむしろ、常につくり続けられること、比較的入手性の良い”日常の道具”をつくることにこだわってきました。新工芸は「熟練の超絶技巧」や「作家性を強調した個性的なプロダクト」を目指しているわけではない。ラジオや照明などの電化製品などは大手メーカーから製品を選ぶことがほとんどですが、もっとたくさんの選択肢から選べたら面白いじゃないですか。もちろん、量産品より値段は高いですが、つくり方やストーリーを知ったら納得してもらえると思っています。
tildeのラインナップ。ボールペンから始まり、徐々に増えている
“本物”だから見える、デジタルファブリケーションの新しい地域性
──直近では、 2023年2月に銀座のSony Park Miniで展示販売会「新工芸店(P)」を開催していましたね。そこでの反応はいかがでしたか。
作品と3Dプリンターを並べ、ボールペンを出力して組み立てるところを来場者にお見せしました。畳を敷いて僕たちが作業しているのは、工芸館で職人が実演しているみたいですよね。
3Dプリント×工芸というキーワードで興味をもってお越しくださる方は、伝統工芸と何かが掛け合わさっているんじゃないかと想像していたようです。3Dプリンターを初めて見る方もいましたね。おそらく期待していたものとは違ったでしょうが(笑)、僕たちが来場者の目の前で部品を熱してキュッと曲げるなどの工程を見ると「たしかにこれは工芸ですね」と納得してくれていました。
新工芸店(P)での展示では、これまで手がけてきたプロダクトが一堂に並べられ、その奥には展示期間中も稼働し続けていた3Dプリンターと作業スペースが設けられていた
一方で、3Dプリンターを普段から触っている学生やデザイナーもたくさん来てくれました。お店に来た人の作品の見方で大体わかるんですよ。プロダクトをいきなりもち上げて底を覗いたり、ディテールを見始めたりする人は、おそらく3Dプリンターを日常的に使っている人。「これってもしかして、こうやっているんですか」と技術について聞いてくる。伝統工芸も体験ワークショップを実際やってみると工芸家のすごさを実感できるように、3Dプリンターも表現で通じ合えるというのは面白かったですね。
──デジタルプラットフォームではなくリアルに3Dプリンターのコミュニティと出会う機会にもなったんですね。
メーカーから独立したデザイナーやスタートアップを始めている人もいるけれど、顔出ししていないインハウスデザイナーも多くて、そういう人たちと出会うことができたのはいい機会でした。
FDM式3Dプリンターが3万円程度から購入できますからプレイヤーの広がりを感じる一方、ハードウェアスタートアップへの投資熱も冷めましたし、業界内でプロフェッショナルな視点をもっている人は正直多くありません。そんな状況だからこそ、これまでのFabのイメージを超えていくクリエイターたちとつながっていけるように京都の亀岡市に店舗をつくろうとしています。
世界最大級の家具の見本市であるミラノサローネに新工芸舎で出展した際に、海外のデザイナーたちと出会うことができました。彼らのなかには僕らと同じように3Dプリンター工房をもって自社で製造をしている人も少なくなく、非常に高いクオリティで製造とデザインを往来していました。彼らも僕らの作品に共感してくれていたし、こうした信頼関係が構築できるならお互いの3Dデータを送り合って、それぞれの拠点で生産販売してもいいじゃないかという話をしています。輸送費や関税がかかりませんし「Designed by XX, Produced by 新工芸舎」という新しいクレジットをつけることができる。いま具体的に話が進んでいるのは、フランスの照明デザイナーです。
──これまでも、どこでも誰でも同じものがつくれるのがデジタルファブリケーションの強みでしたよね。
デジタルファブリケーションはインターネットが前提ですから、世界中でさまざまなコラボレーションや出会いがあるのは当たり前なんですけど、むしろいまは「どこで何をやるか」こそが大事だと思います。
特に、3Dプリンターの生産力が高くないということが、新しい地域とのつながりを生み出すと思うんです。プロダクトができあがるまで、とにかく時間がかかるので大量生産できない。それゆえにマスプロダクトは目指せません。ただ、地域をよく見れば、目の前の人たちがいろんなことに困っている。地域の困りごとを解決するくらいの規模感が、3Dプリンターの生産能力にはちょうどいいんじゃないかと。ご近所の福祉作業所や建築事務所など、案件は意外とたくさんあるように思います。こうした有機的な人のつながりから新工芸舎らしいプロダクトをどんどん生み出していきたい。
──メイカームーブメントだって、自分たちでつくれる環境や設備を手に入れて「ポスト資本主義を目指す」という初期衝動があったと思います。 リーマンショックで製造業・ものづくりの現場が壊滅状態に追い込まれたからこそ。
そうなんですよ。僕もそういった根本に立ち返りたかったんです。そのためには、自分たちがバンドみたいな組織であることが大事だと思っています。「俺がベースを弾いて、お前がドラムをたたいて、あいつがボーカル」というようにお互いの役割がはっきりしていて、シンプルで小さな組織でありたい。今後も、あえて「スケールできない/しない」ということを大事にしていきたいです。
── でもそれって、いろんなスタートアップが抱えているジレンマなのではないでしょうか。最初は、小さくてシンプルな組織だったのに、売り上げとともに組織が大きくなっていく。当然そこには軋轢も矛盾も生まれる。
それはそのとおりで、簡単に答えが出せない問題です。実際僕らもいままさに、売り上げが上がるにつれて生産量が増えて、きちんと計画を立てないと対応できなくなり、ちょっと困っています。でもどうにか耐えて、適度な高さの波にずっと乗り続けたいし、常に転がっている「つくる喜び」を拾い続けたい。良いものができたら、次のものづくりに向かう。新しいチャレンジをしながら、無理しすぎることなく生産し続けるということが、まさに「新工芸」そのものであり、本物の「ものづくりの民主化」につながっていくと信じています。
三田地博史|Hiroshi Mitachi デジタルとアナログを融合した新時代の工芸を標榜し活動する新工芸舎を主宰する。株式会社キーエンスでデザイナーとして働いたのち、株式会社YOKOITOに加入後、2020年に新工芸舎を立ち上げ2023年に独立。デジタルファブリケーションが生み出す、コンピュータとアナログ世界の境界面に現代におけるモノの在り方を模索する。平成元年生まれ。
次週5月30日は、世界最高峰とされるエベレストの南麓で登山客のポーターやガイドとして働く人びと「シェルパ」たちの調査を行ってきた、文化人類学者の古川不可知さんに「道」についてお話を伺います。天候だけでなく、個々人の身体によっても明滅するという山の「道」からどんな問いが見えてくるのか──お楽しみに。
発せられているのにきこえていない「声」をきき、記録し、伝えていくことは、存外に難しい。世界が複雑化するなか、わたしたちはどのような態度で、人と、そして人以外の存在たちと向き合えばいいのだろうか。どうすれば、行為の一方的な「対象」としてではなく、相互的な「関係」を相手と築くことができるのだろうか。スケートボード、フィールドレコーディング、郷土料理、文化人類学、Chat-GPT……他者の「声」に耳を傾け、書き留めることの困難と可能性を探る。
【書籍詳細】
書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]19号 フィールドノート 声をきく・書きとめる Field Note』
編集:WORKSIGHT編集部
ISBN:978-4-7615-0925-5
アートディレクション:藤田裕美
発行:コクヨ
発売:学芸出版社
判型:A5変型/128頁
定価:1800円+税