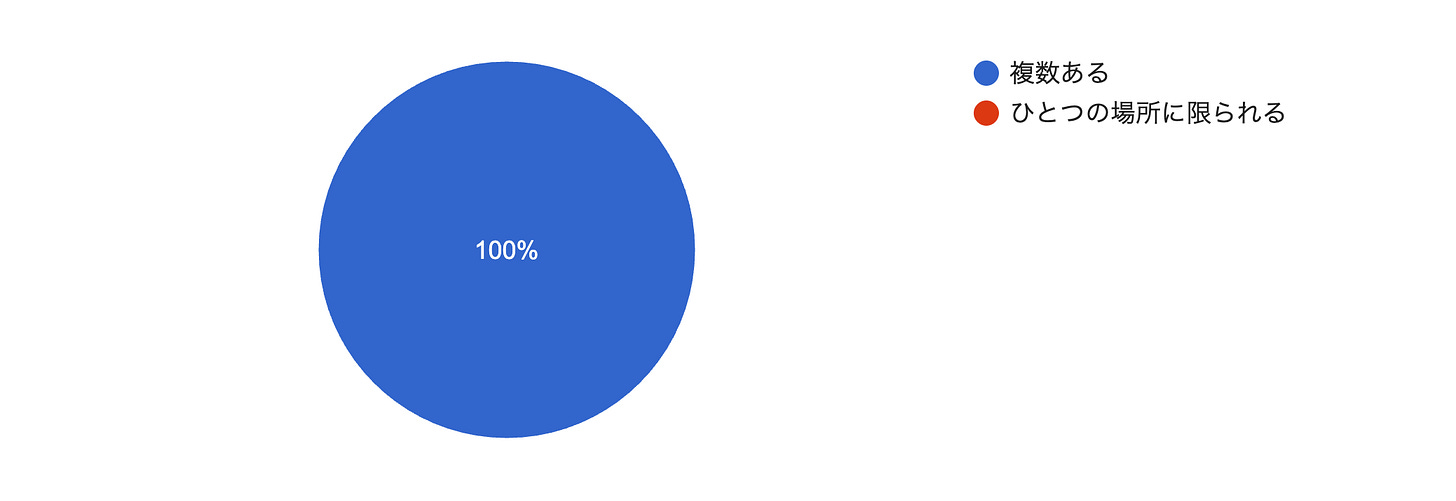アメリカを走る「軽自動車」:25年前の日本車を愛する人びとの集い
コロナ禍前夜からアメリカで萌芽し、パンデミック期に静かに広がっていった「軽自動車」カルチャー。小さく、安く、シンプルな車が、なぜいま多くの人びとを惹きつけているのか。その背景には、巨大化する自動車社会のなかで生まれたもうひとつの価値観と、DIY精神を軸にした人びとのつながりがある。軽自動車の愛好家が集うコミュニティ「Capital Kei Car Club」の代表に、ムーブメントの現在地を訊いた。
ワシントンD.C.内の桜の並木道を走るホンダ「アクティ・トラック」
四半世紀前に日本で製造された小さな車が、いまアメリカで静かな人気を集めている。コンパクトなボディで、日本の狭い道路にも適した軽自動車を「“kei” car」と呼び、そうしたムーブメントの火付け役となったのが、ワシントンD.C.を中心に、メリーランド州とバージニア州を拠点とする軽自動車の愛好会「Capital Kei Car Club」(以下、CKCC)だ。
クラブの魅力はそのフラットでオープンな空気にあり、専門知識を競うのではなく、経験の浅いメンバーも気軽に質問できる学び合いの場として機能している。ささやかながら確かな広がりを見せるこのコミュニティは、“大きい車こそ主流”というイメージを軽やかに揺さぶっている。
アメリカの軽自動車好きの素顔を探るべく、編集部はCKCCの創設者であるアンドリュー・マクソンさんに話を聞いた。最新テクノロジー主導の自動車開発が進む同国において、輸入や登録の手間をかけてでも軽自動車を手に入れる人が増えている理由には、日本のアニメやゲームだけでなく、米軍駐在などを通じて日本での生活を経験した人びとの記憶も影響しているという。
interview by Emiri Komiya, Sho Kobayashi, Hidehiko Ebi
text by Emiri Komiya, Hidehiko Ebi
photographs courtesy of Capital Kei Car Club
軽自動車好きの集合場所
──はじめに、アンドリューさんの普段のお仕事について教えていただけますか。
普段はワシントンD.C.を拠点に、サイバーセキュリティ関連の業務に従事しています。在宅勤務のため、日々コンピュータと向き合いながら仕事をしていますが、休日はたいてい、家からほんの数メートル先にあるガレージで、中古車の整備に時間を費やしています。父が昔から小さなイギリス車の愛好家だったことが影響して、わたしも幼い頃から小さな車に興味がありました。
──CKCCは、いつ、どのような経緯で設立されたのでしょうか。
2021年、パンデミックの真っ只中に、ごくカジュアルなかたちで立ち上がりました。当時、ワシントンD.C.周辺には軽自動車に特化したグループがなく、情報を共有できる場もありませんでした。ちょうどその頃、スズキの「カプチーノ」を所有していた友人がいて、わたしもマツダの「オートザムAZ-1」に乗っていたのですが、ふたりでイベントやカーミーティングに参加するうち、ほかにも軽自動車や軽トラックを時々見かけるようになったんです。「軽自動車を中心としたグループがあってもいいのでは?」と考えるようになったのが、CKCCを立ち上げるきっかけになりました。
──クラブのメンバーはどのようにして集めたのでしょうか。
最初にステッカーをつくり、軽自動車を見かけたらそれを渡したり、オーナーに声をかけたりと、地道な活動から始めました。初めてカーミーティングを開催したときには、3つの州から9台の軽自動車が集まりました。それ以来、毎月少なくとも一度は集まりを開いていて、この活動を通じて、結成以来の友人もできました。
2022年3月に開催されたカーミーティングの様子。一部の軽自動車は、日本用のナンバープレートを付けたままにしている。記載されている地名も「札幌」「宮城」などバラバラだ
──クラブでは具体的にどんな活動をしているんですか?
毎月第3木曜日に定例ミートアップを開いています。バージニア州とメリーランド州を交互に会場にしながら、駐車場で集まり夕食を一緒に取る、カジュアルで社交的な集まりです。
また、年に2回大型イベントを開催していて、春にはワシントンD.C.の桜並木でドライブしながらお花見を、夏にはバーベキューを企画します。直近のイベントでは、軽自動車だけで40台、さらに日本車を含めると80台以上が集まりました。バーベキューだけでなく、帽子やステッカー、ピンバッジなどマーチの販売や、日本のお菓子や雑誌、カーパーツ、ステッカー、アクセサリーなどを景品とした無料のラッフル(抽選会)も行いました。
──クラブにはどんなメンバーが集まっていますか? 若い方が多いのでしょうか。
中心メンバーは若い人たちですが、ご高齢の方が車を見て喜んでくださることもあります。また、地域柄もあり、クラブにはいろいろなバックグラウンドをもつ人が集まります。IT関連の仕事をしている人が中心ですが、製造業や輸送業、軍事関係の人もいますよ。軽自動車以外のイベントやクルーズなどに参加するメンバーも多く、みんな車に乗ることそのものを楽しんでいます。アジアや日本での生活経験をもつ人も多く、ミートアップに来て「アジアを離れて以来、こんな軽自動車を見るのは初めてだ」と、懐かしそうに話しかけてくれる方もいます。
──遠方から来るメンバーも多いと聞きました。
驚くべきことに、4〜5時間以上かけてイベントに参加する人もいて、「最も遠くから軽自動車でやって来た人」にトロフィーを贈るのが恒例になっています。
軽自動車のエンジンは660ccと小さく、最高速度も時速60〜75マイル(100〜120キロ)程度が限界です。アメリカでは高速道路の最低速度が時速70マイル(約113キロ)以上に設定されている区間も多く、軽自動車では速度が足りない場合があります。そのため長距離移動の際も一般道を使わざるを得ず、目的地に着くまでに他の車の倍近い時間がかかるんです(笑)。
(上)2024年春のイベントにて、桜並木を走るホンダ「BEAT」。列の後方にも日本車が数多く並んでいる (下)2022年夏に開催されたバーベキューの様子。軽トラックの荷台に食材を広げるのがCKCC流
知恵と道具のシェア
──実際に対面して交流することを大切にされているようですが、整備や改造も協力して行っていらっしゃるのでしょうか。
もちろん協力し合っています。わたしたちはみんな、改造することが大好きなんです。わたし自身も、自分の軽自動車にはすべてチューニングパーツを入れています。
ただ、長い間この趣味を続けてきて感じるのは、情報を見つけるのが本当に難しいということ。軽自動車に関する情報はほとんどが日本語で、パーツも日本にしかありません。
──なるほど。
だからこそ、英語圏ではオンライン上に大きなコミュニティが自然発生的に誕生しました。FacebookやInstagramには、ホンダのアクティやマツダのオートザムといった車種ごとにオーナーグループがあり、それぞれのグループで情報を共有しています。パーツの買い方、サービスマニュアルの探し方、必要な整備情報などをシェアしながら、オフラインでも実際に集まってお互いの車を整備しています。
これまでにも、おそらく15台ほど、自分のガレージにクラブメンバーの車を入れて、エンジンを下ろしたり、フルメンテナンスをしたりしてきました。それもコミュニティのイベントのひとつと言えるでしょう。誰かが新しく軽自動車を手に入れたときには、港から届いたばかりの車をガレージにもち込み、ピザとビールを用意して、1日かけて整備します。新しいホイールやタイヤを取り付け、しっかり走れる状態に仕上げるんです。
──それは初心者にとっても心強いですね。
軽自動車のオーナーには若い人も多い分、整備の経験がない人も少なくありません。だからこそ、集まることで、これまで培ってきた自分の経験を共有し、実際に整備の工程を見せることができます。チームで車を整備することこそが、このクラブの大きな醍醐味なんです。
2022年秋のミートアップの様子。日本限定の初心者マークが貼られたままの車もちらほら見受けられる
選ばないことが意思表明
──さまざまなクラシックカーがあるなかで、多くの人が軽自動車に惹かれる理由は何なのでしょうか。
アメリカでは、大きな車を運転する人が多いですが、本当にそこまで大きな車である必要はあるのでしょうか。現代の車はとても複雑な構造をしていて、修理も簡単ではありません。
軽自動車は小さいですが、日常の運転に必要な機能のほとんど──わたしは99%だと考えています──を備えています。しかも整備がしやすく、基本的な工具さえあれば自分たちで修理を完遂できる。余計な装飾や機能はなく、改造もなるべくお金をかけずに楽しんでいます。このシンプルさと実用性がもたらす喜びは、アメリカで手に入る多くの車にはなかなかないものだと思います。軽自動車は、車を運転するという行為の本質を思い出させてくれる存在で、そこに惹かれている人が多いんだと思います。
──車そのものを愛するという姿勢が伝わってきます。
わたしの住む地域は比較的裕福なところで、フェラーリやポルシェ、巨大なキャデラックなど、きらびやかな車を日常的に見かけますが、軽自動車の「見せ方」はまったく違います。派手さではなく、工夫や個性で魅せるんです。
──車の「見せ方」の違いについて、もう少し詳しく聞かせてください。
アメリカでは、多くの人が「どんな車に乗るか」ということに自分のアイデンティティを重ねています。ほとんどのアメリカ人は、できる限り新しくて、大きくて、目立つ車に乗りたいと思っている。
だから、軽自動車にたどり着いた人たちは、少し違う考え方をもっているということになります。軽自動車に乗ってもカッコよく見えるわけではありませんが、同時にそれは「いちばん大きくて新しい車」を選ばないという意思表示でもあります。
軍人2世の記憶
──アメリカの人が日本車に興味をもつきっかけとして、アニメやゲームの影響は大きいのでしょうか。
わたしも含め、1990〜2000年代に育った同世代のアメリカ人は、ビデオゲームやアニメ、マンガといった日本発のカルチャーに囲まれて育ってきました。日本車に興味をもったきっかけは、『グランツーリスモ』にはじまるプレイステーションなどのゲームです。アニメからの影響でいちばん大きかったのは、間違いなく『頭文字D』ですね。作中に登場する「AE86」を手に入れてから、もう15年近く大切に乗っています。
──それはつまり、コミュニティを設立する前から、すでに軽自動車を所有している人は一定数いたということでしょうか?
はい、設立前からいました。ただし、軽自動車に関心をもつ人のなかには、アニメや日本文化以外の背景をもつ人も多かった印象です。アメリカには農家や狩猟者など、仕事のためにシンプルな車を必要とする人が一定数います。そうした人びとに向けて、軽トラックをまとめて輸入し販売するビジネスも存在します。特に造園業やグラウンド整備を行う会社では、軽トラックがよく使われています。
また、自身や親族に日本駐在の経験をもつ軍人・元軍人も少なくなく、帰国後に軽自動車を購入する人も少なくありません。
──軍人としての経験から軽自動車にたどり着くとは興味深いですね。
一緒にクラブを立ち上げた友人の父親も軍人でして、軍の配属の関係で、彼自身も子どもの頃に短期間日本に住んでいたんです。大学では日本語を学び、ある程度読み書きもできます。アニメやゲームが好きであっても、その頃は特に車好きではなかったのに、ある日わたしの軽自動車を見たときに「アメリカでもこういう車が買えるなんて知らなかった!」と驚いていました。
CKCCメンバーが所有するホンダ「アクティ」の運転席。任天堂が発売した携帯型ゲーム機「ゲームボーイカラー」が車内に取り付けられ、シフトレバーがデコレーションされている
──ここ数年、アメリカで軽自動車人気が高まっている主な理由は何だと思いますか。
まず大きいのは、アメリカには「25年ルール」があるという点です。これは、外国から輸入できる車は製造から少なくとも25年以上経っていなければならないという規則で、この制限によって、アメリカの車好きが注目するのは1980〜90年代の日本車になります。日産の「スカイライン」、マツダの「RX-7」、トヨタの「スープラ」といった、いわゆる“ヒーローカー”ですね。
しかし、そうした車を日本から輸入するとなると非常に高額になります。そこで、より手頃な日本車を探すなかで、軽自動車の存在に気づく人が増えました。加えて、アメリカでは車、特にトラックや小型トラックの価値が下がりにくい。軽トラックはコスト面でも魅力的で、その存在が次第に注目されるようになったのです。
──価格が安いだけでなく、価値も下がらないのですね。
そして2025年からは、2000年以前の車までが輸入の対象になります。つまり、現行の軽自動車の排気量である660ccの車がちょうど対象になり始めたことで、一気に“おいしい時期”に入ったんです。わたしの理解では、660cc規格が始まったのは1990年。ここ10年ほどが、軽自動車や軽トラックがアメリカに入ってくる“黄金期”だと思います。
──660ccが輸入可能になったことで人気が加速したということは、それ以前の規格だとアメリカでは走るのが難しかったのでしょうか。
660ccという排気量は、実用面で“使えるか使えないか”の境界にあたります。友人のなかには360ccや550ccといった初期の軽自動車を所有している人もいますが、アメリカの高速道路では走れません。最新の660cc規格でもすべての制限速度に対応できるわけではなく、走行可能な道路は限られてきます。
──つまり、アメリカの高速道路を走るには最低でも660ccに達している必要があるというわけですね。
そうなんです。ここ数年で購入者が増えているのもそのためだと思われます。ただし25年ルールは非常に長い規制です。例えばカナダは「15年ルール」で、2010年までの車が輸入できますので、世界的に見てもアメリカはかなり厳しいほうでしょう。
クラブメンバーのライアンさんが所有するマツダ「オートザムAZ-1」
──州ごとに軽自動車所有の可否が違うとも聞きますが、連帯してルール改正を目指すような動きはありますか。
幸いにも、わたしたちの住む州や周辺の州では軽自動車に対して比較的寛容で、登録や名義変更、ナンバープレートの取得に関して大きな問題はありません。
他方、テキサスやコロラド、バーモント、そして北東部のいくつかの州では、軽自動車の所有を規制する動きがありました。しかし、テキサスとコロラドではロビー活動が功を奏し、特定の軽自動車や輸入車の規制が解除されました。これは本当に大きな成果だと思います。
海を越えて、世代を超えて
──CKCCには若いメンバーも多いとのことですが、若者の間で軽自動車を購入する人が増えているのは、車の価格が安いことが理由なのでしょうか? それともコミュニティ独自の価値観によるものでしょうか。
どちらの要素もあると思います。まずひとつは、軽自動車が若者にとって非常に「手に届きやすい」存在であるということ。アメリカ製の車は、小さなピックアップトラックであってもかなり高額です。一方、軽自動車は、自分で輸入の手続きを進め、日本の輸出業者とやり取りすれば、3,000〜4,000ドルほどで手に入れることができます。加えて、燃料代や修理費、保険料などの維持費も安い。だから若い人がカーカルチャーに入るための“入り口”として、とても良い選択肢になっているんです。
──購入時のコストだけでなく、維持費も抑えられるのは大きいですね。若い世代は情報収集にも慣れているので、個人輸入もスムーズにこなせそうです。もうひとつの理由は何でしょうか。
表現が難しいですが……アメリカのカーカルチャーは、これまで一部の限られた層に向けたものという印象がありました。けれども、軽自動車の登場によって、より幅広い層が気軽に参加できるようになったんです。
──と言いますと?
わたしたちがCKCCを立ち上げたとき、最初から常に意識していたのは「オープンであること」と「人を受け入れる姿勢」でした。つまり、車に不慣れな人や、初めて車をもつ人にも安心して参加してもらえるような環境をつくることです。
これは、若い人や女性など、これまでのカーカルチャーにはあまり惹かれなかった人たちにも関心をもってもらえるきっかけになったと思います。
クラブでは、どんなに初歩的な質問にもきちんと耳を傾け説明するようにしています。質問に「愚問」なんてない。そんな雰囲気を意識的につくっているんです。わたしもクラブを共同設立した友人も、そういう空気をもったコミュニティを求めていました。
2022年夏のバーベキューで撮影された、参加メンバーによる集合写真。中央にいる赤いスニーカーの男性がアンドリューさん
──若い人や知識の浅い人も参加しやすい環境づくりが整っているんですね。それでは、クラブの今後の展望を教えてください。
新しいメンバーをもっと迎え入れたいと思っています。軽自動車は、車を初めて所有する人や、カークラブに初めて参加する人にとって、最高の入り口になると思います。だからこそ、今後もこのクラブをオープンで親しみやすい場にし続けたい。いま世界はさまざまな意味で落ち着かない状況にありますが、軽自動車は小さな存在ながらも多くの人に喜びをもたらしてくれるんです。そんなクラブが本当に大好きなので、これからも軽自動車好きの輪を広げていきたいと思います。
──最後に、ここまで過去の車種のモデルについてたくさん伺いましたので、今後、特に楽しみにしている車種がもしありましたら教えてください。
もちろんです。わたしもクラブのメンバーも、現行モデルにはとても興味があります。例えばスズキの新型「ジムニー」は、アメリカでも常に人気があります。クラブにも古いジムニーを所有している人が何人かいて、かつてアメリカでは「スズキ・サムライ」という名前で一世代だけ販売されていました。わたし自身も1986年式のサムライをもっていたことがあります。でも、いまは新しいジムニーがとても欲しいですね。
それからホンダの「S660」。これも本当に大好きで、もし輸入できるようになったら、ぜひ手に入れたいと思っています。その日を楽しみに待ちたいですね。
【WORKSIGHT SURVEY #25】
Q. もし、いま車を買うなら軽自動車? 高性能車?
CKCC設立者のアンドリューさんは、必要十分な機能を備える軽自動車について、そのシンプルさと実用性がもたらす喜びは、他の車ではなかなか感じることができないと語っています。この記事を読んで、もしいま「軽自動車」と「最新技術が詰まった高性能車」のどちらかを選ぶとしたら、あなたはどちらに惹かれますか? ぜひご意見をお聞かせください。
【WORKSIGHT SURVEY #24】アンケート結果
「アーバニスト」がつくる都市を目指して──都市体験のデザインスタジオfor Citiesの実践【「場」の編集術 #03】(10月14日配信)
Q:「地元」は複数あっていい?
【複数ある】思い入れがある街や場所が複数あればよい。何なら「地元」ということばもなくてもよい。
【複数ある】「どこ出身ですか?」と聞かれるたびに、生まれた場所か、愛着のある場所かで悩みつつ使い分けています。
【複数ある】出生地や実家よりも、祖母の暮らす地域に行く方が「帰省」に近い感覚がある。
次週10月28日は、近年、国内外で開発・使用が進んでいる、農業における新たな生産資材「バイオスティミュラント」にフォーカス。スタートアップ「株式会社NEWGREEN」の取締役・甘利芳樹さんのインタビューを配信します。農薬でも肥料でもない、バイオスティミュラントの未確定の領域ならではの面白さや、民間企業を含む多様な主体によるルールメイキングの必要性など、未だ発展途上である市場の現状と将来の展望に迫ります。お楽しみに。